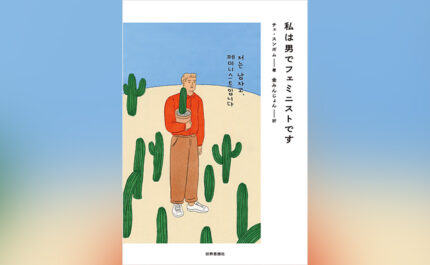【後編】インクルーシブとは? 障がい、性別、年齢など多様性を認め合う共生社会の実現
前編
後編
※関連記事:ダイバーシティとは
障がいがありながらも自分らしく生きる人たち

インクルーシブ社会に向けて、政府もさまざまな取り組みをしていますが、「法律で決められたから障がい者を受け入れなければならない」という考え方では、本当の意味で多様性を認め合う社会を実現するのは難しいでしょう。
障がい者であるかどうかということよりも、個人として相手に向き合い、尊重する気持ちを持ち、相手を受け入れることが大切なことです。
ここでは、障がいがありながらも周りのサポートや理解を受けて、自分らしく生きる人たちを紹介します。
西村大樹さんは、小さい頃からスポーツが大好きでしたが、障がい者ゆえに「危険だから」「責任を取れないから」と周囲からの決め付けに押しつぶされ、やりたいことができない悔しさを感じてきました。それでも諦めず、軟骨無形成症患者としては日本初の体育教師の教員免許を取得、また結成したダンスユニットでは全国3位に。現在ではプロのダンサーとして活躍しています。
真壁詩織さんは、脳機能にある問題ゆえに、聞こえた音声を言葉として識別する作業が困難になるAPD(聴覚情報処理障害)と向き合いながら、教師として活躍しています。宮城教育大学在学中にAPDとの診断を受けた後、自分の障がいについて周囲の人たちに伝え、「APD説明書」を作成してサポートをお願いするようにしました。真壁さんは「まずは工夫しながらやってみる。それでも駄目なら『胸を張って』助けを求めよう。助けてもらった分、違うところで誰かの力になれればいい」と語ります。
かんばらけんたさんは、先天性二分脊椎症という重度の障がいがあります。専門学校を卒業して、日本ヒューレット・パッカード株式会社に入社し、システムエンジニアとして働く傍ら、車いすダンサーとして2016年にリオデジャネイロパラリンピックの閉会式に出演。2017年には、東京都の大道芸ライセンス「ヘブンアーティスト」にも合格しました。かんばらさんは、「僕は、できることはできるし、できないことはできない。車いすダンスに関しては、できること」と話します。
これらは一例に過ぎませんが、障がいがある上で活躍している人は決して少なくありません。
インクルーシブ社会実現に向けて行動する先駆者
日本社会と障がい者の「間」には、意識や価値観のギャップのようなものがあります。それらを取り除くことが、インクルーシブ社会の実現に向けて必要になってきます。その壁を打ち壊そうと取り組んでいる人たちがいます。
森下静香さんは、1996年より「たんぽぽの家」で障がいのある人の芸術文化活動の支援や調査研究、アートプロジェクトの企画運営、医療や福祉などのケアの現場におけるアート活動の調査を行っています。森下さんは障がい者とのかかわりを通じて、「障がいのあるなしに関わらず、誰もが社会に参加したいという気持ちを持っていることに気付いた」と語ります。だからこそ、一人ひとりに合った仕事をつくることが必要で、地域社会で必要とされる多様な仕事を生み出せたらという思いで、活動に取り組んできました。
松田崇弥さんは、障がいのある人が描いたアートをデザインに落とし込み、プロダクト制作・販売や企業・自治体向けのライセンス事業を行っています。松田さんが共同で立ち上げた会社「ヘラルボニー」は障がい者の特性を「異彩」と定義し、「異彩を、放て。」をミッションに掲げています。「『かわいそうだから支援してあげよう』ではなく、障がいのある方の可能性を純粋に感じてほしい」と松田さんは語ります。
平林景さんは、一般社団法人日本障がい者ファッション協会(JPFA)代表理事を務め、JPFA発信のX-styleブランド「bottom’all」を展開しています。平林さんの目標は、パリコレクションでの車いすショーの開催です。このショー開催の目的は「障がいに対する世の中の偏見に対して、『それは今まで世の中の当たり前だっただけで、これからの当たり前は違うんだ』と示して、新しい世界をみんなに見せること」だと、平林さんは力強く語ります。
まとめ

社会は、障がい者を含めた多様な人たちで構成されています。私たちは目の前の相手を「障がい者」「外国人」「高齢者」といった枠でカテゴライズしてしまう傾向があります。しかし、大切なのは、相手がどんな属性や背景があったとしても、まずは、その人自身を理解しようとする姿勢です。それを阻む「心の壁」を取り除くことから、インクルーシブ社会は始まるのではないでしょうか。
前編を読む
星美学園短期大学日伊総合研究所客員研究員、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所名誉所員。専門は、視覚障害教育、イタリアのインクルーシブ教育等。近著として、『イタリアのフルインクルーシブ教育――障害児の学校を無くした教育の歴史・課題・理念』他、多数の著書がある。
みんなが読んでいる記事
-
 2020/02/18内向的な暮らし方では人生を豊かにできない、なんてない。竹下隆一郎
2020/02/18内向的な暮らし方では人生を豊かにできない、なんてない。竹下隆一郎SNSで簡単に自分の意見が発信できる現代。一見、自由な言論の場が増えたように見えて「ネットは自由過ぎて不自由になっている」と話す竹下さん。“炎上”を恐れ、同じような意見が溢れていく世界の中で、大事にしたいのが頭の中で描く自分だけの意見=オリジナリティだ。そのオリジナリティを生み出す場所として最適なのが家だと語る。会社と自宅の往復だった時代から、いつでもどこでも仕事ができる時代へと移り変わる中で、改めて考える竹下流・家の定義とは何か。
-
 2021/09/30苦手なことは隠さなきゃ、なんてない。郡司りか
2021/09/30苦手なことは隠さなきゃ、なんてない。郡司りか「日本一の運動音痴」を自称する郡司りかさんは、その独特の動きとキャラクターで、『月曜から夜ふかし』などのテレビ番組やYouTubeで人気を集める。しかし小学生時代には、ダンスが苦手だったことが原因で、いじめを受けた経験を持つ。高校生になると、生徒会長になって自分が一番楽しめる体育祭を企画して実行したというが、果たしてどんな心境の変化があったのだろうか。テレビ出演をきっかけに人気者となった今、スポーツをどのように捉え、どんな価値観を伝えようとしているのだろうか。
-
 2022/07/26“なんでも屋”になると損をする、なんてない。マライ・メントライン
2022/07/26“なんでも屋”になると損をする、なんてない。マライ・メントラインドイツテレビ局のプロデューサーからドイツ語の通訳・翻訳、カルチャー分野のライター、はたまたコメンテーターとしてのテレビ出演まで、多岐にわたる仕事をこなすマライ・メントラインさんは、自身の肩書について「職業はドイツ人」を自称している。ビジネスシーンでは職種や業務内容を端的に表す分かりやすい“肩書”が求められがちだ。専門性を高めることがキャリア形成に有利になる一面もあることから、さまざまな業務やタスクをこなす、いわゆる“なんでも屋”にネガティブな印象を抱く人も多い。しかしマライさんは自身の経験から「フレキシブルな肩書のニーズは意外とある」と話す。肩書や職種に“こだわらない”ようにしているというマライさんに、そのメリットや時にネガティブになってしまう“仕事との向き合い方”について伺った。
-
 2024/01/25“年相応”でなきゃ、なんてない。―40歳、ロリータモデル青木美沙子が“好き”を貫く原動力―青木 美沙子
2024/01/25“年相応”でなきゃ、なんてない。―40歳、ロリータモデル青木美沙子が“好き”を貫く原動力―青木 美沙子ロリータファッションの先駆者でモデルの青木美沙子さん。長年モデルやインフルエンサー、また外務省に任命されたポップカルチャー発信使(通称「カワイイ大使」)として国内外にロリータファッションの魅力を発信しながら、正看護師としても働いてきた。活躍の一方で、ある時から年齢に関する固定観念に葛藤するようになる。自分らしい生き方を選んできた、青木さんの原動力や考え方について語ってもらった。
-
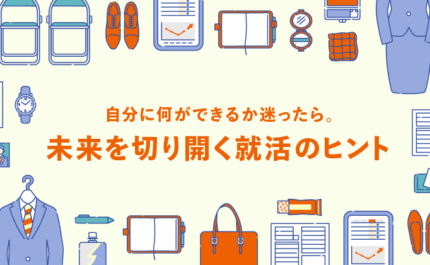 2025/03/06自分に何ができるか迷ったら。未来を切り開く就活のヒント
2025/03/06自分に何ができるか迷ったら。未来を切り開く就活のヒント自分の強みや希望の仕事など「就活」の悩みや不安への向き合い方の参考になる、既成概念にとらわれず自分らしく生きる人々の名言まとめ記事。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」