自分の居場所は今の社会にはない、なんてない。―“ハイヒールを履いた僧侶”、西村宏堂が体現する自分らしい生き方とは―
僧侶、メイクアップアーティストとして活躍する西村宏堂さん。「ハイヒールを履いたお坊さん」としてさまざまなメディアに取り上げられ、Instagramのフォロワーは12万人を超える(2024年4月時点)。
LGBTQ+当事者としての視点も活かし、ニューヨーク国連人口基金本部やスタンフォード大学、増上寺などで講演を行う。2021年にはTIME誌の「次世代リーダー」の一人に選出されるなど、世界で一躍脚光を浴びる存在だ。
自著(『正々堂々』サンマーク出版)の中で「ずっと自分のことを劣等だと思って生きてきた」と意外な過去を明かす西村さんが、自分の居場所を見つけ、ありのままの自分として生きられるようになるまで、どのような道のりを歩んできたのだろうか。
“暗黒期だった”と語る生い立ちから今の活動に至るまでのストーリー、同性パートナーとの結婚について聞いた。
国境を越えて多くのファンがいる西村さん。今回は日本語・英語(翻訳)で記事を公開します。
連載 自分の居場所は今の社会にはない、なんてない。

昨今の国際社会におけるSDGsやダイバーシティへの意識の高まりを受け、「多様性を認めよう」「自分らしく生きよう」といった言説を耳にする機会が増えた。
しかし、私たちの日常にはステレオタイプな価値観や「こうあるべき」といった既成概念が根強く残る。そうした社会において、「普通」「常識」と呼ばれる枠組みに収まらない自分を否定したり、「自分の居場所がない」と疎外感を覚えたりする人もいるかもしれない。
今回取材した西村宏堂さんは、僧侶、メイクアップアーティスト、そしてLGBTQ+活動家として、個性やアイデンティティを活かし世界で活躍する一人だ。
「自分が“普通じゃない”ことに罪悪感を感じ、正直な気持ちを隠し続けて生きてきた」と自著で綴った西村さんが、自分らしく生きられる居場所を見つけられた理由とは。生きづらさに悩む人に届けたいメッセージを聞いた。
これまで私が自分らしくいられないのは、『日本人だから』『同性愛者だから』だと思っていた。でも実は、自分自身に呪いをかけてしまっていたのかもしれないと気付いたんです。
コロンビア人の同性パートナーとさまざまな試練を乗り越え結婚
2023年9月、コロンビア人の同性パートナーと結婚した西村さん。同性同士、かつ国籍が異なる相手との結婚は、決して容易(たやす)い道のりではなかったと振り返る。

「出会いは、旅行先のスペインでした。バルで隣の席にいた彼に声をかけたのが、出会いの始まりです。グラフィックデザイナーとしてクリエイティブな仕事をしていて、関心のあるテーマや悩みも近かった彼とはすぐに意気投合したんです。
しばらくの遠距離恋愛を経て、イギリスで3か月半一緒に暮らしていました。その後コロンビアに行き結婚をしようとしたのですが、同性婚が認められている国であっても、日本とコロンビアの国籍を持つ同性カップル間の結婚は前例がなく、非常に煩雑な申請手続きが必要でした。
結局、私の5週間の滞在中には許可が下りず、一度彼と日本に帰国し、再度コロンビアへ。ようやく結婚ができ、同時に彼の日本でのビザ申請も下りたので、今は日本で一緒に暮らしています」
コロンビアで結婚し、日本では港区のパートナーシップ制度を使った。これほどまでに多くのハードルがあってもなお、「結婚」にこだわった理由。それは、至ってシンプルなものだった。
「彼と一緒に暮らしたい、ただそれだけです。日本とコロンビアという異なる国籍を持つ私たちが『家族』として共に生きていくには、法的な婚姻制度を用いるほかなかったのです。日本ではまだ同性カップルの法的保障が認められておらず、病気や事故など“もしも”が起こった時に『他人』として扱われてしまうのも、根が深い問題だと感じます」
「ありのままの自分では受け入れられない」と気付いた
現在は自分の個性やアイデンティティを活かし、自由に生きる大切さを説いている西村さん。根源にあるのは、「自分らしさ」を存分に発揮していた幼少期の思い出だ。
「まわりのみんなが園庭でドッジボールや鬼ごっこを楽しむ中、私は一人幼稚園の隅で大好きなセーラームーンやディズニープリンセスの絵を描いていました。母のワンピースを着てお姫様ごっこをするのが好きで、『こうちゃん、女の子よ!』と話していました。両親が男の子と遊ばないのか聞くと、私が『男の子は嫌いだ!』というので母は困っていたようです。」
筋の通らないルールや規則の強制が大嫌いで、自分が心から納得できることしかやりたくない。勉強しなくてはいけない意味が分からず、宿題の紙をぐちゃぐちゃにしたり、一人教室で居残りさせられたりしたこともあったという。
幼い頃から意志の強さを見せていた西村さんだが、少しずつ周囲との「違い」に戸惑いを見せていく。
「同じ幼稚園の男の子に興味を持ちました。それが好意だったのかは分かりません。でもなんとなく、この感情は親や先生には隠さなければいけない、とも感じていた記憶があります。小さい頃に見ていたアニメでは、同性愛者は悪役や“気持ち悪い”奇抜なキャラクターとして描かれていたから」
当時、自分のセクシュアリティについて、正確に理解していたわけではない。それでも、「男の子らしく」「男の子なんだから」という周囲の言葉を浴びるたび、ありのままの自分では受け入れられないと気付き始めるようになったという。
ネットの世界と英語に救いを見出した「暗黒期」
そんな息苦しさは、高校に進学してからさらに強くなっていった。西村さんは、高校3年間を人生で最もつらい「暗黒期」だった、と振り返る。
「私立の進学校に進んだのですが、勉強面でも行き詰まり、これまでの交友関係もゼロに。今まで以上にはっきりと男子・女子グループで分かれるようになって、どちらにも入れない私は、教室の隅でいつも一人ぼっち。
自分が同性愛者だと知られるのが怖くて、誰とも話さない日が増えていきました。孤独であること自体より、自分らしくいられなかったのが一番つらかったです」
そんな西村さんの孤独を埋めたのは、ネットの世界だった。放課後は得意な英語を活かし、同性愛者が集まるオンラインチャットに夢中になった。画面の向こうには、世界中に自分と似た境遇の人々がいて、その人たちとつながり、悩みや本音を共有した。さらに空いた時間には英会話教室に通い、得意の英語力に磨きをかけていった。
厳しい現実から逃れるように、オンラインチャットや英会話にのめり込んだ西村さん。映画や音楽にも触れる中で、自由で多様な価値観が存在するアメリカに強い憧れを抱くようになった。
「それまで『なぜ興味がない分野の勉強をしなければいけないんだろう』とか『どうしてセクシュアリティによって差別されなければいけないのか』と、ずっと一人で疑問に思っていたことについて、外の世界に行けば共感してくれる人がいるのかもしれないと考えました。
日本では生きづらい私も、アメリカなら息が吸えるようになるんじゃないか。この世界は、私が考えていたよりもっと広くて寛容なのかも、と希望が持てるようになったんです」
アメリカ、スペインでの価値観を揺さぶる出会いと体験
高校卒業後、念願だったアメリカ・ボストンの短期大学へ留学した西村さん。さまざまなバックグラウンドを持つ人々と触れ合ううち、自身を固く覆っていた“鎧”が少しずつ剥がされていったという。
「世界では同性愛者であるというだけで生命に関わる暴力や迫害を受ける国もあるということ、外からは幸せそうに見える人でも、実は他人には分からない悩みや葛藤を抱えていることを知りました。
何よりも、属性や枠組みに囚われていたのは自分自身だったと気付いたのが、私にとって大きな前進でした。
これまで私が自分らしくいられないのは、『日本人だから』『同性愛者だから』だと思っていたけれど、実は自分自身に呪いをかけてしまっていたのかもしれない。そう思うようになったんです」
少しずつ思考が前向きになり、行動範囲も広がっていく。ボストンの教会にあるゲイコミュニティに入り、初めてリアルな世界で同性愛者の友人ができたという。さらに、一人旅で訪れたスペインでの出来事やニューヨークで見た景色が、西村さんの価値観を大きく揺さぶったそうだ。
「スペインで仲良くなった同性愛者の親友は、愛するパートナーと街中で手をつないだり、キスをしたり、堂々と交際を楽しんでいて。彼は両親にカミングアウト(※)もして受け入れられていたことにも衝撃を受けました。親に自分のアイデンティティを打ち明けられずに日本を出てしまった私にとって、自分らしく生きる彼の姿は眩しくも映りました。
さらに、ニューヨークで見た大規模なLGBTQ+パレード(ニューヨークプライドパレード)にも大きな勇気をもらいました。私は劣等な存在なんかじゃないし、アイデンティティを隠さず、正々堂々と自分らしく生きていいんだ。先を歩く人々の姿から、そんなメッセージを受け取った気がしました」
※カミングアウト:自分の性のあり方を自覚し、誰かに伝えること
「ずっと避けてきた」仏教の道、両親へのカミングアウト
幼い頃からメイクに興味があった西村さんは、ボストンの短大を出て、ニューヨークのパーソンズ美術大学へ編入。その後5年間著名なメイクアップアーティストのもとで修行を積み、本格的にメイクアップの道に進むことになる。

「日本では『男性に生まれた自分がメイクをしたら馬鹿にされるのでは』と手を出せなかったけれど、ここ(アメリカ)では生まれた時の性別は関係なく、みんな自由にファッションやメイクを楽しんでいる。もうまわりの視線を気にして、自分の心に蓋をしたくなかったんです」
ミス・ユニバース世界大会で各国の代表者のメイクを担当し、著名人やモデルから高い評価を受けるメイクアップアーティストとして活躍。しかし、24歳の時に日本に帰国し、一転、仏教の修行に入った。
「ずっと避けてきた」と語る仏教の道を選んだのは、一体どんな心境の変化があったのだろうか。
「お寺の家に生まれましたが、両親から寺を継ぐように言われたことは一度もありません。ロングヘアに憧れていた私は坊主にするのも嫌だったし、木のお人形(仏像)に拝むなんてナンセンスだと思っていましたから。
でも、一度は自分のルーツである仏教にきちんと向き合わなければ、本当の意味で変わることはできないんじゃないかとも考えていました。深く知りもせず、否定や批判をする資格はないと思ったんです。
日本人として、自分のルーツである仏教を学ぶことで、私にしかできない表現ができるようになるのでは、という思いもありました」
もう一つ、「ずっと避けてきた」ことがある。両親へのカミングアウトだ。
「どんなに自分らしくいられる環境で、好きな仕事に就いたとしても、『両親に同性愛者だと打ち明けたら、見放されるのでは』という恐怖心が、“クモの巣”のようにずっと頭上に張りめぐらされているような感覚でした」
これまで海外で出会ってきた友人たちの中には、親からの応援を受けてパートナーと過ごす人もいたという。そんな彼らの姿が、西村さんの背中を押した。
「『このまま大切な人に隠して生きたくない』という気持ちが強くなっていって、帰国後、修行に入る前に思い切って両親にカミングアウトをしました。
すると、少し驚きながらも『宏堂の人生なんだから、宏堂の好きにしなさい』と言ってくれて。はっきりと言葉に出さなくても、両親なりに私の幸せを願ってくれていたんだ。そう分かって、大袈裟ではなく、モノクロだった視界に一気に虹がかかったような喜びを感じました。
24歳で、ようやく自分の本当の人生がスタートしたような気持ちになったんです」
僧侶、アーティスト、LGBTQ+活動家。3つの肩書きをつなげる思い
現在は、“ハイヒールを履いたお坊さん”として、唯一無二の存在感を放つ西村さん。僧侶、メイクアップアーティスト、LGBTQ+活動家――。一見結びつかない3つの肩書きだが、西村さんの中では一つにつながっている。
軸にあるのは、「自分らしく生きられず苦しんでいる人を励まし、応援したい」という思いだ。

「メイクやファッションで外見をおしゃれに着飾ることで、もっと自分を好きになったり、自信がついたりしますよね。メイクには、そんな“魔法”みたいな力があると思っています。『どんな人も平等に救われる』という教えがある仏教の力も借りて、色々な側面から人を励まし、応援していけたらと思っています」
こうした活動の背景には、さまざまな偏見や差別を乗り越えてきた西村さんらしい特別な思いがあるようだ。
「世間では『お坊さん/同性愛者はこうあるべき』という役割やイメージが固定化されてしまっていることで、苦しんでいる人もいます。だから私は、異質に感じられるもの同士をあえてミックスすることで、本質が浮かび上がってくるんじゃないかと思っていて。これまでの『お坊さん像』や『同性愛者像』を覆したいんです」
昨今の日本社会において、多様な働き方や生き方、性の在り方を尊重しようとする流れが加速している。一方で、「こうあるべき」といった既成概念やステレオタイプな先入観は色濃く残り、「普通」や「常識」と呼ばれる枠組みにおさまらない自分を否定したり、「自分の居場所がない」と疎外感を覚えたりする人も少なくないだろう。
そんな人には、「たった一人でいいから理解者を見つけてみて」と西村さんはアドバイスを送る。
「私は、アメリカやスペインで、自分と似た境遇の友人を見つけてから一気に心が楽になりました。両親にカミングアウトしていたり、同性パートナーと楽しく過ごしていたり、“少し先を歩く”仲間の存在も、大きな力になって背中を押してくれたように思います。
海外に行かなくても、いろいろな講演会へ足を運んだり、本を読んだりすることで、新しい価値観や世界に触れることはできますよね。『なぜ差別はなくならないのか』と、歴史や自分のルーツを学んでみるのも手がかりになるかもしれません。
『誰にも理解されないんじゃないか』『自分は一人ぼっちなんだ』と絶望したくなる瞬間もあるでしょう。それでも、この世界のどこかに、あなたを理解してくれる人はいるはずです。だから大丈夫。そう伝えたいです」
昨今、自分が望まない状況下に置かれ八方塞がりなことを「○○ガチャ」などと表現することが多い。特に、家庭や就職など自分だけの力ではどうにも好転させられない事情が絡むケースも決して少なくない。「なんで自分だけ」「なんでこんな運命なんだ」と人生を悲観する人もいるだろう。だが、自分の可能性に蓋をせず、自分らしく生きることを諦めなければ道は開かれるのではないだろうか。自分の周りだけが世界のすべてではない。西村さんの言うように、あなただけの居場所がきっとある。
だから私は、「多様性」という言葉が浸透してきた今の日本社会は、「一人ひとりが生きやすい世の中になるための準備ができつつある」とポジティブに捉えています。
今いる場所で「居場所がない」と疎外感を感じている人は、あなたにとっての「普通」や「常識」の枠組みを壊すような世界に触れる、ほんの少しの勇気を持ってほしい。この広い世界には、自分のアイデンティティを打ち立てるべく途方もない努力を積み重ねてきた先人たちや、あなたを理解し共感してくれる仲間はきっとたくさんいますから。
取材・執筆:安心院 彩
撮影:大崎えりや

1989年東京生まれ。ニューヨークのパーソンズ美術大学を卒業後、アメリカを拠点にメイクアップアーティストとして活動。2015年、浄土宗の僧侶となる。LGBTQ+活動家として「性別も人種も関係なく皆平等」というメッセージを発信し、ニューヨーク国連人口基金本部、ハーバード大学などで講演を行う。2021年にはTIME誌「次世代リーダー」に選出され、2022年にはNHK紅白歌合戦で審査員を務めた。著書『正々堂々 私が好きな私で生きていいんだ』(サンマーク出版)は7カ国後に翻訳されている。
X @kodonishimura
Instagram @kodomakeup
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
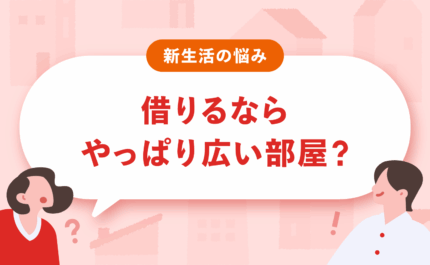 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
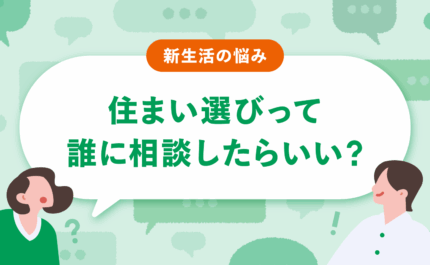 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
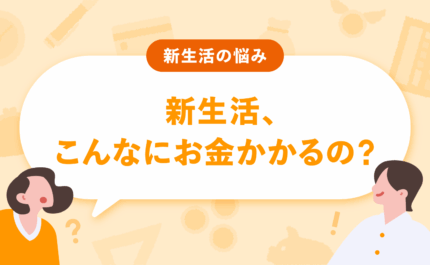 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
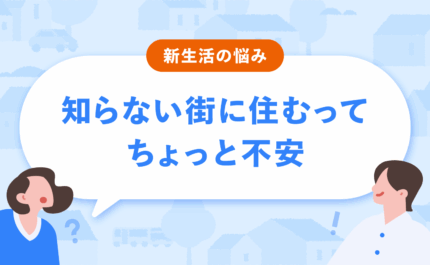 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。













