心地よいはみんな違う。私たちのパートナーシップ【モーリー・ロバートソンの場合】
誰かと一緒に生きていきたい。そう思った時、あなたは誰とどんな関係性で生きていくことを望むだろうか。心地よいパートナーシップは、一人ひとり違う。しかしながら、パートナーシップのあり方にはまだまだ選択肢が乏しいのが現状だ。
既成概念にとらわれない多様な暮らし・人生を応援する「LIFULL STORIES」と、社会を前進させるヒトやコトをピックアップする「あしたメディア by BIGLOBE」では、一般的な法律婚にとどまらず、様々な形でパートナーシップを結んでいるカップルに「心地よいパートナーシップ」について聞いてみることにした。既存の価値観にとらわれず、自らの意志によって新しいパートナーシップの在り方を選択する姿には、パートナーシップの選択肢を広げていくための様々なヒントがあった。
今回話を聞いたのは、タレント、ミュージシャン、ジャーナリストなど幅広く活躍するモーリー・ロバートソンさん。俳優の池田有希子さんと事実婚という形でパートナーシップを築いている。モーリーさんの視点から見た「心地よいパートナーシップ」について話を聞いた。
▼パートナーの池田有希子さんにお話を聞いた記事をあしたメディアで読む
心地よいはみんな違う。私たちのパートナーシップ【池田有希子の場合】

珍しい体験を共有して深まった関係
「舞台に立つゆっこちゃんを見て、その輝きに圧倒されました」
パートナーである池田有希子さんの第一印象についてそう語るモーリーさん。
現在さまざまなメディアで幅広く活躍するモーリーさんは、2005年頃からネットでPodcast番組の配信をしていた。2006年、池田さんが出演する舞台の取材にモーリーさんが訪れたのが2人の出会いだったという。
「当時の僕は、ハードルが高いことをひたすらやっていましたね。ゆっこちゃんと付き合い始めて半年くらい経った頃には、一緒にチベットに行きました。どんどんとハードルを高くしていくうちに、標高まで高くなった(笑)。
チベット自治区と新疆ウイグル自治区の様子を、ネットを経由して日本に届けるという企画があったので、『せっかくだからゆっこちゃんも一緒に行こう』と、クルーに入ってもらったんです。砂漠を歩いたり、羊の腎臓のシシカバブを食べたり、過酷な時間や珍しい体験を共有して、2人の関係も深まっていきました」
今でこそ個人でネット配信やPodcastをやることが一般的になっているが、当時は随分と珍しい取り組みだった。
モーリーさんはその10年ほど前に1人で発展途上国の取材を試み、警察に拘束されて帰ってきたという経験を振り返りながら、「1人だったらできなかったですね。2人だから勇気を出してできたんだと思います」と話す。
そんな2人は事実婚という形でパートナーシップを築いているが、その背景にはどのような思いがあるのだろうか。

大切にしたいのは「そこに情熱があるのか」
「僕は、とにかくさまざまな理由をつけて『結婚』という制度に抵抗したいと思うんです。日本だったら『家父長制に基づいた法律に過ぎない』と言いたいし、欧米だったら『キリスト教会によって作られた制度だ』と言いたい。
ゆっこちゃんは比較的どっちでもいいという考えなので『節税になるのなら婚姻届を出したほうがいいんじゃない?』と言うこともあるけれど、僕は税金を少し多く払ってでも事実婚を選びたいと思っています」
その理由として、モーリーさんは「法律婚は情熱を失わせる装置に感じる」という。
「法律婚をしたカップルの何割が情熱を持ち続けられているのか、疑問です。情熱はとっくに失われているけれど、経済的な理由で別れないというような、形だけの夫婦もたくさんいるんじゃないでしょうか。その背景にはもちろん、男女の不平等など、解決されるべき社会的な要因があると思います。
でもそんな中で自分たちはどんな関係性で在りたいかを考えた時、法律で縛らなくても続いていく関係が本物だと思いました」
さらに「ゆっこちゃんは素敵な俳優だから、『既婚者』とか『妻』とかに囚われずに、特別な人として自由に羽ばたいていてほしいという気持ちもあるんです」と付け足すモーリーさん。
池田さんは隣で「ありがとう。そういうイメージでいてくれて嬉しい」と応える。そんな2人の間にはたしかにお互いへの情熱が感じられる。

事実婚という在り方だからこそ得られたこと
事実婚のデメリットはどうカバーしたのか。
「弁護士に相談して、自分たちで婚姻届と同等の契約書をつくりました。どちらかが病院にかかる時に立ち合ったり意思決定をしたりするため、また経済的に不利にならないためにも、かなり綿密にリスクヘッジしてあります」
婚姻届というフォーマットの決まった書類を提出しない代わりに、弁護士に相談して自分たちの契約書を作った2人。「自分たちのことは自分たちで決めたい」というこだわりがあるからこそ、得られることもあるのだろう。事実婚を選んだことで感じたメリットについてはこう語る。
「やはり常に『結婚とは』『事実婚とは』『よりよい関係とは』と考え続けているので、僕自身のジェンダーにまつわる考え方が柔軟になりましたね。事実婚という形で理想を共有しているパートナーと暮らしているからこそ、その視点を持つことができていると思います。それは、男性だけで会議をしていると欠落してしまいがちな視点だとも思うんです。
コンプライアンスの概念が広がったことで変わってきた部分もあるけれど、まだまだ社会の中ではジェンダーギャップを感じますよね。たとえば、僕ばかりがニュース番組に呼ばれることにも正直違和感がある。たしかにジャーナリストなのでニュースにコメントができるけれど、男性だからというバイアスがかかってキャスティングされている場合もあるかもしれません。同じ発言内容でも、もし話し手が女性のゆっこちゃんだった場合、『生意気だ!』と受け取られることもあると思います。そういう状況は変わっていってほしいですね。」

関係性のためにも、クリエーションのためにも、コミュニケーションを欠かさない
モーリーさんにとっての理想のパートナーシップが伝わってくるようなお話だが、生活の中で、よりよいパートナーシップのために具体的に心掛けていることはあるのだろうか。
「『親しき仲にも礼儀あり』は大切ですよね。どれだけ仲がよくても、ちゃんと考えて、相手に配慮して言動する。『阿吽の呼吸』みたいな関係を好む人もいると思いますが、大概それはだんだんとどちらかがしんどくなったり情熱がなくなっていったりするんじゃないかな。
うちの場合、普段はテレビもしまってあって、ずっと会話をし続けているんです。『ヒッチコックが』とか『コッポラが』とか映画の話もしますし、一緒に出かけた時の出来事について話していたらそれがクリエーションの種になることもあります」
最近は、2人の暮らしにほぼ住み込みのアシスタントの方が1人加わり、3人暮らしをしているという。
「『事実婚+1』になって、さらに生活が引き締まった気がします。仕事以外ではお酒も飲まなくなったんですよ。3人で飲むと誰か1人の調子が悪くなることが多かったので、全員でノンアルコールにしてみたら、健康レベルがアップしました」
お酒を控えるようになった背景については池田さんも「夕食の後にもひと仕事したい3人なんですよね」と話す。
 一緒に暮らす3人で制作したというアニメ「ラララの冒険」
一緒に暮らす3人で制作したというアニメ「ラララの冒険」
https://www.youtube.com/watch?v=1JF-Wb_Xmic
現在は、CGの動画制作に夢中だというモーリーさん。池田さん曰くモーリーさんは、「ジャーナリズムからアートへとまた活動の軸を移しているフェーズ」とのこと。
「一緒に住んでいるアシスタントの方が絵を描くので、彼女が描いた漫画を、僕がアニメーションにしています。キャラクターに当てる声はゆっこちゃんにもやってもらいました。僕は熱中するタイプなので、ここ半年くらいはずっとCGのことを考えています」
アニメーションのストーリーも、日常の中で家族で共有した体験が基になることがあるのだそう。
「たとえば強烈に理不尽な体験をした時、ただ憤って終わらせるともったいないから、エンターテインメントに昇華させたいと思います。
着眼点さえあれば街の中も家の中もネタが満載。3人ともやる気がものすごくあるので、それぞれの情熱で刺激を与え合っていますね。構成作家が3人でチームを組んでいるくらい、次から次へとおもしろいネタを考えつくので、共有しては盛り上がっています。そういう意味で撮れ高が高い家族だと思いますね(笑)」
▼パートナーの池田有希子さんにお話を聞いた記事をあしたメディアで読む
心地よいはみんな違う。私たちのパートナーシップ【池田有希子の場合】
取材・文:日比楽那
編集:大沼芙実子
写真:服部芽生

1963年生まれ。米ニューヨーク出身。幼少期に日本に引っ越し、日米を行き来しながら両国の教育を受けて育つ。1981年、東京大学とハーバード大学に現役合格。ハーバード大学では電子音楽を専攻。近年は国際ジャーナリストとして、テレビ・ラジオの多くの報道番組や情報番組、インターネットメディアなどに出演するかたわら、ミュージシャン、DJとしても幅広く活躍している。
Twitter @gjmorley
Instagram @morley_robertson
みんなが読んでいる記事
-
 2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜
2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。
-
 2022/01/12ピンクやフリルは女の子だけのもの、なんてない。ゆっきゅん
2022/01/12ピンクやフリルは女の子だけのもの、なんてない。ゆっきゅんピンクのヘアやお洋服がよく似合って、王子様にもお姫様にも見える。アイドルとして活躍するゆっきゅんさんは、そんな不思議な魅力を持つ人だ。多様な女性のロールモデルを発掘するオーディション『ミスiD2017』で、男性として初めてのファイナリストにも選出された。「男ならこうあるべき」「女はこうすべき」といった決めつけが、世の中から少しずつ減りはじめている今。ゆっきゅんさんに「男らしさ」「女らしさ」「自分らしさ」について、考えを伺った。
-
 2023/04/14【前編】SNS上で起こる「エコーチェンバー現象」とは? デマやフェイクニュースへの対策を解説
2023/04/14【前編】SNS上で起こる「エコーチェンバー現象」とは? デマやフェイクニュースへの対策を解説「エコーチェンバー現象」についてこの記事では下記の5点を解説します。①「エコーチェンバー現象」とは? ②過激な考えに傾倒してしまう危険性がある ③エコーチェンバーの要因となる確証バイアス ④SNSを健全に利用するためには? ⑤思い込みや偏見に支配されず、多様な意見を理解するには
-
 2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題
2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。
-
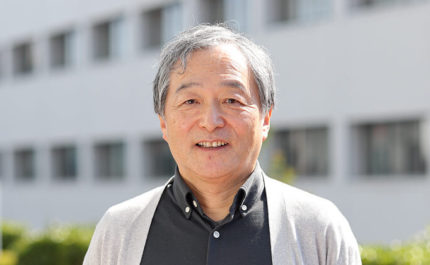 2023/11/14なぜ「結婚しなきゃ」に縛られてしまうのか|社会学者・山田昌弘
2023/11/14なぜ「結婚しなきゃ」に縛られてしまうのか|社会学者・山田昌弘「おひとりさま」「ソロ活」という言葉や、事実婚や選択的シングルマザーなどが話題になり、「結婚」に対する一人ひとりの価値観が変化し始めている。「婚活」「パラサイト・シングル」などの言葉を提唱した家族社会学者の山田昌弘さんに、結婚に関する既成概念についてお話を伺った。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」















