障がいがあるからスポーツはさせられない、なんてない。
現在、2つのダンスユニットに所属し、プロのダンサーとして活躍をしている。2021年春には「ダンスを福祉でデザインする」をコンセプトとするダンスチーム、SOCIAL WORKEEERZの2代目代表に就任したばかりだ。夢は障がい者が気兼ねなくダンスを楽しめる、本当のバリアフリーの環境をつくること。幼い頃からスポーツが大好きだったが、ずっと「危険だから、責任を取れないからやめてほしい」と、自分の「やりたい!」を周囲からの決めつけに押しつぶされながら生きてきた。自分の体のことなのになんで自分で決められないんだ、という悔しい思い。それでも何度も立ち上がって道を探し、今はプロのダンサーだ。スポーツを愛して道を切り開き続けてきた、西村大樹さんのこれまでとこれからを伺った。

2021年夏。延期されていた東京オリンピック・パラリンピックがついに開催された。「パラリンピックの開催までは、今までになく障がい者スポーツ・芸術活動が注目を浴びていた実感があります。しかし、パラリンピックが終わったあと、社会の目はどうなるのか。どれくらいの障がい者スポーツやアーティストがちゃんと生き残っていけるのか。パラリンピック後が本当の勝負だと思っています」と語るのは、LIFULLのCMではじける笑顔で踊っているプロダンサーの西村さん。
私たちは気がつかないうちに、オリンピック・パラリンピック前の「感動のストーリー」として、スポーツに真剣に取り組む方々の歴史や活動を、都合良く消費してしまっているのかもしれない。一瞬の注目のあと、何もなかったかのように忘れてしまうことは、とても残酷なことに違いない。障がい者がスポーツや芸術活動を楽しむことは、何も特別なことでも、一時的なことでもないという自戒を込めながら、ダンサーとして活躍する西村さんにお話を伺った。
自分のやりたいことをいつも周囲の判断で止められる人生に心底うんざりだった
小さな頃からさまざまなスポーツに打ち込んできた西村さんは、驚異的な運動神経の持ち主だ。しかし、いつも周囲の都合で勝手に道を塞がれてきた。最初は幼稚園で始めようとした水泳。
「母親が3歳上の姉が通っていた水泳教室に僕を入れようとしたらしいんですよ。軟骨無形成症患者は肺が小さいから、水泳で肺活量を鍛えること、また体への負担が他のスポーツに比べ少ないことからも医師から勧められていて。でもそこの水泳教室で入室を断られたらしいです。『事故が起きたら責任が取れないから』って」
「何か起きたら責任が取れないから(やめてほしい)」この、水戸黄門の印籠のような言葉は、その後しばしば西村さんの行く手を阻む壁となる。
「小さい頃は自分に障がいがあるなんて知らなかったから、何でもみんなと同じようにできると信じて疑わなかったんですよね。友達ができるのに自分ができないのは、単に努力が足りないからだって。だからできないことがあると、ひたすら練習して努力をしていたんです」
授業をサボり続けていたおかげでダンスと出合う
中学校では野球部に入り打ち込むものの、学校生活や人間関係において障がいを理由にさまざまなことを禁止され、馬鹿にされるその理不尽さに怒りを覚えるようになっていた。禁止する側の言うこと、または、制する指導者側の言うことも十分にわかるからこそ、きついのだ。
「その頃はとにかく全てに腹が立って、授業中も教室じゃなくて廊下で仲間と過ごすことが多くなりましたね。髪の毛も奇抜にして、いわゆる不良仲間たちとつるんで。『どうして自分の体はこうなんだ』『どうして禁止されるんだ』『どうしてどうして』と怒りに満ちており、自分の人生を窮屈に感じていました。そんな中で人生を変える2つのことに出合ったんです。一つは不良仲間が廊下で踊っていたヒップホップダンス。『うわーすげーかっこいい!!』って思って、すぐに習いに行ったんですけど、少し習ううちに『足のステップについてこられないから通うのは無理』って先生に言われて。じゃあ足がダメなら腕を使えばいいんじゃないか?と次にやろうとしたのはブレイクダンス。これは主治医に反対されましたね。自分はずっと野球をやってきたけど、団体競技と違ってダンスは一人で踊っていればいいから誰にも迷惑をかけないじゃないですか。そこもすごく魅力に感じたんですよね」
西村さんの身体的特徴を見た人から無意識に投げかけられる「危ない」「できない」という言葉が、また西村さんの前に大きく立ちはだかる。しかし、「絶対にやりたい!踊りたい!」という西村さんの情熱が次に見つけてきたのは、“クランプ”というダンスだった。
「クランプは1990年代にアメリカのサウスセントラルで生まれたダンスです。当時、サウスセントラルには2000万人ものギャングがいて、抗争や殺し合いが日常。翌日友達と会える保証なんて全くない。そんな世界への怒りを伝えるために生まれたのが、クランプです。『体の動きで怒り・生きていることを伝える』って俺そのものだな、って思って。このクランプとの出合いが、独学でダンスにのめり込むきっかけとなっていきましたね」
授業をサボっていた時代の、もう一つの運命の出会い

多くのことに怒りを感じて世界に反抗していたとき、ダンスの他にも運命を変える出会いがあった。中学のときの担任だ。
「なんだか信じられないほどしつこい先生でねー。どこでサボっていても、必ず俺を探し出して目の前に現れるんですよ。GPSでもついてんのかな?って思うくらい。他にもサボっている生徒はたくさんいるのに、他の生徒には行かずにひたすら俺なんですよ。なんて執念深いんだ、と思ってあるときに聞いたんです。『なんでそこまでして俺のところに来るんだ』って。そうしたらその先生が『お前のことは見捨てられない』って。
それを聞いて、『教師ってすげーな。この人すげー』って思ったんですよ。教師って一人の生徒のためにここまでできるんだ、って。それで自分は将来教師になるって決めたんです。こういう先生になるって」
そこからの行動は早かった。今まで全く授業にも出ず反抗的な態度を取り続けていた西村さんは、「高校に行きたいです。勉強を教えてください」と丸坊主にし、迷惑をかけた先生たちや育ててくれた母に土下座でお願いをしたのだ。遅刻も欠席も多く、授業も全く出ていなかったので勉強の理解も足りず、高校進学がかなり厳しい状況だった。しかし、周囲の助けで無事に高校へ入学したあとに目指したのは、保健体育の教員。
「今まで日本で、軟骨無形成症で体育教師になった人はいないんです。だったら一番最初になってやろうって。高校の体育の先生には『お前の体じゃ無理だよ!』って言われましたけどね。その言葉を聞いて、ますます『見てろよ』って奮起させられました(笑)」
ダンス大会で全国3位に
体育の教員免許の取得ができる大学へ入学し、母校で行う教育実習では生徒を巻き込みながら授業を進めるプランを立て、無事に教員免許を取得した。粗暴で問題児だった彼が、教育実習生として母校に戻ってきた。口では「お前は黒板に書けないから無理だろう」などと言いながら全面的にサポートをしてくれた先生たちの感慨は、いかばかりだっただろう。
「大学に入って、またすぐに野球を始めました。高校では、『ボールが頭に当たったら危険だから』とやめさせられてしまい、部活ではなく外のクラブチームで野球をしていたので。ほどなくして腰に大けがをして大学1年生の冬に大きな手術をすることになって。そのとき、子どもの頃からの主治医の先生に『もう辞めた方が良い』って言われたんです。本当に大好きでしょうがなかった野球を辞める時がついにきたなって泣きじゃくりましたが、やりきった感じもあり大学1年生で野球を卒業することにしたんです」
この手術後、大学2年生時の1年間は、体育教員に必要な実技の授業に参加できず、そのかわりに、課題レポートを多めに提出して単位取得していました。そして、ある授業を受講したときにまた運命の出会いが。
「たまたま担当の先生がダンスチームをやっていて『一緒に踊ろう』と誘われたんです。でも最初は、即断りました。だってグループで踊ったら絶対に迷惑をかけるから。『僕はソロで踊るからグループには参加しません』って言ったのに、この先生も中学の担任みたいに熱血で半ば引きずられるように参加して、どっぷりとチームに入り込んで最終的には全国3位までいったんですよ!」
どこにいても、何をしていても「ピンチ」と思うシーンになると、誰かが助けてくれるのだ。それは西村さんの放つ強力な陽のオーラと、人を引きつける魅力のせいだろう。その後、西村さんの強力な味方となる先生が現れた。その先生は「何がなんでも君を体育教師にしたい」と、宮城県の学校の就職口を見つけてきてくれたのだ。軟骨無形成症として初めて体育の教員免許を取得し、そして就職先も決まる。まさに夢をかなえる寸前だったが、なんと卒業式直前にとある事情でその内定が取り消されてしまった。
「夢をかなえるほんのちょっと手前で、夢が消えてしまって。きついですよね、いきなりやることが無くなるんだから。当時は実家にいたのでアルバイトをしたり、ダンサーとしてちょこちょこ活動していたんです。そんなある日、急にダンスのイベントの予定が流れてすっぽり空いてしまって。でも踊りたい気持ち満々だったから『何か踊れるイベントないかな』とインターネットで調べて、川崎のダンスイベント『チョイワルナイト』を見つけたんです。それが俺と、チョイワルナイトを主催していた『SOCIAL WORKEEERZ』との出合いです」
 2018年に、ダンス仲間のTOMOYA(左)、YU-Ri(右)とともに結成したアガイガウガ
2018年に、ダンス仲間のTOMOYA(左)、YU-Ri(右)とともに結成したアガイガウガ
SOCIAL WORKEEERZは「ダンスで福祉をデザインする」というコンセプトのダンスチーム。西村さんはそこに参加するとともに、創立者であり初代代表のTOMOYAさんとYU-Riさん3人組のダンスユニット「アガイガウガ」を結成し、一度は教職に進むために離れたダンスの道へ、強い力に導かれるように戻っていった。
「俺の夢は、障がいがあっても当たり前にスポーツをしたりダンスをできたりする世界を創ることなんですよ。障がいがあっても体を動かしたい、ダンスをやってみたいっていう人はいっぱいいます。でもダンスの教室まで誰かに連れてきてもらって、階段で車椅子を運んでもらわなければいけない、と考えると、『ダンスをする』以前に『ダンススタジオまで通う』ことがあまりにハードルが高くて諦めてしまいます。でもそこの道を開きたい。体が不自由な人がなんの気兼ねもなく楽しめる、完全バリアフリーなスタジオを作りたい。そんな夢をTOMOYAさんに伝えたら『SOCIAL WORKEEERZで、その夢を実現してほしい』と突然言ってくれたんですよ」
2021年春には2代目のSOCIAL WORKEEERZの代表に就任した。初代代表のTOMOYAさんは、今もダンサー、アガイガウガのメンバーとして活動している。2022年8月開催のチョイワルナイトを持って正式に継承される。幾度となく迫る試練を乗り越え、「自分の夢」が「SOCIAL WORKEEERZの夢」に形を変えた今、西村さんはCMで見せる大きな笑顔で仲間たちと未来へまい進している。

1994年、神奈川県生まれ。ダンスユニット・アガイガウガのメンバーとして、そしてSOCIAL WORKEEERZというダンスチームの2代目代表を務めるプロのダンサー。日本の軟骨無形成症患者として初めて保健体育の教員免許を取得する。小学校から野球に打ち込むも、大学1年生で大きなけがをして引退。NHK(Eテレ)『バリバ』『Eダンスアカデミー』、NHK『ひるまえほっと』『NHK WORLD』などに出演し、さまざまなイベントやメディアなどを通じて、障がい者がスポーツやダンスを楽しめるバリアフリーの実現を目指して活動をしている。
SOCIAL WORKEEERZオフィシャルサイト
http://social-workeeerz.com/
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
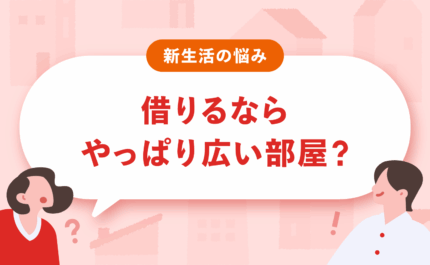 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
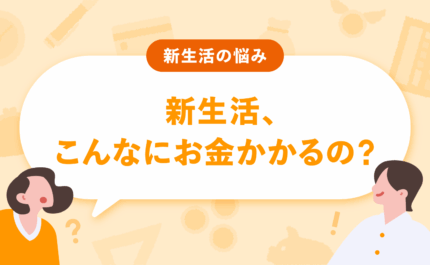 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
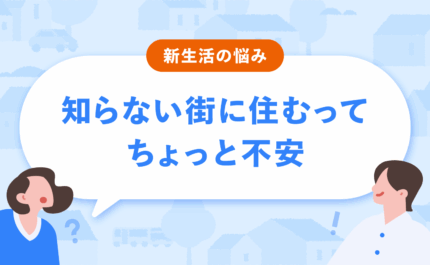 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
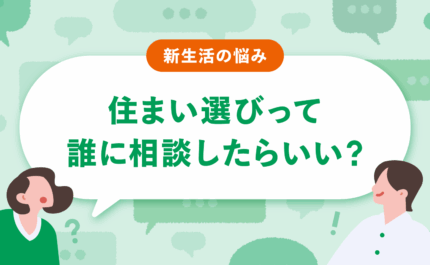 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。

















