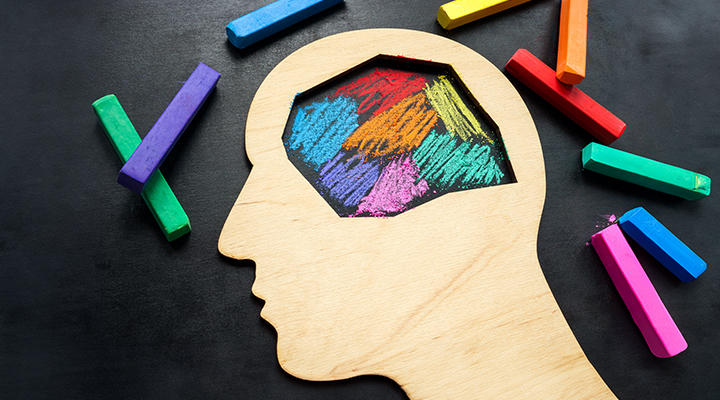ニューロダイバーシティとは? あらゆる特性の人が活躍できる社会を目指す取り組みと企業事例
現在「ダイバーシティ」という言葉はビジネスや教育などさまざまな文脈で用いられます。
ダイバーシティとは多様性を意味し、元々は、「ジェンダー、人種・民族、年齢」などの属性の多様性を指すことが多かった言葉です。近年では企業の経営戦略において、多様な価値観を尊重することでイノベーションの創出や生産性を高める「ダイバーシティ経営」の観点でも注目されるようになっています。
経済産業省も、国内企業の経営戦略としてのダイバーシティ経営の推進を後押しするために、さまざまな施策を打ち出しています。
この記事では、人間のより本質的な多様性に注目する「ニューロダイバーシティ」という考え方ついて解説します。
ニューロダイバーシティとは?
ニューロダイバーシティとは、Neuro(脳・神経)とDiversity(多様性)という言葉が組み合わさった造語であり、「脳や神経、それに由来する個人レベルでのさまざまな特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、それらの違いを社会の中で活かしていこう」という考え方です。
1990年代にオーストラリアの社会学者Judy Singer氏が提唱した言葉で、同氏は「すべての人間はそれぞれユニークな神経システムも持っている」と主張し、ネガティブに評価されがちな発達障がい(神経発達症)によって生じる現象も、そのうちの一つであると捉えました。
すなわち、ニューロダイバーシティとは、精神疾患の診断の有無にかかわらず、一人ひとりが持つ、個性・特性をお互いに尊重しようという考え方です。とはいえ、発達障がいの文脈で語られることが多かったため、以下では、発達障がいに注目して解説します。
2022年に文部科学省が行った調査(※1)によると、発達障がいの可能性がある児童生徒は小学生の約10.4%、中学生の約5.6%、高校生の約2.2%でした。2012年よりも、小中学生の割合は2.3ポイント増加しています。とはいえ、発達障がいとは生涯変わらない特性であり、時代とともにその有病率が増えることは基本的にありません。すなわち、このような数字が出ているのは、発達障がいの特性を受容できない教育現場が増えていることを示唆するとの指摘もあります。
一人ひとりの特性を理解し、その特性に合った教育を提供することで、本人の持つ可能性を引き出せる可能性もあります。
実際、最近の調査報告(※2)によると、発達障がいのある人が持つロジカルな思考や集中力、計算能力などは、データアナリティクスやサービス開発といったIT分野において適性がマッチする可能性が指摘されています。
※1 出典:文部科学省 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について
※2 参考:令和3年度産業経済研究委託費 イノベーション創出加速のためのデジタル分野における「ニューロダイバーシティ」の取組可能性に関する調査 令和4年3月(令和5年3月改訂)
発達障がいと主な特性・強み
発達障がいとは「脳機能の発達が関係する障がい」のことで、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、限局性学習症(学習障がい)、チック症、吃音などがあります。同じ発達障がいでも特性の現れ方が異なったり、いくつかの障がいを併せ持ったりすることもあります。
※3 出典:発達障害って、なんだろう? | 政府広報オンライン
そのため、特性は個別具体的ですが、共通項を一般化すると以下のようになります。(※3)また、指摘されている強みはすべての人が同様に持っているわけではなく、あくまでも可能性の一つであることに注意が必要です。
自閉スペクトラム症(ASD)
主な特性
- コミュニケーションの障害、対人関係・社会性の障がい、パターン化した行動、こだわり、興味・関心の偏り
- (アスペルガー症候群の場合)言語発達に比べ不器用
- (自閉症)言葉の発達の遅れ
先行研究で示唆された強み
- 細部への注意力が高く、情報処理と視覚に長けており、仕事で高い精度と技術的能力を発揮
- 論理思考に長けており、データに基づきボトムアップで考えることに長けている
- 集中力が高く、正確さを長時間持続できる
- 知識や専門技能を習得・維持する能力が高い
- 時間に正確で、献身的で、忠実なことが多い
注意欠如・多動症(ADHD)
主な特性
- 不注意(集中できない)
- 多動・多弁(じっとしていられない)
- 衝動的に行動する(考えるよりも先に動く)
先行研究で示唆された強み
- リスクを取り、新たな領域に挑戦することを好む
- 洞察力、創造的思考力、問題解決力が高い
- マルチタスクをこなし、環境や仕事上の要求の変化に対応する能力が高い
- 精神的な刺激を求め続け、プレッシャーのかかる状況でも極めて冷静に行動できる
- 刺激的な仕事に極度に高い集中力を発揮する
学習症(LD)
主な特性
「読む」「書く」「計算する」等の能力が、全体的な知的発達に比べて極端に苦手
先行研究で示唆された強み
- 脳が視覚処理に長けており、イメージで捉える傾向が強く、より多角的に物事を考えられる
- アイディアをつなげて全体像を把握する能力に長けており、データのパターンや傾向を見抜くこと、洞察力や問題解決能力に長けている
- 異なる分野の情報を組み合わせることに長けており、発明や独創的思考ができる
ニューロダイバーシティが注目される背景

ニューロダイバーシティが注目される背景には、大きく分けて2つの要素が関係しています。「企業の社会的責任の増大」という、いわばコンプライアンスの視点と、「産業構造変化の加速化」への対応という企業の根幹に関わる課題です。
企業の社会的責任の増大
ニューロダイバーシティが注目されている一つの理由は、企業の社会的責任の増大、すなわち、SDGsへの貢献です。
いうまでもなく、SDGsは2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい成果を目指す国際目標です。地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っており、その中にはもちろん発達障がいを持つ人たちも含まれます。しかし、ロイター社によると、「世界全体で推定7,000万人とも言われる自閉症のある人々のうち、約8割が無職もしくは著しく能力以下の仕事に従事している」とのことです。(※1)
発達障がいを持つ人の中には、相手の目を見て話すことや他の人との会話を積極的に進めることが不得手な方もいるため、従来の面接を中心にした採用手法では、彼らのポテンシャルや強みを図ることができず、採用から漏れやすくなっている点が考えられます。
日本に限定すると、障害者雇用促進法で定められた、障がい者の雇用率(法定雇用率)が年々上昇しており、この雇用率を達成するために、急増している発達障がいなどメンタル系の障がいを有する人材を雇用するノウハウを知りたいというニーズが高まっています。
産業構造変化の加速化
ニューロダイバーシティが注目されている背景のもう一つに産業構造の変化が挙げられます。日本社会に限らず、世界の産業のあらゆる分野にITが導入され、デジタル社会が加速するにつれて、イノベーションの創出が課題になっています。
IT人材の不足は喫緊の課題であり、日本では2060年までに生産年齢人口は約35%減少し、IT業界では2030年時点で需要に対して約79万人の人材が不足するという試算もあります。(※1)
この点、上述したように発達障がいのある人たちが持つ特性が、まさにIT分野でのさまざまな業務において 強みとなる場合があることが研究や実例によって分かってきています。
例えば、ニューロダイバーシティを導入し、先進的な取り組みを行ってきたのが高福祉国家のデンマークです。IT企業のスペシャリステルネは、2004年に自閉症のある人材を積極的に雇用するソフトウェアテストコンサルティング業を創業しました。自閉症を持つ求職者の中でも特にIT分野で優れた能力を発揮できる人材に焦点を当てた雇用プログラムを持つことで知られています。
また、企業が発達障がいのある人材を雇用し、ニューロダイバーシティなチームをつくることにも多くのメリットがあります。経営学を扱うアメリカの専門誌によると、「ニューロダイバースなチームはそうでないチームに比べ、約30%効率性が高く」、「障がいを持つ同僚の仲間、メンターとして行動するバディシステムを実装している組織では、収益性は16%、生産性は18%、顧客ロイヤリティは12%上昇している」というデータがあります。(※1)
こうした報告から、人材不足を解決し、生産性を向上するためにニューロダイバーシティが注目されていることが見えてきます。
※1 出典:発達障害って、なんだろう? | 政府広報オンライン
ニューロダイバーシティに取り組むべき理由と成功事例

企業がニューロダイバーシティに取り組むことが成長戦略といえる理由は主に3つあります。
- 人材獲得競争の優位性
- 生産性の向上・イノベーションへの貢献
- 社会的責任
ここでは、主に1番目の人材獲得競争の優位性にフォーカスし、国内外の成功事例についていくつか紹介します。(※1)
海外先進企業におけるニューロダイバーシティ活動への期待と成果
例えば、マイクロソフトでは自社の雇用需要を満たすことや社会的影響、インクルーシブな文化形成、プロダクトアクセシビリティ向上を期待し、ニューロダイバーシティ推進のためのプログラムを導入しました。結果として、従来の採用プロセスで不採用にしてしまっていた人材を獲得でき、マネージャー層にもポジティブな影響があったといいます。
また、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーでもマイクロソフトと同様の期待を抱いてニューロダイバーシティ活動を推進した結果、1次雇用者らの生産性は雇用半年後に48%増加し、2次雇用者らの生産性は雇用半年後には90~140%も増加したそうです。
日本企業の人材獲得成功事例
日本のある企業では、ゲームが好きな元フリーター・元ひきこもりの人材を積極採用し、訓練と合理的配慮を提供した結果、特に集中力や目標達成への意識が高い人材が活躍しているそうです。
ゲーム開発現場において不可欠なデバッグ(バグと呼ばれる間違いを発見し、不具合の原因を突き止めること)業務では、発注先のマイクロソフトのエンジニアも発見できなかった多数のバグを特定するスペシャリストも登場しているとのことです。
多様な人材が活躍できる社会の実現
障がいの有無に限らず、すべての人々に社会的活躍の機会があることは人々の幸せや社会の発展に寄与するとともに、経済成長にも貢献できます。そのためには、雇用する企業側が発達障がいなどの精神疾患を有する社員の特性を踏まえ、組織の心理的安全性を高め、イノベーションや生産性向上につながる取り組みを行うことが重要になるでしょう。
その際、思い込みや決め付けを持たず、柔軟なサポートや工夫が大切です。「できないこと」に目を向けるのではなく、本人が持つ「才能や能力」を活かせるポジションで採用するなら、会社と人材のWin-Winな関係を実現できる可能性が高まるでしょう。
障がいと向き合い、自分らしく生きる3人のストーリー
齊藤菜桜さんは、テレビ番組やファッションショー、雑誌などで活躍する“ダウン症モデル”です。母である由美さんと二人三脚で障がいがあっても夢を諦めない姿は、同世代の若者たちに多くの励みと勇気を与えています。菜桜さんが幼稚園に通うようになった時、最初は周りの子たちは「お世話してあげよう」としていたのに対し、由美さんは「菜桜ちゃんを応援してほしい」と伝えたとのこと。障がい者との関わりにおいて、じっくり話すことで双方に良い影響が及んだ好例と言えるでしょう。
猪狩ともかさんは、2018年に不慮の事故に遭い、脊髄損傷による両下肢麻痺と診断され、それ以降、車椅子生活を送りながらアイドル活動を続けています。インクルーシブな社会の実現に向けて私たち一人ひとりができることとして、猪狩さんは「生きづらさを抱える人が『こんなことに困っている、苦しい』と発信する時、“受容”まではしなくてもいいから“否定”しないことが大切」と言います。
吉藤オリィさんは不登校とひきこもりの経験を通じて、孤独感や劣等感、焦燥感を抱え続け来ました。しかし、「できないことは悪いことじゃない。重要なことはその価値を知ることなんだ」と語る彼は学校へ行きたいのに行けなかった体験から「分身があればいいのに」と考え、ロボットの研究を始めました。現在は自ら会社を立ち上げ、誰もが孤独を解消し、「適材適所社会」を目指して活動しています。
まとめ

ニューロダイバーシティは加速するデジタル社会の需要を満たすための人材供給に貢献するだけでなく、これまで少数派の特性ゆえに採用から漏れてしまっていた発達障がいなどの特性を有する人たちがポテンシャルを発揮する場所を提供する基盤になるはずです。企業だけでなく、私たち一人ひとりがこれまでネガティブにとらえられてきた精神疾患に対する見方を変化させることが求められています。
日経BP総合研究所主任研究員
1994年東京大学卒。1997年日経BP入社。バイテクノロジーの専門誌「日経バイオテク」、薬剤師向け専門誌「日経ドラッグインフォメーション」、医師向け専門誌「日経メディカル」などを経て2024年4月より現職。2004年にフルブライト奨学生として米国UCSFに留学。臨床倫理や終末期医療、脳科学に詳しく、文部科学省の科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会、ライフサイエンス委員会脳科学作業部会の委員なども務める。日経BPが2024年度に設立したニューロダイバーシティ&インクルージョン・フォーラムの仕掛け人。
多様な暮らし・人生を応援する
LIFULLのサービス
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」