あなたの“普通”がみんなにとっての“普通”、なんてない 。―「障害は世界を捉え直す視点」を掲げ活動する田中みゆきが語るアクセシビリティ―
「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、フリーのキュレーター/プロデューサーとして活動している田中みゆきさん。障害のある方と一緒に、多くのプロジェクトを手がけてきた田中さんに、今の社会に必要な「アクセシビリティ」について伺った。「多様であること」がある種ブームのように、無意識的に尊ばれている今だからこそ、真剣に考えるべき言葉だと思ったからだ。

「インクルーシブ」「多様性」「共生」……、さまざまな表現が現代社会の理想を彩るようになってきた。それらの言葉に込められた、それぞれの人間の思いもまた一様ではないかもしれないが、人々の多様なあり方が尊重される社会の空気は、醸成されてきていると言えるのかもしれない。
しかし、そのような空気だけができあがっても、社会は決して誰もが生きやすいようにはつくられていない。車椅子利用者の中には、出かける時に車椅子用のトイレがある場所を把握しなければ不安な人がほとんどだろうし、視覚に障害のある人が映画鑑賞をしたいと思っても、音声ガイドがない作品では見るのをためらってしまうだろう。あらためて、この社会の大部分は、“一般的な”体や感覚を持ったマジョリティのためにつくられているのだと実感する。
そこから弾かれた人は、どうすれば暮らしやすさを手に入れられるのか。
それを考えるキーワードのひとつに「アクセシビリティ」という言葉がある。「アクセシビリティ」は「利用しやすさ」や「近づきやすさ」という意味を持つ英単語で、そこから転じて、一般的には「さまざまな体や感覚の違いを持った人が、物事や情報にアクセスしやすくするために、伝え方を工夫すること」という意味合いで用いられている。
日本でも最近よく見かけるようになった言葉だが、我々は本当にこの言葉を理解できているのかを考えたい。本当の意味で誰もが暮らしやすい社会とは何なのだろうか。今、我々が考えるべき「アクセシビリティ」という言葉について、田中みゆきさんに伺った。
みんなバラバラでいい。盲学校で見た景色
「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、これまでさまざまな展覧会、イベントを手がけてきたフリーのキュレーター・プロデューサーの田中みゆきさんだが、初めから「障害」と関わった仕事をしてきたわけではなかった。大学卒業後は広告代理店で働いていたという田中さん。その後、仕事を辞めイギリスへデザインのキュレーションを学びに留学。帰国後に都内のデザイン展示施設「21_21 DESIGN SIGHT」でキュレーターとして働くようになったことが、「障害」と関わる契機となった。
「21_21 DESIGN SIGHTで一番最初に担当したのが『骨』展という展覧会でした。その準備期間の最中、オスカー・ピストリウスという南アフリカの両足義足の陸上選手が健常者を超える記録を出し、オリンピックに出場できるか否かが大きなニュースになっていました。私はそのピストリウスの走りを見て、義足で走る姿がとても美しいと思ったんです。それがきっかけで、展覧会ディレクターだった山中俊治さんと私は義足に人体の未来の骨としての可能性を見出し、『骨』展では義足ランナーの方と一緒にイベントを行ったりしました。それが障害との一番最初の接点でした」

人のオルタナティブなあり方としての義足。そこに未来の可能性を見たことが、田中さんが障害に興味を持つきっかけになった。その後、いくつかの文化芸術施設で働いた後、2015年に田中さんはフリーのキュレーターとして独立。独立を決めた背景には、日本科学未来館に勤めていた時に企画のリサーチで訪れた盲学校でのある出来事があった。
「盲学校で体育の授業を見学させてもらった時、手を上げる、膝をまげる、深呼吸するとか、そういうシンプルな体操をしていたんです。ただ、手を上げるといっても、目が見えないのでみんな手の上げ方がバラバラなんですね。もし目が見えていたら、みんなと同じように手を上げないと変に思われるかもしれないですけど、そこはみんなバラバラで良しとされる空間だったんです。みんなが『手を上げる』ことを好きなように解釈しているその風景に、とても感動しました。私が企画を立てる時は、あんな風景をつくりたいなと今でも思い出します」
フリーのキュレーターとなってからは、視覚に障害のある人もない人も一緒にダンスを鑑賞することで、ダンスの多様なあり方を問うワークショップ『音で観るダンスのワークインプログレス』や、ろう者と聴者が互いに共有できる“視覚言語”をさぐりながら演劇をつくる『視覚言語がつくる演劇のことば』など、田中さんは精力的にさまざまな展覧会やイベントを企画・プロデュース。社会から除外されてきた、あるいはいまだ拾い上げられないマイノリティの視線を独自の切り口で発信してきた。
 『音で観るダンスのワークインプログレス』複数の視点からつくられたオーディオディスクリプション(視覚に障害がある人に視覚情報を補助するナレーション)をつかって、目の見える人と見えない人がダンスを鑑賞する。上演後に観客が感じたものを共有する時間も含めたイベントとなっている。撮影:西野正将 主催:神奈川芸術劇場
『音で観るダンスのワークインプログレス』複数の視点からつくられたオーディオディスクリプション(視覚に障害がある人に視覚情報を補助するナレーション)をつかって、目の見える人と見えない人がダンスを鑑賞する。上演後に観客が感じたものを共有する時間も含めたイベントとなっている。撮影:西野正将 主催:神奈川芸術劇場
その場限りのアクセシビリティではなく、その先まで
ここで筆者の個人的な話で恐縮だが、先日車椅子利用者の方と公園にあった公共トイレに立ち寄る機会があった。そこには車椅子利用者をはじめ、小さな子ども連れやオストメイトの方など、あらゆる人々の利用に配慮した機能が備わった「誰でもトイレ」があったが、その方はそのトイレを見て、車椅子を転回するには少し狭い空間と、重度の身体障害のある方には不可欠な介助ベッドが備えられていないことを残念がった。その方にとっては、十分な“アクセシビリティ”がなかったのだ。
私にとっては「誰でもトイレ」と名付けられているだけで、そのトイレに対する根拠のない信頼があったが、実際に利用する当事者の声を聞いてその浅はかな自分の思考を恥じた。
アクセシビリティとは、何なのだろう。
筆者が体験した車椅子利用者と誰でもトイレの話をすると、田中さんは大きく頷きながらトイレにまつわるアクセシビリティの話をしてくれた。
「さまざまな人の利用に配慮したいわゆる『誰でもトイレ』や『ユニバーサルトイレ』がありますが、私はそれが“誰もが”使いやすいものになっているとは思っていません。たとえば目が見えない人がトイレを使う時、『誰でもトイレ』に案内しようとする人がいるんですよね。でも、『誰でもトイレ』にはオストメイトやベビーチェアなどいろいろな機能がありますが、トイレごとに配置や設置されているものが異なります。さらに、『誰でもトイレ』は普通の個室トイレより広いです。無駄に広い空間で、どこに何があるかを手探りで確認しなければならない。だから誰でもトイレは目が見えない人にとっては必ずしもアクセシブルではないんです。
それに大便器だと、流すボタンが各メーカーやトイレごとで設置されている場所が異なります。あるトイレでは横の壁についていたり、あるトイレでは便器の後ろについていたり。そのトイレ自体はユニバーサルな仕様のものでも、メーカーごとにデザインや配置が違っていたら意味がないんですよね。本当の意味でのアクセシブルなトイレ環境とは、マーケットの事情など関係なく、トイレのデザインや設備を統一することだと思います」

「たとえば最近は劇場で舞台の公演がある時に、手話通訳や音声ガイドをつける取り組みが増えてきていますが、それもその場だけそうしたガイドがあっても十分ではありません。その人がどうやって情報を得て劇場にたどり着いて、どうやって帰っていくのか。そこまでケアしなければ本当の意味でのアクセシブルな体験を提供できているとは言えないと思うんです」
アクセシビリティを考える時、我々は音声ガイドや手話通訳のような「手法」に目が行きがちだ。しかし重要なのは、その場限りでのアクセシビリティを考えるのではなく、その人の日々の生活、もっと言えば人生全体までを考慮すること。そこまで行き渡らなければ、アクセシブルとは言えないと田中さんは語る。
アメリカでの滞在調査で感じた、日本との違い
昨年、ニューヨーク大学・障害学センターの客員研究員として、半年間ニューヨークに滞在し、アメリカの芸術に関するアクセシビリティなどについて調査していた田中さん。田中さんはアメリカと日本における「個人」の捉え方の違いについて語ってくれた。その意識の違いはアクセシビリティにも深く関わってくるという。
「アメリカは個人主義の国なので、その人に障害があったとしてもまず“個人”であることが尊重されます。その人を障害者として見るのではなく、その個人の中に障害が要素としてあるという考え方をします。逆に日本では、いまだに属性で見られることが多いですよね。それは教育の問題でもあり、人権意識の問題でもあるのでなかなか根深いのですが、アクセシビリティもそれと無関係ではなくて、人権意識が反映されてしまうものだと思うんです」
インタビュー場所として我々が喋っていた喫茶店を見回しながら、田中さんは言葉を続ける。
「エイブリズム(Ableism)という、健常者を基準にした規範やそれにもとづいてモノやサービスをつくる考え方があります。たとえばこの喫茶店も、私たち健常者に向けてしかデザインされていない空間ですよね。通路も狭いし、座席も固定されていて、車椅子の方がここに来ることは想定されていません。やはり、健常者にとっての“当たり前”の意識でつくられている。これがこの社会の前提なんです」
エイブリズム、ゾッとする言葉だ。自分も知らぬ間に、決してそんなつもりはないのに、自分が持っている価値観を絶対的なものとして、持たざる誰かを無意識に差別しているような瞬間が確実にあったはずだ。その単語を聞いた時、アクセシビリティが抱える問題の根深さを思い知った。
アメリカでの調査は、そうした個人主義についてあらためて考える契機となったほか、コミュニティのあり方についても考えさせられた時間だったと田中さんは語る。
「アメリカに滞在中、障害当事者のコミュニティが仲間のためにつくるアクセシビリティに出会いました。当然ながら、当事者がつくるアクセシビリティは、当事者のことがすごく考えられているんです。
たとえば障害のある人たちのダンスグループが行う公演では、手話通訳と音声ガイドはまず当たり前のようについていて、それに加えてニューロダイバージェント(学習障害や自閉スペクトラム症など、脳や神経の発達の特性が異なる人)に向けたキットが配られていたんです。
そのキットの中には、何かを持っていないと落ち着かない人のために、手で握る用の柔らかいボールやトゲトゲした形のものが入っているほか、音や照明の刺激を敏感に感じすぎてしまう人のために、アイマスクや耳栓も入っていました。加えて、劇場内の座席の配置もすごく配慮されていたんですよね。一番前に車いすや盲導犬ユーザーのためのスペースが確保され、疲れやすい人のために、避難所のような静かなフロアからも公演を見ることができるようになっていました。
さらに感心したのは、公演の間の幕間の時間を長く設けていたことです。そうすることで、障害当事者たちが交流する時間になっていました。ただ公演を行うのではなく、コミュニティが交流する社会的なイベントとしても機能していたことに感動しました」
 アメリカ滞在時、ダンスグループの公演にて発達障害の人向けに配られた鑑賞キット
アメリカ滞在時、ダンスグループの公演にて発達障害の人向けに配られた鑑賞キット
田中さんによると、そうした障害当事者のコミュニティがコミュニティのために設計するアクセシビリティについては、当事者間でのフィードバックが盛んに行われているという。それを受けて、次回の公演の改善につなげていくのだ。
「当事者側が声を上げたり、改善の要望を出したりすることって、日本だと『あるだけでありがたい』となりがちで、あまり盛んには見られません。実際にそのアクセシビリティの質がどうなのか、本当に自分たちのことが考えられているのか、当事者側がもっと声を上げていかないと、日本でのアクセシビリティは進んでいかないと思います。どうしても私たち健常者はエイブリズムにまみれていて、気づけないことが多いので」
人権について考えることから始めてみよう
エイブリズムにまみれた状態であると言える健常者が、アクセシビリティを考えるうえで、そしてエイブリズムから少しでも抜け出すために大事なことは何なのだろうか。
田中さんは、「まずは人権について考えること」だという。
「『人間が本来得られる知る権利を保障すること』を指す『情報保障』という言葉がありますが、これはアクセシビリティの根底にある考え方です。そして、人間の尊厳に関わる基本的人権ともつながる言葉です。先ほどのトイレを例に挙げると、目が見えない人にとって、どこにボタンがあるかわからないトイレというのは、人権が侵害されていることと同じなんです。このようにアクセシビリティというのは、人間の尊厳に関わる話なんだということを、まず理解することが重要だと思います」

「あとは障害のない人たちは、障害のある人たちと実際に接することが重要だと思います。当事者との生の経験がない限り、自分の中のエイブリズムを実感することは難しいからです。当事者たちと一緒に過ごし、その人が今の社会における生活の中で直面するままならないシチュエーションをともにする。そしてそれがその人にとっては、毎日直面するものだということをあらためて考える。そうした経験から、アクセシビリティについての理解が深まっていくと思います」
田中さん自身も、アメリカから帰国後、福祉施設で働き始めた。キュレーターとして、これまでアートの側面から障害のある方と接する機会が多かった田中さんだったが、それだけでは関われないような、日常に関わる福祉の世界のことを知りたいと思い働き始めたという。
田中さんが働く福祉施設には、身体、発達、知的など障害の種類に関わらず、さまざまな人がいるそうだ。活動の中にはレクリエーションの時間も設けられており、そこでの経験がまた大切な気づきをもたらしてくれたと語る。
「本当にいろんな障害のある人が集まっていて、レクリエーションの時間にも医療的ケアやトイレの介助が必要だったりで、みんなが同じ場所に集まることすら難しいんですね。それに半分以上の人は言葉によるコミュニケーションが難しい。そうなると、みんなで楽しめるレクリエーションというもの自体が成り立ちづらいんです。
それだけいろいろな人が集まると、みんなで同時に何かひとつのことをやりましょうというのは無理があると実感するんです。それこそ最近よく耳にする言葉ですが、『インクルージョン』って何なのかと考えざるをえません。でも、別にそれでいいと思うんですよ。『インクルージョン』という言葉自体、マジョリティがマイノリティを包摂するようなニュアンスがあるのが気になります。そうではなく、みんなバラバラで、一人ひとりが欲することがそれぞれのやり方で満たされている状態をつくるべきではないか、と思うんです」
その言葉を聞いて、田中さんがかつて感銘を受けたという盲学校の体操の風景を想像した。
その風景を見たことがフリーとなるきっかけとなり、その後多くの仕事をしてきた田中さんが、今あらためてみんながバラバラな風景と対峙しているのは、とても運命的なものを感じるとともに、それこそが社会の理想のあり方だと、突きつけられているような気がしてくる。

取材を依頼した時に私が思い描いていた「アクセシビリティ」のイメージは、こういう障害のある人にはこういう取り組みが必要だ、というような「手法」としてのイメージだった。
しかし話を聞いていく中で、「アクセシビリティ」は、社会や人々が歴史の中でつくり上げてきた“自明”とされる価値観やシステム、加えて人権といった人間の尊厳に関わる部分を、あらためて考え直すことにつながる言葉なのだと考えを改めた。
「多様性」や「インクルーシブ」という言葉がホットワードになっている今だからこそ、表面的で形式的なアクセシビリティについて考えるのではなく、その言葉が存在する根本の理由をあらためて考えることが、我々には必要なのだ。
最後に、田中さんは既成概念に苦しむ人、あるいは自分の中の既成概念に気づいていない人に向けてのメッセージをくれた。

キュレーター/プロデューサー。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを通して表現の捉え方を障害当事者含む鑑賞者とともに再考する。最近の仕事に『音で観るダンスのワークインプログレス』、『オーディオゲームセンター』、『ルール?展』、展覧会『語りの複数性』など。オーディオディスクリプションやバリアフリー字幕の執筆も行っている。2022年7月から12月までACCのフェローシップを経てニューヨーク大学障害学センターの客員研究員としてニューヨークに滞在後、帰国。
https://miyukitanaka.me/
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
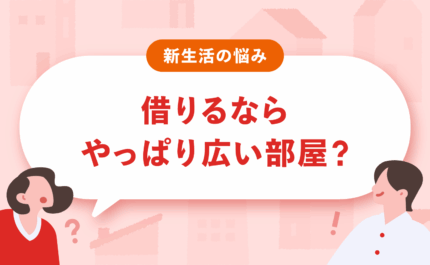 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
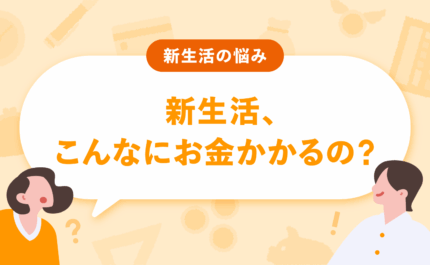 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
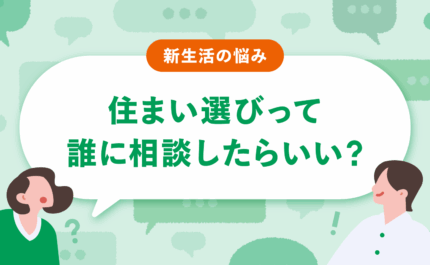 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
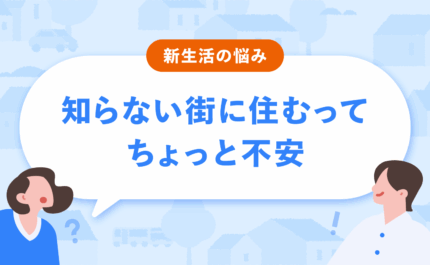 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。












