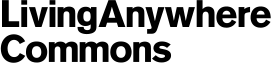家は「日常」、避難所は「非日常」、なんてない。

度重なる地震や豪雨、台風など多くの自然災害によって被害がもたらされている日本。災害時に被災者が長期間生活をするのが「避難所」であるが、その環境については他の国に比べて遅れをとっているという。LIFULL ArchiTech代表取締役を務める北川啓介と小池克典(※2024年1月現在の代表者は北川 啓介、幸田 泰尚)。二人が目指すのはインスタントハウスの開発・研究を通して、避難所のあり方を変えていくこと。そして住宅困窮者が安価で手軽に安心・安全な家を持てる世界に変えていくことだと語る。

日本の避難所は体育館や公民館などの公共施設の広いスペースを使用しているケースが一般的です。一時的とはいえ、仕切りもない空間で見ず知らずの人たちと雑魚寝をして、不安な生活を送ることは肉体的にも精神的にも苦しいもの。また、その環境が災害時の避難所生活をより非日常にしてしまっていると考えられる。そんな“避難所のあり方”を変え、日常と災害時の非日常をシームレスにするために生まれたのが、わずか数時間でどこにでも設置でき、快適に過ごすことができるインスタントハウスである。インスタントハウスはどのようにして生まれ、これからの“避難所のあり方”そして人々の“住環境”にどのような影響を与えていくのだろうか。
避難所で言われた一言がインスタントハウス誕生のきっかけとなった
-インスタントハウスが生まれた経緯についてお話を伺う。

北川:2011年の東日本大震災の影響がとても大きいです。私は2001年から大学の教員として建築の設計や教育・研究をしており、いわゆる建築家に憧れ、格好良い建築物や大きな建築物を求めて仕事に従事してきました。そうした中、2011年の震災が起きて1カ月もたっていないときに、調査のために宮城県のさまざまな避難所に足を運びました。それが大きな転機となりました。
避難所になっていた石巻中学校の体育館で、小学3年生と4年生の男の子2人から「大学の先生だったら、来週か来月にでも、すぐに仮設住宅を建ててよ」と言われたんです。調査に行ったときは4月の上旬で、宮城の避難所ではまだ気温がとても寒く、何百人もの避難している方々が冷蔵庫みたいなところでみんな身を寄せている状況だったこともあり、とてもハッとさせられました。
そのあと名古屋に戻ってきて、翌日いつも通りに大学で建築設計の講義をしていたのですが、私自身ため息が出ちゃいまして。黒板を使って木造の伝統住宅のディテールや工法をお話しするよりも、やらなきゃいけないことがあるのになと。それからはもっと簡便で、早く、どんな人でも実現させることができる家を提供しようと志すようになりました。それでインスタントハウスの研究を始めました。
空気を多く含むと軽くなるだけでなく、断熱性も上がり、耳栓のように吸音性も高くなる特徴があるため、研究は空気を多く含んだ素材を活用することから始めました。風船や固まるシャボン玉、食器洗いなどでも使用する軟質スポンジなどの素材から始め、想定外の素材や今まで見たことのないつくり方など、とにかく思いついたらなんでも試行錯誤しました。約5年間の失敗の連続からわかってきた知見の数々をもとに、今のインスタントハウスの原型ができました。2016年の10月には、大学の運動場にて、建築構造の先生、伝統工法の大工さん、素材メーカーの技術者、吹き付けの職人さん、研究室の学生、みんなが見守る中、インスタントハウスの1回目の試験を行いました。試験前は、本当にうまくいくのかと、私以外のみんながまさにため息交じりで半信半疑だったのですが、試験は思いの外うまくいき、形ができ始めて完成したときには、そこにいる全員が大興奮して喜び合いました。眼前に未来がパーッと広がった瞬間でした。

-LIFULLがインスタントハウスを取り扱う理由について伺う。
小池:私はもともとLIFULLで「LivingAnywhere」というプロジェクトを推進していました。文字通りどこでも暮らせる社会、自由な生き方を目指すことを掲げており、現在は「LivingAnywhere Commons」という、「LivingAnywhere」を実践することを目的としたコミュニティ・拠点づくりに注力するとともに「LivingAnywhere」の世界観をかなえられるプロダクトやスタートアップの発掘なども行っています。その一環で、あるときたまたま、名古屋工業大学の北川先生のYouTubeチャンネルを見つけて、産官学連携センターがつくっていた「膨らむ家」が紹介されているのを見たのがきっかけです。漫画の世界に出てきそうな家を本当に形にしようとしている人がいることに純粋に興味を持ち、メールのフォームから問い合わせをしたのです。
その後、この技術に関して先生と話し合いをしていく中で、世界中の住宅困窮者の課題に対してインスタントハウスを通じて「快適で、誰もが手に入れられる価格の住宅を提供することで解消していきたい」とおっしゃった先生のビジョンに我々としてもすごく共感をし、そのビジョンをかなえるために、LIFULLの事業としてスタートさせました。
どこにでも住環境ができるということ自体が新しい価値発見につながる
-事業開始から1年。 現在に至るまでの成果、そして新たな発見とは。

小池:現在までに北海道から九州までの各地に25棟ぐらい建てさせていただきました。研究開発を進めていく中でアウトドアでの活用に適していることがわかってきて、グランピングやアウトドアの事業者さまに導入いただく機会が増えています。群馬県にある無人駅の土合に直結するDOAI VILLAGEにもインスタントハウスを設置させていただき、グランピング場としてたくさんの方に利用していただいています。また、グランピング場の利用者が増えるだけでなく、周辺地域を観光する人も増えたため地域の経済活動が活発にもなり、地方創生の一環にもなっています。
北川:インスタントハウスの中の住環境面で大きな発見がありましたね。インスタントハウスの設置後、私たちも時々現地に行って利用状況を確認するのですが、2021年の正月過ぎに何十年ぶりかの大雪があったときは北海道や岩手県や群馬県でインスタントハウスがまるまる埋まってしまうほどでした。そうした中、マイナス15℃の屋外環境にもかかわらず、驚いたことに、インスタントハウスの中では小さいホットカーペットやオイルヒーターを置くだけで、だいたい20℃台後半まで暖かくなり、みんなTシャツで過ごせる環境になっていました。いわゆる極寒の環境下でも不自由なく、気軽に、もう肌身で暖を感じていただけて、今までは「安心・安全を守るための建築」と考えていたものが、「楽しむための建築」という新しい体験価値を提供できたことを実感しました。
– 新たな用途の開発で意識していることとは
小池:安心、快適、素早く、安いを開発の際の共通項として私たちは考えています。「誰にでも手に入る」素材をベースにしながら、さまざまなかなえたい住環境を建築技術面で解決していくことを意識しています。
例えば、インスタントハウスの建物の中には構造上、2つの空気穴があって、重力換気でずっと空気が流れるようにしているんですね。昨今のコロナ禍で、従来の換気の方法だとすると、換気装置や装置を支える柱が必要になりますが、それだと当然コストが上がってしまうんですよね。コストの増加を建築技術のちょっとした簡便な仕組みで解決するように私たちはすごく知恵を絞っています。その結果が安価に快適なものを提供していくことにつながると考えています。
北川:新たな用途の研究開発にあたっては利用者の声やマーケットをとても大事にしています。ビジネス的な意味のマーケットである「市場」ではなく、利用者のお一人お一人からいただく「ニーズ」ですね。ニーズに合わせて、いわば利用者のDIY感覚で形や大きさや構成を変えることができるのがインスタントハウスの最大の特徴の一つなので、私たち主導でこんないいものつくりましたよ、と出すのではなく、利用者の声に耳を傾けて、そのニーズに合わせた研究開発を何度も続けています。この1年は常にそのニーズを反映していくことを集中的に行ってきました。
日本から世界へ、誰もが自分たちの手で簡単に安心な住居をつくっていける世の中に。
-インスタントハウスを通じて今後実現していきたい未来とは。
小池:この1年を通して自信を持てるプロダクトができてきたので、次は海外を目指しております。海外ではウイグルやミャンマーなどをはじめ、難民の課題などが多くあります。また、世界では経済格差が広がっており、コロナ禍で仕事を失いホームレスも増えている状況の中で、インスタントハウスを通じて社会貢献ができるのではないか、と考えています。実は北川先生のもとには難民支援をしている政府機関や国際機関から避難所に対する支援のお問い合わせがあったり、国会でも取り上げていただいたりと、社会的な反響もすでにあるんですよ。
今後、海外を目指すにあたり私たちがクリアするべき点は2つあります。一つは「オフグリッド化の実現」です。「オフグリッド」とはいわゆる電気やガス、水道などのライフラインをつないでいない環境のことで、難民キャンプなどの衛生的にも防犯的にも快適ではない環境下でも、安心・安全な住環境が提供できる可能性がインスタントハウスには十二分にあると考えているので、まずこれをかなえていきたいです。
もう一つは、「生分解性素材」の開発です。テントの場合、化学物質のウレタンからつくられているものが多く、難民の方に大量に供給したのち、不要になったときには処分する必要があるので、テント自体が最終的に自然に返る素材であることが非常に大切だと考えています。なので、素材の開発のところから新しいプロダクトにチャレンジをしています。もっというと素材の開発さえできれば、国際機関などが安心して支援してくれる可能性が出てきて、安価に提供可能になるので、ぜひ実現していきたいです。
北川:インスタントハウスはオフグリッドかつ、どこにでも建てられる気軽さから、非日常である発災後の簡易住宅や避難所にも活用していくことができると考えています。日本の避難所は日常とかけ離れており、寝ると食べるの繰り返しで、肉体的にも精神的にも苦しくなる環境が多いです。2016年の熊本地震の直後に避難所を訪れたときも、避難所のあり方に大きな改善はありませんでした。いつもの日常と災害が起きてしまった非日常がシームレスにつながり、災害時でも安心して普段通りの生活が送れることはすごく大事だと思いますので、インスタントハウスを通じて日本の避難所のあり方をより良い住環境へと変えていきたいです。また、オフグリッドや素材開発、安価に提供することが実現していけると、最終的には私たちがいなくてもインスタントハウスが世界中にできてくる世界にもなるのかなと考えています。世界中の国や地域の現地の皆さんが、自分たちの手で自分たちの家をつくっていける簡便なつくり方を世界に広めていくことで、私が一番最初に考えていたビジョンである「住宅困窮者みんなが家を持つ世界」を実現できるように活動を続けていきます。
小池:「まずはやってみる」のがすごく大切で、やり続けていくと、想像したことが形になり、それを繰り返していき、また新たな発想がどんどん生まれてきます。北川先生がまさにそうで。東日本大震災のときにハッとさせられたのをきっかけにすぐに動きだして今に至るまでにいろんなチャレンジをしてきたと思います。なので、「しなきゃ、なんてない」このマインドセットがすごく大切で、「まずやってみよう」と、トライをしてほしいですね。私たちもトライを続けています。論理で語るだけでなく現場に赴き自身で施工もをしたりもします。これからも形にすることへのトライをし続けていきたいなと思っています。

北川啓介(左):
名古屋工業大学大学院工学研究科 社会工学専攻 建築・デザイン分野
高度防災工学センター 教授
1974年愛知県生まれ。1999年ニューヨークのReiser+Umemoto建築設計事務所にて建築設計に従事。2001年名古屋工業大学大学院工学研究科博士後期課程修了、博士(工学)。同大学助手、同大学大学院講師、准教授、米国プリンストン大学客員研究員を経て、2018年から現職。約20年の国内外での建築設計や建築教育の経験を経て、知財をもとにした未来志向の建築や都市を考案し、実用化した上での事業化を推進。建築構造物領域のプロフェッショナルであり、インスタントハウス技術の考案者。受賞歴に科学技術分野の文部科学大臣表彰等。
小池克典(右):
株式会社LIFULL地方創生推進部
LivingAnywhere Commons事業責任者
1983年栃木県生まれ。株式会社LIFULLに入社し、LIFULL HOME'Sの広告営業部門で営業、マネジメント、新部署の立ち上げや新規事業開発を担当。現在は場所の制約に縛られないライフスタイルの実現と地域の関係人口を生み出すことを目的とした定額多拠点サービス「LivingAnywhere Commons」の推進を通じて地域活性、行政連携、テクノロジー開発、スタートアップ支援などを行う。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/02/25なぜ、災害時にデマが起きるのか。│防災心理学・木村玲欧教授「善意のリポスト・転送が、助かる命を奪うかもしれない」
2025/02/25なぜ、災害時にデマが起きるのか。│防災心理学・木村玲欧教授「善意のリポスト・転送が、助かる命を奪うかもしれない」災害時のデマが引き起こすリスクについて詳しく解説しています。感情を揺さぶる巧妙なデマが増加する中、情報の真偽を確認し、防災に備えることの重要性を兵庫県立大学の木村玲欧教授が語ります。災害時に適切な情報活用法を知り、デマ拡散による危険を防ぐ対策を紹介しています。
-
 2023/02/28私の価値観を会社に乗っ取られないために ―『魂の退社 会社を辞めるということ。』を読む―
2023/02/28私の価値観を会社に乗っ取られないために ―『魂の退社 会社を辞めるということ。』を読む―日常の中で何気なく思ってしまう「できない」「しなきゃ」を、映画・本・音楽などを通して見つめ直す。今回は『魂の退社 会社を辞めるということ。』(稲垣えみ子・東洋経済新報社)から、会社と働くことについて考えます。
-
 2024/09/30
2024/09/30 特別な手法で営業しなきゃ、なんてない。LIFULL HOME'S 営業 マネジャー 加藤 直
特別な手法で営業しなきゃ、なんてない。LIFULL HOME'S 営業 マネジャー 加藤 直ソーシャルエンタープライズとして事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLには、業界の常識を変えたい、世の中に新しい仕組みをつくりたい、という高い志をもつ同志たちが集まっています。LIFULLの描く未来の実現や個人が解決したい社会課題への取り組みなど、多様なLIFULLメンバーのこれまでの「挑戦」と「これから実現したい未来」を聞く、シリーズ「LIFULL革進のリーダー」。今回はLIFULL HOME'S事業本部 営業 マネジャーの加藤 直に話を聞きます。
-
 2023/06/13車椅子だから“しょうがない”、なんてない。―26歳で車椅子ユーザーに。織田友理子が語る障がい者の生きやすい社会への道筋―織田 友理子
2023/06/13車椅子だから“しょうがない”、なんてない。―26歳で車椅子ユーザーに。織田友理子が語る障がい者の生きやすい社会への道筋―織田 友理子車椅子で行くことができるエリア・スポットが表示されるバリアフリーマップアプリ「WheeLog!」を手掛ける織田友理子さん。進行性の病気が原因で26歳の時から車椅子での生活を続けている。重度の身体障がい者として日常生活は全介助を受けながら、同じ車椅子ユーザーや障がい者、マイノリティーのための活動を行う織田さんの原動力を取材した。
-
 2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント
2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。