【寄稿】友達がほしくて「いい人」を演じていたら、心が疲れていることに気がついた|少年B
ライターの少年Bさんに、かつてとらわれていた“しなきゃ”についてつづっていただきました。
幼少の頃から周囲とうまく付き合うことができず「嫌われ者だった」と語る少年Bさん。ある出来事をきっかけに「人から好かれるためには“いい人”にならなきゃ」と考え、コミュニケーションのあり方を見つめ直しました。
その結果、どんどん友達が増えていく一方、心は疲れていったそう。“しなきゃ”と“自分らしさ”の間で悩む方に届けたいエッセイです。

『わかり合える友達』がほしかった、嫌われ者のわたし
「空気が読めない」。
小さなころからずっとそう言われ続けてきた。
余計なことを言って場を凍りつかせたり、不用意に人を怒らせたり。「自分に正直であることが正しい」と思い込み、何でもそのまま口に出した。理屈や表面的な言葉を優先して、その裏にある感情にはとことん無頓着だった。当然、友達は少なかった。
世間の常識やマナーをまったく知らず、それでいて、興味関心のあることにだけはどんどん突き進んでいく。人と仲良くしたいのに、気づけばどんどん孤立していく。そんなわたしは周囲とくらべてちょっと、いや、かなり「ヘン」な子どもで「いじり」という名のいじめも受けていた。
高校生になって、自閉スペクトラム症(アスペルガー症候群)であることを親に告げられた。わたしがこうなのは病気のせいなんだ、わたしが悪いわけじゃないんだと、責任の所在を病気に押し付けることができ、内心ほっとしたのを覚えている。
「免罪符」を手に入れた当時のわたしは「病気なんだから、空気を読むことなんてできない。できなくて当たり前なんだから、みんな配慮してほしい」と本気で思っていた。
“嫌われ者”の自分がイヤで、なんとか居場所を作ろうと「この人なら分かってくれる」と思う人が見つかれば、関係性をつなぎ、連帯することで孤独を避けようと考えた。しかし、正直であることが「真摯」だと思い込んでいたわたしは、すぐに自分の感情をすべて表に出し、結果、相手に拒否されてしまう。
「自分がこれだけしているのだから、相手も返してくれるはずだ」。そんな期待は失望に、そして怒りに変わってゆく。自分と他者の望むものは、同じではないということに気づかず、ごく少数の友達が、さらに消えていく。
自己と他者の境界線が曖昧で「友達」という存在に固執し、スライムのようにドロドロと他者にまとわりつき、「ヒトツニナロウヨ……」と同化しようとする。まさにホラー映画の一幕のような存在。それがかつてのわたしだった。
嫌われたくないから“いい人”でいなきゃと、と思い込んだ
社会人になり、20代後半で介護業界から建築業界に転職。30歳のとき、とある建築会社に出向することになった。
超がつくほどの体育会だったその会社は、上下関係が厳しく、業界に入りたての自分は周囲から当然のように「下」に見られていた。理不尽な言動や、半ば、いや完全にいじめのような扱いは日常茶飯事。今よりずっと太っていたこともあり、体型をいじられることも多かった。
30歳になっても相変わらず「自分なりの真摯さ」でコミュニケーションをとっていたわたしは、同僚からの「いじりは愛情」という言葉を真に受けて、空気を読まずに上司をいじり返したり、明らかな罵倒に対して同じくらい罵倒仕返したりし、最終的には半ばクビのようなかたちで会社を追われた。
同時期に、SNSで仲のよかった人ともトラブルになり、会社でもネットでもひたすら悪口を言われる日々に、心に余裕のなかったわたしはとにかく荒れていた。
ただ唯一幸運だったのは、当時のわたしはSNSを通じてこれまでと異なる人間関係を少しずつ築けており、親しくしてくれる人もできていたことだった。「こんな状況でも仲良くしてくれるこの人たちを失望させたくない」。その時はじめて、冷静に「自分」を振り返ってみようと思えた。
元同僚や仲違いした友人の言動を反面教師に、わたしは「嫌われ者」のままでいいのだろうか? もしかしたらこれは、長年嫌だった“自分”から生まれ変わるチャンスなのではないか? と考えた。
「ああいう人間にはなりたくない」という人物像は見えたけど、じゃあ、わたしは一体どういう人になりたいんだろう。これまで出会った「好きな人」のことを思い浮かべて考えた結果が“いい人”になることだった。
“いい人”になったら友達が増えた。ただ、心はどんどん疲弊していった
それから私は、言葉に含まれた「感情」や「意図」について考えるようになった。自分の発した言葉が相手にどのように伝わるか。逆に、相手から発せられた言葉にどんな意味が込められているのか。
すると、相手から発せられた一見失礼と感じる言葉に「悪意がない」ケースがあると気づいた。これまでは「言葉」をそのまま受け取り、脊髄反射で反発したり、怒ったりしていたが、それをやめ、相手の性格や言葉に合わせて「相手が望みそうな」反応を返すようにした。
こういった小さな努力の積み重ねで驚くほど人間関係は円滑になり、わずか2年ほどで、SNSはもちろんリアルでも友達が一気に増えた。コミュニティの中心にいることが増え、周囲からは「いい人だね」と言われるようになった。あんなに嫌われ者だったこのわたしが、だ。
「友達がほしい」とずっと願っていたわたしにとって、こんなにうれしいことはない。それなのに、だんだんと“いい人”であることに疲れている自分がいた。
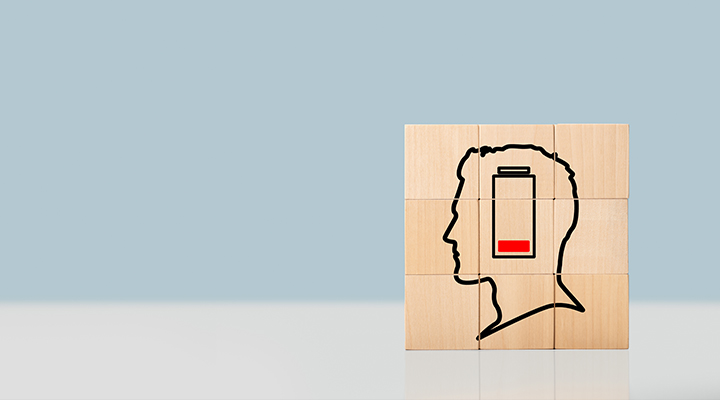
わたしがしていたのは、あくまでも“いい人に見える振る舞い”であり、空気が読めるようになったわけではない。すべてのコミュニケーションは相手の心を推察して「当てに行く」ことが必要になる。対面なら表情や口調である程度は何とかなるが、SNSなど文字ベースのコミュニケーションになると、とにかく精神の疲弊がすごい。いつしか、わたしのメンタルは大根おろしのように、ゴリゴリと削られていった。
それから、コミュニケーションには「ここまでは許すけど、ここからは嫌だ」というラインがある。もともとコミュニケーションが下手だったわたしには、「嫌だ」と思っても相手を不快にさせないように伝えるのが難しかった。
笑顔でやんわりとニュアンスを含ませて伝えても、その“ライン”が見えない人には伝わらない。そもそも敏感に察してくれるような人なら、最初からラインは踏み越えてこないよな、と気づいたのは最近のことだ。
結局「嫌がっていないから、これでいいんだ」と相手に思わせてしまったまま、状況はまったく変わらず、気づいたら精神がすり減っていた。
でも、“いい人”を演じてできた友達が離れてしまうのは怖かったし「この人、嫌だから“切ろう”」とも思えなかった。だって“切られるつらさ”は、誰より自分がいちばんよく知っていたから。
わたしに必要だったのは「人間関係に執着しすぎないこと」だった
「嫌われたくないから、いい人であり続ける」という考え方が大きく変わったきっかけは、30代のはじめに訪れたある友人とのちょっとしたトラブルだった。
その人とは、しょっちゅう2人で飲みに行き、気心知れた人にしか話さない「自分の大切な価値観」を打ち明けたり、深い悩みを相談していた。相手はどう思っていたのかわからないが、少なくとも自分は親友だと思っていたし、“いい人”になってから初めて背中のチャックを下ろした人間でもあった。
しかし彼が荒れていた時期に、どうしても許せない一言を言われてしまった。わたしの表面だけを見ての発言であれば「まぁそうも見えるよな」と思える、本当に何気ない一言。だけど、自分の本心を、どうしようもない弱点をさらけ出した相手には言われたくない、あまりにも重く、鋭い一言だった。
「……昼間から悪いお酒になってるよ。落ち着いて」自分としては、精一杯の落としどころのつもりだった。彼は今酔っているようだし、仕方がない。普段の彼とは違うんだ。そう、自分を無理やり納得させようとした。しかし、それに対して彼は言った。
「酔ってないし! ちょっと飲んでるだけでそういう風に言うんじゃねぇよ!」
その瞬間、わたしは気づいた。あれだけ仲良くしていても、どれだけ深いところまで自分の心の内を見せていても、しょせん他人は他人。結局わかり合うことなんてできないんだ。
学生時代からずっと無理だとわかっていたはずなのに、それでもあきらめきれなかった「他者と分かり合いたい」という思いを、その時ようやく手放すことができたのだった。そうして、彼とそっと縁を切った。
「あきらめる」というと、ネガティブに聞こえるかもしれない。でも「周囲に期待しすぎない」「執着をしないと決めた」というとニュアンスが変わって聞こえるだろう。期待をするから裏切られる。執着をするから怖さが生まれるのだ。
幸いなことに、この2年で友達もたくさんできた。ひとりに強く依存するんじゃなくて、多くの人にちょっとずつ体重をかければいい。1/1に見捨てられたら恐怖でしかないが、もしも1/50や1/100であれば、そこまで恐れることもないはずだ。……たぶん。
それに、一方がものすごく我慢をする関係は健全じゃない。友達を選ぶ権利は、相手にもあるけど、自分にだってあるのだ。これまでは「選ばれるため」に一生懸命がんばってきた。でも、残りの人生は、お互いに「選んで選ばれて」対等な関係で友達を作っていけばいいんじゃないか。
“嫌われ者”と“いい人”の中間地点にいる、今の自分が好きだ

「“いい人”でなきゃいけない」という縛りから解放され、じゃあ昔のように嫌われ者に戻ったか、と言われるとそうではない。ちょっと前のわたしを知る友達には「変わったね」と言われたこともあったけど、自分としては極端に入れすぎていたギアを、ちょっと戻したような感覚でいる。
昔よりは言動に気を遣うようになったけど、言いたいことは無理に飲みこまず、自己主張もするし、自分の意志を優先させるようになった。「無理して我慢をし続けるぐらいなら、最悪嫌われてもいいかな」と、カジュアルに人間関係を考えられるようになったのは、ちょっとした成長なのかもしれない。
思うまま口に出して嫌われていた自分と、好かれたいあまりに人に合わせてばかりで疲れていた自分。両極端に生きてきたけど、今はその中間でフラットに人生を楽しめているような気がする。
もちろん、自分に正直に生きるのも、人に合わせて生きるのも、どちらも悪いことでは決してない。でも、人には自分に合った生き方があるはずだ。わたしにとっては、どちらも難しく、中間がちょうどよかった、というだけのこと。
これからギアを上げるのか、それとも下げるのか。まだもうちょっと微調整が必要かもしれないけど、だいたいこのへんがちょうどいいのかもしれないなぁ、なんて、この年になってようやく気づいてきた。だいぶ遠回りをしてしまったけど、わたしは適度にやさしくて適度にワガママな「今のわたし」が一番好きだ。
Profile
少年B
介護士から建築士を経てフリーライターに。文章を書くことが得意ですが、食べることと寝ることはもっと得意です。
Twitter @raira21
⇒⇒⇒「周りと同じ」の既成概念にとらわれない、他のストーリーも読んでみる⇒⇒⇒
編集協力:はてな編集部
多様な暮らし・人生を応援する
LIFULLのサービス
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
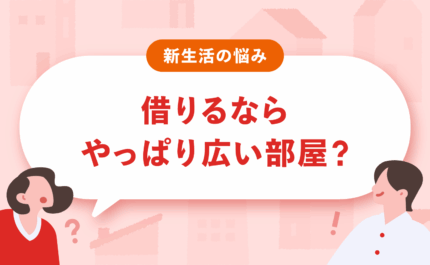 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
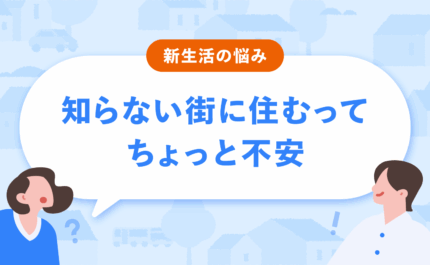 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
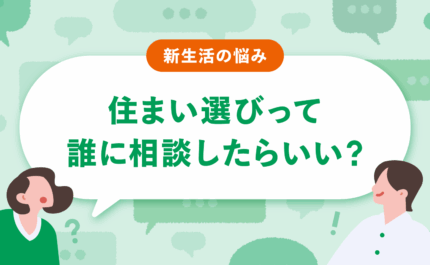 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
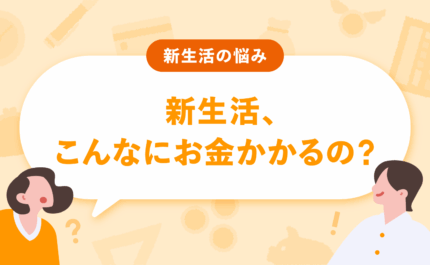 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」













