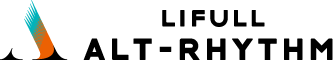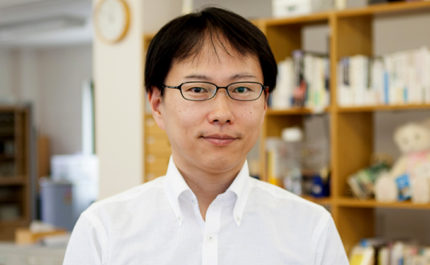好きという気持ちがなければ一流にはなれない、なんてない。
「好きを仕事に」という理想を掲げる人は多いが、本当に好きなことだけで成功している人はごくわずかだ。置かれた場所でいかに自分らしい花を咲かせるか、というのが多くの人が向き合う現実であろう。清塚信也さんの場合も“好き”という気持ちが始まりだったわけではない。世界的ピアニストという地位を築くまでの軌跡について語ってもらった。

「好きこそものの上手なれ」とはよく聞く言葉だが、誰しもが好きなことだけで生きていけるわけではない。そもそも「好き」という思いがなければ成功することはできないのだろうか? 親に決められた過酷な環境の中でも自分らしさを見つけ出し、マルチかつ自由自在に活躍するピアニスト・清塚さんの場合はどうだったのだろうか。

ピアノは僕にとって
木と鉄の塊でしかない
幼い頃から数々のコンクールで入賞。音楽留学やピアノの大家と呼ばれる音楽家への師事を経て、現在は国内外を問わずマルチに活躍……。華々しい経歴だけを見ると、ピアノに対して深い愛情を持つのでは?という印象を受ける。だが「清塚さんにとってピアノとは?」と聞くと、「木と鉄の塊であり、楽器であり、ただの機械。僕はただこれを弾きこなすだけ」と淡々とした言葉が飛び出した。
5歳の頃から学業よりもピアノを優先する生活で、1日の練習時間はなんと12時間。過酷な状況にもかかわらずピアノを続けてこられた原動力は、底知れぬ恐怖だったという。
「とにかく母親と先生が怖かったんです。『音楽を楽しもうと思わなくていい』『ピアニストになれなかったら生きていなくていい』と言われ続けた恐怖が『練習しなきゃ』という脅迫観念になっていた。普通の子どもが好きって気持ちでやるくらいでは練習量が足りないのである意味正解だったのかもしれないけど、人間としてはいろんなものを失った気もします」
とはいえ年相応の男の子ならではの趣味もあった。そのひとつが野球だ。
「小学生の頃、西武ライオンズがすごく好きだったんです。試合だけはテレビで見させてもらっていたのですが、やっぱり自分でもやりたくて。当然、大反対されるから『なんて言えばやらせてくれるかな?』と子ども心ながらに考えて。で、『ボールを投げる時の最後に指で球を押し出す動きが、鍵盤を強く引く時のプラスになる』とうそをついて、無理やりやらせてもらっていました(笑)」
ピアノの上達に絡めれば許してもらえるし、褒められるというのは画期的な発見だ。しかし、どれだけ理由を考えてもゲームだけは却下されたという。大人からは「ゲームで遊んでいても実にならない」と言われたそうだが、清塚さんがゲームから受けた音楽的影響は大きい。
「ゲーム音楽も好きだったので、気晴らしにドラクエのテーマなどを耳コピして弾いていたのですが、そのことが今の作曲やアレンジ能力にすごく直結しているんですよね。特にロールプレイングゲームで遊んだことは物語に沿った曲が登場するため、劇伴(ドラマや映画などのBGM)の楽曲作りにも生かされています」
他者に届ける自己表現ができれば
手段はピアノじゃなくても構わない
どれだけつらく苦しい思いをしても、好きなものを見つけても、「ピアノ以外のことをやってみようと思ったことはない」と清塚さんは語る。その理由はなぜか?
「何をやるにしてもプロフェッショナルになりたかったんですよね。子どもの頃から音楽をやっていた分、ひとつの物事を追求することの大変さは身に染みて分かっていた。だから今さら新しいことを始めても幼少期から経験を積んでいる人には追いつけないだろうなって。そういった意味でも僕の場合はたまたまピアノと縁が深かったというだけ。ただ、僕はピアノという物ではなく表現することに重きを置いているので、自分の表現ができればその手段は正直何でもいいんです」
「表現に重きを置く」。表現者として欠かせない概念は、中学生になる頃には自然と芽生えていたものだったという。
「やっぱりすごくつらかったんですよね。音楽以外の世界を知らなかったので小さい頃からの思い出もないし、友達も作れない。練習は過酷だし毎日のようにけなされるし。だから音楽でそういう気持ちを誰かに表現したり、フラストレーションやストレスを発散したいという思いが出てきたんです」
人生初のコンクール落ちを経験し
初めて死ぬ気で頑張ろうと思った
ジレンマを感じながらも練習に没頭する毎日。そこへ追い打ちをかけるように、人生初にして最大の挫折が訪れる。
「中学1年生の時、初めてコンクールの予選で落ちたんです。それまでは必ず3位以内に入って賞を取っていたのに……。だからもう1年頑張ってコンクールに出て、同じような結果だったらピアノをやめようかなって」
女子の発育が格段に上がる小6~中1という期間は、同年代の男子ピアニストにとって一番不利な時期だという。たった1年にもかかわらず、身長も手の大きさも感情的な部分も大きく差をつけられてしまうからだ。来年はさらに差が開いてしまうかもしれないという絶望と不安。だが、その追い込まれた状況が清塚さんを覚醒の道へと導く。
「幼少期から人生の全てを捧げてきたピアノをやめるかもしれないわけですからね。これまでは親や先生に言われるがままに練習に打ち込んできたけれど、区切りというか自分自身を説得するためにも、初めて自分から死ぬ気で頑張ろうって思いました。あの頃は本当に狂気的な精神状態で。命を懸けるほどの練習も自分の意志だけではできなかったでしょうね」
1年後、同じコンクールで見事1位に輝くも「順位以上に、全力で努力したという事実が大きな糧となった」と清塚さんは語る。狂気的な努力は高校から始まった音楽学校生活でライバルたちに大きな差をつけただけでなく、その後の人生を決定づけるものにもなったからだ。この時に身につけた自信が、音楽家としての活動のワクを無限に広げる礎にもなっている。
「批判やジャッジされるということが何の意味ももたなくなり、プレッシャーも感じなくなりました。人間、振り切った努力をすると『やることを全力でやったんだから、何を言われても仕方ない』っていう開き直りができるようになる。おかげで中学の時に芽生えた『ピアノで他者に対しての自己表現をしたい』という思いを形にできるようになり、高校生になってからはオリジナルの曲を作るようにもなりました。自分が目指す表現をするためならタブーに挑戦することにも迷いはないし、それで批判されてもまったく怖いと思わないです」

全力で努力したという
自負があるから
タブーを打ち破るのも怖くない
伝統や作家へのリスペクトを重んじるクラシックという音楽には、いくつかのタブーが存在する。タブーとは簡単に言うと、作家への敬意がないとみなされる行為。例えば名だたる作家の曲と一緒に自作の曲をコンサートで演奏すること。これは作家と自分を同列に扱っていると解釈されるからだ。またコンサート中のMCも業界内ではタブー中のタブーである。演奏家は曲に込められた作家の思いや背景を音だけで表現しなければならないため、そこに言葉を用いることは批判につながるという。
「コンサートの演目を作る時に、ベートーベンと清塚の曲を並べるというのは非常におこがましいこと。作家に対するリスペクトがないとみなされるので、非常に嫌われる要因になるんです。MCもそう。僕らは『耳が聞こえなくなったベートーベンが絶望的な気持ちで遺書まで書いた時に作った曲です』というような背景を音で伝える美学を持っていなければいけないのに、僕は弾く前に『こういう曲です』って紹介してから弾き始める。昔クラシックを聴いていた貴族には音楽の教養や音感がたしなみとしてありましたが、現代の人全てにそれがあるとは限らない。何度も言いますが僕はピアノ自体ではなく他者に対する表現に重きを置いているので、音で相手の感情に訴えかけるだけでなく、分かりやすさも大事だと思っています。だからこそ音楽の専門知識がないお客さまにも曲の成り立ちなどの前提をMCで知ってもらって、心を開いた状態で聴いていただきたいんです」
既成概念を軽やかに飛び越える自由さと表現に対する真摯さ。そして培われた技術。多くの聴衆を魅了できるのも、これらのバランス感覚の妙であろう。古典と現在をつなぐというコンセプトで作られたアルバム「connect」にも、彼ならではの発想と遊び心が込められている。
「古い物語って『ダ・ヴィンチ・コード』のように新たな解釈ができるんです。音楽も同様でバッハやモーツァルト、ベートーベンらをよりミステリアスに、新事実のように語ったら面白いかなと。300年以上前に生まれた音楽を提示することってファッションと同じで、一周回ってカッコ良かったりする。意外性のある曲を選んだのもこだわりです。『本当は怖いモーツァルト』という都市伝説のような感じで、親しみをもって聴いていただけたらなと」
自分の意志で始めたわけでも、誰かに背中を押されたわけでもない。それでも己の力で道を切り開き、プロの表現者としての信念に従い突き進む。その道を見つける極意とは?

1982年、東京都生まれ。5歳よりクラシックピアノの英才教育を受ける。中村紘子氏、加藤伸佳氏、セルゲイ・ドレンスキー氏に師事。桐朋女子高等学校音楽科(共学)を首席で卒業後、モスクワ音楽院に留学。国内外のコンクールで数々の賞を受賞。知識とユーモアを交えた話術と繊細かつダイナミックな演奏で全国の聴衆を魅了し続け、年間100本以上の演奏活動を展開している。
人気ドラマ「のだめカンタービレ」(2006年)にて玉木宏氏演じる「千秋真一」、映画『神童』(07年)で松山ケンイチ氏演じる「ワオ」の吹き替え演奏を担当し脚光を浴びる。13年には映画『さよならドビュッシー』で岬洋介役として俳優デビューし、15年には映画『ポプラの秋』(主演:本田望結)でのメインテーマおよび劇伴音楽の作曲&演奏を手掛けた。
近年ではTBS系ドラマ「コウノドリ」(15年、17年、主演:綾野剛)でピアノテーマおよび監修を手掛けたほか、ライブハウスのマネージャー役でも出演。映画『新宿スワンⅡ』(17年、主演:綾野剛)、舞台「シラノ・ド・ベルジュラック」(18年、主演:吉田鋼太郎)で劇中音楽を担当するなど作曲家としても活動の幅を広げ、「Fantasy on Ice」(17年、18年)では世界的なフィギュアスケーター(ステファン・ランビエール、ジョニー・ウィアー、羽生結弦選手など)と共演。ほか、TVバラエティー番組やラジオ番組にも出演するなど、マルチピアニストとして活躍。
2018年12月12日、「connect」を発売。
公式サイト http://tristone.co.jp/kiyozuka/
みんなが読んでいる記事
-
 2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん
2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん「整形の綺麗な面だけじゃなく、汚い面も知った上で選択をしてほしい」と語るのは、自身が1,350万円(2023年4月時点)かけて美容整形を行った、整形アイドルの轟ちゃんだ。美容整形を選択する人が増える中で、彼女が考えていることとは?
-
 2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題
2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。
-
 2024/05/24
2024/05/24 “できない”、なんてない。―LIFULLのリーダーたち―LIFULL HOME'S事業本部FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群(キョウ イグン)
“できない”、なんてない。―LIFULLのリーダーたち―LIFULL HOME'S事業本部FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群(キョウ イグン)2024年4月1日、ソーシャルエンタープライズとして事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLは、チーム経営の強化を目的に、新たなCxOおよび事業CEO・責任者就任を発表しました。性別や国籍を問わない多様な顔ぶれで、代表取締役社長の伊東祐司が掲げた「チーム経営」を力強く推進していきます。 シリーズ「LIFULLのリーダーたち」、今回はFRIENDLY DOOR責任者の龔軼群(キョウ イグン)に話を聞きます。
-
 2019/05/24アイドルは自分らしく生きられない、なんてない。高橋 愛
2019/05/24アイドルは自分らしく生きられない、なんてない。高橋 愛「モーニング娘。」のメンバーとして、10代、20代を全力で駆け抜けてきた高橋愛さん。立ち止まったら抜かされ、スパートをかけても追いつけない厳しい世界で、彼女はどう自分軸を保ちながら戦ってきたのか。女優やモデルのみならず、ファッションアイコンとしての地位も築き上げたこれまでの軌跡を綴る。
-
 2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜
2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。