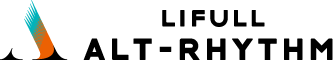アートと日常はかけ離れた存在、なんてない。
情報社会の発達により、誰もが情報を発信し、自己を表現することができるようになった現代。デジタルアートのような新たな芸術の分野も登場し、「作品」を生み出すクリエイターの属性は多様になってきた。しかし、アートに触れ、愛でるという行為は、日常からは少し離れた遠いもののように感じられることもあるのではないだろうか。
「人々が日々の中でアートに触れ、楽しむことができたら、社会はもっと豊かになる」そう話すのは、練馬区立美術館館長の秋元雄史さん。ベネッセの「直島アートプロジェクト」に携わったほか、金沢21世紀美術館や東京藝術大学大学美術館の館長を務め、人々とアートとの間をつないできた。「芸術や文化に触れることは不要不急だ」そんな言葉も聞こえてくる今の社会で、芸術文化を最前線で見てきた秋元さんは何を感じ、何を考えるのか。

未知のウイルスとの闘いの中、私たちの日常を支える店や施設の存続が危ぶまれてきたコロナ禍。美術館や博物館といった文化施設も一時は休館に追い込まれた。人々の芸術鑑賞の場が失われてしまっただけでなく、アーティストたちにとっても、その表現の機会が「不要不急」の対象として位置付けられてしまった現実があった。
しかし秋元さんは、「我慢」を強いられ、リアルなものに触れられない時期が続いたコロナ禍だからこそ、私たちの暮らしには芸術が必要だと改めて感じたという。人の心を動かすアートの力について、お話を伺った。
抱える悩みが多様な時代だからこそ、アートと向き合って対話を
子どもながらに「試されている」と感じた、父との強烈な記憶
東京藝術大学(以下、藝大)を卒業後、アートライターの仕事の傍ら作家として活動し、その後はベネッセのアートプロジェクトや美術館で人々にアートを届ける仕事をしてきた秋元さん。そんな秋元さんのアートとの出合いは、幼少期にさかのぼる。
秋元さんは、『鉄腕アトム』や『鉄人28号』など、数々の名作漫画に囲まれて少年時代を過ごした。主人公が自己矛盾や絶対悪との戦いを通して成長していくという、当時の日本の漫画に多くみられた正義感や人道をテーマにした漫画に触れて育った。
自身も漫画家になる夢を思い描いていた秋元さんだったが、時を同じくして衝撃的な芸術体験をしたという。
「小学6年生の時に親父が連れて行ってくれた近代絵画の展覧会での体験があまりに強烈で、よく覚えています。そこで目の当たりにしたのは、裸の男女が描かれた、とても生々しく肉感的な絵でした。ロートレックという、酒場やいわゆる娼婦宿、劇場などで繰り広げられる男女の擬似恋愛や人間模様を題材に描いていた画家の絵です。まさに生々しい人間模様なわけです。
子どもにとっては『見てはいけないものを見ている』という気持ちになりますよね。でも驚いたのは、隣にいる親父は至ってって何気なくその絵を鑑賞しているということ。『この絵、お前はどう思う?』と試されているような気がして戸惑いましたし、美術館という公の場でこんなものを見ていいのかという不思議な気持ちになりました」
しかしその衝撃的な出来事は、秋元さんにとって原点と言える体験でもあった。
「初めは困惑しましたが、奇妙で面白い体験だとも思いました。人間存在のエロスというか、重さというか、そういうものを美術作品から感じたわけです。今から振り返れば、ですが、当時はなんだかわからない。そういうものを親父が当たり前のように見せてくれるのがうれしかった。好奇心を刺激する場にたくさん連れて行ってもらったその時期が、僕にとって初めて美術への興味が湧いた時でした」

迷いの先にあった、現代アートへの共感
小学生や中学生の頃から、刺激的で自分の常識を超えてくるような芸術作品を見てきた秋元さん。芸術の道に進むと決め、高校卒業後も藝大受験の予備校に通い、入試に向けて必死に技術を磨いた。
鍛錬の末に藝大への入学をかなえるが、そこには受験生時代のような「超えるべき相手」がいない、誰も正解を教えてくれない世界での葛藤があった。
「受験生時代は、競争相手が目に見える場所にいて、彼らを上回るために磨くべき技術や目指すべき正解が明確でした。しかし藝大に入ると、技術や知識を前提に『自分が何を作り出すか』がテーマとなり、誰も正解は教えてくれません。自分を解放するために自由に美術を見ていたはずが、技術や知識を身につけた結果、美術が自分を縛るものになってしまっていた時期でした」
「頑張って。好きにやれよ」教授陣はそう言うが、「今の時代を生きている僕にとって、自分の表現とは何なんだ」と心がざわつく。どこにもたどり着けない、無限に広がる不安があった。そんな時期に秋元さんが通っていたのが、前衛的な現代アートを手がけるアーティストたちの発表の場であるギャラリーだった。そこで感じた同時代感が、秋元さんにとって現代アートがその後の人生の軸になるきっかけとなった。
「彼らは自分よりも少し上の世代でしたが、自分と同じように今の時代でどう生き抜き、どう表現するかを手探りしていて、同じ時代を生きているという感じがしました。時に、彼らのアイデアに共感できたし、自分も大いに悩んでいいんだと思いました。彼らとの出会いで、現代アートに自分の居場所が見えてきたんです」

作り手の喜びや苦悩が裏側にあるからこそ、アートは面白い
自分の表現スタイルを探し求めて思い悩み、同じ時代を生きるアーティストへの共感から居場所を見つけた秋元さん。作り手としての経験をもとに、これまでアートの面白さや奥深さを人々に伝えてきた。アートの魅力を生み出すもの、その要素の一つとして挙げるのが「集中」だ。
「作品に表現されるものは、アーティストの喜びや苦悩、そして言葉では表せないような感情です。さらに奥には、それぞれが置かれた境遇や時代背景があります。私たちと同じように、当然彼らも一人の人間としてそれぞれの人生を生きている。一つひとつのアート作品は、そんな彼らが極限まで集中した状態で生み出した結晶なのです」
これはスポーツにも通ずるところがあるという。
「オリンピックやワールドカップなどの大舞台で華々しく活躍するトップアスリートたち。彼らは鍛え抜かれた力によって極限的な状態で記録や技術を披露する。それは人間の通常の状態を超えたものです。我々はそれを見て驚き、そしてまだこんなにも人間には可能性があるのだと感心する。その時のアスリートが私たちに披露しているものは、芸術作品と通じる『何かを超えた」世界だと思うのです。唐突な比較に思われるかもしれないですが、共に極限を超えた、まだ私たちが見たことのない世界をもたらすという意味で、時にスポーツと芸術は似ているなあ、と思うのです。
しかし、『何かを超えた』ものというのは、何も芸術とスポーツだけの専売特許ではなく、人間の“行い”のいろいろなものに存在すると思います。“突き詰めたもの”一般に共通する感覚と言ってもいいかもしれません。そういう瞬間に出合うと、何か自分の中の可能性も開かれていくような気になりますね。それは人間のポジティブな面だと思うのですが、とても前向きな気持ちになります」
自分の手で作る、そして使うことで、アートはもっと身近になる
現在、秋元さんは練馬区立美術館の館長を務めている。いまだかつてないパンデミックによる休館を経験したが、条件を定めて美術館を開館し、準備を進めてきた企画展を開催した。ここで気がついたのは、実際の作品を見ることの楽しさという、当たり前の美術館での経験の“ありがたさ”だという。
「やっぱり芸術に触れるというのは、実際の作品体験抜きにはありえないのですね。長く休館後に久しぶりに美術館を開館した時に、待ってましたとばかりに多くのお客さまが来館されました。それは“実物が見たい”という思いなわけです。その反応に我々職員は驚きました。同時に、縮小していた区民美術展も通常の内容に戻し、本格的に開催しました」
その応募作品の傾向に、コロナ禍が人々の心にもたらした変化が見られたという。
「一般の人たちが応募してくれた作品のクオリティは想像以上に高く、いつになく審査の先生方も驚くほどでした。コロナ禍で外出がはばかられる中、それぞれが家で一生懸命、集中して、自分と向き合って作ったんだなと感じました。私たちが思う以上に、人は心で生きているんです。人間は手を動かして自分を表現したり、心動かされるものに触れたりする機会を無意識に求めているんですね」
リアルのものに触れることで、自分と向き合うことができる。だからこそ、芸術に触れることで豊かさを追求することが当たり前になってほしい。秋元さんはそう訴える。そして自分の手で表現し、作るだけではなく、作品を「使う」ことでアートをもっと身近に感じてほしいと考えている。

近年、秋元さんは暮らしの道具である工芸品に焦点を当て、北陸・金沢を拠点に人々と芸術との接点をつくろうと取り組んできた。古い街並みが残る金沢では暮らしの中で工芸品を使う場面が残り、観光資源ともなっているのだ。アートが「使う」というシーンごと受け継がれてきたことで、伝統工芸や美術といった芸術文化は大切に残されてきた。
「普段使う食器や花瓶でも、作家さん、職人さんが作ったものには大量生産されたものにはないオリジナリティがあり、温かみがあって、使っていくうちに手になじんで愛着が湧いてきますよね。まず工芸で基本的なことは、自分で自分に合ったデザインを頼めるということです。オーダーメイドできるのです。製品というと、完成されたものを購入することだけだと取られがちかと思いますが、工芸では、作家さんとのやり取り、コミュニケーションで生活品を作っていくことを指します。自生の時代だ、といわれながら、身の回りにあふれる製品は、どれも既製品ばかりです。自分の価値観に合わせて、うまくアートや工芸を生かすことができたら、今よりもっと暮らしを楽しむことができるし、日本の伝統工芸やそこにあるオリジナリティを守ることにもつながってくると思います」
美術館で作品を鑑賞するだけでなく、自分で作り、そして使う。アートのある日常のシーンを守っていくことで、世の中を豊かにしていきたい。そんな秋元さんの芸術に対する思いを知り、アートがぐっと身近なものに感じられた。「思い描く人生も抱える悩みも多様だからこそ、アートに向き合ってほしい」という言葉に、この時代を生きていくヒントが見えた気がした。
音楽を聴いたり美術館で作品を鑑賞したりする以外にも、陶芸や書道など、土や泥を触ったり手を動かしたりすることで心が落ち着いて疲れが取れたり、体の不調が治ったりする人もいます。日々の中でそうやって芸術に触れ、鑑賞や体験を楽しむことができる社会にしていけたらと思っています。
編集協力:「IDEAS FOR GOOD」(https://ideasforgood.jp/)IDEAS FOR GOODは、世界がもっと素敵になるソーシャルグッドなアイデアを集めたオンラインマガジンです。
海外の最先端のテクノロジーやデザイン、広告、マーケティング、CSRなど幅広い分野のニュースやイノベーション事例をお届けします。

東京藝術大学名誉教授、練馬区立美術館館長、金沢21世紀美術館特任館長、台湾の国立台南芸術大学栄誉教授。1955年生まれ。東京藝術大学美術学部卒業。1991年からベネッセアートサイト直島のアートプロジェクトに携わる。2004年より地中美術館館長、ベネッセアートサイト直島・アーティスティックディレクターを兼務。2007年4月〜2017年3月金沢21世紀美術館館長。2015年4月〜2021年3月東京藝術大学大学美術館館長・教授。2018年4月〜練馬区立美術館館長。主なプロジェクト、展覧会は、「直島家プロジェクト」、「地中美術館」、「直島スタンダードⅠ、Ⅱ」(直島・香川)、「金沢アートプラットホーム2008」、「金沢・世界工芸トリエンナーレ」(金沢、台湾)、「工芸未来派」(金沢、ニューヨーク)、「ジャポニズム2018『井上有一』展」(パリ、アルビ・フランス)、「あるがままのアート 人知れず表現し続ける者たち」展(東京・日本)、「井上有一展」(北京、上海・中国)等。2021年から、北陸三県を跨ぐ工芸祭『GO FOR KOGEI』、『KUTANism(クタニズム)』をディレクション。著書には『アート思考』(プレジデント社)、『直島誕生』(ディスカバリー21)など。
Instagram @akimotoyuji
練馬区立美術館 https://www.neribun.or.jp/museum.html
GO FOR KOGEI https://goforkogei.com/
KUTANism LIBRARY https://kutanism.com/
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
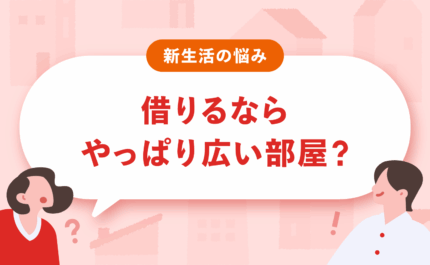 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
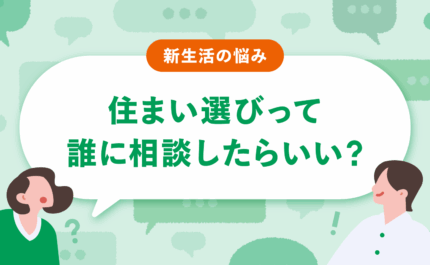 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
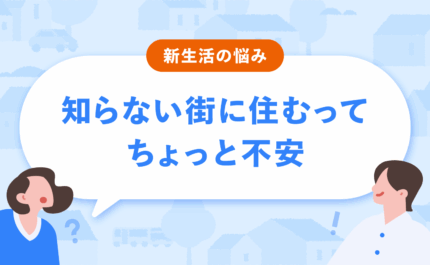 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
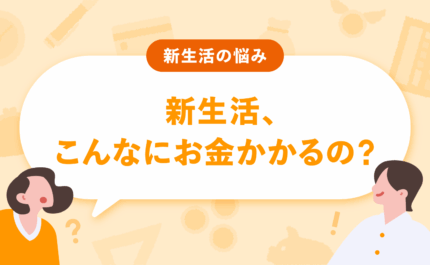 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。