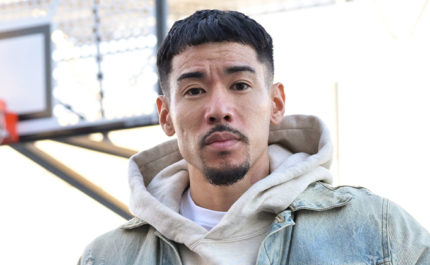子どもに性教育はいらない、なんてない。
「性の話をもっと気軽にオープンに」をモットーに、性教育YouTuberとして活動するシオリーヌさん。助産師・思春期保健相談士の資格を持ち、YouTube動画だけでなく学校などでの講演会、イベント登壇、本の出版といった多岐にわたる形で、性に関する正しい知識を発信する。シオリーヌさんが語る性の話は明るくて楽しく、性教育に付きまとう「恥ずかしい」「つまらない」「気まずい」イメージを感じさせない。そんな彼女のYouTubeチャンネルは好評を呼び、若者を中心に14.7万人(2021年5月現在)もの人がチャンネル登録をしている。

学校での性教育は、単に「男女の体の機能や生殖の仕組みの話」に終始しがちだ。しかし、シオリーヌさんの性教育は、避妊具の使い方や生理への具体的な対処法からフェミニズム、性のあり方の多様性、ルッキズムやホモソーシャルの問題までと、現代社会を生き抜くために欠かせないテーマを扱う。そうした背景には、「自分の体や健康、安全を守るための知識を届けることで、全ての人が自分らしい人生を歩めるよう応援したい」という思いがあった。
性教育は恥ずかしいものではなく、自分の人生を自分で選び取るための必修科目
“性教育YouTuber・シオリーヌ” としての原点は、産婦人科の入院病棟で助産師として働いていたころの体験にある。分娩介助で多くの妊産婦と接する中で、妊娠・出産・避妊などについて正しい知識を持たない人があまりに多いことに衝撃を受けた。
「性に関する知識を持つことは、自分の意思で人生計画を立てることと密接に結びついているはず。けれど、今の社会では『産んで育てる』という段階の人でさえも、十分な知識を備えていないことが少なくありません。適切な性教育が行われず、必要な情報が必要な人に届いていない現状があるんです」
学校の性教育の授業では、性行為などの重要な部分については詳しく説明されない。教室に漂う気まずい雰囲気から、“性=恥ずかしいもの” と思ってしまった人もいるかもしれない。また、学校の外にも、性について真摯(しんし)に教えてくれる大人はあまり多くないだろう。日本人の大半が性の話を「下ネタ」「エロ」と混同して敬遠したり、正しい知識を持てずにいたりするのも無理ないことだ。
シオリーヌさんは、そんな現状を変えるべく、2017年に思春期保健相談士の資格を取得。以降、助産師・看護師の仕事と両立しながら講演やYouTubeでの発信を行い、2019年秋からは現在の活動に専念している。
YouTubeの視聴者の約半数は中学生から20歳前後の若者であり、初の著書『CHOICE 自分で選びとるための「性」の知識』も同じ年代の読者を想定している。2021年4月に発売した『こどもジェンダー』は、幼稚園児~小学校低学年の子ども向けの本だ。なぜ、若者や子どもに性知識を届けることを重要視しているのだろうか。
「世間では『性行為に興味を持ったら困るから、子どもに性知識は必要ない』とみなされがちですが、まったくそんなことはありません。自分の体を奇麗に洗う方法や、プライベートなパーツを無理やり触られそうになったときのSOSの出し方、誰かの体に触れたいときは相手の同意が必要なこと――本来はどれも、幼いうちから知っておくべきですよね」
実際に、ユネスコが定める国際セクシュアリティ教育ガイダンスでは、年齢ごとの学習目標を5歳から設定している。世界基準で「性教育は5歳ごろから始めるべき」とされている中、日本だけが「子どもに詳しい性教育は必要ない」と言いきることはできないはずだ。
性のあり方は一人一人違って当たり前

子どもへの性教育に積極的に取り組むモチベーションには「情報を素直に吸収できる幼少期こそ、正しい性教育によって多様な価値観に触れてほしい」という願いもある。
「子どもたちが『男らしさ・女らしさ』のような凝り固まったジェンダー規範を無意識に取り込んで内面化してしまう前に、性のあり方は多様だと知ってほしい。その上で、自分らしい性のあり方、自分らしい生き方を選び取れるようになってほしいんです」
「性のあり方」には、自分の性別をどう捉えているかという「性自認」、どんな性自認を持つ人に対して性的欲求を抱くのかという「性的指向」のほか、生まれたときに決まっていた性、ファッションや言葉遣いで表現したい性などが含まれる。
近年は「性のあり方は多様なもの」という認識が広がりつつある。しかし、それでもなお「私は女性として生まれ、女性として生きて、女性として男性が好き。だから、私には関係のない話」と切り離してしまっている人もいるのではないだろうか。
「性のあり方は生き方と深く関わっているので、この社会に生きて他者と接する以上、人ごとの人はいないはず。世の中の多数派といわれるシスジェンダー※1でヘテロセクシュアル※2の人でも、実際の性はグラデーションになっています。
※1……性自認と生まれたときに決まっていた性別が一致している人
※2……異性に対して性的な感情を抱く人
例えばシスジェンダー、ヘテロセクシュアルの女性であっても、スカートははかないし化粧はしないという人もいるし、『女の子だから重いものは持たなくていい』と言われることをうれしく思う人もいますよね。性のあり方はごく当たり前に多様だし、どんな性も尊重されるべきなんです」
もし「女性は“女性らしく”あることが普通」のような価値観を持っていたら、自分の思う女性らしさから外れている人に対し「そうであってはならない」「もっとこうするべきだ」と、口出ししたくなってしまうかもしれない。そうした無理解による干渉は、誰かの選択肢を奪うことにつながる。
「私たちには、自分の体や人生のことを自ら決める権利があるけれども、人の人生にとやかく言う権利はありません。誰かの権利を知らないうちに侵害してしまわないように、多様な性のあり方があることを前提知識として知っておいてほしいですね」
“褒め言葉” も誰かを傷つける凶器になり得る

シオリーヌさんは、性教育を通して「あなたの体はあなたのもので、あなたの人生はあなたのもの」というメッセージを発信し続けている。本来であれば当然のことだが、今の社会で心の底からそう思いながら生きられる人は、果たしてどのくらいいるのだろうか。
私たちは、子どものころから誰かが誰かをジャッジする言葉をシャワーのように浴び続け、常に誰かの目を気にしながら人生の選択を重ねている。不躾(ぶしつけ)に投げかけられる「女の子なんだから、もっと女の子らしくしないと」「そんなの男らしくないよ」という言葉。まるで気の利いたあいさつかのように「ちょっと太った?」などと容姿に言及する人も、決して少なくはない。
「ただ生きているだけなのに、いろんな人が生き方や性のあり方をジャッジして干渉してくる。そんな生活が当たり前になっている中で、『私の人生は私のものだ』と思い続けるのはすごく難しいですよね。だからこそ私は、口を酸っぱくして『あなたが決めていいですよ』と言い続けたいと思っています」
そんなシオリーヌさんも、幼いころからの刷り込みで生じた固定観念によって、学生時代には数々の失敗をしてきたという。
「褒めるつもりで “女子力” なんて言葉を平気で使っていたし、痩せている友達がうらやましくて『また痩せた?』と言ってしまい、太れないことに悩んでいたその子を傷つけてしまったこともあります。自分だって体形のコンプレックスを指摘されるのが嫌だったのに……。そのときの反省が、普段の言動を見直すきっかけになりました」
たとえ褒めているつもりであっても、人を勝手にジャッジする行為は、予期せぬ形で相手を傷つける。「自分の言動が相手にトラウマを植え付けるかもしれない」と私たち全員が心に留め、少しずつコミュニケーションのあり方を変えていく必要があるだろう。
マジョリティこそ「社会を変えよう」と声を上げる必要がある

近年の日本では「それぞれの生き方を尊重しよう」という価値観が徐々に広がる一方、制度や法律といったハード面の進歩が追いついていない現状がある。シオリーヌさんは「社会の空気のようなソフト面はもちろん、ハード面も積極的に変えていきたい」と述べ、理由についてこう語った。
「残念ながら、従来の凝り固まったジェンダー規範を支持する人はまだまだたくさんいます。ですが、仮にその人たちの考え方が変わらなくても、制度や法律が整備されれば何かを伝えたいときの後ろ盾ができるんです。
例えば、性的マイノリティへの差別を禁止する法律が成立すれば、差別的取り扱いを是正する確かな根拠になりますよね。また、ハードが変わることで『自分も考え方を改めよう』と、気持ちがついてくる人も少なくないはずです」
性教育の改革には学習指導要領の改正が、LGBTQ+(※3)差別がはびこる現状の改善や、同性婚の実現には法律の改正が求められる。そうした変化を起こすのは、この国に生きる私たち一人一人の声の積み重ねだ。
「私は性的にはマジョリティの立場にあるので、『なぜ当事者でもないシオリーヌが性差別に意見するの?』と、快く思わない人もいるかもしれません。けれど、多数決の文化がある日本では、マジョリティこそ声を上げる必要があるんです。そもそも、人権の問題はどんな立場であっても見過ごすわけにはいきません。
これからも、一人でも多くの人に『声を上げなきゃ』と思ってもらえるよう、性教育や発信活動を通して『性のあり方は多様で当たり前だよ』と言い続けていきたいです」

助産師・思春期保険相談士・性教育YouTuber。総合病院産婦人科で助産師としての経験を積んだのち、精神科児童思春期病棟で若者の心理的ケアを学ぶ。2017年より性教育に関する発信活動をスタートし、2019年2月より自身のYouTubeチャンネルで動画を投稿。2021年5月現在、動画本数は240あまり、チャンネル登録者数は14.7万人。著書に『CHOICE 自分で選びとるための「性」の知識』(イースト・プレス)、『こどもジェンダー』(ワニブックス)がある。
YouTube
【性教育YouTuber】シオリーヌ
Twitter
@shiori_mw
公式サイト
yottoko.net
みんなが読んでいる記事
-
 2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子
2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。
-
 2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと
2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。
-
 2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会
2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。
-
 2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト
2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。
-
 2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題
2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。