女性は男性に合わせなきゃ、なんてない。
ビジネスニュースサイト「Business Insider Japan」統括編集長を担う浜田敬子さん。「男女雇用機会均等法」改正(1986年)直後の1989年に朝日新聞社に入社したが、当時は「女性の働き方」についてあまり意識することはなかったという。しかし、さまざまな社会経験を積むなかで徐々に意識し始め、やがて社会課題であることを認識し対峙するようになった。2018年には『働く女子と罪悪感「こうあるべき」から離れたら、もっと仕事は楽しくなる』(集英社)を上梓した浜田さん。何故この本を出版することに至ったか。そこにはどのような思いを抱え、どんな社会課題と向き合ったのか、本人に伺った。

厚生労働省が2019年6月に発表した「平成30年版働く女性の実情」によれば、就業を希望していながら実際に働いていない女性の数は約230万人にも上るという。その一方で、労働局雇用関連機関に寄せられた「男女均等」に関する相談は19,187件(平成 29 年度)あったといい、「女性の働き方」について悩む人はいまだ多いというのが実情だ。ちなみにこの約2万件の相談内容は、大きく「性差別」(募集、採用、配置、昇進などを含む)、「婚姻および出産を理由とする不利益取り扱い」、「セクシャルハラスメント」に分けられる。この社会課題について浜田さんはどのように考え、そして今、どんな取り組みをしているのだろうか。
男女共に意識を変えないと既成概念は取っ払えない
大学卒業後の就職先として新聞社を選んだ浜田さん。入社当時は「女性の働き方」ついて意識していたのだろうか。
「当時、私は男性と同じように働きたいし、働ける職業という理由から新聞社を就職先に選びましたが、実際に入社してみると、非常に“中途半端”な存在だったなと思います。深夜まで働き、宿直勤務もこなす。つまりほかの男性記者と同等か、新人だからそれ以上働きながら、「女性だから危ない」という理由でやらせてもらえない仕事もいくつかありました。まだ女性記者は少なかったので、私が記者だと思われない時もしばしばありました。たとえば会社に電話がかかってきて、私がとると『記者の人を出して』なんて言われて。「私も記者ですが」と返すと、『女の記者なんかに話せねえよ』という言葉を浴びせられたこともありました。その時はショックを受けたというよりも、世の中そんなもんなんだと“理解”しましたが、思えば、こういうことが積み重なる中で、女性の働き方について意識するようになったと思います。男女差を感じる出来事もありました。社内のルールが私の入社後に変わり、女性記者も泊まり勤務が始まりました。宿直勤務の日はほとんど眠れず、その次の日も通常勤務だったので、1年目は体力的なキツさを感じていました。ついに入社1年目の秋頃に体を壊してしまったのです。そのとき、私はこの仕事をこのまま続けていけるのだろうかと不安に陥りました」

「男女の差」を感じながらも働き続け、入社10年目となった1999年に浜田さんは雑誌『AERA』編集部に異動することとなった。そこでは、女性観点からのニュースを書く機会が増えたという。
「AERA編集部には1つ年上の女性記者が4人いました。当時編集部では『政治や経済、事件だけがニュースではないのでは?』などよく議論を交わしていました。先輩女性記者たちは『自分たちが本当に読みたいニュースは何か』と考え、『女性の生き方』や「働き方」についての記事をよく書いていました。私もその議論に参加すること、自分自身が働いてきた環境や、同世代の友人たちが退職を選ばなければならなかった理由、そんなテーマがニュースになるのか、と覚醒しました。今でこそ『女性ならではの視点』なんて言葉をよく耳にすると思いますが、こう言われ出したのは2000年代に入ってから。それまでは女性というのはどちらかというと“イロモノ”扱いで、会社の会議などで女性記者としての意見を求められたこともほとんどなかった。私もAERAに異動する前までは、むしろ『女性記者ならでは』なんて言われるのがすごく嫌でした。男性と同じに扱ってほしい、と強く思っていたので。でも、そんな中でAERA編集部での議論に触れ、私自身、記事を書いたり企画を考える中で、自分が抱えている悩みや、私の周りにいる人の悩み、そこから派生した女性の格差についての悩みなどを強く意識するようになりました。AERAでの仕事を機に『女性の働き方』について深く考えるようになりましたね」
「仕事と育児」両立の経験から本を書くことに
2018年に、著書『働く女子と罪悪感「こうあるべき」から離れたら、もっと仕事は楽しくなる』(集英社)を出版した浜田さん。この本を出すきっかけとなった出来事は大きく2つあるという。
「まず1つが出産(2006年)とその後に体験する『仕事と育児(家庭)の両立』です。出産後、多くの女性は育児のために仕事をセーブするか、場合によっては退職して、育児を優先します。それは家庭内や社会にまだ育児は母親の仕事、という価値観が根強いことが大きいのですが、一方で、女性自身も『母親のくせに』と言われることを恐れ、『母親なのに』と自分を責めるという内面の問題も大きいと思います。『仕事が好き』とか『子育てを忘れて仕事に没頭したい』と思っていても、それを言いにくい世の中になってしまっている。私自身、この社会からの押し付けられる価値観がすごく辛かった。女性たちもいろいろです。思い切り働きたい女性がいれば、働ければいいと思うし、それができる世の中であってほしい。出産と育児を経験するうえで強くこのことを思いました。一方で、男性は子どもが生まれても、こういう経験はしませんよね。男性は仕事に没頭しても非難されないのに、女性が仕事に没頭して子育てを後回しにしたりすると、すぐに非難される……。私自身、子どもを育てながら仕事を続けるなかで、あるときに子どもに対して罪悪感を抱くようになってしまったんです。出産前と変わらないペースで仕事をしていると、どうしても子どもとコミュニケーションをとる時間が短くなる。子どもといても、ふと気づくと仕事のことを考えていると気付いた時、子どもに申し訳ない、と感じました。それでも私は働きたかった……。そういった葛藤を踏まえ、女性が『仕事が好き』と言っても非難されない世の中にしたい、女性が働くうえで縛られている既成概念を取っ払いたいと思ってこの本を書きました」

2つ目は、テレビ朝日の女性記者が元財務省事務次官からセクハラを受けた事件が明るみになったことだという。
「テレビ朝日の女性記者の告発は、メディアで働く女性たちが取材先や社内から長い間、セクハラを受けてきた事実を明らかにし、多くの女性たちが声を上げるきっかけになりました。またこの事件が国内で『#MeToo』運動が高まる、一つのきっかけにもなったと思います。その一方で私たち世代のメディアで働く女性たちは反省もしました。私たちが若かったときも同様の経験をしてきたにも関わらず、私たちはそれに対して声を上げなかった。ここで声を上げてしまうことは「面倒臭い女」と見られて、仕事を失ったり、男性たちに同じ働く仲間としてみてもらえなくなる、と思ってしまって。もしあのときに『ノー』と言っていたら、世の中はきっと変わっていたと思います。この事件に後押しされて私は本を書く決意をしました」
夫に交渉を続けることで女性の働き方は変えられる
「女性の働き方」について自身の著書で訴える浜田さん。今まさに活躍する女性たちや、その周りにいる男性たち、そして世の中に対してある願いを込めたという。
「働く女性たちにとっての環境は、ここ30年で変わってきています。育児休業制度や時短勤務制度が企業で整備されるなど、その変化は海外に比べれば遅いですが。しかし、『母親だったらこうするべき』とか『女性だったらこうするべき』という、日本の社会における女性たちへのプレッシャーはいまだに残っていますし、伝統的な性別役割意識からも抜け出せていません。まだまだ環境的な変化も必要ですし、女性たち自身の内面の変化も必要だと思っています。そんな中、今の若い世代の男性意識が大きく変化していることは、女性たちにとって1つの希望になると思っています。大学生や、20代前半の男子学生に話を聞くと『共働き』はデフォルトです。男性だけが『外で稼ぐ』モデルは男性たちにとってもしんどい。それに気づき始めているのだと思います。より男性が女性と対等に育児や家事を担うようになり、仕事における女性の能力を認めるようになれば、結果的に女性の意識も変わります。
そしてその少し上の世代、今の30、40代の後輩の女性たちにはこう言ってます。『社会を変えようと思ったら、あなたがあなたの夫と交渉してね』と(笑)。すごく優秀な女性たちが夫の考え方を変えられないことによって、家事育児を全面的に1人で担い、能力を100パーセント発揮できないのは、みていて非常に悔しい。私は、能力的に女性が劣っているなんて一度も思ったことはありません。私自身、体力的にキツいなと感じたことはありましたが、長時間労働していたら男性だってキツいわけで、女性だけの問題ではなかったなと今では思っています。私はこの本を通じて『女性だから、母親だからこうするべき』という意識から少しとき離れて、本当に自分がどう生きたいのか、どう仕事をしていきたいのか考えて、ということを伝えられたらと思っています」
「女性の働き方」について、社会人になったばかりの頃は特に意識することのなかった浜田さん。AERAに所属し、結婚・出産を経験し、著書を出す過程において、一貫した考え方を持ち続けていた。
さらに、「withコロナ時代」と呼ばれる今、女性の働き方や育児に関する価値観はどのように変わっていくのだろうか。
「コロナによって半強制的に在宅勤務を体験することに、多くの人が家族とより多くの時間を過ごしたことで、改めて自分にとって大事なものは何か、ということに気付いたり、通勤がなくなり、その分の時間を効率的に使えるようになったことで、ワーキングマザーが能力を発揮しやすくなったり、といろんな変化を体感したと思います。この期間に体験したことのよかった部分はコロナ危機が終わっても生活に定着させたいと思っている人は多いと思います。企業も完全に元に戻すのではなく、より多様な人事がその人なりの能力を発揮しやすいような環境づくりに努めるべきだと思います。会社に行かなくても仕事ができる、という体験は、場所と時間の制約からとき離れることになるので、女性にとってはプラスになると私は思います」

そして、今後浜田さんは、Business Insider Japan統括編集長としてさまざまなニュース記事を配信し続けるだけでなく、自分自身の働き方やキャリアについても“実験”をしている。
「実は2019年末に会社を退職し、今は業務委託、フリーランスという形でBusiness Insider Japanの統括編集長を務めています。これまで若い世代の多様な働き方を取材してきて、自分自身も会社員という働き方以外を試してみたくなったこと、そして統括編集長以外の仕事も受けることで、自分も新しい分野にチャレンジしてみたり、学んだりしてみたいと思ったことがきっかけです。人生100年時代と言われ、より長く働くことも視野に入れて、この選択をしました。そしてもっと柔軟に個人が働きたい形で働こうよということを世の中に発信していきたいと思っています。将来的には子どもがもう少し大きくなったら場所や時間をもっと自由に。たとえば1カ月のうち1週間は地方で働いてみたり、旅をしながら働いてみたりということをやってみたいです。コロナ危機によって、そんな働き方をしたいと思う人も増えていると思うのですが、まずはみんなできることからちょっとした変化を楽しんでみてはどうでしょうか?

1966年生まれ、山口県出身。上智大学法学部国際関係法学科卒業後、朝日新聞社に入社。前橋、仙台支局を経て、週刊朝日編集部、1999年にAERA編集部へ。記者を経験した後、2004年に副編集長に就任。2006年に出産し、育児休業取得。2014年に女性初のAERA編集長に就任。2017年に退社し、Business Insider Japan統括編集長に就任。『羽鳥慎一モーニングショー』などでコメンテータを務めるほか、働き方などについての講演も行なっている。
多様な暮らし・人生を応援する
LIFULLのサービス
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
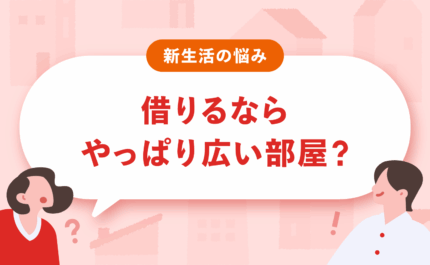 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
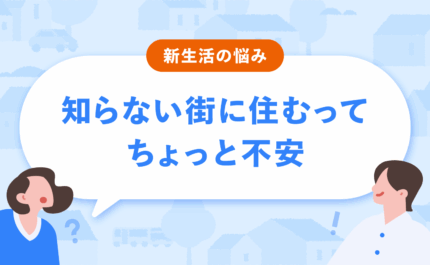 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
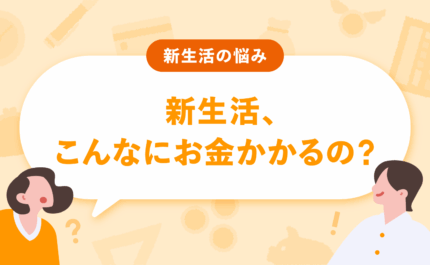 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
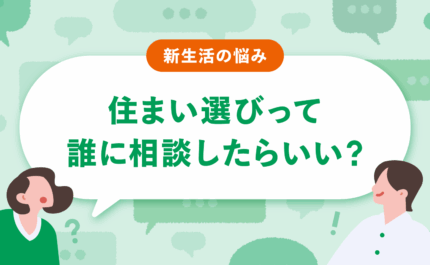 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。















