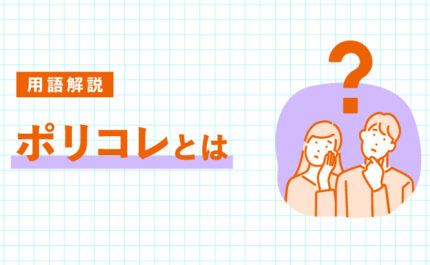マンスプレイニングとは? 問題視される理由と対策
マンスプレイニングとは、男性が女性に対して上から目線で説明や解説をすることを指します。相手に説明すること、情報を提供することが問題視されているわけではなく、その根底には「男性である自分は女性よりいろいろと知っている」という無意識の偏見が存在することが指摘されています。
この記事では、「マンスプレイニング」について解説します。
マンスプレイニングの意味とは?

マンスプレイニングとは、「Merriam Webster Dictionary(メリアム・ウェブスター)」によると、「男性が女性にその話題について何も知らないと考え、見下した態度で説明すること(to explain something to a woman in a condescending way that assumes she has no knowledge about the topic)」です。2010年にニューヨークの「ワード・オブ・ザ・イヤー」に選ばれ、2018年にはオックスフォード英語辞典にも掲載されたことで徐々に社会にも認知されるようになってきました。(※1)
具体的には、男性が女性に対して何かを説明するときに相手の知識や経験などを軽視して一方的に自分の知識をひけらかしたり、過度の自信をもって話すことで相手に居心地の悪さや違和感を感じさせたりすることで表れます。
社会的地位や年齢、人種、文化的背景に関係して引き起こされる現象であることに注意が必要です。より注目すべきはその行為が個人的な会話の中でどう表れるかということよりも、マンスプレイニングを引き起こす背景に無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)や社会的条件付け、構造的権力構造が関係しているという点です。
マンスプレイニングは過去の歴史でも常に存在していたと考えられますが、フェミニズム運動やジェンダー平等が社会的課題として取り上げられるようになる中で、多くの人々に認知されるようになってきました。
出典
※1 マンスプレイニングの定義と意味 – メリアム・ウェブスター
マンスプレイニングの語源と歴史的発展
マンスプレイニングは「man(男性)」と「explaining(説明する)」を組み合わせた造語です。この言葉が社会に広く認知されるようになったきっかけの一つにレベッカ・ソルニットが2008年に書いた「説教したがる男たち(Men Explain Things to Me)」という記事があります。作家であり、アクティビストでもある彼女はこの記事の中で印象深いエピソードに触れています。(※2)
2003年にコロラド州の山小屋で催されたパーティーに参加したソルニットは、まさに「マンスプレイニング」を経験します。主催者の男性は、ソルニット自身が出版した本について熱心に解説しはじめ、「今年出たばかりの重要な本」として自慢げに語り始めたといいます。友人はその男性に何度も著者がソルニットであることを伝えますが、意に介さず講釈を続けたそうです。ソルニットは、2014年に「Men Explaining Things to Me」を含む7つのエッセイを1冊にまとめ、同名の書籍を出版しました(日本版は2018年)。(※3)
ソルニットの書籍をきっかけに、「マンスプレイニング」という言葉が注目されるにようになりましたが、中には「自分が攻撃されている」と感じた男性たちもいたようです。
しかし、ソルニット自身が「マンスプレイニング」という言葉を考案したわけではありませんし、書籍を通して男性たちが内在的に「説教したがる」傾向を持っていると断定しようとしたわけでもありません。それどころか、ソルニットは「マンスプレイニング」を一般的に使用することには違和感を覚えていたようです。
ジェンダー論の観点では、マンスプレイニングという行為そのものを非難するよりも、男女の賃金格差やセクシャルハラスメントなどの他の社会課題とどうつながっているのかを紐解き、分析することが重要なのではないでしょうか。
出典:
※2 Men Explain Things to Me | Guernica
※3 現在の社会を予言?作家レベッカ・ソルニットが再び注目される理由|The New York Times Style Magazine : Japan
なぜ、マンスプレイニングが問題なのか

ここでは、なぜマンスプレイニングが問題視されるのか、またマンスプレイニングを避けるための具体的な対策について解説します。
マンスプレイニングが問題視される理由
- 個人の尊厳と能力の軽視
マンスプレイニングは必ずしも男性から女性に対する行為ではありません。同性同士や、女性から男性に対してすることも考えられます。その根底にあるのは、個人としての尊厳や能力を軽視する態度です。
相手を理解しようとせず、「〇〇だから知らないはず」などと相手のジェンダーや属性に基づいた決め付けや偏見をしてしまうことが問題です。
- コミュニケーションの阻害
マンスプレイニングは相手が知らないことを前提にして、上から目線で情報を一方的に伝達します。そのため、相手の話を傾聴し、それに基づいて会話するインタラクティブなコミュニーションが阻害されます。結果として相互理解や創造的な議論は奪われてしまいます。
- 職場での不平等の助長
マンスプレイニングが横行している職場では待遇面で男女間の不平等が構造化していることが考えられます。そのような職場環境では女性のキャリア形成は困難です。
- 心理的ストレスの増加
上述したようにマンスプレイニングはたとえ悪意がなくても相手を理解しようとせず、尊厳を軽視する行為です。そのため、マンスプレイニングを受ける人は多かれ少なかれ心理的ストレスを受けます。メンタルヘルスへの悪影響も懸念されます。
- 社会の進歩の妨げ
マンスプレイニングが常態化している職場や企業においては、従業員の心理的安全性は脅かされ、萎縮していることが考えられます。その結果、メンバーは自分の考えやアイデアを積極的に発信することを控えてしまいます。イノベーションは生まれづらくなり、従業員の問題解決能力も低下しがちです。
マンスプレイニングを解決するためには個別の行為に注目するだけでなく、何がマンスプレイニングを許容する雰囲気やカルチャーを引き起こしているのかを理解することが重要です。ジェンダー、人種、階級など社会的なカテゴリーがどのように関係しているのか、俯瞰的に分析する視点が不可欠と言えるでしょう。
マンスプレイニングを避けるための具体的な対策
- 自信を持った自己表現
マンスプレイニングを受けた時は自分の知識や経験について自信をもって表現しましょう。相手が聞き入れてくれないとしても自分自身の尊厳を守ることができます。
- 丁寧な意思表示
相手が一方的に説明してきたら、無視をしたり、反論したりするのは逆効果になる場合も。お互いの尊厳を守るためには、「ありがとうございます。その点については理解しています」と丁寧に不要な説明を心がけるようにします。
- 自己啓発と自己価値の再確認
マンスプレイニングに陥ってしまう傾向が強い人は、自己啓発を続ける重要性を理解しましょう。つまり、自分には学ぶべきことが多くあり、人からも学ばなければならないことを認めると、独りよがりに自分の知識や経験を一方的に話すことは避けられるでしょう。
- 相手の意図の確認
相手が望んでいないのに一方的な説明をしないように、意志を確認するようにします。必ずしも毎回相手の同意を得る必要はありませんが、様子を観察しながら、自分が持っている専門知識や情報を相手が必要としているのか知るようにしましょう。
- 同僚や上司のサポート
善意からマンスプレイニングが起こるケースもあります。職場における業務フローが属人的であるため、上司や同僚が「この人はこの業務のやり方を知らないから」と、一方的に情報伝達されることもあり、無意識にマンスプレイニングにつながります。それを避けるためには、職場でのサポート体制を仕組み化、制度化することです。
マンスプレイニングの具体例

職場でのマンスプレイニング
- 女性よりも多く知っているように振舞う
社内での雑談の折、女性社員の何気ない発言に対し、男性社員が「教えてあげないと」といわんばかりに口を挟みます。男性社員は女性社員に変わって会話の主導権を取り、女性社員は気まずい思いをします。
- 専門知識の否定
上司に対して、プロジェクトメンバー数人が分析情報や経験に基づきアイデアを提案します。若手のメンバーが発言しますが、上司は他の経験あるメンバーに比べ、そのアイデアの重要度は低いと考え、軽視する発言を繰り返し、押し通そうとします。
- 昇進に関する偏見
管理職の立場にある社員が集まり、部下の昇進を検討しています。若手社員と経験ある社員が候補に挙がり、同じだけの業績を残しているにもかかわらず、若手社員を過小評価する意見を述べ続けます。
- プロジェクト配属での差別的扱い
重要なプロジェクトの人員配置を決めています。専門知識や経験に基づくと女性メンバーがプロジェクトリーダーに相応しいにもかかわらず、軽視する自説を述べ、男性メンバーが選ばれるようにします。
日常生活でのマンスプレイニング
- 女性の趣味や関心事の軽視
日常的な会話の中で、女性の趣味や関心ごとが男性よりも「劣る」ように扱われます。女性はスポーツや自動車、機械などに関心を持つと「女性なのに珍しいね」と男性から驚かれます。
- 家事や育児に関する経験の軽視
家庭内で夫の給料の額や企業でのキャリアに比べ、妻の家事や子育ての貢献が低く評価されます。夫は「女性は家庭を守るべき」という偏ったジェンダーロールに基づき、発言します。
- 聞かれていないのに説明する
女性が動物園で好きな動物を見ています。知らない男性がやってきて、唐突に動物についての蘊蓄を語り始めます。女性は何も質問していないのに一方的に説明され、不快な気持ちになります。
- 日常的な意思決定の場面
家族や同僚と一緒に旅行の計画を立てたり、買う物を決定する時に「女性の決定は衝動的」「女性は男性の決定に従うべき」などと、女性の意見や希望が軽視されたり、無視されたりします。
まとめ

上から目線で接することが多いマンスプレイニングのような言動は、男性に限ったことではありません。その根底にあるのは、アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)や偏見、ジェンダーに基づく差別構造などさまざまな要因が複雑に絡み合っています。注意したいのは、「自分はマンスプレイニングと無縁で、したことがない」と思い込んでいる人が、マンスプレイニングをしているケースが少なくないということです。
職場や日常生活でマンスプレイニングを経験したり、見かけたりしても、そういった言動をしている人を批判するよりも、自分自身の中に無意識の思い込みや偏見がないかを見つめる機会にしたいものです。
執筆:河合 良成
立命館大学産業社会学部特任教授・名誉教授。1989年より立命館大学産業社会学部、人間科学研究科・応用人間科学研究科で研究と教育に携わる。専門分野は社会病理学、臨床社会学、男性性研究。『「男らしさ」からの自由』『家族のゆくえ』『家族の暴力をのりこえる』『ドメスティック・バイオレンスと家族の病理』『治療的司法の実践』など著書・共著書・訳書多数。立命館大学副学長など歴任。現在、日本社会病理学会会長、対人援助学会理事長、内閣府女性に対する暴力に関する専門調査会委員など。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント
2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜
2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜
2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。
-
 2024/07/04インターセクショナリティとは? 世界の差別問題と外国人に対する偏見や固定観念を取り払うには
2024/07/04インターセクショナリティとは? 世界の差別問題と外国人に対する偏見や固定観念を取り払うには21世紀において、多様性への理解やジェンダー研究において注目されているのが、ブラック・フェミニズムをはじめとするマイノリティ女性の運動から生まれた「インターセクショナリティ」の概念です。日本語で「交差性」と訳される「インターセクショナリティ」は地域文化研究、社会運動、政策に影響を与えていますが、ここでは差別問題の文脈にフォーカスして取り上げます。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」