【前編】ニューロダイバーシティとは? あらゆる特性の人が活躍できる社会を目指す取り組みと企業事例
現在「ダイバーシティ」という言葉はビジネスや教育などさまざまな文脈で用いられます。
ダイバーシティとは多様性を意味し、元々は、「ジェンダー、人種・民族、年齢」などの属性の多様性を指すことが多かった言葉です。近年では企業の経営戦略において、多様な価値観を尊重することでイノベーションの創出や生産性を高める「ダイバーシティ経営」の観点でも注目されるようになっています。
経済産業省も、国内企業の経営戦略としてのダイバーシティ経営の推進を後押しするために、さまざまな施策を打ち出しています。
人間のより本質的な多様性に注目する「ニューロダイバーシティ」という考え方があります。この記事では以下の5点について解説します。
前編
後編
ニューロダイバーシティとは?
ニューロダイバーシティとは、Neuro(脳・神経)とDiversity(多様性)という言葉が組み合わさった造語であり、「脳や神経、それに由来する個人レベルでのさまざまな特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、それらの違いを社会の中で活かしていこう」という考え方です。
1990年代にオーストラリアの社会学者Judy Singer氏が提唱した言葉で、同氏は「すべての人間はそれぞれユニークな神経システムも持っている」と主張し、ネガティブに評価されがちな発達障がい(神経発達症)によって生じる現象も、そのうちの一つであると捉えました。
すなわち、ニューロダイバーシティとは、精神疾患の診断の有無にかかわらず、一人ひとりが持つ、個性・特性をお互いに尊重しようという考え方です。とはいえ、発達障がいの文脈で語られることが多かったため、以下では、発達障がいに注目して解説します。
2022年に文部科学省が行った調査(※1)によると、発達障がいの可能性がある児童生徒は小学生の約10.4%、中学生の約5.6%、高校生の約2.2%でした。2012年よりも、小中学生の割合は2.3ポイント増加しています。とはいえ、発達障がいとは生涯変わらない特性であり、時代とともにその有病率が増えることは基本的にありません。すなわち、このような数字が出ているのは、発達障がいの特性を受容できない教育現場が増えていることを示唆するとの指摘もあります。
一人ひとりの特性を理解し、その特性に合った教育を提供することで、本人の持つ可能性を引き出せる可能性もあります。
実際、最近の調査報告(※2)によると、発達障がいのある人が持つロジカルな思考や集中力、計算能力などは、データアナリティクスやサービス開発といったIT分野において適性がマッチする可能性が指摘されています。
※1 出典:文部科学省 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について
※2 参考:令和3年度産業経済研究委託費 イノベーション創出加速のためのデジタル分野における「ニューロダイバーシティ」の取組可能性に関する調査 令和4年3月(令和5年3月改訂)
発達障がいと主な特性・強み
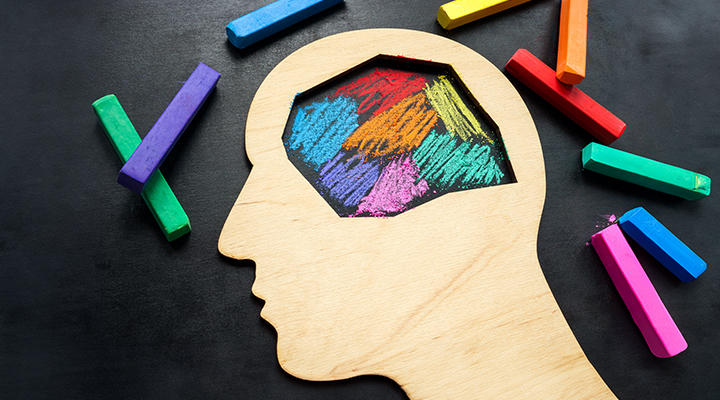
発達障がいとは「脳機能の発達が関係する障がい」のことで、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、限局性学習症(学習障がい)、チック症、吃音などがあります。同じ発達障がいでも特性の現れ方が異なったり、いくつかの障がいを併せ持ったりすることもあります。
※3 出典:発達障害って、なんだろう? | 政府広報オンライン
そのため、特性は個別具体的ですが、共通項を一般化すると以下のようになります。(※3)また、指摘されている強みはすべての人が同様に持っているわけではなく、あくまでも可能性の一つであることに注意が必要です。
自閉スペクトラム症(ASD)
主な特性
- コミュニケーションの障害、対人関係・社会性の障がい、パターン化した行動、こだわり、興味・関心の偏り
- (アスペルガー症候群の場合)言語発達に比べ不器用
- (自閉症)言葉の発達の遅れ
先行研究で示唆された強み
- 細部への注意力が高く、情報処理と視覚に長けており、仕事で高い精度と技術的能力を発揮
- 論理思考に長けており、データに基づきボトムアップで考えることに長けている
- 集中力が高く、正確さを長時間持続できる
- 知識や専門技能を習得・維持する能力が高い
- 時間に正確で、献身的で、忠実なことが多い
注意欠如・多動症(ADHD)
主な特性
- 不注意(集中できない)
- 多動・多弁(じっとしていられない)
- 衝動的に行動する(考えるよりも先に動く)
先行研究で示唆された強み
- リスクを取り、新たな領域に挑戦することを好む
- 洞察力、創造的思考力、問題解決力が高い
- マルチタスクをこなし、環境や仕事上の要求の変化に対応する能力が高い
- 精神的な刺激を求め続け、プレッシャーのかかる状況でも極めて冷静に行動できる
- 刺激的な仕事に極度に高い集中力を発揮する
学習症(LD)
主な特性
「読む」「書く」「計算する」等の能力が、全体的な知的発達に比べて極端に苦手
先行研究で示唆された強み
- 脳が視覚処理に長けており、イメージで捉える傾向が強く、より多角的に物事を考えられる
- アイディアをつなげて全体像を把握する能力に長けており、データのパターンや傾向を見抜くこと、洞察力や問題解決能力に長けている
- 異なる分野の情報を組み合わせることに長けており、発明や独創的思考ができる
日経BP総合研究所主任研究員
1994年東京大学卒。1997年日経BP入社。バイテクノロジーの専門誌「日経バイオテク」、薬剤師向け専門誌「日経ドラッグインフォメーション」、医師向け専門誌「日経メディカル」などを経て2024年4月より現職。2004年にフルブライト奨学生として米国UCSFに留学。臨床倫理や終末期医療、脳科学に詳しく、文部科学省の科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会、ライフサイエンス委員会脳科学作業部会の委員なども務める。日経BPが2024年度に設立したニューロダイバーシティ&インクルージョン・フォーラムの仕掛け人。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/01/28一つの居場所にいなきゃ、なんてない。多様な「居場所」があることが、人生の価値を高める要素の一つ高橋愛莉・酒井景都
2025/01/28一つの居場所にいなきゃ、なんてない。多様な「居場所」があることが、人生の価値を高める要素の一つ高橋愛莉・酒井景都「THE LIONS JOURNEY」プロジェクト推進に携わった株式会社大京「THE LIONS 2050」ディレクターの高橋愛莉さんと、鎌倉でこだわりの家に住むモデル・デザイナーの酒井景都さんの対談第3回。人生の価値を高める“多様な「居場所」の創出”につい語り合います。
-
 2022/08/04結婚しなくちゃ幸せになれない、なんてない。荒川 和久
2022/08/04結婚しなくちゃ幸せになれない、なんてない。荒川 和久「結婚しないと幸せになれない」「結婚してようやく一人前」という既成概念は、現代でも多くの人に根強く残っている。その裏で、50歳時未婚率(※1)は増加の一途をたどり、結婚をしない人やみずから選んで“非婚”でいる人は、もはや珍しくないのだ。日本の結婚の現状や「結婚と幸せ」の関係を踏まえ、人生を豊かにするために大切なことを、独身研究家の荒川和久さんに伺った。
-
 2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト
2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。
-
 2023/06/22心地よいはみんな違う。私たちのパートナーシップ【サムソン高橋の場合】
2023/06/22心地よいはみんな違う。私たちのパートナーシップ【サムソン高橋の場合】ゲイライターのサムソン高橋さん。エッセイストやイラストレーターとして活躍する能町みね子さんと、恋愛感情なし・婚姻届も出さない「結婚(仮)」という形で同居を始めて5年が経つ。サムソンさんの視点から見た、「心地よいパートナーシップ」について話を聞いた。
-
 2024/06/18【前編】高齢者の生きがいとは?60・70歳シニア世代の働く意欲と年齢との向き合い方
2024/06/18【前編】高齢者の生きがいとは?60・70歳シニア世代の働く意欲と年齢との向き合い方「人生100年」といわれる時代において高齢者の生きがいは非常に重要なテーマです。高齢者の生きがいを満たしていくには、社会や周りの人たちのサポートも必要ですが、高齢者自身が積極的に社会とつながり交流していくことが大切です。その一つの要素として“働き続ける(活躍し続ける)”ということも有効な視点です。この記事では高齢者と仕事について解説します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」













