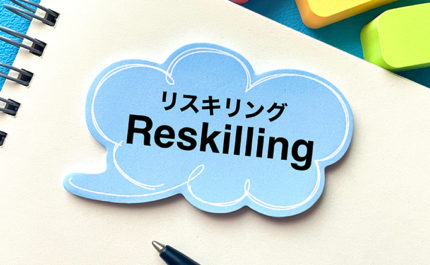インターセクショナリティとは? 世界の差別問題と外国人に対する偏見や固定観念を取り払うには
多様な背景を持つ人々が暮らす現代社会では、世間の常識や本人に刷り込まれている偏見や思い込みで他人を批判したり差別をしたりする場面が往々にしてあります。自分と異なるルーツや背景を持つ人に対する理解と尊重は、社会をより豊かにし、多くの人が自分らしい生き方をするために重要な視点です。
21世紀において、多様性への理解やジェンダー研究において注目されているのが、ブラック・フェミニズムをはじめとするマイノリティ女性の運動から生まれた「インターセクショナリティ」の概念です。日本語で「交差性」と訳される「インターセクショナリティ」は地域文化研究、社会運動、政策に影響を与えていますが、ここでは差別問題の文脈にフォーカスして取り上げます。
インターセクショナリティ(差別の交差性)とは?

インターセクショナリティ(交差性)とは、「人種、エスニシティ、ネイション、ジェンダー、階級、セクシュアリティなど、さまざまな差別の軸が組み合わさり、相互に作用することで独特の抑圧が生じている状況」と定義されます。
差別問題の文脈で取り上げられることが多い「インターセクショナリティ」ですが、単に複数のマイノリティ性を抱えている個人に対する差別だけではなく、複数の要因が交差したところに生じる固有の経験、リアリティを重視し、それを可視化しようという試みを指します。
インターセクショナリティの概念を理解するために前提として以下の3要素を念頭に置いておくことが必要です。
- 私たち一人ひとりの間には「差異」が存在する。それは人種や国籍、性別、性的思考、階級や障がいの有無などによって割り当てられる「社会的カテゴリー」に由来する。
- それらの差異は「力関係」を生み出す。どの「社会的カテゴリー」に属するかによって、有利な位置に立つ人もいれば、逆の状況に追い込まれる人もいる。
- 社会における個人の有利・不利の力関係は1つではなく、複数の「社会的カテゴリー」の「重なり合い」の中で生じている。
つまり、インターセクショナリティとは、以上の「差異によって生じている力関係」が「交差」することを指します。
出典:内閣府日本学術会議事務局「未来からの問い―日本学術会議100年を構想する」 内閣府
インターセクショナリティ(差別の交差性)の概念
弁護士で人権活動家のK.W.クレンショーが1989年に初めて分析概念として「インターセクショナリティ」という言葉を使いました。クレンショーは、「黒人」や「女性」という「社会的カテゴリー」で均質的かつ相互排他的に分析されることで、「黒人女性」が経験する多面的差別や複雑で入り組んだ支配や従属構造が軽視されてしまうと主張しました。
クレンショーがよく取り上げるインターセクショナリティの事例として「デグラフェンレイド対ゼネラルモータース裁判」があります。これはエマ・デグラフェンレイド含め4名の「黒人女性」が自動車メーカーのゼネラルモータースを相手に差別を受けていると主張して提起した裁判です。
裁判所は人種差別と男女差別の申し立てを別々に検討し、「白人女性」を事務所や秘書として雇っているため、男女差別はないと判断しました。さらに「黒人男性」も工場で雇われており、人種差別はないとしました。クレンショーはこうした訴訟において裁判所は「黒人女性」特有の経験を無視する傾向があると主張しました。
分析概念としてインターセクショナリティの視点が重要である理由について、福岡女子大学の徐阿貴氏は次のように述べます。
<女性>や<黒人>を均質、かつ相互に関係のないカテゴリーとみなすと、内部の多様性や権力関係、不平等な配置が見えなくなる。交差性の概念は、一枚岩的なアイデンティティを再考し、集団内部の差異、集団間関係、集団と個人の関係をあぶり出す。
※引用:Intersectionality(交差性)の概念をひもとく | ヒューライツ大阪(一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター)
認定NPO法人国連ウィメン日本協会は「インターセクショナル・フェミニズム」が重要なのは、世界中の国や地域が経験している危機が一様ではなく、複合的な脅威である点を挙げています。つまり、さまざまなグループが経験している経験や課題を細分化しないで受け止める必要があります。
出典:インターセクショナル・フェミニズムとは?なぜ今、重要なのか?(国連ウィメン日本協会)
ブラック・ライヴズ・マターから学ぶインターセクショナリティ
2012年、フロリダ州で黒人の高校生トレイヴォン・マーティンさんが自警団の白人男性に射殺された事件が起こりました。射殺した白人男性は殺人罪に問われましたが、無罪評決が出たことで黒人への人種差別だと批判が集まり、全米で抗議デモが広まりました。これが、ブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動誕生のきっかけとなる事件です。
2020年5月、ミネソタ州で黒人男性のジョージ・フロイドさんが白人警官に殺害された事件を発端に、「ブラック・ライヴズ・マター」をスローガンに掲げる人々が大きな抗議行動に出ました。
立命館大学文学部教授の坂下史子さんは、ブラック・ライヴズ・マターの重要な特徴の一つは、女性や性的マイノリティなど、これまで周辺化されてきた人々が運動の中心になった点だと語ります。過去に起きた公民権運動に代表される黒人解放運動は黒人男性が中心だったのに対し、フェミニズム運動は白人女性が中心だったのです。
ブラック・ライヴズ・マターを理解するにあたり、シンプルな「白人」と「黒人」の人種的な対立ということで片付けることはできません。アメリカ社会では、「黒人女性」に対してレイシズムとジェンダーの両面について差別や迫害が起こっており、それらを交差させて制度的差別と理解するインターセクショナリティの観点が重要なのです。
SDGsでは「人や国の不平等をなくそう」が目標10として掲げられ、人種や性別による差別や差別的な法律、政策、慣行の撤廃を求めています。ブラック・ライヴズ・マターが目指す制度的人種差別の撤廃とも大きく重なっていると言えるでしょう。
出典:坂下史子:ブラック・ライヴズ・マターとは何だったのか~現在進行形の運動を理解するために~
暮らしの中に存在する「マイクロアグレッション」(無自覚な差別)

人種による差別は何も米国だけの話ではありません。日本でも外国人への差別は実際に起きています。
『日本における「難民・避難民の住まいの実態調査」』では、「外国籍・難民背景があることが原因で、賃貸探しで不便に感じたり、困ったことがあるか」という質問に対して、54.6%が「ある」と回答しました。
また、「不動産ポータルサイトで賃貸物件を探した際や、不動産会社の店頭に訪れた際、不便に感じたり、困ったこと」として、「『外国籍』であることがハードルとなり候補となる物件が少なかったこと(39.5%)」、「日本人の保証人が必須だった(31.1%)」、「日本語が読めず、分からなかった(28.6%)」、「『外国籍』『難民』であることを理由に差別を受けた/不平等さを感じた(25.2%)」、「来店、対応を断られた(24.4%)」などが挙げられました。
日本に暮らす外国籍の方は、言葉が通じないという固定観念を持つ日本人から「コミュニケーションが取りづらい」と思われているケースがとても多いのではないでしょうか。
「外国人だから」、「外国人風の顔立ちをした人は〇〇に違いない」という偏見や固定観念は、少なからず誰にでもあるのではないでしょうか。こうした無意識の思い込みに基づいた言動は「マイクロアグレッション」と呼ばれます。
大東文化大学教授の渡辺雅之さんは、マイクロアグレッションとは、「日頃から心の中に潜んでいるものであり、口にした本人に『誰かを差別したり、傷つけたりする意図』があるなしとは関係なく、対象になった人やグループを軽視したり侮辱するような敵対・中傷・否定のメッセージを含んでおり、それゆえに受け手にダメージを与える言動」のことと語ります。(※1)
難民を含む外国人、高齢者、LGBTQ、生活保護受給者であることなどが理由で住まい探しに困る人たちのことを、「住宅弱者」と呼びます。
不動産オーナーとして借り手の支払い能力や事故、トラブルのリスクを考慮に入れて判断することは一定程度の合理性を持つと考えられますが、相手の「社会的カテゴリー」のみで判断してしまうのは問題です。例えば、相手の事情を確認することなく、「外国人だからコミュニケーションが取れない」とか「友人を呼んで騒ぐかもしれない」と決め付つけるなら、それは不合理な扱いと言わざるを得ません。
出典:※1 知らずに相手を傷つけてしまう言動「マイクロアグレッション」を防ぐには?専門家に聞いた(日本財団ジャーナル)
差別のない社会を目指して

出入国在留管理庁が2024年3月に発表した資料によると、令和5年末の在留外国人数は、341万992人で前年末比33万5,779人、10.9%増で過去最高でした。在留資格で最も多かったのは永住者でしたが、次に大きな割合を占めたのが「技能実習」で前年に比べ約8万人も増加しました。
日本在住の外国人の割合が増加するにつれ、私たちの日常生活で自分とは違う言語を話し、異なる文化や宗教を実践する人たちと接する機会が増えてきます。前出の調査が示す通り、外国人に対する固定観念や偏見が存在していることを認識し、社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の視点を身に着けることが大切になってくるでしょう。
初のスウェーデン人落語家として日本で活躍する三遊亭好青年さんは、「外国人である」ことを理由に住まい探しに苦労したそうです。三遊亭さんはお互いを理解し合うための秘訣について「まず文化やルールの違いについては『外国人にはわからない』と決め付けず、どう対応すべきかしっかり説明してもらえたら嬉しいです。話せばわかることも、きっとあると思いますよ」と、コミュニケーションの大切さについて強調します。
ノルウェー出身の動画クリエイター、コメディアンであるMr Yabatan(ミスターヤバタン)さんも、賃貸物件の入居拒否を経験した一人ですが、やはりコミュニケーションの重要性を強調します。ヤバタンさんは「外国人がより日本で暮らしやすくなるためには、お互いのバックボーンや気持ちをイマジンすること、そしてコミュニケーションを取ることだと思います。小さなことでもやってみたら、世界が変わってくる気がします」と言います。
出典:令和5年末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁)
まとめ

世界のどこであっても偏見や固定観念は存在し、日本社会にもすでに構造化されている差別があります。それらを多面的に分析するのにインターセクショナリティは欠かせない視点です。
しかし、アメリカの人種差別を背景として議論されるインターセクショナリティは、日本においてはまだまだ認知度が低く、理解している人も少ないでしょう。日本では、国籍や人種の前にジェンダー、セクシュアリティ、そして障がい、見た目といった観点から差別意識が生まれ、それらが交差した社会構造の中に課題が潜んでいます。「自分には差別や偏見はない」と思い込まず、普段の暮らしの中で無意識に偏見、差別の目を向けてはいないか、社会生活における人との関わり方を見つめ直してみてはいかがでしょうか。
東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター特任教授。専門はジェンダー、セクシュアリティ、ディスアビリティ理論。一般社団法人ふぇみ・ゼミ&カフェ運営委員。著書に、『レズビアンである〈わたしたち〉のストーリー』(生活書院、2008年)、『合理的配慮――対話を開く、対話が拓く』(共著、有斐閣、2016年)や『クィア・スタディーズをひらく 1――アイデンティティ、コミュニティ、スペース』(共編、晃洋書房、2019年)、『「社会」を扱う新たなモード――「障害の社会モデル」の使い方』(共著、生活書院、2022年)などがある。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント
2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜
2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜
2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。
-
 2021/01/21不妊治療がうまくいかないなら子どもはあきらめなきゃ、なんてない。【前編】池田 麻里奈・池田 紀行
2021/01/21不妊治療がうまくいかないなら子どもはあきらめなきゃ、なんてない。【前編】池田 麻里奈・池田 紀行2度の流産と死産、10年以上にも及ぶ不妊治療を経験した池田紀行さん(現在48歳)と麻里奈さん(現在46歳)は、特別養子縁組で生後5日の赤ちゃんを迎え、現在家族3人で暮らしている。「血のつながらない子どもを本当に愛することができるのか」。それは、二人が不妊治療から特別養子縁組を受け入れるまでの10年もの間、ためらった問いかけだった。さまざまな葛藤を乗り越え、3人が見いだした「家族」のかたちとは?
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」