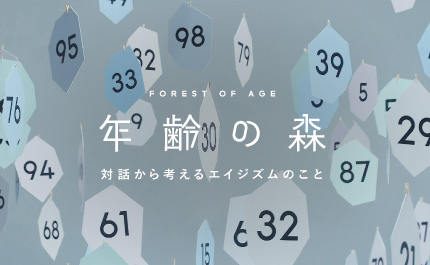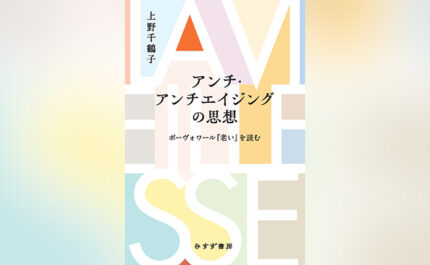高齢者に向けられるエイジズムとは?高齢者への差別・偏見・問題点と世界の取り組み
エイジズムとは、年齢に基づいた偏見のことで、対象には若者も含みます。ただ、高齢者に向けられることが多く、実際の行動に表れてはいなくても、多くの人が無意識のうちに持ち続けていることが少なくありません。自分の中に潜むエイジズムに気付くことがエイジズム克服の第一歩です。
この記事では下記の4点を解説します。
- 高齢者へのエイジズムとは?
- 高齢者エイジズムの問題点とは?
- 高齢者エイジズムを取り扱う映像作品3選
- エイジズムに対する世界の取り組み
高齢者へのエイジズムとは?
「エイジズム」とは、年齢に基づいた固定観念や偏見、差別のことです。言い換えると、「固定観念」とは、私たちの中にある考え方であり、「偏見」とは感じ方、「差別」とは実際に表れる行動を指します。
例えば、「高齢者は頑固だ」「頭が固い」「ITに弱い」などの固定観念を持っていれば、「高齢者に接するのは負担だ、面倒くさい」という偏見を生み、高齢者を「避ける」「無視する」「軽視する」といった差別につながります。
日本に限らず、世界のどの場所にも高齢者に対するエイジズムは存在します。例えば、WHOの報告書によると、スイスで実施された調査では、企業において全世代の53%の従業員が「高齢者のトレーニングは難しい」と信じており、52%の従業員は「高齢の社員は挑戦的な仕事への興味が薄い」と信じていたとのことです。
※出典::WHO Global report on ageism
高齢者エイジズムの問題点とは

高齢者エイジズムの問題点について、ここでは2つ取り上げます。
1つ目にエイジズムは人権侵害につながりかねません。「人権」とは、「全ての人が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」のことです。高齢者も含め、誰もが持っている人権をエイジズムは損なったり、奪ったりする可能性があるのです。
例えば、内閣府が2022年8月に実施した「人権擁護に関する世論調査」によると、「高齢者に関し、体験したことや、身の回りで起きたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことか」という質問に対し、「悪徳商法、特殊詐欺の被害が多いこと」を挙げた人の割合が44.7%と最も多く、以下、「病院での看護や介護施設において劣悪な処遇を受けること」(33.6%)、「高齢者が邪魔者扱いされること」(31.7%)、「働く能力を発揮する機会が少ないこと」(28.4%)、「経済的自立が困難なこと」(27.9%)の順でした。こうした調査結果が示す通り、高齢者に対する固定観念や偏見が具体的な差別という行動に表れ、人権侵害を引き起こしています。
※出典:人権擁護に関する世論調査(令和4年8月調査)調査結果の概要 – 内閣府
2つ目にエイジズムは「ジェロントフォビア(Gerontophobia)」につながります。ジェロントフォビアとは、老いに対する恐れや嫌悪ですが、その対象は他人ではなく、主に自分です。
米イェール大学公衆衛生大学院のベッカ・R・レビ教授らの研究によれば、老化に対して恐れや嫌悪を抱く人ほど、血圧や心拍数が上がったり、急性心筋梗塞からの回復が低下したりするとのことです。また、メンタル面でもストレスを感じやすく、結果として老化に対して前向きな人に比べて平均寿命が7.5年ほど短くなるという調査結果もあります。
年齢だけに基づき一般化してしまうエイジズムにより、「高齢者=容姿が衰える=能力が低い」という偏見に陥りやすくなります。そのため、自分が年を重ねることに対して前向きに捉えることはできず、「年を取ると能力が低くなる」などとネガティブな面ばかりに注目し、恐れが大きくなってしまうのです。
ジェロントフォビアを引き起こす原因として、SNSなどで拡散される動画があります。公共の場で高齢者が行う迷惑行為を一律に「老害」として取り上げるため、「高齢者=迷惑な人、理不尽にキレる要注意人物」というレッテルを貼ってしまいます。当然ですが、全ての高齢者が迷惑行為を行うわけではありません。あくまでも一個人の振る舞いであることに注意しなければ、誰でも容易にエイジズムに陥りかねません。
高齢者エイジズムを取り扱う映像作品3選

エイジズムは私たちの意識に根深くある偏見の一つであるため、自分でもなかなか気付けません。ここでは、自分の傾向を客観的に認知し、気付きを与えてくれる映像作品を3つ取り上げます。
1.『PLAN75』
『PLAN75』とは、少子高齢化が一層進んだ将来の日本で施行される「75歳以上は自ら生死を選択できる」という架空の制度のことです。夫と死別した78歳の主人公は高齢を理由にホテルの客室清掃の仕事を突然解雇され、住む場所も失いそうになります。そこで「プラン75」の申請を検討するようになります。
この映画には他にも「プラン75」の申請窓口で働く人や、「プラン75」の関連施設に転職したフィリピン人なども登場し、全世代に「生きる」という究極のテーマを問いかけます。
この映画に関してX(旧Twitter)には次のようなコメントが寄せられました。
自分は何歳まで生きるのだろうか
どうやって、一生を終えるのだろうか
最近、そういうことを考えるようになりました#コメントプラス しました映画PLAN75の「未来」避けるには 「簡単な処方箋はなくても」:朝日新聞デジタル https://t.co/sbwe6GwiIz
— 中川文如 (@nakagawafumi) January 16, 2024
2.『マイ・インターン』
アン・ハサウェイ演じる主人公ジュールズは、華やかなファッション業界で成功し、プライベートも充実している、誰もが羨むような人生を送っています。ある日、彼女は自分よりも40歳も年上である、ロバート・デ・ニーロ演じる70歳のインターンとしてベンを迎えることになります。最初はベンにイラついていたジュールズが次第に彼の豊富な経験や、シンプルな生き方から学び、変化していく、というストーリーです。
この映画に関してX(旧Twitter)には次のようなコメントが寄せられました。
『マイ・インターン』
とても素敵な作品でした。先入観や偏見にとらわれず新しい考え方や広い視野を手に入れる大切さや、インターネットは便利だけれど経験には勝てないことがあること、他人を思いやる親切心、でも自分で決めたことは貫くこと、見習いたいことが詰まってる映画です。 pic.twitter.com/B04h7m2QGM— プロフェッサーMM (@ProfesMM) February 19, 2021
何回見てもいい映画『マイ・インターン』
ロバート・デ・ニーロのいいおじいちゃん感がとても好き
自分も新しい物に偏見を持たず芯を持って歳を重ねていきたい
若い頃のグットフェローズとかタクシードライバーの役の感じも好きだけどこうやって歳を取って落ち着いた役も似合う pic.twitter.com/JyWAKl2Oem— jeroron (@jerororororon) June 22, 2021
3.「年齢の森」
「年齢の森」は、エイジズムをテーマにしたLIFULL発のドキュメンタリーフィルムで、10代から80代までの生き方も価値観も異なる11人が「年齢を重ねること」「高齢者とは?」「心の年齢は?」などの問いについてお互いの考えを伝え合います。こうした対話を通じて、今まで意識していなかった「エイジズム」に対する気付きを得ていきます。
▼関連ページはこちら
エイジズムに対する世界の取り組み

日本でも顕在化しているエイジズムに対して、私たちはどのように取り組んでいくべきでしょうか?ここでは、WHOとオランダの先進的な取り組みについてご紹介します。
1.WHO
国連総会は2021年から2030年の10年間を「Decade of Healthy Ageing」(ヘルシーエイジングの10年)と発表しました。具体的な取り組みには「年齢やエイジングに対する考え方や行動を変える」「高齢者の社会参加や貢献を促進する」「個々のニーズに対応した統合ケアやプライマリヘルスサービスを提供する」「介護を必要とする高齢者がケアにアクセスできるようにする」などが含まれます。
WHOは人口高齢化が医療システムだけでなく、労働や経済、サービスの需要など社会のさまざまな側面に影響を与える点に注目しており、社会全体としてのアプローチが必要だとしています。
※出典:WHO’s work on the UN Decade of Healthy Ageing (2021-2030)
2.オランダの取り組み
オランダ政府は2020年に「全国認知症計画 2021-2030」を発表し、認知症政策に関する今後の優先事項をまとめました。この戦略では「認知症のない世界:認知症研究」「認知症の人の尊重:スティグマ(特定の人や集団を大雑把にカテゴライズし、ネガティブなイメージを持ったり、不利益な扱いをしたりすること)や差別減少に向けて」「個々に合った認知症支援:支援やサービスの改善」の3点に重点が置かれています。
オランダでも高齢者に対するエイジズムの傾向が強まっていると言われています。その背景には、第2次世界大戦以降、3世代同居から核家族化へとシフトしてきたことに加え、夫婦2人暮らしや一人暮らし、母子家庭、LGBTのペアなど家族の形が多様化する中で、若者と高齢者が一つ屋根の下に住むことはほとんどなくなり、若者と高齢者との交流の機会が減っていることが挙げられます。
※出典:Nationale Dementiestrategie 2021-2030 | Publicatie | Rijksoverheid.nl
まとめ

エイジズムを乗り越えるためには、単に法律や制度を変えれば良いわけではなく、自分自身の意識を変えることから始める必要があります。気付きを与えてくれる映像作品や、他国の現状や取り組みを通じて、一人一人が自分の中にある根深い偏見に向き合うことが大切ではないでしょうか。
執筆:河合 良成
みんなが読んでいる記事
-
 2025/02/25なぜ、災害時にデマが起きるのか。│防災心理学・木村玲欧教授「善意のリポスト・転送が、助かる命を奪うかもしれない」
2025/02/25なぜ、災害時にデマが起きるのか。│防災心理学・木村玲欧教授「善意のリポスト・転送が、助かる命を奪うかもしれない」災害時のデマが引き起こすリスクについて詳しく解説しています。感情を揺さぶる巧妙なデマが増加する中、情報の真偽を確認し、防災に備えることの重要性を兵庫県立大学の木村玲欧教授が語ります。災害時に適切な情報活用法を知り、デマ拡散による危険を防ぐ対策を紹介しています。
-
 特集 2023/10/31【特集】本から学ぶ社会と自分の「しなきゃ」の視点
特集 2023/10/31【特集】本から学ぶ社会と自分の「しなきゃ」の視点 -
 2025/03/25つらくてもここで頑張らなきゃ、なんてない。 ―日本から逃げた「インド屋台系YouTuber」坪和寛久の人生のポジティブ変換術―坪和寛久
2025/03/25つらくてもここで頑張らなきゃ、なんてない。 ―日本から逃げた「インド屋台系YouTuber」坪和寛久の人生のポジティブ変換術―坪和寛久「インド屋台メシ系YouTuber」坪和寛久さんインタビュー。日本での挫折が転機となり、インドで自らの居場所を見つけた坪和さんのストーリー。ネガティブをポジティブに変える天才、坪和さんの人生のストーリーを伺いました。
-
 2024/01/25“年相応”でなきゃ、なんてない。―40歳、ロリータモデル青木美沙子が“好き”を貫く原動力―青木 美沙子
2024/01/25“年相応”でなきゃ、なんてない。―40歳、ロリータモデル青木美沙子が“好き”を貫く原動力―青木 美沙子ロリータファッションの先駆者でモデルの青木美沙子さん。長年モデルやインフルエンサー、また外務省に任命されたポップカルチャー発信使(通称「カワイイ大使」)として国内外にロリータファッションの魅力を発信しながら、正看護師としても働いてきた。活躍の一方で、ある時から年齢に関する固定観念に葛藤するようになる。自分らしい生き方を選んできた、青木さんの原動力や考え方について語ってもらった。
-
 2024/03/19「若いね」「もういい年だから」……なぜエイジズムによる評価は無くならないのか|セクシズム(性差別)、レイシズム(人種差別)と並ぶ差別問題の一つ「エイジズム」。社会福祉学研究者・朴 蕙彬に聞く
2024/03/19「若いね」「もういい年だから」……なぜエイジズムによる評価は無くならないのか|セクシズム(性差別)、レイシズム(人種差別)と並ぶ差別問題の一つ「エイジズム」。社会福祉学研究者・朴 蕙彬に聞く『日本映画にみるエイジズム』(法律文化社)著者である新見公立大学の朴 蕙彬(パク ヘビン)先生に、エイジズムに対する問題意識の気付きや、エイジズムやミソジニーとの相関関係について、またメディアやSNSが与えるエイジズムの影響や、年齢による差別を乗り越えるためのヒントを伺ってきました。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」