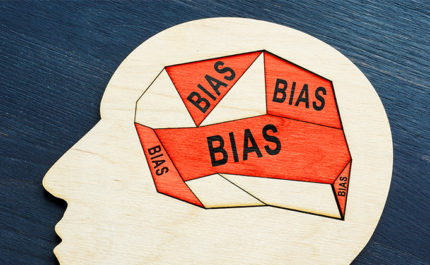目が見えないと写真は撮れない、なんてない。
大学院生だった24歳の時、事故で失明し全盲となった大平啓朗さん。それからも、子どもの頃から好きだった写真を撮り続けている。聴覚や嗅覚を研ぎ澄まし、音や匂いを頼りに、心が動いた瞬間を切り取る。だから、自らを写真家ではなく、“写心家”と名乗る。撮った写真を人が見て喜んでくれるのが何よりの喜び。そう、視覚を失っても、写真は撮れるのだ。

障がいには、大きく分けて生まれながらの「先天性」と、生まれた後に障がいが生じる「後天性」のものがある。24歳で失明した大平さんは、後天性の視覚障がい者だ。視覚から得る情報は、人間の知覚情報のうち約8割にも及ぶという。それほど重要な役割を果たしてきた視覚を失うということは、とてつもないインパクトをもって、その人の人生に襲いかかる。生活は一変し、それまで楽しんできたこともできなくなるかもしれない。それが、視覚を使って楽しむものであればなおさらだ。
大平さんが親しんできた写真撮影とは、まさに視覚があって成り立つ活動だった。しかし彼は、そんなことは意にも介すこともなく、今なお写真を撮り続けている。「目が見えなければ写真は撮れない」、果たして本当にそうだろうか? 写真家大平さんの心が写す、その景色とは――。
大好きな写真を撮ることと、
目が見えないことは関係ない
大平さんが、写真の魅力の虜になったのは、小学校低学年の時だった。家族パーティーの様子をフィルムで撮影。現像してみると、楽しかった時間が写真にそのまま写っていた。
「あの時の感動は今でも鮮明に覚えています。『僕がこの写真を撮ったんだ』と思うとすごく嬉しかったですね」
高校も大学も写真部。モノクロ写真の現像のやり方も覚え、大学時代はアパートの部屋を暗室にするほどのめり込んだ。

視力を失って「ワクワクした」自分がいた
しかし、山形大学理学部の大学院生だった大平さんは、薬品の誤飲が原因で、視力を失う。研究室にあった薬品をペットボトルに入れ、友人との飲み会に参加したのだが、目を覚ました時、鏡に写っていたのは、視点が定まらず「不気味な」顔をした自分だった。飲み会で飲んだ薬品は、アルコールの一種「エタノール」のつもりだった。しかし、飲むと最悪死に至る「メタノール」だったのだ。病院に行くと意識を失い、3日間、生死の境をさまよったが、一命は取り留めた。しかし、目の前が霧に包まれ、何もはっきりとは見えない。日が経つにつれ、失われていく視力。目の前の霧がどんどん濃くなっていった。
しかし、大平さんにとって、“失明=絶望”ではなかった。自分の行動に対する後悔や両親への申し訳なさはあったが、「ワクワクもしていた」と振り返る。にわかには信じがたいその心境を、人生をゲームに喩えて教えてくれた。
「僕、RPGが好きだったんですよ。目が見えなくなった時に思ったのは、クリアしたゲームをもう一回やれるなってこと。『新しいゲームが始まるんだ』ってワクワクしたんです。ゲームの主人公ばりに、何でもできる無敵感に溢れてました。だって、攻略法をバッチリわかった状態で、ゲームをリセットしてやり直せるんですよ。これからまた、何だってやりたいことができるし、それって、とてつもなく幸せだなって」
目が見えた人生で得た「攻略法」があれば、これから新たに始まる、目が見えなくなった人生は、もっと楽しめるのではないか。全盲という事実を、とてつもなくポジティブに受け止めた。

好きで続けていることに、目が見えるかどうかは関係ない
そうは言っても、すべてがこれまで通りとはいかない。日常生活を営む技術を身につけるため、自立訓練施設に通い、白杖を使っての単独歩行やパソコン画面を読み上げるソフトの訓練を受けた。その後は、47都道府県を旅したり、音楽活動をしたり、目が見えなくなってからの人生を謳歌している。その傍らには、いつもカメラがあった。
「目が見えなくなったからって、写真が撮れなくなるとは、一切思わなかったですね。これまでやめようとしたことも一度もありません。目が見えない人、そして目が見えている人にも、全盲の人が写真を撮る姿を想像しにくいかもしれませんが、『目が見えないと写真は撮れない』というのは、よくない決めつけじゃないかなって思うんです。僕が好きな写真を続けることと、目が見えるかどうかはまったく関係ないのに」

視覚以外の感覚と心で撮るから“写心”
しかし、目が見えないのに、どうやって撮るのだろう。疑問をぶつけてみた。すると、大平さんは「目をつぶってみて」と返した。
「今、何も見えてないでしょう。これが、僕が生きている世界です」
当然だが、何も見えない。方向感覚やモノ・人との距離感や、方向感覚を失い、人がいかに視覚情報に頼っているかを思い知らされる。この状況で写真を撮ることは、どうにも想像ができなかった。しかしその時、大平さんは、スタッフの名前を呼び、返事があったほうを向いた。そして、しばしの雑談。お互いリラックスし始め、笑い声が上がった瞬間を逃さず、シャッターを切った。
「人物を撮りたい時は、その人の声の大きさや聞こえてくる向き、会話の間がヒントになります。話しながら『今、この瞬間、この素敵な笑顔を撮りたい!』って僕の心が動いた時を狙ってシャッターを切るんです。そんなふうに撮っていたら、当時住んでいた函館の知人たちから『心で撮ってるんだね』と言われて、なるほどと思ったんですよね。それからは、“写心家”と名乗り、自分の撮ったものを“写心”と呼ぶことにしたんです」
最後は必ず、どんなシチュエーションで、何に心を動かされたのか、デジカメの音声録音機能を使って記録する。そうしておけば、いつでも、その場の光景やその時の感情が甦ってくる。写真の選定にも役に立つ。

信じられるのは、自分の感覚だけ
イメージさえ湧けば、被写体は選ばない。人物でも風景でも何でも撮るという。街の雑踏に行くと、両手を叩いたり、白杖で地面を叩いてその反響音から、自分の周りにあるものの大きさや距離を確認。そして、顔を上げ、温度を感じ、光が差してくる方向を見つける。
「足音の種類や歩幅、人やモノがすれ違うスピードからドラマが浮かんでくるんですよね。だから、『ここには、白い看板があって、その隣は……』と周りの人から説明されて撮るのは好きじゃないんです。自分が感じたものを、自信を持って見てほしいから。目が見えていた頃から、人から言われるのがイヤなタイプではあったんですけどね。それを知っている友達は、僕の撮影スタイルを見て『相変わらずだな』って言ってます(笑)」
函館の街を散歩中に撮った一枚は、だんだん近づいてくる葉の揺れる音に惹かれたという。まず、ガサガサ、カサカサといった葉音の微妙な違いから、木のシルエットを頭の中に描き出した。杖で幹を叩くことで、幹の情報が加わり、木のイメージはより具体的になっていく。木の周りを時間をかけて歩き、葉の隙間から落ちてくる木漏れ日の温もりがいちばん優しく感じられるベストポジションを探り、描いたイメージがもっとも色づいたタイミングでシャッターを切った。夏の青々と茂った緑と強い光のコントラストが見事に表現されている。

「音、光、温度、空気の流れ、匂い……。いろんなことを感じ取ってるんです。“写心
”は、目に入ってくるものを撮っているわけではないことがわかってもらえたら嬉しいですね」
誰かが喜んでくれる限り、撮り続ける
目が見えなくなってから、撮る時は、最初に感じたことをより大切にするようになり、構図へのこだわりはなくなったという。では、目が見えなくなってからも変わらなかったことは何だろうか。
「僕にとって、写真は人とのコミュニケーションツール。写真を撮っている時、撮った後のコミュニケーションを楽しんでいます。これは、初めて現像した写真に感動した時から、まったく変わっていません。だから、僕の目が見えても見えなくても、誰かが喜んでくれるんだったら、僕は撮り続けるし、喜ぶ人がいないならやめる。ただ、それだけのことです」
これまでたくさんの人に助けられ、自らも写真を通じて気持ちを交わし合ってきた。改めて、出会いの大切さが身に染みている。

1979年、北海道生まれ。NPO法人「ふらっとほ~む」理事長。2008年、筑波大学で心理学を学ぶ。16年、旅をテーマに自身が制作した楽曲『さぁーいこう!やれるさ』『ゆめの星たち』の手話・字幕・音声ガイド付きMVを監督。現在は、講演会などで全国を回る日々を過ごしながら、自身の半生やメッセージを綴った著書を 執筆中。
オフィシャルサイト http://flat-home.com
みんなが読んでいる記事
-
 2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子
2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。
-
 2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと
2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。
-
 2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会
2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。
-
 2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト
2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。
-
 2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題
2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。