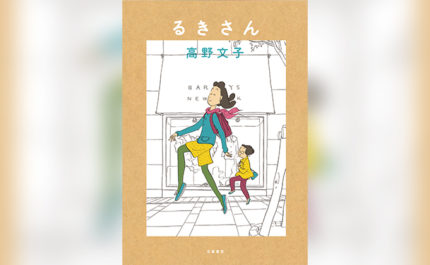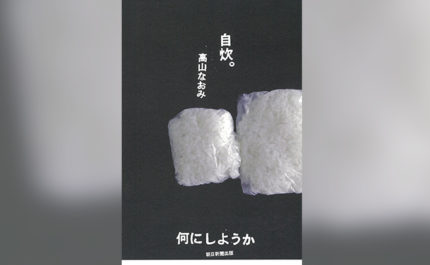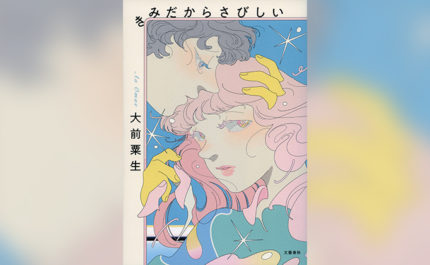“抗えない老い”の受け止め方を見つめ直す「アンチ・アンチエイジング」の思想
日常の中で何気なく思ってしまう「できない」「しなきゃ」を、映画・本・音楽などを通して見つめ直す。今回は『アンチ・アンチエイジングの思想――ボーヴォワール『老い』を読む』(上野千鶴子/みすず書房)から、『年齢で区切らず、すべての人が何歳でも堂々と自分らしく輝ける未来を想像できるのか』について考えます。
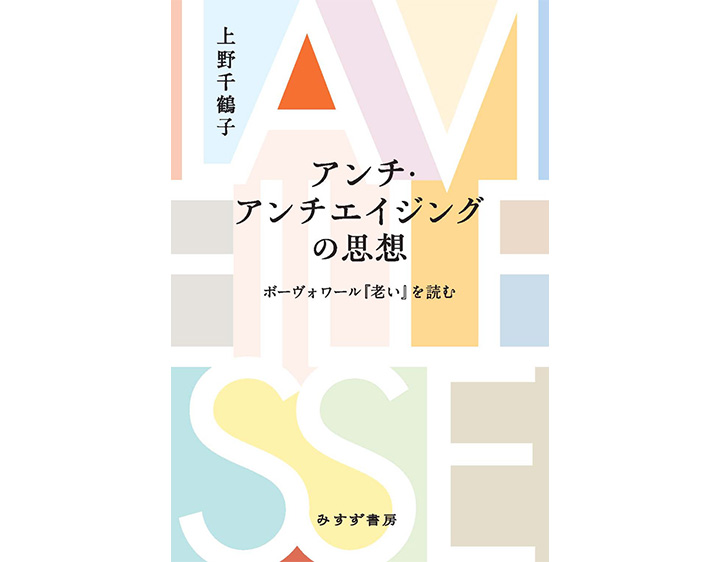
アンチ・アンチエイジングの思想――ボーヴォワール『老い』を読む(上野千鶴子/みすず書房)
日本は今、「超高齢社会」である。超高齢社会とは、65歳以上の人口の割合が総人口の21%を占めている社会のことだ。実際、内閣府が公表した令和7年版の「高齢社会白書」では、総人口に対する65歳以上の人口率は29.3%であった。
総人口の減少という問題も抱えている日本では、高齢者を支える現役世代の人口比率も減少している。「高齢社会白書」によれば、昭和25年に65歳以上の高齢者ひとりに対する現役世代の人口比率(15~64歳)は12.1人だったが、令和5年には2.0人であったそう。
今後も、高齢化率の上昇や現役世代の人口比率の低下は続くと予想されており、令和52年には65歳以上の高齢者ひとりに対して現役世代1.3人という、より厳しい現実になるだろうと「高齢社会白書」は指摘する。
歳を重ねることや自立できなくなる未来に不安が募って当然なこの現状の中で、私たちは一体、どう自分の老いを受け入れていけばいいのだろうか。
『アンチ・アンチエイジングの思想――ボーヴォワール『老い』を読む』(上野千鶴子/みすず書房)は、そうした疑問を持った時に開いてほしい一冊だ。
著者の上野千鶴子さんは社会学者で、東京大学名誉教授。家族社会学やジェンダー論、女性学を専門としており、家族社会学者や女性学研究者の立場から、積極的にフェミニズムの思想を世に伝えてきた。
本書は70代になった上野さんが、フランスの作家で哲学者のシモーヌ・ド・ボーヴォワールの『老い』を読み説いた作品である。『老い』は、ボーヴォワールが62歳で執筆した。
上野さんは歴史的、哲学的、社会的など様々な角度から「老いとは何か」を深く追求するボーヴォワールの一言一句を丁寧に受け止めつつ、各国の高齢者福祉の歩みや様々な文献、統計などを用いて、私たちが老いを恐れる理由を考察。
加えて、老いて弱くなることを否定する「アンチエイジング」にアンチ(「反対」「対抗」の意)を唱える、「アンチ・アンチエイジング」という思想の重みを訴えている。
老いとは他人になる経験である
老いは、誰しもに平等に訪れるものだが、人は他者の老いを「劣化」と嘲笑い、自分の老いには必死で抗う。「アンチエイジング」という思想はいつの時代も私たちの心を引き付け、同時に老いへの恐怖心を煽り立てる。
一般的に「アンチエイジング」は美容の領域で使われることが多いが、本書に綴られているのは美容関連の「アンチエイジング」への批判ではない。老いに抗う行為を「アンチエイジング」という言葉で表現している。
老いは文明のスキャンダルである
アンチ・アンチエイジングの思想――ボーヴォワール『老い』を読む(上野千鶴子/みすず書房)(引用/P1)
かつて上野さんは『老い』に綴られていたと記憶していたこの言葉に頭を殴られたような思いがし、自身が老いた今、「時が来た」と感じ、同書を深く読み解くことにしたという。
本書ではボーヴォワールが生きた1908年から1986年のフランス社会にあった老いの捉え方や考え方も知ることができるのだが、そこから感じ取れるのは、いつの時代も人々は老いを忌避しているという事実だ。
実際、自分の中にも“老いへの恐怖心”はある。だから、「老いとは他人になる経験である」というボーヴォワールの言葉が胸に刺さった。自分が感じてきた言語化できなかった戸惑いや恐怖心を見透かされたような気がしたからだ。
人はみな老いていくのに、なぜか私たちは「自分は変わらない」と思っている。いや、思い込みたいのだ。だから、他者の老いは“笑い話のネタ”にできるし、時には自分よりも年上の人に差別的な言葉を向けることもある。
だが、そんな風に「老い」を他人事と思っているからこそ、知らない人から「おばさん(おばあさん)」や「おじさん(おじいさん)」と呼ばれると、“自分が見ている自分”と“社会から見える自分”のギャップに戸惑う。
電車の窓に映る自分の顔がずいぶん老けたことに気づくなど、日常の中で食らう“思わぬ一撃”のダメージも大きい。
弱くても尊厳を持って自分を生ききる「アンチ・アンチエイジング」の思想
なぜ、老いの自己受容はこんなにも難しいのだろう。そして、アンチエイジング以外の思想で老いと向き合うことはできないのだろうか。
そう悩む人に上野さんが提唱するのは、弱いまま尊厳を持って生ききる「アンチ・アンチエイジング」という思想だ。
アンチ・アンチエイジングは「活き活きと老後を楽しむ」などという短絡的な思想ではない。上野さんは高齢社会を研究し、今日できたことができなくなるという“老いの現実”を知っているからこそ、明るくも楽しくもない老いの過程や老い衰えて弱くなる自分をどう受け入れるかを、綺麗事抜きで説く。
中でも、心にずしっときたのが、上野さんが講演会の後で伝えることがあるという、この言葉だ。
「人間、役に立たなきゃ、生きてちゃ、いかんか」
アンチ・アンチエイジングの思想――ボーヴォワール『老い』を読む(上野千鶴子/みすず書房)(引用/P259)
現代社会ではタイパやコスパが重視され、人間も効率的であることを求められているように感じられる。だが、そんな時代だからこそ、考えたい。私たち人間は効率的で誰かの役に立たなければ価値がないのだろうか、と。
人は人の手を借りて生まれ、人の手を借りて死んでゆく。そういうものだ。そのどこが悪いのか。
アンチ・アンチエイジングの思想――ボーヴォワール『老い』を読む(上野千鶴子/みすず書房)(引用/P301)
そう語りかける上野さんは、こんな疑問も投げかける。老いて自立できなくなり「弱者」と呼ばれる存在になっていくのは悪なのだろうか。本当の悪は周囲への依存を可能にしない(できない)社会なのではないか、と。
「老害」という言葉が普通に飛び交い、高齢者問題を“お荷物”として捉える人も少なくないのが、日本の実情だ。そんな社会であるからこそ、老いて弱り、「弱者」という存在になる恐怖心に寄り添い、弱いままでも尊厳を持って生ききることができると訴える「アンチ・アンチエイジング」の思想は心の支えになる。
医療の発展などで、人類は長生きできるようになったが、悲しいことに、先人たちが望み続けた“長寿”は予想以上に残酷であった。だから、現代人は長寿よりも、身内に迷惑をかけない“ピンピンコロリ”を願うようになってきているが、それもアンチエイジング思想のひとつだと上野さんは指摘する。
人生の最期に「ピンピンコロリ」を願わないために社会は、どう変わっていけばいいのか。そして、最後まで自分らしく生ききるには、私はどう「老い」を受け入れていけばいいのだろう。
そう考えたくなる本書は今まさに老いに直面している方だけでなく、老後など考えてもいない年代の方にも勧めたい一冊だ。
文=古川諭香
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」