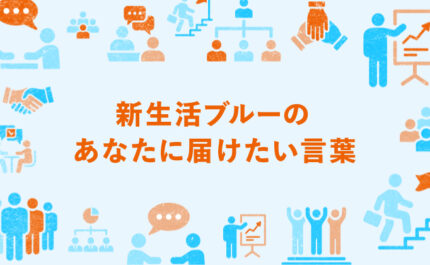表舞台じゃないと輝けない、なんてない。
“華やか”で“幸福”、そして“夢”が生まれ、かなう場所。そこに、自らの信念で辿り着いた女性がいる。ガールズダンス&ヴォーカルグループの「Dream」「E-girls」の元ヴォーカル、Ayaさんだ。ステージでスポットライトを、カメラの前でフラッシュを浴びてきた彼女は、自ら表舞台を去り、後輩たちをサポートする道を選んだ。Ayaさんの唯一無二な人生を辿れば、誰もがぶつかる「人生の岐路」を乗り越えるヒントが見えてくる。

キャッチーな楽曲とキレのあるダンス、トレンドの一歩先を行くファッションで注目を集めるガールズ・エンタテインメント・プロジェクトとして始動した「E-girls」。その初代リーダーを務め、グループをまとめ上げてきたのが、E-girlsを構成するグループのひとつ「Dream」のメンバーでもあるAyaさんだ。
大規模なアリーナツアーの成功やNHK紅白歌合戦への連続出場など加速度的に成長するグループをけん引して来た彼女。昨年6月、グループ拡大に伴う新体制が発表される中、彼女自身はアーティストとしての引退を発表。長かった下積み時代を経てブレイクをつかみ取り、多くのファンからの憧れを一身に集める彼女が、自ら下した決断。その裏には、周囲に流されない彼女の確固たる信念から生まれる “新たな夢”があった。

ずっとこの世界にいたい、
と思ったからこその
“引退”だった
Ayaさんが芸能界にデビューしたのは15歳のとき。当時エイベックス・グループに所属していたdream(Dreamの前進)の追加メンバーオーディションに応募し、見事合格を勝ち取った。しかし、加入からの数年間はまだ知名度が無い状況。楽曲のリリースや音楽番組の出演など、本来やりたい活動はなかなかできず、当時大ブームだった芸能人女子フットサルリーグでしかメディアへの露出が無い状況が続いた。
「正直不安はありました。でも、『いつか音楽につながる。私たちが、スポーツと音楽の架け橋になれるはず』という気持ちで踏ん張り続けたんです」
しかし、フットサルブームが終了すると、彼女たちに待ち受けていたのは「解散危機」だった。中学時代から芸能一筋だったAyaさんは、人生の指標を見失ってしまう。
「芸能界は芽が出なければ続けられない厳しい世界ですし、当時所属していたエイベックスの方は私たちのために、感謝してもしきれないほどいろいろな手を尽くしてくれました。ブレイクできなかったのはその結果だったんです」
事務所からは「まだ全く違う道も目指せる年齢だから……」という言葉もあったという。このときAyaさんには、芸能以外の道を目指すという選択肢は無かったのだろうか?
「『まだまだ努力が足りない』というのが率直な気持ちでした。報われるという自信があったわけではないのですが、『まだ何も結果を出していないのに、諦めるなんてありえない』と感じて。悩む余裕もありませんでした」
その気持ちは、他のメンバーも同じ。「続けたい」という思いで一致し、路上でのライブを開始するなど活動を模索する。そんな彼女たちをすくい上げたのが、当時EXILEのリーダーとして活動していたHIROさんだった。

信念が動かした運命の歯車
事務所から離れる直前、所属アーティストが集まる食事会に参加したAyaさんは、HIROさんと“再会”する。彼はかつてdreamにダンスを指導していたのだ。
「当時は私たちにとって、親しみのある“先生”という存在でしたが、その後どんどん有名になられて、そのときもお会いするのは久々でした。でも、HIROさんから『元気?』と声をかけてくださって……。事務所を離れることを報告すると、『もったいないね』と残念がってくれました」
同時に、当時のマネージャーさんも、Ayaさんたちの諦めない姿勢を見て動きだす。エイベックス・グループ代表取締役、松浦勝人さんに直談判すると、松浦さんは旧知の仲であるHIROさんに連絡。dreamを気にかけていた彼は、すぐに彼女たちに自身のプロダクションLDH(現 LDH JAPAN)への所属をオファーした。
「HIROさんとLDHには本当に感謝しています。以前の事務所を離れることになったとき、続ける意思は固かったのですが、実際には収入はゼロになりましたし、住む家も出ていかなければならなかった。自分には何も無いと思ったとき、『そうじゃないんだよ』と言ってもらえた気がしました」
積み上げた実力があったから得た、ブレイクと信頼
そして2011年。HIROさんの発案により、ガールズ・エンタテインメント・プロジェクト「E-girls」が始動する。「Dream」「Happiness」「Flower」という独立した3つのグループが一堂に会するというこれまでのガールズグループに無い形態は、一躍世間の注目を集めた。それぞれに違うストーリーを持つ3つのグループ、違う個性を持つ20人以上のメンバー。まとまるのは困難なはずだ。しかし、5つのグループ、40人以上のメンバーを擁する「EXILE TRIBE」を有機的に融合させ、進化させてきたHIROさんの手腕により、E-girlsの人気は瞬く間に爆発した。

E-girlsの魅力は枚挙にいとまがないが、特筆すべきはパフォーマンスレベルの高さだ。10人以上のメンバーが、一糸乱れぬ歌とダンスを披露する。日陰の時代にも向上心を持ち続けてきたAyaさんたちメンバーの努力が実った瞬間だ。彼女たちのファッションやダンスをコピーするファンが急増し、アリーナツアーの実施や紅白歌合戦出場も果たすなど、グループは加速度的に成長していく。Ayaさんも憧れ続けたステージの上で、憧れられる存在として懸命にパフォーマンスに励んだ。
そんなあるとき、AyaさんはHIROさんに呼び出される。そこで告げられたのは、E-girlsのリーダーへの就任要請だった。
「最初はお断りしました。そもそもE-girlsはリーダーをあえて決めていなくて、『Dream』『Happiness』『Flower』それぞれにも特定のリーダーはおらず、“みんながリーダー”という意識でやっていましたから。3つのグループの、20人以上の女の子たちをまとめるなんて、自分には想像もできなかったですし、自分のグループやパフォーマンスだけで精一杯という思いでした」
しかし、HIROさんの意思もまた固く、他のメンバーからのAyaさんへの信頼も厚かった。苦楽を共にしたDream Amiさんから「Ayaちゃん、絶対やったほうがいいよ!」と背中を押され、Ayaさんはリーダー就任を引き受けることを決意する。

夢をつかんだからこそ見えた、その先のビジョン
リーダーになったことで、Ayaさんには自分自身でも思いがけない変化があったという。それは、自分以外の才能を見つけ、伸ばし、育てる喜びを感じるようになったことだ。
「E-girlsの中には、私より年齢が一回りも下のメンバーもいます。リーダーとして全員が気持ちよく活動できる空気づくりを心がける中で、そういった若い世代の子たちが持っている才能に改めて気づかされましたし、私がかける声や指導によって、こんなにも輝くんだというのを目の当たりにしました。そうなると、LDHが運営するダンススクールに通う子たちにも自然と目が行くようになって……。後輩たちを輝かせる環境づくりに私も協力したいと考えるようになったんです」
そして、HIROさんから受けた学びも、Ayaさんの視野をさらに広げることになる。
「HIROさんは、トップパフォーマーから退き、プロデューサーとしてLDH全体をまとめてこれだけ大きなプロダクションにまで成長させた方。私はLDHに来てからの10年間でその過程を間近に見てきて、芸能の世界でも表舞台だけが輝ける場所じゃないんだということを実感したんです。
HIROさんから頂いた言葉の中でも、『グループに何かひとつ伝えたとき、全員がわかってくれたと思っちゃいけないよ。みんなそれぞれ個性がある。一人一人に向き合って、丁寧に伝えるべきだ』という教えが心に残っています。その教えを胸に後輩たちと接し、一人一人が成長する姿を見るたびに、彼女たちをサポートする仕事に全力を尽くしたい思いが徐々に強まりました」
そして2017年、さいたまスーパーアリーナで行われたメモリアルライブ「E-girls LIVE 2017 ~E.G. EVOLUTION~」を最後に、Ayaさんはヴォーカル、パフォーマーを引退し、新たな道へと足を踏み出した。

彼女だけができること、やらなければならないこと
現在の肩書は、E-girlsを中心としたプロジェクト「E.G.family」のチーフ・クリエイティブ・マネージャー。その活動は多岐にわたり、業界でも独特のポジションだ。
「アーティストでもなくマネージャーでもない、独自のポジションで活動させていただいています。もともと好きだった絵や写真で、ヴィジュアル面をディレクションすることもありますが、もっとグループの根幹に関わる仕事も多いです。例えばリリースするCDの企画段階から会議に参加したり、全体の方向性を考えるところから関わらせていただいています」

メンバーともプロダクションとも、そしてファンとも近い存在。その特殊な立ち位置だからこそできる仕事にやりがいを感じるという。
「カメラの前やステージを経験した私だからこそ、スタッフさんがいい準備をしてくれたときにどれだけパフォーマンスに集中できるかがわかる。細かな作業一つ一つも絶対に手を抜きません。
同時に、メンバーたちにスタッフさんへ感謝することの大切さを心から伝えられるのも両方を経験した私の立場だけ。メンバーとスタッフさんをより強くつなげることで、一体になる手助けをしたいと思っています。E.G.familyをより魅力的な集団にすることが私の生きがいであり、引退を惜しんでくれたファンの方々との約束でもあります」

私が表舞台から去ったのは、一生音楽やダンス、エンタテインメントの世界にいたいと思ったから。自分自身がパフォーマンスをし続ければ、いつか限界が来て、燃え尽きてしまう。それよりも、これからどんどん輝いていくE.G.familyのメンバーや後輩たちに私自身の思いを託しながら、彼女たちが輝くために力を尽くしたい。みなさんに届く作品やパフォーマンスの裏では、必ず私も関わっています。
今思えば、全ては人との縁だなと思います。HIROさんやLDH、メンバーや後輩たちに出会えたことが、今の私を作っています。これを読まれている方の人生には、苦手な人や付き合いづらい人ももちろんいると思いますが、自分の悪いところを指摘してくれたり、叱ってくれたりする人がいない状況のほうが怖いと私は思います。いろんな人と出会って話をして、自分の道を決めていってほしいです

1987年、大阪府生まれ。ガールズ・エンタテインメント・プロジェクト「E.G.family」のチーフ・クリエイティブ・マネージャー。2002年に「dream」のメンバーとしてデビュー。11年に発足した「Dream」「Happiness」「Flower」の合同プロジェクト「E-girls」に参加。13年からはリーダーに就任。17年7月、ヴォーカルとパフォーマーを引退し現職に就任。TOKYO HEADLINE WEBに「Dream Ayaのフォトコラム【フォトバイアヤ】」を連載するなど、フォトグラファーとしても精力的に活動し、注目を集めている。
みんなが読んでいる記事
-
 2023/04/11無理してチャレンジしなきゃ、なんてない。【後編】-好きなことが原動力。EXILEメンバー 松本利夫の多彩な表現活動 -松本利夫
2023/04/11無理してチャレンジしなきゃ、なんてない。【後編】-好きなことが原動力。EXILEメンバー 松本利夫の多彩な表現活動 -松本利夫松本利夫さんはベーチェット病を公表し、EXILEパフォーマーとして活動しながら2015年に卒業したが、現在もEXILEのメンバーとして舞台や映画などで表現活動をしている。後編では、困難に立ち向かいながらもステージに立ち続けた思いや、卒業後の新しいチャレンジ、精力的に活動し続ける原動力について取材した。
-
 2025/06/30ウェルビーイングの最新潮流石川 善樹
2025/06/30ウェルビーイングの最新潮流石川 善樹ウェルビーイングとは何か?予防医学博士・石川善樹さんが語る“よく生きる”ための科学的アプローチとは。LIFULLセミナーの模様をダイジェストで紹介。
-
 2024/05/17女性の生き方に「しなきゃ」、なんてない。 ―LIFULLのリーダーたち―LIFULL FaM事業 CEO 秋庭 麻衣LIFULL FaM事業 CEO 秋庭 麻衣
2024/05/17女性の生き方に「しなきゃ」、なんてない。 ―LIFULLのリーダーたち―LIFULL FaM事業 CEO 秋庭 麻衣LIFULL FaM事業 CEO 秋庭 麻衣2024年4月1日、ソーシャルエンタープライズとして事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLは、チーム経営の強化を目的に、新たなCxOおよび事業CEO・責任者就任を発表しました。性別や国籍を問わない多様な顔ぶれで、代表取締役社長の伊東祐司が掲げた「チーム経営」を力強く推進していきます。シリーズ「LIFULLのリーダーたち」、今回はLIFULL FaM事業CEO秋庭麻衣に話を聞きます。
-
 2024/05/24
2024/05/24 “できない”、なんてない。―LIFULLのリーダーたち―LIFULL HOME'S事業本部FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群(キョウ イグン)
“できない”、なんてない。―LIFULLのリーダーたち―LIFULL HOME'S事業本部FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群(キョウ イグン)2024年4月1日、ソーシャルエンタープライズとして事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLは、チーム経営の強化を目的に、新たなCxOおよび事業CEO・責任者就任を発表しました。性別や国籍を問わない多様な顔ぶれで、代表取締役社長の伊東祐司が掲げた「チーム経営」を力強く推進していきます。 シリーズ「LIFULLのリーダーたち」、今回はFRIENDLY DOOR責任者の龔軼群(キョウ イグン)に話を聞きます。
-
 2023/02/21【後編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説
2023/02/21【後編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説少子高齢化により、日本の人口減少は加速しています。その結果、さまざまな問題が引き起こされていますが、その一つが空き家問題です。「家の片付けができていない」「売りたくても売れない」といった理由で空き家を放置している所有者も少なからずいて、相続した家が「負の不動産」となり得る問題もはらんでいます。総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、2018年時点での空き家は全国で約848万9000戸と過去最大となっており、空き家の管理や活用は喫緊の課題と言えるでしょう。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。