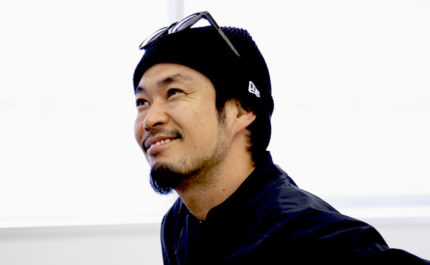地方移住で仕事を探す方法は? 移住先の働き方、自治体支援制度の活用、移住体験者の事例を解説
自分らしいライフスタイルを追求するため、生活の基盤を地方へと移す「地方移住」への関心が高まっています。働き方改革が進み、リモートワークで働けるようになったことをきっかけに、大都市を離れ地方移住を決意した人も少なくないようです。しかし、実際に移住をするとなると考えるべきことはたくさんあります。特に転職や独立など、仕事を変えるケースでは移住先にどんな仕事があるのか、どんな働き方をするのか不安な人もいるでしょう。
移住を考え始めた人に向けて、この記事では以下の6点を解説します。
- コロナ禍で高まる地方移住への関心
- 地方移住先の働き方には何がある?
- 移住先で仕事を見つける方法は?
- 地方移住で新しい働き方を見つけた人
- 地方移住後の暮らしに対して不安に思うこととは?
- 地方移住や新しい暮らし方を通じて自分らしい生き方を実現した事例
(最終更新日:2023/9/13)
コロナ禍で高まる地方移住への関心

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が2020年5月に発表した「移住等の増加に向けた広報戦略の立案・実施のための調査事業報告書」によると、20~59歳の東京圏在住者の49.8%が「地方暮らし」に関心を持っていることが分かりました。また、東京圏出身者よりも地方圏出身者の関心が高いこと、中高年よりも若者が地方移住に高い関心を持っていることも分かりました。
出典:「移住等の増加に向けた広報戦略の立案・実施のための調査事業 報告書」(内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局)
こうした傾向を踏まえ、各自治体も移住者を呼び込み、定住させようとさまざまな政策を実施しています。
地方移住への意識が高まっている理由の一つはコロナ禍によるテレワーク導入など、働き方の変化だといわれており、その動きはとりわけ東京圏で目立っているようです。
内閣府の「第6回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によると、地方移住に「関心がある」と答えた東京圏在住者の割合は、2020年5月には30.2%だったものが、2023年3月には35.1%まで上昇していました。その理由は、「テレワークによって地方でも同様に働けると感じたため」という内容が2番目に多い結果となりました。
※出典:「第6回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」内閣府
コロナ禍を契機に移住の希望者が増えていますが、この傾向は新型コロナウイルス感染症による一過性のブームではないと思われます。というのも、認定NPO法人ふるさと回帰支援センターが2021年10月に公表した「地方移住に関する調査結果」では首都圏の地方移住希望者は約309万人と推計されていますが、その要因を新型コロナウイルス感染症だと答えた人は、地方移住を検討している人全体の3割ほどにしか達していなかったからです。今後、コロナ禍が落ち着いても、移住を希望する人は一定程度いることが予想されます。
※出典:地方移住に関する調査結果公開 – 認定NPO法人 ふるさと回帰支援センター
また、総務省の「『地方への人の流れの創出』に向けた効果的移住定住推進施策事例集」によると移住先の住居形態について新築の持ち家の割合が2017年の36.9%から2020年には30.9%と低くなり、中古の持ち家を希望する割合が13.5%から20.6%へと高まっています。これにより今後地方の空き家活用が進むことも期待されます。
出典:「地方への人の流れの創出」に向けた効果的移住定住推進施策事例集(総務省)
地方移住先の働き方には何がある?

地方移住と言っても、ふるさとに戻って家族と暮らすため、都会を離れて地縁のない地方で農業をするため、定年退職後に田舎暮らしをするためなど目的はさまざまです。転職や結婚、子育てなどのライフイベントにも影響します。まずは移住する目的や理想の暮らし方、働き方を明確にして移住先を決めると良いかもしれません。移住をきっかけに働き方は変わります。ここでは地方移住の働き方を3つ紹介します。
働き方①就職する
企業や自治体に所属し、社員・職員として働きます。就職先は転職支援サイトや地方創生推進サイトで移住先の地方や田舎の求人情報を検索できます。
働き方②起業する
個人事業主や会社を設立して起業する方法です。国や自治体による公的支援制度を活用することで、必要なコストを抑えられます。
働き方③地域おこし協力隊制度を利用する
総務省が実施する地域おこし協力隊制度を利用して働きます。各自治体が募集している地域おこし支援や農林水産業に応募すれば、一定期間は報酬をもらいながら働けます。地域おこし協力隊については、下記リンクを参照ください。
移住先で仕事を見つける方法は?
地方移住を成功させるためには、入念な調査と準備が不可欠です。移住者を積極的に誘致している自治体は求人情報の発信や支援制度を整備しているので、情報収集に努めてください。
まずは、自治体が開設している「就職支援相談窓口」や「ハローワーク・インターネットサービス」を利用しましょう。また、都内在住の方は認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」の窓口で直接相談するのも手です。ここでは、北海道から沖縄まで全国約5700を超える自治体と連携し、地方移住希望者をサポートしています。ハローワークもあるため、就農も含めた仕事の相談も受け付けています。
国内唯一!全国の移住相談ができる窓口|ふるさと回帰支援センター
現地企業の採用担当者と直接コミュニケーションを取れるのが、就職・転職フェアなどのイベントです。U Iターン希望者を積極的に採用している企業が参加しているので、興味が湧いた企業とオンライン面談ができます。フェアイベントは、各自治体が主催なので移住先のエリアが明確な人は、自治体へ問い合わせてみると良いでしょう。
「まだ、移住したいエリアが明確になっていない」または「農業体験をしてから考えてみたい」という人は移住関連イベント情報をまとめるポータルサイトなどで情報収集するのもおすすめです。
移住関連イベント情報|移住のためのWEBマガジン|FURUSATO
地方移住マッチングサービスを利用するという方法もあります。「LOCAL MATCH」は地域の仕事情報から移住先を探せるマッチングサービスです。希望条件・プロフィールを登録することで、地元企業からスカウトが届くため、職場環境や給料など希望条件を相談できます。
仕事が探せる地方移住マッチングサービス LOCAL MATCH(ローカルマッチ)【LIFULL 地方創生】
地方移住で新しい働き方を見つけた人
移住を経験し、地域で活躍されている2人の事例を紹介します。
宮崎県新富町に移住した有賀沙樹さんの事例
過労で体調を崩して会社を辞め、フリーランスとして独立した有賀さん。もともと地方創生に興味があり、起業家育成セミナーに参加してことをきっかけに、宮崎県新富町へ移住しました。セミナーを主催した財団の仕事とベンチャーキャピタルの仕事を掛け持ちしているそうです。地方創生やまちづくりの取り組みを通して、「自分がこの町で何を実現したいのか」を模索しながら、地域貢献活動に励んでいます。
宮崎県新富町に移住した有賀沙樹さんのLOCAL MATCH STORY 〜出会いが出会いを呼び、無限の選択肢から移住を決断〜|LIFULL 地方創生
岡山県西粟倉村に移住した寺尾武蔵さんの事例
LOCAL MATCH主催の移住キャリア相談に参加し、地域おこし協力隊として岡山県西粟倉村に移住した寺尾さん。村産業観光課に勤務する中、村と民間企業が共同出資した新しい電力会社が設立。その後、新会社の社長に就任しました。環境省の「脱炭素先行地域」に指定された村で、地産地消のエネルギー循環が可能なモデル地域を目指す取り組みに尽力しています。
岡山県西粟倉村に移住した寺尾武蔵さんのLOCAL MATCH STORY 〜移住キャリア相談が転機をもたらした40代からの移住〜|LIFULL 地方創生
地方移住後の暮らしに対して不安に思うこととは?

地方移住により道路の渋滞や通勤ラッシュから解放され、のびのびとした生活を楽しめるイメージがありますが、デメリットもあります。移住後に地方暮らしの現実に直面し「こんなはずじゃなかった」と後悔しないように、地方での生活のメリット・デメリットを総合的に判断した上で移住を決定したいものです。
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が2020年9月に報告した「東京圏、地方での暮らしや移住及び地方への関心に関する意識調査」によると、地方へ移り住むことを妨げている理由や移動に関心を持てない理由として「求めている業種・職種の働き口が見つからないこと」が39.4%と一番多い意見でした。その他にも、「生活利便性(買い物、交通利便性など)が低いこと」(35.6%)、「現在と比べ賃金が安くなってしまうこと」(34.2%)の回答が続きます。
また、男性と女性では不安を覚えるポイントが異なる傾向にあり、男性は「求めている業種・職種の働き口が見つからないこと」の割合が最も高く、女性は「生活利便性(買い物、交通利便性など)が低いこと」を最たる要因に挙げています。
同意識調査に基づき、男性・女性が感じる不安を具体的に挙げてみましょう。
【男性の声】
- 給与面。見ていたら圧倒的に首都圏が高い。また、(就職情報)条件の要綱を見るとやっぱり地方に比べると1割か1.5割は全然違うなという感じがする。
- 車がないと生きていけないかなと思うほど交通の便が悪い。バスとかも田舎だと多分8時とかに終わってしまうので不安。
【女性の声】
- 田舎だとスーパーが早く閉まるイメージなので生きていけるだろうか。
- また一から人間関係をつくることになり、今みたいに気心の知れた友人たちと疎遠になるのは不安。地方のコミュニティーがあって、そこに入るのは勇気がいる。
- 仕事と地域コミュニティーの不安以外にも、交通や生活の便といった不安がある。
移住は、住む場所や職場、人間関係などたくさんの変化を伴う人生の転機とも言えるイベントです。理想とする地方暮らしには何が必要か、どういう移住先が自分に合っているのかを入念にリサーチしておくと安心です。
失敗しない移住先選びのポイントについては、こちらも併せてチェックしましょう。
【LIFULL HOME'S】地方移住者が語る、失敗しない移住先の選び方とポイント
※出典:調査報告書(本編) – 地方創生 令和2年9月 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局
地方移住や新しい暮らし方を通じて自分らしい生き方を実践した事例

地方移住を実践している人の体験談に触れることも、移住後の生活をイメージするのに役立ちます。また、そこから地方移住するにあたってどんな備えが必要なのかヒントも得られるはずです。ここでは地方移住で自分らしい生き方や働き方を楽しんでいる2人の事例を紹介します。
「家族との時間をもっと持ちたい」、東京を離れて家族5人で北海道に移住した田中全亮さん
世界的に有名なスポーツ&アパレルブランドの会社に勤務しながら東京・目黒区でマンション暮らしをしていた田中さん。仕事は充実していたものの、長年勤める中で家族との時間をもっと大切にしたい。子どもが成長していく中で環境を変えたほうがよいのではと考え、移住を決断しました。
移住にあたって経済的な面など不安がなかったわけではないようですが、ポジティブ思考の田中さんは北海道で農業と漁師に挑戦。そうした新しい経験を通して東京にいたら得られなかった多くの学びや気づきを体感できたとのことです。
田中さんはこれから移住を考えている人に「やっておけば良かった、と後悔するよりも、できる時にやる!という気持ちと行動力が大切なのだと思います」とメッセージを送ります。
世界を旅し、田舎暮らしも経験した上でたどり着いた自分を満たす生き方
「TABI LABO」創設者であり、運営会社のNEW STANDARD株式会社の代表取締役でもある久志尚太郎さん。中学校卒業後アメリカに留学、16歳で飛び級卒業し、17歳で起業、21歳で世界を回る旅に出たというユニークな経歴の持ち主です。
旅を終え、世界的テクノロジー企業のデル・テクノロジーズ株式会社で3年間会社員生活を送るも26歳で退社し、「自分たちが欲しいものや未来は自分たちの手でつくり上げたい」と宮崎県の串間市に移住。築70年の古民家を借り、農家支援やエコツーリズムなどを経験しました。
地方での暮らしで多くの経験を経て、「令和時代の幸せな暮らしは、自分の価値観がすべての軸になる」と、ライフスタイルの多様化について語ります。
まとめ

新型コロナウイルス感染症の流行は、くしくも「今の暮らし・働き方の是非」を私たちに問いかけるきっかけになりました。都市圏では仕事の見つけやすさ、生活の利便性などのメリットがありますが、地方移住によって家族との時間や自然に触れる機会が増加するなどまた違った魅力があります。移住を考え始めた方は移住先として魅力を感じる場所について情報収集したり、移住経験者の話を聞いたりすることから始めてみてはいかがでしょうか。自分と家族にとって幸せな時間を与えてくれるのは、もしかしたら地方での生活かもしれません。
1947年生まれ、福島県出身。1970年に早稲田大学を中退し、1977年に自治労本部に入職。廃棄物行政、社会保障、組織対策などの仕事を手掛ける。1997年から連合へ出向、社会政策局長として国土・土地・住宅政策、環境政策、教育政策、農業政策などを担当する。連合勤務を経て2002年に認定NPO法人ふるさと会期支援センターの事務局長に就任。2017年に理事長、現在に至る。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」