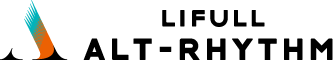ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【後編】
世界共通の目標として掲げられるSDGs(持続可能な開発目標)には「ジェンダー平等を実現しよう」というゴールがあります。性別による差別や偏見をなくし、全ての女性と男性が対等に権利・機会・責任を分かち合える社会をつくることを目指し、世界中で取り組まれている目標です。
日本では性別の違いにより、社会的・文化的な不平等や差別が生まれている現状があります。ジェンダーレスとは、そういった社会的・文化的な性差が取り払われた状態、もしくは取り払おうとする考え方です。この記事ではジェンダーレスの意味や、ジェンダーフリーとの違いについて紹介します。
この記事では下記の3点を解説します。
前編
後編
ジェンダーにとらわれず自分らしく生きることの大切さ

ジェンダーにまつわる悩みや課題に向き合い、さまざまな取り組みを実践している3名を紹介します。
ジェンダーレスな自分を素直に表現できるようになったKanさん
Kanさんは、セクシュアリティやボディポジティブについてSNSで発信する他、学校・企業での講演活動を行っています。同性愛者であることを自覚したのは15歳の頃でしたが、当時のセクシュアルマイノリティーのイメージは、テレビで見る「オネエキャラ」の人たちだけでした。「男性が好きな僕は、オネエとして生きていかなきゃいけないんだ」と、自己実現に迷っていた経験を明かしています。Netflixの人気コンテンツ『クィア・アイ in Japan!』に出演したことをきっかけに、Kanさんはジェンダーレスな自分を素直に表現できるようになりました。
ダイバーシティ推進のプロジェクトで編集長を務める遠藤祐子さん
遠藤さんは、女性目線で考えるダイバーシティ推進のプロジェクト「MASHING UP」の編集長を務めています。例えば、「女子アナと呼ぶのに、なぜ男子アナとは言わないんでしょう」と遠藤さんは疑問を投げかけます。これは、先に紹介した女性名詞の一つと言えます。さらには「女性活躍という言葉があるのに、男性活躍って言わないのはなぜ?」と問いかけます。
女性活躍と叫ばれて久しい現代。しかし女性だから活躍しなければならないのではなく、ジェンダーにかかわらずどんな人でも「自分の人生を愛して生きられるようになるといい」と遠藤さんは語ります。
「男らしさ」からくる生きづらさを研究する田中俊之さん
大正大学心理社会学部准教授の田中さんは、「男性学」を研究しています。「デートでは男性がお金を多く支払うべき」「男性なら定年まで正社員で働くべき」といった男性に対する固定観念が日本では根強く残っています。しかし、こうしたジェンダーロールに生きづらさを感じる男性は少なくありません。男性だからといって「弱音を吐いてはいけない」「強くあらねばならない」といった考えにとらわれる必要はないと田中教授は語っています。
まとめ
ジェンダーはそもそもグラデーションであり、「男性」「女性」をくっきりと分けることはできません。ノンバイナリー、Xジェンダーなどのジェンダーもあります。ピンクやフリルが好きな男性もいないというわけではありません。しかしながら、社会的・文化的に刷り込まれた「男らしさ」「女らしさ」は知らず知らずのうちに脳に刻み込まれています。こうした無意識の思い込みであるアンコンシャスバイアスは、誰もが持っているものです。とはいえ、ジェンダーにまつわるアンコンシャスバイアスを、無自覚のまま相手に押し付けたり心ない発言を投げかけたりすると、相手に悪影響を与えることになりかねません。ジェンダーレスの考え方が広まり、浸透していった先の未来には、あらゆる人にとって生きやすい社会が待っているのではないでしょうか。
前編を読む
一般社団法人パートナーシップ協会代表理事。会社員、個人事業主を経て20代半ばでマーケティング会社を設立。ジェンダー問題に直面した自身の経験から、「誰もが働きやすい社会の実現」に向け、当協会を立ち上げる。男女の昇進格差や賃金格差の改善に向け調査・研究を行い、ジェンダー平等経営を企業に向け推進する。内閣府SDGs分科会メンバー。「ジェンダー平等SDGs経営」「ジェンダー平等企業は業績が伸びる」ほか各種セミナーを開催。
https://www.gb-work.or.jp/
みんなが読んでいる記事
-
 2021/09/06運動は毎日継続しないと意味がない、なんてない。のがちゃん
2021/09/06運動は毎日継続しないと意味がない、なんてない。のがちゃん人気YouTuber、のがちゃん。2018年にフィットネス系チャンネル「のがちゃんねる」を開設し、現在は登録者数86万人を超えている。もともとはデザイナーとして活動しており、フィットネスやスポーツに縁があったわけではない。そんな彼女の原点は、中学や高校時代のダイエット。食べないダイエットなどに挑戦しては、リバウンドの繰り返し。当時の経験と現在のYouTube活動から見えてきたのは、「継続の大切さ」だ。多くの人が直面する体作りや健康について、のがちゃんの考えを伺った。
-
 2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】
2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】ジェンダーレスという言葉を耳にしたことがあるかもしれません。この記事では、ジェンダーレスの意味やジェンダーフリーとの違い、ジェンダーレス社会の実現に向けた取り組み、ジェンダーにとらわれず自分らしく生きることの大切さについて紹介します。
-
 2022/09/27日常の光をつかむ写真家・石田真澄 【止まった時代を動かす、若き才能 A面】
2022/09/27日常の光をつかむ写真家・石田真澄 【止まった時代を動かす、若き才能 A面】あしたメディア×LIFULL STORIES共同企画第2弾は、写真家・石田真澄さん。大塚製薬・カロリーメイトの『部活メイト』、ソフトバンクの『しばられるな』などの広告写真、そして俳優・夏帆さんの写真集『おとととい』などを手がけてきた写真家だ。
-
 2023/01/12“もうおばあさんだから”、なんてない。BACK STREET SAMBERS(三婆ズ)
2023/01/12“もうおばあさんだから”、なんてない。BACK STREET SAMBERS(三婆ズ)BACK STREET SAMBERS、通称「三婆ズ」は、65歳、68歳、72歳の女性3名で構成されるダンスユニットだ。Instagramのフォロワーは10万人超。ダンス動画には、コメントで「キレキレですね」「カッコいい」といった声が集まっている。年齢にとらわれず新たなことを始める原動力について、話を伺った。
-
 2023/02/21【前編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説
2023/02/21【前編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説少子高齢化により、日本の人口減少は加速しています。その結果、さまざまな問題が引き起こされていますが、その一つが空き家問題です。「家の片付けができていない」「売りたくても売れない」といった理由で空き家を放置している所有者も少なからずいて、相続した家が「負の不動産」となり得る問題もはらんでいます。総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、2018年時点での空き家は全国で約848万9000戸と過去最大となっており、空き家の管理や活用は喫緊の課題と言えるでしょう。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」