家族の在り方はひとつでなきゃ、なんてない。
「趣味や好きな食べ物、話し方や声のトーンもそう。母とは似ている部分がたくさんあるんです」と、サヘルさんはほほ笑む。柔軟な考え方や思慮深さ、人との接し方も養母から愛情とともに受け継いだもの。今でこそ「母とは絶対に離れないほどの強い絆がある」という彼女だが、養子であることに引け目を感じたり、「家族はこうじゃなきゃ」という既成概念に縛られ、思い悩んだ時期もあったという。

「血は水よりも濃い」とは血縁による家族や親子の絆の強さを表すことわざのひとつだ。しかし、血がつながっていても良好な関係を築けずに傷つけ合ってしまう親子は多く、虐待や自殺といった悲しいニュースは後を絶たない。一方で、血のつながりがなくても実の親子以上に深い関係を築く人々もたくさんいる。女優として活躍するサヘル・ローズさんもそのひとり。彼女にとっての家族とは、養母をはじめとする心のつながりで強く結ばれた存在。「孤児である私には血のつながりのある家族はひとりもいませんが、私は自分のことを大家族だと思っています」と語るサヘルさんに、家族として心でつながるための向き合い方について伺った。

自分だけを見てくれる
大人がいない子どもは
家族も愛もわからない
イランの孤児院にいたサヘルさんが、育ての母親であるフローラさんの養子になったのは7歳のとき。翌年には日本にいる知人を頼って親子で来日したものの、生活が軌道に乗るまでは苦労の連続だった。
大人の事情で母子家庭になってしまったため、母は朝から晩までトイレ掃除などの清掃業で、働きづくめ。サヘルさんが小学校6年生の時からはペルシャじゅうたんの販売員となり、出張で一週間家にひとりきりということもあった。テレビドラマのように、いつも一緒にいて何でも話せて、泣きたいときは抱きしめてくれる。それがあるべき親子の姿だと思っていたのに、現実の母は想像していたイメージから大きくかけ離れていた。
「母は常に一生懸命で、親として完璧な姿を見せてくれていました。でも、その分私も『親が求める子どもにならなきゃ!』と気負ってしまい、本音や弱さを見せられなくなってしまって……。そのためしばらくお母さんと呼べなくなった時期もありました。育ててもらっている恩もあるし、これ以上何かを求めちゃいけない気もするし。だからきっと、この人は“お母さん”じゃなくて“フローラ”なんだと思い、名前で呼ぶようになったんです」
当然、母は驚き「親子なのにどうして名前で呼ぶの?」と尋ねた。だが、幼い時期を孤児院で過ごしたサヘルさんには親子や家族というものがわからなかったのだ。
「“大勢の中のひとり”として育つと、家庭の温かさや愛を知る機会がないんですよね。職員の方は精いっぱい接してくれますが、人数が多いから自分だけを見てくれるわけではないですし。それなのに急に『家族だよ』と言われても『何?』って。言葉や人との接し方と同じで、愛情や家族の在り方だってゼロから教えてもらわないと子どもは理解できないんです」

思い合う気持ちがあれば血縁がなくても家族になれる
互いに伝えたい思いがあるはずなのに、声に出せない。そんなぎくしゃくした関係に転機がおとずれたのは、サヘルさんが中学生のときに自死を考えたことがきっかけだった。
「つらいことが重なりギリギリの状態になって、やっと『つらい』『苦しい』という本音を言えたんですよね。それまでは『家の外のことだし、言っても理解してもらえないんじゃないか?』という思いもあったのですが、母はちゃんと向き合ってくれた。初めてお互いの本音と感情をぶつけ合ったことで『この人のためにも生きなければ』と思えるようになり、ようやく“家族”になれたと感じることができたんです。
大切なのは『こうあるべき』という既存の枠にはめた家族像ではなく、“家族”というつながりの先にある関係性の築き方。たとえ血のつながっている家族であっても、何でもわかり合えているわけではない。だったらなおさら、血のつながりのない他人同士の自分たちが黙ったままで理解し合えるはずがないじゃないか。毎日きちんと会話をしよう。少しずつ心を見せて、互いに歩み寄っていこう」
そう気づいてから母子の心の結びつきはどんどん強まっていったという。
「私が母に求めているのは、『完璧なお母さんでなくていいから、もう少し気持ちを打ち明けてほしい』ということ。親だって失敗するし傷つくし、不安を抱えたりパニックを起こすことだってあるじゃないですか。弱い部分を隠さず見せてもらえたほうが、子どもも『大丈夫?』と手を差し伸べられるし、感情だって吐き出しやすくなる。『言わなくてもわかるはず』『これはこう』と決めつけないことや、意見の食い違いを尊重し合うことも、母と私が大事にしていることです」

母のフローラさん(右)と。「私のために人生を捧げ、向き合い続けてくれた母には感謝でいっぱい。だから今度は私が母をたくさん幸せにしてあげたい!」(サヘルさん)
家族に等しい存在はたくさんつくることができる
サヘルさんにとっての家族は、養母のフローラさんだけではない。イランから来日して間もないころに生活を手助けしてくれたご近所さんや、旅先やボランティアなどで出会った子どもたち、現地のお父さん・お母さん、仕事仲間や友人たち。「自分が安心できる人と心でつながり合えることも、家族の在り方だと思うんです」と彼女は語る。
「家族とはとても大きなもの。私にとっての母はフローラだけですが、広島のお母さんも、埼玉の給食のおばちゃんも自分にとってはお母さん。みんな『ただいま』と言えば、『おかえり!』と温かく出迎えてくれる。世界のあちこちに自分が落ちついた気持ちで帰れる場所があるのはとても心地良いです」
自身が温かい“家族”の輪を広げていく一方で、人々が孤立しがちな現代社会の風潮に対する懸念もあるという。
「私と母が日本に来た28年前は、良い意味での”おせっかいおばちゃん”が街にいて、困ったときに助け合えるコミュニティがありました。でも、いまはそういったつながりが薄くなりつつある。隣人の顔を知らなかったり、SNSなどの内輪の世界にこもって身近な人を頼らなくなってしまったり。家族もそう。どんなに普通を装っていても、みんな何かしらの思いを抱えているじゃないですか。それなのに『自分の家のことは自分で』と壁をつくってしまったら、もしものときに苦しくなってしまいますよね」
誰にも自分の声を届けられない大人のストレスは、自死や子どもへの虐待の原因になることもある。だが、ここで彼らを責めても負の連鎖は終わらない。この悲しい問題を解消するためには、「ひとりで悩みや問題を抱え込んでしまう大人を救う社会にしなければいけないと思うんです」とサヘルさんは声を上げる。
「もし身近に困っている人や家族、外国籍の親子がいたら、声をかけて友達になってあげてください。軽く話を聞くだけでもいいんです。もし具体的に力になりたいのなら、周囲の人と協力し合ってもいい。自身が人をつなぐハブになることで達成できることもあるし、困っている人たちにとっても新しいつながりを生むきっかけになるはずです」

サヘルさん自身が「たくさんの人に守られながら生きてきたからこその恩返し」として行っているのが、児童養護施設の子どもたちや日本に住む難民をサポートするボランティア活動。目指しているのは、家庭を持てない子どもたちの家族代わりになることだという。
「子どもたちに『施設を出たあとも、ずっとひとりにさせないから大丈夫だよ』と伝えて安心感を与えたい。そして、進むべき方向に迷ったときの道しるべや、困ったときの駆け込み寺的な存在になってあげられたらなと。彼らの持つ希望や目標をかなえる手助けをすることも大きな目標。親のいない子どもでも夢や可能性を持てるということを社会に示し、ロールモデルを作りたいんです」
施設で暮らす子どもたちは、性格も家庭背景も抱える心の傷もそれぞれ異なる。大人を信じられなくなった子も多く、いきなり通じ合えるわけではない。まずは「あなたという人間をちゃんと見ているよ」と真剣に向き合い、信頼してもらうことから。相性が合わないことももちろんある。だがそれは、血のつながった実の親子でも十分あり得ること。ひいては、向き合いながら関係を築き上げていく過程は、世間的な家族とさほど変わらないのだ。

「施設の子どもたちと里親の交流を見ていても感じるのですが、ずっと同じ大人がそばにいると子どもの表情や発する言葉の数が違ってくるんですよ。例えば、無口でなかなか感情を出さなかった子が週末だけ里親と過ごすようになったら、これまで見せなかったような笑顔が出てきたり、たくさん話すようになったことも。日本にも家族を必要としている子どもはたくさんいて、彼らの里親になりたいと思ってくださる方も実は結構多いんです。ただ、現状ではまだ両者を結ぶシステムがうまくつながっていないんですよね」
里親の子どもの受け入れ方にも種類があること、里親研修や里親手当といった制度や、養子縁組との違いについてあまり知られていないことも課題だという。これらがより広く認知されれば子どもたちの可能性も、そして家族の在り方も大きく広がっていくだろう。
「いきなり里親ではなく、『誰かの居場所になる』という考え方でもいいと思うんですよね」とサヘルさん。大事なのは相手を大切に思う心。家族の在り方はそれぞれに合った形を見つけ出していけばいいのだ。
撮影/尾藤能暢、取材・文/水嶋レモン

1985年イラン生まれ。7歳までイランの孤児院で過ごし、8歳で養母とともに来日。
高校生の時から芸能活動を始め、舞台『恭しき娼婦』では主演を務め、映画『西北西』や主演映画『冷たい床』はさまざまな国際映画祭で正式出品され、イタリア・ミラノ国際映画祭にて最優秀主演女優賞を受賞。
映画や舞台、女優としても活動の幅を広げている。
また、第9回若者力大賞を受賞。芸能活動以外にも、国際人権NGOの「すべての子どもに家庭を」の活動で親善大使を務めている。また、アメリカで人権活動家賞を受賞する。
今後も世界中を旅しながら難民キャンプや孤児・ストリートチルドレンなど子どもたちと共にいきていく事が目標。
2015年からは「Fresh Faces ~アタラシイヒト~」(BS朝日)でナレーターを務めている。
Twitter https://twitter.com/21sahel?lang=ja
Youtube https://youtube.com/channel/UCE3h8QRgs4GS_ClgReaAMVA?view_as=subscriber
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
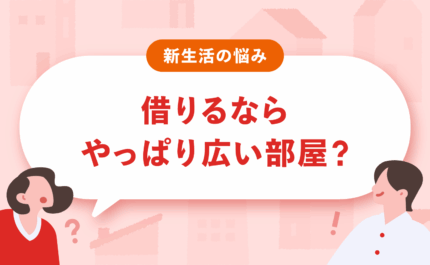 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
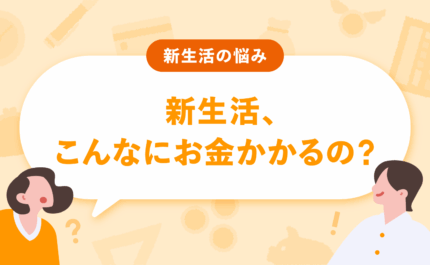 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
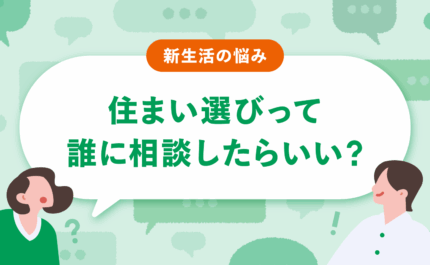 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
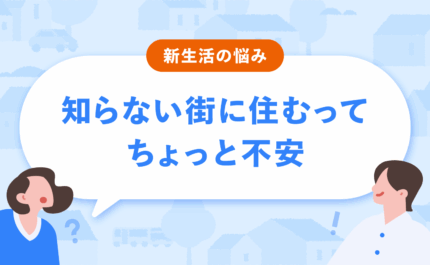 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。












