なぜ「結婚しなきゃ」に縛られてしまうのか|社会学者・山田昌弘
男性28.3%、女性17.8%(※)——これは、日本の生涯未婚率を表す最新のデータです。「おひとりさま」「ソロ活」という言葉がメディアに露出したり、事実婚や選択的シングルマザーなど多様な家族・パートナーシップのあり方が取り上げられたりするなど、「結婚」に対する一人ひとりの価値観が変化し始めているようです。
漠然と「結婚しなきゃ」という気持ちに囚われて婚活する人もいれば、法律婚にこだわらず自分たちらしい幸せの形を模索している人もいます。
「婚活」「パラサイト・シングル」などの言葉を提唱した家族社会学者の山田昌弘さんに、結婚に関する既成概念についてお話を伺いました。
※2022年内閣府『少子化社会対策白書』

日本は「結婚したくてもできない」人が増えている
――結婚にまつわる問題を社会学の観点から研究してきた山田さんは、生涯未婚率が上昇している現状をどのように見ていますか?
山田昌弘さん(以下、山田):おっしゃるように、統計的には未婚の人の数は増えています。しかし、実は「結婚願望」自体に大きな変化は見られません。私が『結婚の社会学』という著書を出版した約20年前にも、生涯独身を選択する人は一定数いたのです。
では、今の日本社会における問題は何かというと、「結婚したくてもできない」人が増えていること。これを、私は「結婚困難社会」と呼んでいます。
つまりこの20年ほどで変わったのは、個人の意識というよりも社会・経済の状況だと捉えています。
――著書『結婚不要社会』の中で、結婚したくてもできない「結婚困難社会」から「結婚不要社会」に移行していると先生は書いておられますね。
山田:現在は日本も欧米も、結婚が必要ない「結婚不要社会」に突入しています。ただ、「不要」の意味・ニュアンスが少し異なるんですね。
欧米では、幸福のためにパートナーは必要とするけれど、結婚という形式をとらず、同棲や事実婚を選ぶカップルが多い。お互い経済的に自立していて、パートナーに求めるのは親密性、つまり愛情のみ、ということですね。パートナーと結婚しなくても子どもを産み育てられる社会制度も整っています。
一方で、日本の近代社会は、結婚をしないと経済的・心理的に生きにくくなる「結婚不可欠社会」でした。今の日本社会も、社会保障や税制など制度上はもちろん、人々の意識的にも変わらず「結婚不可欠社会」のまま、結婚したくてもできない「結婚困難社会」に陥ってしまっている。
結婚を望んでいてもできないなら「パートナーを持たずに楽しく暮らそう」とする人が増えるんです。そして、「パートナーなしでそれなりに楽しく生活できる」産業や習慣などの仕組みが整ってきてしまった。
パートナーでなくても、友人やアニメ・漫画などの趣味や“推し”、ペットなどの存在が心理的な支えになり、人生を充実させることができます。「おひとりさま」とか「ソロ活」なんて言葉が流行したのも、日本独自の「結婚不要社会」への突入を表していると感じます。
「いつかは結婚できる」時代は終わった
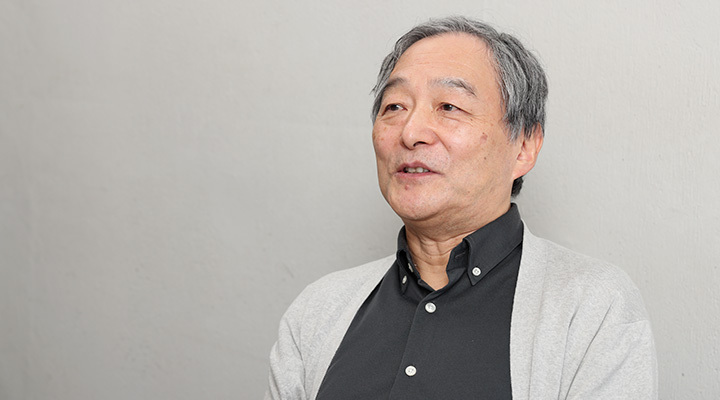
――「結婚したくてもできない」人が増えたのは、社会全体がどう変わったことが影響しているのでしょうか。
山田:最も大きいのは、経済的な要因です。終身雇用制度は崩壊し、経済の低成長にともなって非正規雇用が増加し、20~30代の中での所得格差が広がっています。女性の社会進出などの社会変化はありましたが、結婚という文脈においては「男性は仕事、女性は家庭」という旧来型の性別役割分業意識はいまだに根強い。
「結婚すれば生活の安定が保障される」時代は終わり、結婚して豊かになれないなら一人でいよう、という発想になるわけです。
こうした状況で日本では「パラサイト・シングル」、つまり実家で親と同居する若者が非常に多く、ますます「結婚せずとも生活できる」状況になっています。
親が建てた家で、親と暮らしていれば当面の経済的・心理的な不安は先送りにできますが、やがて親も高齢になり、病気になったり介護が必要になったりする。生活の破綻が見えてきた40~50代になって「婚活」を始める人も多いのです。
――先ほど個人の意識は変わらないとのことでしたが、「婚活」や恋愛行動に対する意識に変化はあるのでしょうか?
山田:今の若い世代は、独身の中高年世代を見て「誰でもいつかは結婚できる」時代はとっくに終わったのだと理解しているように思います。“結婚適齢期”と呼ばれる年代になると親から結婚を急かされなくても自ら行動を起こし、相手を見つける「婚活」をしなければ結婚ができない時代なのだと肌感覚でわかっているんでしょうね。
「恋愛する相手とは将来、結婚するはず」という固定観念がありますが、結婚相手にふさわしくない相手と恋愛するのは時間とお金の無駄だと考える人も増えました。これが若者の恋愛離れが進んでいると言われる所以です。
さらに今はSNS時代で、マッチングアプリなどネット上の出会いが増えています。国立社会保障・人口問題研究所の調査では、インターネットをきっかけに出会って結婚した夫婦の割合が13.6%(※)いると発表されました。コロナ禍はリアルな出会いの減少に拍車をかけたというデータもありますね。
※国立社会保障・人口問題研究所「現代日本の結婚と出産―第16回出生動向基本調査(独身者調査ならびに夫婦調査)報告書」p.13 https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou16/JNFS16_ReportALL.pdf
今も「結婚」の意味合いは薄れていない
――価値観やライフスタイルが変化しても、「結婚しないと一人前になれない」という風潮はいまだに根強いと感じます。それはなぜなのでしょうか。
山田:一言で言うと、今の日本社会においても「結婚」を選んだほうがいろいろな意味で都合が良いからだと思います。
国や時代にかかわらず、「信頼できる存在が欲しい」という願いは共通ですよね。欧米では事実婚でもその願望が担保されていますが、日本社会において信頼や永続性を保証するのは今も法的な婚姻制度によるところが大きいと言えるでしょう。
どれだけ経済的に自立していたとしても、そして一緒に楽しめる相手(パートナーや友人)、コミュニティなどの存在があったとしても、多くの人は病気や介護など「いざ」という時に頼れる存在を求める傾向にあります。その意味で、今も「結婚」の意味合いは薄れていないと感じます。
――最近では、事実婚や自らの意思で結婚せず子どもを持つ「選択的シングルマザー」など多様な家族・パートナーシップの在り方が広がっているように感じますが、その点はいかがでしょうか?
山田:たしかに「未婚」の中には、結婚という形式によらずさまざまな家族やパートナーシップの形態を選択する人もいますよね。
しかし、事実婚だと日常生活や仕事のあらゆる場面で周囲への説明が必要なケースもあります。社会保険や相続、「もしも」の時の公的手続きなどにおいてもデメリットが大きくなってしまうこともあるでしょう。
未婚でシングルマザーになる人は貧困に陥りやすいなどの問題もあります。欧米と比較して日本で養子や里親といった選択肢がなかなか浸透しないのは、血縁関係を重視する文化も影響していると思います。
――他にも「結婚しなきゃ」という価値観に影響を与えていることはありますか?
山田:日本で「結婚しなきゃ」という既成概念が根強いのは、「世間体社会」も大きく影響しています。
日本人は「人からどう見られるか」を非常に気にしますし、「多数派であること」を重要視しますよね。いまもなお「結婚」の意味合いが薄れていない中で、「結婚しないと」という強迫観念にも似た感情を抱くのは自然なことだと考えます。
そして、世間から「惨めだと思われたくない」という思いが強い。だからこそ、周りから認めてもらえる経済力や社会的地位を持たない人と結婚したら惨めに思われるんじゃないか、それならば結婚しないほうがいいだろう、という負のループが生まれているんです。
「結婚」しなくても、幸せになる選択肢はある

――日本社会の「結婚」にまつわる価値観は、これからどのように変化していくと分析されていますか?
山田:結論からお伝えすると、選択肢は増えたとしても、欧米のような「結婚不要社会」になるのは時間がかかると考えています。
先ほどもお話ししたように、未だ日本では、経済的・心理的安定と信頼を保証する仕組みとして「結婚」は大きな意味を持っています。雇用が不安定で所得格差が埋まらず、国の社会保障制度への信頼が揺らいでいる中で、「結婚」せずに安心して生きていく難易度は高いと言えるでしょう。
また、世間体を気にする風潮も、簡単になくなるとは考えにくいですね。
とはいえ、経済的・心理的な自立が担保されているのであれば、可能性は広がると思います。今ではペットや“推し活”など、結婚せずとも精神的な居場所が保障され、人生が充実する選択肢はいろいろあります。
個人がどんな選択肢をとっても、安心して楽しく暮らせる社会になるといいなと思いますね。
私たちを縛る「結婚しなきゃ」という価値観も、実は社会が生んだ既成概念に過ぎないのかもしれません。
時代の流れとともに、生き方の選択肢は多様化しています。いかなる家族、パートナーシップのあり方であっても、個人の選択が尊重され、誰もが自分のありたい生き方を選べる社会になることを願います。
取材・執筆:安心院彩
撮影:大浦タケシ
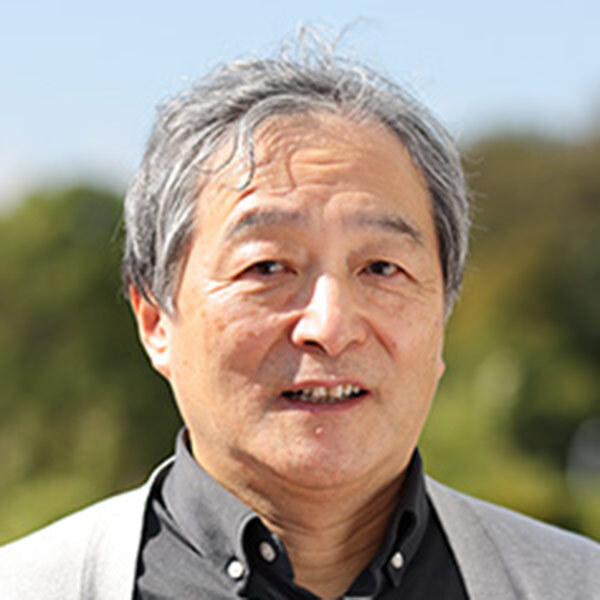
中央大学文学部教授。1957年、東京都生まれ。子ども・若者・夫婦・家族を取り巻く現状を常に多角的に解析し、その打開策を提言し続ける社会学者。専門は家族社会学・感情社会学・ジェンダー論。未来に希望や夢を抱けなくなった現代社会において、子どもや若者の導き方、夫婦の関係や家族のあり方など、未来を見据えた鋭い提言を続ける。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」













