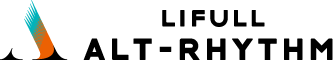本で読んだだけで「LGBTQ+を理解した」、なんてない。
歌人として活躍する鈴掛真(すずかけしん)さんは、デビュー作の書籍でゲイとしての恋の喜びや葛藤を伝えるなど、活動当初から自分の性的指向をカミングアウトしていることでも知られる。それが売名と呼ばれたり非難されたこともあるが、鈴掛さんにとっては名前を名乗ると同じような、ごく自然なこと。親へのカミングアウトが成功した理由や、近年LGBTQ+という概念が広まったからこそ生まれたと感じる新たな誤解や偏見と、その解決策とは。

2018年に発売されて大きな話題を呼んだ書籍『ゲイだけど質問ある?』。ここ最近、性別を書く欄に「その他」が加わるなど、LGBTQ+に対する理解を広めようとする動きが強まってきた。この本の発売はそうした風潮の少し前だったので、とてもセンセーショナルだったと記憶している。本を発表したのは、ゲイであることを公表しながら作家活動を続ける、歌人の鈴掛真さん。
日本では以前に比べるとLGBTQ+の理解が広がってきたといわれているが、当事者の方は実際どのように感じているのだろうか。誹謗(ひぼう)中傷を覚悟の上で自身のセクシュアリティを公表した理由とは? 偏見をなくすためにできることは? 当事者にしか分からない、さまざまなことを伺った。
LGBTQ+を「概念」で捉えず、
「個人」で見てほしい
ゲイの歌人「鈴掛真」の誕生秘話
まずは、LGBTQ+の当事者である鈴掛さんという歌人の誕生秘話から。
「僕は『自分は男の人が好きなんだ』と幼稚園生の頃に気付いていました。また同時に、『これは他の人には気付かれちゃいけない』ということもなんとなく感じていましたね。同性愛がどういうものか、『同性愛』という言葉すら全く知らなかったのに。
初めてカミングアウトしたのは、中学生の時の親友だった女友達に対して。それも、『カミングアウトして関係が壊れるかもしれない』という気持ちから、中学校を卒業した春休みに伝えたんです。彼女は驚きながらも受け入れてくれましたが、それからしばらくの間も、特に周囲にカミングアウトすることなく生活していました」
そんな鈴掛さんに、転機が訪れる。サラリーマンを辞めて書籍を出版することになった。
「大学を卒業してから広告会社でコピーライターとして働いていたのですが、諸事情で退職することになり、たくさんの縁があって半年後には初めての著書である『好きと言えたらよかったのに。』を出すことになりました。今から10年前のことです。
この本は、同性への片思いの経験を短歌でつづったフォトエッセイです。これを機に親も含めて周囲にカミングアウトするようになりました」
思春期の失敗を経て、ラスボスである両親へのカミングアウト
「10年前はLGBTQ+という言葉がまだ一般的ではなかったので、『作家活動になぜセクシュアリティが必要なのか』『個人的な性的指向をオープンにする意味は?』『売名なんじゃないか』などいろいろ言われましたね」
身近な人はもちろん、両親にもこの時が正式なカミングアウトだった。“正式”という言い方をするのには理由がある。それは、思春期の頃に一度、勢い余って母親に告げて失敗してしまった経験があるからだ。

「自分の親にカミングアウトすることは、セクシュアル・マイノリティにとっては一番難しい。ゲームで言うところの『ラスボス』です。僕は逆に、思春期の時に勢い余って母親にカミングアウトしてしまった経験があります。
急に言われた母親もどう接していいか分からず戸惑っただろうし、僕自身もそんな母親の姿を見て、心配をかけてしまったことにとても罪悪感を覚えました。
それ以来、お互いにそのことには一切触れなくて。家族が元々オープンで仲が良く、兄や姉が自分の恋人を連れてくるような家だったからこそ『自分はこういうふうに親を喜ばせることはできないな』と感じて、だんだん自分の殻にこもるようになってしまった10年でした。
そして最初の書籍を手紙と一緒に送ったところ、母はとても喜んでくれて、父からは『とても良い本だから自信を持って』というハガキが送られてきたんです。それが僕の、“正式”な親へのカミングアウト。うれしかったですね。ラスボスだからこそ最初にそこをクリアしておきたかったし、逃げたくなかったんです。
今になって思うと、著書を出版するほど息子が社会人として成功し、自分の道で頑張っている姿を目の当たりにしたことは、両親を安心させると同時に、セクシュアル・マイノリティの息子を受け止めるための土台になったんだと思います。やっぱり両親としては、子どもが自分の理解の及ばない存在になったようで不安だったり、セクシュアル・マイノリティであることで差別を受けるんじゃないかとか、社会で生きづらくなることを心配していたんだと思います」
LGBTQ+という概念が広まったからこそ生まれた、新たな偏見と誤解
本の出版を機にゲイであることを周囲にも公表し、自身がとても楽になったそう。

「カミングアウトしてから、『本当の自分を隠さなくていいことの身軽さ』に気付いて、何の気負いもなく、『僕はゲイなんだよね』ということを伝えるようになりました。
ある時、友人が別の友達を飲みの席に連れてきたので、いつものように『僕はゲイで』という話をし、その後とても楽しい時間を過ごしたんですよね。
それからだいぶたって知ったのですが、その時に紹介された方はそれまで同性愛者のことをとても嫌悪していたそうで、友人は僕と引き合わせて大丈夫かととても心配していたらしいんですね。ところが僕があまりに普通に言ったものだから、初対面だった方も構えることなく受け入れてくれて。そんな様子に友人はすごく驚いて、『あれだけ同性愛者に嫌悪感を持っている人にすんなり受け入れられるなんて。しかも説得したり、何かを訴えたわけでもないのに。しんちゃん、すごい!』って。
これは僕にとってとても大きな出来事でした。世の中の人って、LGBTQ+のことを“知識”や“概念”で知っているだけで、当事者としてカミングアウトされた状態で話したことがない人が大半。だからこそ勝手に『同性愛者ってこういう人』『バイセクシュアルってこういう人間』って、型にはめて捉えてしまっているんじゃないでしょうか。
異性愛者にもさまざまな性格の人や個性が存在するのと同じように、セクシュアル・マイノリティだって一人ひとりが個別の人間であり、とてもひとくくりにはできないんです。でも実際に話す機会が少ないからこそ、『たまたまメディアで見た』『たまたま本を読んだ』という人のイメージが、そのまま“セクシュアル・マイノリティってこうなんだ”という固定観念になってしまうんだな、って。これって、LGBTQ+が知られるようになったからこそ生まれた、新たな偏見とも言えますよね。
友人が連れてきてくれた人も、きっと今まで同性愛者に偏見を持っていたと思いますが、僕という当事者と初めて話して、なんら自分たちと違わない人間なんだと気付いてくれたんじゃないかな。結局『差別をなくす』ってこういうことで、つまり『一人でも多くの当事者に出会う』ことなんじゃないかと思います」
ノンバイナリーをカミングアウトした宇多田ヒカルさんを「彼女」と表現することについて
ここ数年、日本でLGBTQ+に関する認知度は高まり、ニュースやネットで関連した報道や記事を目にする機会が多くなった。しかし、同性愛者だけでなく当事者を指し示す言葉が複数存在し、表現が難しいために偏見が広がったり、戸惑っている人が多いのも事実だ。
そんな中でも世間に衝撃を与えたのは、歌手・宇多田ヒカルさんの「私はノンバイナリーだ」というカミングアウト。聞きなれない「ノンバイナリー」とは何なのか?
「ノンバイナリーとは、『男性・女性という2つの性別にとらわれない性自認』を意味します。僕は元々宇多田さんの大ファンですし、ノンバイナリーの知人がいるのでその人に話を聞いてみたりしながら、僕なりにノンバイナリーについて分析した記事を某メディアで執筆しました。すると、一般の方から『ノンバイナリーは性別にとらわれない人なのに、記事の中で宇多田ヒカルさんのことを“彼女”と呼称しているのはおかしい』という指摘を頂いたんです。
しかし、これこそノンバイナリーという“概念”に対する偏見です。ノンバイナリーには『男性と女性のどちらにも当てはまらない』あるいは『どちらにも当てはまる』『男性と女性の中間』『男性と女性を行き来する』など、さまざまな性自認のパターンが存在します。
確かに、戸籍上の女性として生を受けたノンバイナリーの中には『自分を“彼女”と呼ばないでほしい』という人もいるかもしれませんが、宇多田さんの場合は『自分を“彼女”と呼んでほしい』とInstagramのプロフィールに明記しているんです。その指摘を送ってこられた人は、概念にとらわれるあまり、宇多田ヒカルさん個人と向き合えていなかったように思います。
セクシュアル・マイノリティを理解するのは、確かに複雑で、難しい。けれど、いくら書籍や記事などで学んでも、答えは載っていません。答えは、セクシュアル・マイノリティの一人ひとりによって違うからです。“概念”を知っただけで、セクシュアル・マイノリティを知ったつもりにならないでほしい。一人ひとりと向き合って、対話をしてほしい。それがひいては、セクシュアル・マイノリティ全体を理解することにつながると信じています」
私たちがまずできることは、身近にいるはずのセクシュアル・マイノリティの方々が安心して話せる環境づくりではないだろうか。しかし、マイノリティであろうとなかろうと、そもそも思い込みや偏見で「きっとこうだ」と決めつけるのはナンセンスであり、知ったかぶりにほかならない。鈴掛さんのお話から、性の多様性を認め合うことは、「人と向き合う姿勢」そのものを問われている気がした。
取材・執筆:阿部知子
撮影:内海裕之

愛知県春日井市出身。東京都在住。ワタナベエンターテインメント所属。第17回 髙瀬賞受賞。2012年にフォトエッセイ『好きと言えたらよかったのに。』でデビュー以来ゲイであることをオープンにしながら活動を広げ、2018年のエッセイ集『ゲイだけど質問ある?』が大きな話題となる。近年は歌集『愛を歌え』や、YouTubeで同性愛について寄せられたお悩みに答えるなど、多方面で精力的な発信を行っている。
Twitter @suzukakeshin
YouTube 歌人 鈴掛真YouTubeチャンネル
歌人 鈴掛真公式サイト
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。