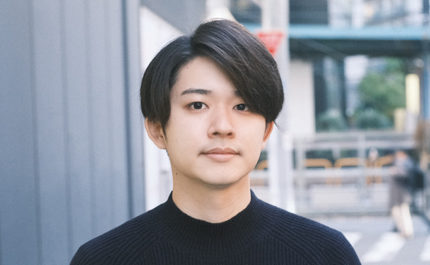人の話を聞き取れないから教師にはなれない、なんてない。【後編】
「聞こえるのに聞き取れない」──そんな矛盾したような症状を示す、APD(聴覚情報処理障害)。これは、聴力自体に異常はないものの、脳機能に何らかの問題があることにより、「聞こえた音声を言葉として識別する」作業が困難になる障がいである。このAPDの症状と試行錯誤しながら向き合い続け、2020年春、教師になる夢をかなえたのが真壁詩織さんだ。「大変なことはあるけれど、ちょっとしたサポートがあれば、障がいは『障害』じゃなくなる」──そう語る彼女に、苦手と付き合うコツや上手に助けを求めるためのヒントを伺ってきた。
連載 人の話を聞き取れないから教師にはなれない、なんてない。

「人に迷惑をかけてはいけない」
多くの人がそう教わってきただろう
「分からないことがあったら聞いて」「助けが必要なときは教えて」──学校でも職場でも当たり前のように飛び交っているセリフだ。だが、実際に助けを求めるのは難しいことである。ささいなことで相手の作業を中断させてしまっていいのだろうか? 自分に「相手の労力に見合った何か」を提供できるだろうか?……そういったことをぐるぐると考えると、「助けを求めてもいい」というGOサインを自分に出してあげられなくなってしまうのだ。
「人に迷惑をかけてはいけない」は、裏を返せば「私に迷惑をかけないで」ということでもある。相手を助けなくてはいけない理由が明白ならまだしも、「自分でできるはず」のことを頼まれたときには、思わず心の中で毒づいてしまう、という人もいるだろう。
聴力に問題はないのに、なぜか聞き取りにくい──そんな矛盾したような症状が理解されず、周囲からの助けを得づらい障がいがある。それが、APD(Auditory Processing Disorder)=聴覚情報処理障害だ。
APDの人は主に「うるさい環境にいるとき」「複数人で会話しているとき」「相手の話すスピードが速いとき」「口元が見えない状況でコミュニケーションするとき(電話越し、マスク着用時など)」に聞こえづらくなったり、話の内容が理解できなくなったりしてしまう。聴覚障害とは異なり音や声は聞こえるが、聞こえてきた音声を言葉として聞き取ることが困難なのが特徴だ。聴力検査で異常が見つからないため、これまであまり認知されてこなかったのだという。
まずは工夫しながらやってみる。
それでも駄目なら、『胸を張って』助けを求めよう。助けてもらった分、違うところで誰かの力になれればいい
APD当事者である真壁さんは、幼い頃から「聞き取りづらさ」に悩まされてきた一人だ。人よりも聞こえづらいという自覚はあるのに、聴力検査では異常が認められない──周囲から理解してもらえず、「私の頑張りが足りないのだ」と自分を責めたこともあった。
聞き取りづらさと葛藤する日々の中で、いつしか「自分と同じような思いをしている人を助けたい」と思うようになった彼女は、教師を目指し、宮城教育大学へ進学。そこで聴覚障害児の支援について学ぶうちに、APDの存在を知り、病院を受診、診断を受けた。
周囲の人に自身の特性についてきちんと知ってもらうことに決めた真壁さんは、自身のAPDについての説明書を作成し、皆に読んでもらうことにした。また、教授たちに「授業の要点が書かれた資料の共有」や「発話者の声を聞きやすくする送受信機の使用」をお願いしたり、友人たちに聞き取れなかった箇所を教えてもらえるよう頼んだり……とちょっとしたサポートをしてもらえるように声をかけたのだった。
「困ったことがあったら声をかけてね」と快く返事をしてくれた友人たちの助けのおかげもあり、真壁さんは2020年に大学を卒業。同年4月には、晴れて教師になる夢をかなえた。
「新年度が始まるときに、職員室で、自身がAPDであることを説明する時間をつくってもらいました。先生たちのほとんどは、そのときにAPDを初めて知ったようでしたが、『電話が苦手』『ざわざわした場所が苦手』といった特性を理解してくれました。現在は、『話し合いをするときは静かな部屋に移動する』『(さまざまな音がしている)職員室ではなく、より静かな事務室の電話を使えるようにする』といったちょっとしたサポートをしてもらっています。大学時代に作った『説明書』は、現在も活躍中。いつでも誰でも読める場所に置かせてもらっていますよ」
そんな真壁さんは、生徒と接する際にもさまざまな工夫を取り入れている。
「私が担任を受け持っている支援学級はかなり人数が少ないので、普段は『いろいろな音が多すぎて聞き取れない』状況が発生することはありません。しかし、通常学級で大人数の子たちと交流するときは、人数が一気に増える分聞き取りづらさを感じます。例えば、休み時間、特にざわざわしている中だと話しかけられても気づかなかったり、授業で生徒が発表する際に恥ずかしがって声が尻すぼみになってしまうと聞き取れなかったりしますね。
そうした聞き取りづらさをカバーするために、『大事な話をするときは生徒と一緒に静かなところに移動する』『発表する内容を先にノートで見せてもらう』というような対策を取っています。
今は、授業を設計する側になったので、自分の経験を生かして『皆にとって聞き取りやすく分かりやすい』授業が設計できるように日々試行錯誤しているところです。一番気を付けているのは、口頭で話をするだけでなく、黒板を使うなどして同時に視覚情報を提示することですね。また、自分の場合、全体像や要点が見えない話を整理しながら聞くのがとても苦手です。ですから、話をするときは『全体の見通しが分かる』ようにすることも意識しています。話し始めるときには『今日は○○と◇◇と△△について話します』と提示し、内容ごとに区切って整理しながら、順序立てて話をするといった具合ですね。
『こういうふうにできたらいいな』と思いついても、実践の場になると、なかなかうまくできないことも多くあります。自分の経験を生徒たちの授業づくりにどう役立てるかは、まだまだ模索している途中ですね」
ちょっとしたサポートがあれば、障がいは「障害」じゃなくなる
職場でも自身の障がいを公表し、周囲にサポートをお願いしたり、自分でやり方を工夫したりしながら、APDと向き合い続ける真壁さん。彼女はいま、APDをどのように捉えているのだろうか。
「聞き取りづらさで大変な思いをしたり、『自分が駄目なんだ』と落ち込み、やけになったりすることもありました。でも、今は、APDってちょっとしたサポートがあればどうにでもなる障がいなのかもしれないな、とも思えるんです。
私の場合、過去を振り返ってみると、ありがたいことに『いつも周囲の人が自然に手助けをしてくれていたな』ということに気づきます。大学の友人にAPDであることを伝えたときにはすぐ『困ったら助けるからね』と言ってくれましたし、自身の障がいを知らなかった小学校~高校時代も、聞き取れなかった部分は、隣の席の子が嫌な顔一つせずに教えてくれていました。
APDの症状で困ることは確かにあります。でも、助けてくれる人が周りにいれば、自分がAPDだということはさほど気にならなくなるんです。だからこそ、『適切に助けを求める』ことはとても大切なのだと思います」
真壁さんは、自身と同じように「苦手なこと」がある人に向けて、こんなことを話してくれた。
「適切に助けを求めるためには、まず、『自分が何に困っているのか』を徹底的に見つめてみることがとても大切だと思います。先ほど、同じAPDの人でも、聞こえづらさの原因や生活スタイルが違えば人によって困りごとも違う、とお話ししました。つまり、自分と同じ特性について解説している書籍があったとしても、それがそのまま自分のための取扱説明書になってくれる、とは限らないのです。自分の困っていることやお願いしたいサポートについて、他者にもきちんと理解できるよう説明するのは、意外と難しいもの。だからこそ、困りごとに向き合う時間を持つことが必要なのではないかと思います。
自分の困りごとをとことん研究していくと、一口に『できない』『苦手』な作業といっても、その中に『自分で何とかできそうな部分』と『自分の努力だけではどうにもならない部分』があることに気づくはずです。まずは自分でできそうな部分に取り組んでみる。その上で、『やっぱり自分の力だけではどうにもならないな』『誰かの手が必要だな』と思った部分については、潔く『助けて』と声を上げてみたらいいんじゃないかな、と思います。
……そうは言っても、助けてほしいとお願いするのは難しいことですよね。相手に労力をかけてもらうことへの申し訳なさから、声をかけるのをためらうこともあるでしょう。私も、いまだに悩むことがあります。ですが、今は『その分、自分のできるところで相手を助けよう』と考えるようにしているんです。最終的に、自分を助けてくれた人が得をするように──そう考えて動けたらいいんじゃないかなって思います。
また、他者が平然としている場面で、自分だけが『助けて』と声を上げていいのか、とためらってしまう人がいるかもしれません。しかし、『発言していない』ことと『不満がない』ことが必ずしもイコールだとは限りませんよね。よく、『APDの人が聞き取りやすいよう配慮された環境は、結果的に誰もが聞き取りやすい環境になる』といわれます。ある人の意見は、当人だけでなく、『他の誰かにとっても』より良い環境を形作る可能性を秘めている、ということですよね。助けが求めづらいと感じたら、『自分は“環境調整”に貢献できるかもしれない』というふうに考えてみるのも良い手段だと思います」
今後もさまざまな形でAPDについて発信していきたい、と話す真壁さん。最後に、今後の夢を語ってくれた。
「自分の活動を通して、少しずつ障がいの認知度が上がり、誰もが自然に手を差し伸べられる社会になる──自分の起こしたアクションが巡り巡って『理想の社会』という形になって自分の元へと戻ってくる──それってすごくハッピーじゃないですか?」
~人の話を聞き取れないから教師にはなれない、なんてない。【前編】へ~
この言葉で正確に表現できるか分からないけれど、誤解を恐れずに言うと、どんなに頑張ってもできないことは、負い目を感じず「胸を張って」助けてもらったらいい。人の助けを借りる。その分、自分もできることを生かして誰かを助ける。そんなふうにして、補い合うことが大切なのではないでしょうか。
編集協力:「IDEAS FOR GOOD」(https://ideasforgood.jp/)IDEAS FOR GOODは、世界がもっと素敵になるソーシャルグッドなアイデアを集めたオンラインマガジンです。
海外の最先端のテクノロジーやデザイン、広告、マーケティング、CSRなど幅広い分野のニュースやイノベーション事例をお届けします。

APD当事者。教師。宮城教育大学卒業。APDの認知を広めるため、メディア取材や講話の依頼にも積極的に応じる。大学時代、人前で話すのが苦手であるのを克服しようと、自分が読んだ本の面白さを言葉のみで5分間プレゼンするビブリオバトルサークルに入部。2018年度の全国大学ビブリオバトルで優勝するまでに。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。