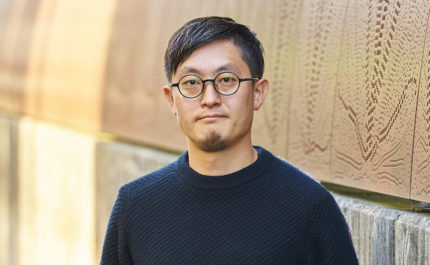シェフは自分の店を持なきゃ、なんてない。
小・中・高校と野球一筋だった少年が、あるきっかけからフレンチのシェフに。しかし、彼はその後レストランを辞めて、フリーランスの道を選ぶ。今自分が発信をすべきことは何なのか、そしてフード業界の将来を見据えどのような道を歩むべきなのか……。人生最高のチーズケーキ とも称される『Mr.CHEESECAKE』を生み出した料理人の田村浩二さんが見せる新しい“食”へのアプローチは、消費者、生産者、同業者、さまざまな人に“気付き”をもたらす――。
(2021年2月25日加筆修正)

近年、無農薬や生産者の顔が見える食材などが一般消費者にも認知され、手に入りやすくなるなど、食卓に並ぶ料理に対してのこだわりがより深まっているように感じる。しかしその一方で、インスタ映えメニューなど、見た目重視の料理がブームとなっているのも事実だ。このような食の多様化は、良くも悪くも、その人の意識によって姿を変える。見た目だけではなく、食材や料理とおのおのが向き合うことのできる現代だからこそ、田村さんは第一次産業の危機や食の価値・可能性を問いかけている。
新宿調理師専門学校を卒業後、乃木坂「Restaurant FEU(レストラン フウ)」にてキャリアをスタート。六本木「Edition Koji Shimomura(エディション・コウジ シモムラ) 」の立ち上げに携わる。表参道の「L’AS(ラス)」で約3年シェフを務めたのち、渡仏。フランス南部マントン「Mirazur(ミラズール) 」やパリ「Restaurant ES(レストラン エス) 」で修業を重ね、2016年に日本へ帰国。2017年には、世界最短でミシュランの星を獲得した「TIRPSE (ティルプス)」のシェフに弱冠31歳で就任。世界のベストvレストラン50の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018 期待の若手シェフ賞」を受賞するなど経歴を重ねた今、あえてレストランから離れたことで見えてきた課題や、未来への展望などを伺った。
野球から離れる決心をして、親友に誕生日ケーキを作ったことが料理の道に入るきっかけだった
神奈川県三浦市、海沿いの街で育った田村さん。父親が少年野球のコーチを務めていたことなどもあり、幼い頃は野球に打ち込む日々だったそう。
「小・中・高校とずっと野球をやっていたので、このまま大学野球に進んで、できればプロになりたいと考えていたんです。けれど、大学のセレクションに落ち、これを機に野球をきっぱりとやめることに。大学へは“野球をやるために行く”つもりだったので、進学の道も選ばなかったですね」
野球から離れる決心をした高校2年生の彼が、料理の道に目覚めたきっかけとは。
「2学期が終わるタイミングで親友の誕生日があったんです。今まで野球しかしていなかったのでお金もないし、どうしようかと考えて、何を思ったのかケーキを作ったんです(笑)。当時、家で包丁を握ったこともなかったですからね。母親に聞くのはなんだか恥ずかしかったので、ネットで調べて作ってみました」
試作を重ね、満を持してプレゼントしたケーキには、友達から予想以上の反応があったそう。
「親友とは違うクラスだったので、休み時間にケーキを持って行ったんです。背が大きくて目つきも悪い、しかも坊主のガラの悪いやつが誕生日ケーキを作ってくるという不思議な光景(笑)。仲の良いメンバー以外も興味津々で集まってきて、みんなで『おいしい!』と喜んで食べてくれたんです。そのとき、自分の料理で喜んでくれる姿やみんなが食を通じて盛り上がるのっていいなと思いました。この出来事が料理の仕事をしたいと思ったきっかけです。あと、幼い頃からの食環境もありますね。昔からポテトチップスとかジャンクなものを食べることが少なくて、デザートはドーナッツや蒸しパンなど母親の手作り。食を改めて意識したときに、料理がすごく身近にあるものだと気付いたんです」
自身で常に課題を立てることが、今後の糧となる
その後、新宿調理師専門学校に進学。自分の中でルールを決めながら目標に向かって勉強をしたそう。
「当時、30歳には自分のお店を持つという計画を立てていました。結果的にはそうなっていないんですけどね。野球をやめたからには料理でどうにかすると決めていたので、無遅刻無欠席の皆勤賞、実技と筆記全ての平均が85点以上でもらえる努力賞を取り、自分の中のルールを守り通しました」
専門学校卒業後は、数々のレストランで修業を積み、本場フランスへ。そこで現地の人からたずねられたことが、今の活動にもつながっている。
「フランスに行ったときに、現地の人にしょうゆの作り方を聞かれたんです。なんとなくは分かっていたのですが、ざっくりとしか説明ができなくて。自分の国のことなのに分からないなんてまずいなと思いましたね。帰国して今2年ちょっとなのですが、しょうゆ、みそ、酒……と、30都道府県ほどまわりました。あのときの問いかけがなかったら、生産者の方々に会いに行っていないかもしれません」

生産者との出会いが料理人としての意識を変えた
現場を訪ねたことで、さまざまな課題も見えてきたそう。
「実際に生産者を訪ねたことで、良い食材が多く世にでていない現状など第一次産業の課題が見えてきたんです。それと同時に、料理人だったらこの問題を解決できると感じました。僕たちは食材がなくなってしまったら料理ができない。生産者の方たちが前に出ることで、消費者の意識も高まるので、そうなるためには僕たち料理人が発信をすることが、一番説得力があるのではと思いました」
取り組みをするうえで必要なのは、消費者に対する“きっかけづくり”。そのためには自身の立場も変えなくてはいけないと考えた。
「レストランにくる人が求めているのは、このシェフが作るから、このレストランの料理だからということ。違う部分にスポットが当たってしまうので、生産者の気持ちやストーリーが伝わりにくいんです。自分のテクニックを見せるような料理って素材が生きないので……。そう思うと評価のために右往左往していた自分の料理がすごくダサく見えてきたんです。そんな想いの中、僕が今いるべきなのはレストランではないと考えるようになりました」

プロダクトに込めた生産者の思いが消費者のもとへ
生産者との出会いをきっかけに田村さんがはじめたプロダクトは多数ある。
「このアイスクリームに使っている国産のバラが素晴らしいとか、干物屋さんの伝統的な技術が素晴らしいなど、僕のプロダクトを通して、その食材を作っている生産者の方がいることにまずは気付いてほしいです。生産者の技術や取り巻く環境への認知が広がることで、消費者の食への関心もさらに高まり、食に携わるみんなが幸せになれる作用が生まれるはずです。2019年1月には家庭料理のレシピ本を出すのですが、誰かのために料理を作ると、もっとおいしいものを作りたい、おいしい食材を使いたいと素材に目が向くと思うんです。こういう取り組みの一つひとつが、生産者と消費者をつなげるきっかけになっていったらと思っています」

最近手掛けた仕事を伺うと、面白い取り組みが。
「LIFULL Table Presents『地球料理 -Earth Cuisine-』という、地球上でまだ光を当てられていない素材にフォーカスし、その素材を食べることで地球のためになる、地球の新たな食材を見つけるプロジェクトのメニュー開発を担当しました。僕、サステナブルシーフードという日本の水産業を継続可能なものにする活動をしていたので、このお話にもサステナブルというキーワードがあり、自分にピッタリだと思ったんです。雨が山に降り、それが川に流れて、海に戻る。その川と海が交わる場所(汽水域)にはプランクトンが発生し、そういう場所ではカキが育つ。だからカキをメニューに採用するなど、さまざまなストーリーを込めました」
料理人だからといってスタイルを決めることはない
食に携わる者として、自身のスタイルを確立する田村さん。今までで立ちはだかった壁はあるのだろうか。
「『TIRPSE』でシェフを務めていたとき、シェフになったのは僕で3人目。3人目ともなるとシェフが変わったところで注目されない。賞を取って評価は上がるけれど、お店の売り上げは変わらなかったんです。それもあり、自分でレストランをやってもはやるヴィジョンが見えなかった。売り上げにはいろんな要因があるのですが、それを料理の力で覆せなかったというのが自分の中の大きな壁でした。けれどそのときに、自身の見せ方の問題だと気付いたんです。それまではレストランに来てくださるいわゆるコアな相手にしか発信をしていなかったのですが、例えばツイッターをはじめてみたり、加工食品のプロデュースやオリジナルチーズケーキのブランドを作るなど、マス(大衆)向けに発信をしていくことの重要さを感じました。もしあのまま順調に売り上げが上がっていたら、自分でレストランをやっていたかもしれませんね」
やめるという選択をしたことに関しては、後悔をしていないという。
「料理人って自分のお店を持ってオーナーシェフになるという道に向かっている方が多いと思うのですが、そうではない生き方もあるということを、僕は下の世代にも知ってほしい。上の世代の方も、王道を通り、賞を取ってきた料理人が現場を変えたら、時代が変わったのかなと思ってくれると思うんです。そう思わせる人が必要だと思ったので、僕がやろうと。これを実現させることで、上世代も下世代も料理人としての見方が今までと変わると思います。スタイルにとらわれていては、僕がやりたいことは実現しないんです」

1985年生まれ、神奈川県出身。食のUI、UXをデザインする料理人兼デザイナー。開店わずか2か月でミシュラン1つ星を獲得したフレンチレストラン「TIRPSE (ティルプス)」元シェフ。 世界のベストレストラン50の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018 期待の若手シェフ賞」受賞。 現在はMr.CHEESECAKEの他、複数の事業を手掛ける事業家として活動。.science 株式会社 取締役。
公式Twitterアカウント @Tam30929
公式note note note.mu/koudy
多様な暮らし・人生を応援する
LIFULLのサービス
みんなが読んでいる記事
-
 2023/08/31身体的制約のボーダーは超えられない、なんてない。―一般社団法人WITH ALS代表・武藤将胤さんと木綿子さんが語る闘病と挑戦の軌跡―武藤将胤、木綿子
2023/08/31身体的制約のボーダーは超えられない、なんてない。―一般社団法人WITH ALS代表・武藤将胤さんと木綿子さんが語る闘病と挑戦の軌跡―武藤将胤、木綿子筋萎縮性側索硬化症(ALS)の進行によりさまざまな身体的制約がありながらも、テクノロジーを駆使して音楽やデザイン、介護事業などさまざまな分野でプロジェクトを推進。限界に挑戦し続けるその姿は人々の心を打ち、胸を熱くする。難病に立ち向かうクリエイター、武藤将胤(まさたね)さんとその妻、木綿子(ゆうこ)さんが胸に秘めた原動力とは――。
-
 2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題
2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。
-
 2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん
2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん「整形の綺麗な面だけじゃなく、汚い面も知った上で選択をしてほしい」と語るのは、自身が1,350万円(2023年4月時点)かけて美容整形を行った、整形アイドルの轟ちゃんだ。美容整形を選択する人が増える中で、彼女が考えていることとは?
-
 2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)
2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。
-
 2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記
2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記人と会話をするのが苦手。場の空気が読めない。そんなコミュニケーションに自信がない人たちのことを、世間では“コミュ障”と称する。人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めたり、人気芸人やアーティストと交流があったり……アナウンサーの吉田尚記さんは、“コミュ障”とは一見無縁の人物に見える。しかし、長年コミュニケーションがうまく取れないことに悩んできたという。「僕は、さまざまな“武器”を使ってコミュニケーションを取りやすくしているだけなんです」――。吉田さんいわく、コミュ障のままでも心地良い人付き合いは可能なのだそうだ。“武器”とはいったい何なのか。コミュ障のままでもいいとは、どういうことなのだろうか。吉田さんにお話を伺った。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。