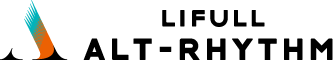無駄なものはなくした方がいい、なんてない。
Twitterで「バーベキュー」と呟かれると藁人形に五寸釘が打ち付けられるマシーンや、回線状況が悪い状態を演出しオンライン飲み会から緊急脱出できるマシーンなど、一見すると「役に立たない、無駄なもの」を、発明家・クリエイターの藤原麻里菜さんは、10年近く制作し、インターネット上で発表し続けている。
なぜ時間とお金をかけてわざわざ「無駄づくり」をするのか、と疑問を覚える人もいるだろう。しかし、生活に「無駄」がなくなってしまうと、効率的であることだけが重視され、人によってはそれを窮屈に感じてしまうかもしれない。実際に、藤原さんは「誰の生活の中にも必要な『無駄』があるはず」と言う。
藤原さんは、なぜ「無駄づくり」にたどり着いたのか。「無駄」と「効率」をテーマにお話を伺った。

「無駄」という言葉を辞書で引くと、「役に立たないこと」「効果・効用がないこと」と書かれていることが多い。たしかに食品ロスの問題など「無駄をなくす」ことが必要な場合もあり、「無駄なものはない方がいい」のかもしれない。しかし、ものを手放していくことが推奨されたり、効率的であることが重視されすぎたりすると、窮屈さを覚えることもあるのではないか。
そんな、一見するとネガティブな印象を感じる「無駄」という言葉を、ポジティブにとらえているのが藤原さんだ。
藤原さんは、つくったものが何の役にも立たなかったとしても、自分にとって必要な「無駄」を切り捨てないことで、心に余裕が生まれることがあると語る。
自分にとって必要な「無駄」は切り捨てず、大切にする
オンライン飲み会緊急脱出マシーン | 無駄づくり
藤原さんが「無駄づくり」と称した工作・発明の動画をYouTubeに投稿し始めたのは、2013年のことだった。
「最初は、NHKの番組『ピタゴラスイッチ』に出てくるようなからくり装置を作れないかな、と軽い気持ちでつくったんです。でも、すごくしょぼいものが出来上がっちゃって。これを『失敗』にしたくないなと考えて思いついたのが『無駄』でした」
「無駄」という言葉に注目したのは、星野源がリーダーを務めていたバンド・SAKEROCKの影響があったという。
「学生の頃、SAKEROCKをよく聴いていて。当時はTwitterなどのSNSも盛んじゃなかったので、毎日バンドの公式サイトをチェックしていたんです。そしたらある日突然、たしか『ムダ』というページができて、その直後に『MUDA』というアルバムがリリースされて。それが印象的で、『無駄っていい言葉だな』とずっと頭の片隅にあったんです。SAKEROCKが表現している心の愉快さのようなものが好きだったし、『無駄』というのは自分がやりたいことにも通ずるような気がしました」
幼い頃からものづくりやアイデアを考えることが好きだったという藤原さんだが、高校時代は「面白いことをやりたい」という気持ちも強かったという。面白い=お笑い、と思い立ち、高校卒業後はお笑い芸人を目指して吉本興業の養成所に入所する。卒業後はしばらく芸人として活動を続け、仕事の一環としてYouTubeチャンネルを開設したのもこの頃だ。
「無駄づくり」の動画投稿はハイペースで続けていたが、「こうなりたい」「こんなものをつくりたい」という目標は特になかったという。
「昔から、何かをつくる時にあまり高いハードルを設けない方なんです。子どもの頃から三日坊主で、何かに挑戦しては諦めて、を繰り返していたんですけど、両親や友達はそれをばかにしない人たちでした。私が何かに興味を持つたびに応援してくれたので、その影響も大きかったと思います」
ものづくりに高いハードルを設けない、という姿勢は、藤原さんの考える「無駄」の定義にも結びついている。藤原さんにとって「無駄づくり」とは、「役に立たなさ」を許容することだという。
「エイブラハム・フレクスナーという化学者の言葉に『有用性という言葉を捨てて、人間の精神を解放せよ』というものがあります。ものづくりをする時って『ちゃんとしたコンセプトを』『何かの役に立つものを』と考えがちですが、フレクスナーの言葉のように、もっとふわっとした感覚でつくってもいいと思うんですよね。
そうしてできたものが回り回って何かの役に立つかもしれないし、そうでなくても、好奇心に任せて何かをつくった経験て、絶対にプラスになると思うんです。それによって心に余裕が生まれたり、社会が少し豊かになったり。
役に立つものを目指さなくても、覚悟を決めなくても、ものづくりはできる。『無駄づくり』という言葉にはそういう意味も込めています」
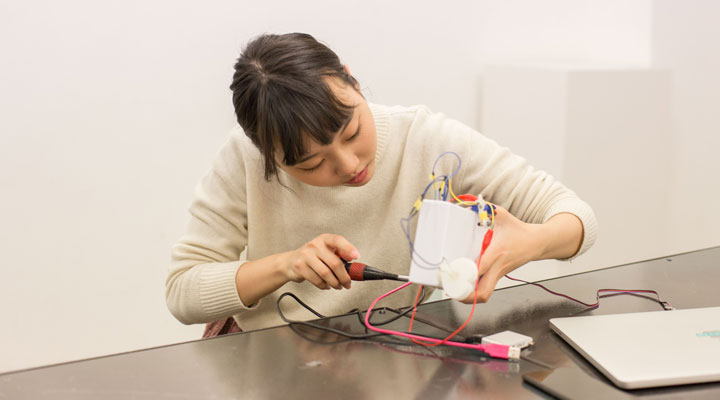
これまでにつくってきた「無駄発明品」は200を超える。どれも実用性や有用性は全くないけれど、なんとなく共感できたり、クスッと笑えたりするものばかりだ。
制作で意識しているのは、日常の中で見逃してしまいがちな感情に「わざわざ引っかかる」ことだという。
「感情が物体として具現化されるから、自分の気持ちに向き合わざるを得なくなるんですよね。例えば『Twitterでバーベキューと呟かれるたびに藁人形に釘を打ち付けるマシーン』は、友達が開催したバーベキューに誘われなかったことがきっかけで……。みんながバーベキューをしている動画を見て傷ついた自分を、マシーンをつくったことで認めることができて、ちょっと楽になったんです。
『無駄づくり』を通して、今まで見て見ぬふりをしていた感情に立ち向かうことができているし、それで少し自分の世界が明るくなった気がします」
無駄を愛することは、「効率を無視する」ことではない
前述の通り、藤原さんの活動の根幹には、役に立たないこと、意味のないことを肯定したいという思いがある。
「そもそも、全てのものにあまり意味はないと思っているんです」と藤原さんは言う。
「小さい頃、名前の由来をお母さんに聞いたら、『別に意味はない』って言われたんです。当時は全てのものに何か理由や意味があると思っていたけれど、意味がないものも存在していいんだなって。その時から、意味がある・ない、役に立つ・立たないは、はっきりと分けられるものじゃないんだと考えるようになりました。
今、語学を勉強しているんですけど、これもキャリアアップのためとかじゃなくて、単なる好奇心で続けていて。さっきもお話ししたように、私はすごく三日坊主なんですが……。好奇心で何かを始めてみて、諦める時は諦めるみたいなことも別に否定しなくていいと思うんです」
何の役に立つか分からないものに時間を割くことは、一般的に「非効率的」と言われがちだ。「無駄」を愛する藤原さんにとって「効率化」は正反対の考え方かと思いきや、「自分には、すごく効率重視の部分もある」のだそう。
「効率化した方がいいものって、何に重きを置くかで変わると思うんです。私は『無駄づくり』をたくさんしたいから、生活に関してはすごく効率重視で動いている部分もあります。
今って、家事も仕事も効率化が進んで、便利になっていますよね。その分、好きなことに使える時間が増えたはずなのに、他人に対する寛容さや心のゆとりは、逆に減っている気がします。生活に必要な余白まで削っているというか……。

本当はもっと、一人で何かを考えたり、人とコミュニケーションをとったりする時間をつくるべきだと思います」
こうした効率化が進み続けた時代の先に待っているのは、膨大な「無駄」な時間ではないかと藤原さんは指摘する。
「その無駄にどうやって向き合うかを考えないといけないですよね。余計なことと言われるものの中にある『自分にとってはこれが必要』というものを見つけないと、ただ時間を溶かすことになる。
例えば私は、家からアトリエまで往復1時間歩く生活を続けています。一般的には『無駄だなあ』と思われることも、私にとっては『この時間は必要だな』という感覚がある。そういうものが、人それぞれにあると思うんです」
忙しい人のタイムラインに現れて、数分だけでも「無駄」を提供したい
「無駄発明品」はたびたび話題になり、SNSでの動画総再生回数は4,000万回を超えた。さらに台湾で開催された個展には25,000人以上が来場するなど、クリエイターとして注目を集めている。
最初は「こんな無駄なものをわざわざつくるなんて」と批判されるのではないかと、反応が怖かったという。しかし実際に寄せられる反響は、ほとんどが歓迎の声だ。
「動画を見た人からは『たしかに無駄だけど、いいね』と言ってもらえることが多いですね。最近、世の中の様子からすごくギスギスした空気を感じるんですが、『無駄づくり』のことは寛容に見てくれている印象があります。
人ってやっぱり、生活がどうしようもなく忙しい現状もあると思うんです。私は『無駄』が好きだから、色々なところで『無駄な時間をつくろう』って言うんですけど、忙しくてお金もなかった頃の自分に向かっては言いづらいなって。だから、無駄な時間なんてほとんどない、とれない、という人の気持ちも分かるんです」
 札束で頬をたたくマシーン
札束で頬をたたくマシーン
藤原さんの生活が上向いた理由には、「無駄づくり」の活動を続けたことでお金が貯まり、余裕が生まれたということもある。しかしそれ以上に、思いきって「好きなこと」をする時間を設けるようにしたことも大きかったという。
「本当に忙しくてお金もなかった時、それでも1日1時間は個人制作をする、と決めたことが心の余裕に結びついた気がします。依頼される制作も好きですが、個人制作は何の制約もプレッシャーもないし、自分のペースでできるから本当に楽しくて。当時は、これでもし仕事が全然こなくなったら、アルバイトをしながらでも『無駄づくり』を続けようと思っていました。
こんなに楽観的だったのも、『自分はここさえ守れれば幸せ』と自覚して、それ以上は求めなかったからかもしれません。私、大物になりたいみたいな野望も特になくて。お金も時間もあればあるだけ消費してしまいがちなので、これ以上はいらない、というゾーンを見極めて、あとは『余剰』として考える必要があるんじゃないかと思います」
視聴者の数が増えるにつれ、「無駄づくり」を続けるためのモチベーションや活動の意義にも少し変化が生まれてきたという。
「最初は、どうやったら『無駄づくり』で自分を表現できるか、どうやったらこれで生活できるようになるかを模索していました。でも最近は、自分が『無駄づくり』をすることで社会にどんな影響を与えられるかを考えるようになりました。
私は『無駄づくり』で経済活動に身を置いていて、一応お金も稼いでいる。それ自体が何か新しい価値を生み出すんじゃないか、と今は思っています。
近年は『何もしない時間の大切さ』を見直す動きも起きていますし、それは自分が大切にしたい『無駄』にも似ていると思います」
自分にとって必要な「無駄」を切り捨てず、丁寧に守り抜いている藤原さんの活動は結果的に、それを目にした人の生活の中に少しの「無駄」な時間と心の余裕を生み出している。そんな「無駄」を社会に広めていける存在になりたいと藤原さんは言う。
「昔からインターネットが好きだったから、嫌なことがあった時も、いつもインターネットで偶然見たものに励まされてきたような気がしています。
インターネット上に『無駄づくり』の動画を投稿し続けているのは、自分もそうでありたい、という気持ちがあるからかもしれない。毎日忙しくて余裕がないと感じている人のタイムラインにちょっとだけ現れて、数分だけでも『無駄』な時間を提供できる存在に私がなっていたらうれしいですね」
そういうふうに、人それぞれの「いい無駄」って絶対にあると思うから、それに気づいて、その「無駄」を大切にする生活ができたらいいんじゃないかなと思います
取材・執筆:生湯葉シホ
編集協力:はてな編集部

1993年生まれ。コンテンツクリエイター、文筆家。株式会社 無駄 代表取締役。
2013年から頭の中に浮かんだ不必要なものを何とかつくり上げる「無駄づくり」を主な活動とし、YouTubeを中心にコンテンツを広げている。2016年、Google社主催の「YouTubeNextUp」に入賞。2018年、国外での初個展「無用發明展- 無中生有的沒有用部屋in台北」を開催。25,000人以上の来場者を記録した。2021年『考える術(ダイヤモンド社)』無駄なマシーンを発明しよう(技術評論社)』を上梓。
「総務省 異能vation 破壊的な挑戦者部門 2019年度」採択/「オンライン飲み会緊急脱出マシーン」文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門審査委員会推薦作品に選出/ 2021年 Forbes JAPANが選ぶ「世界を変える30歳未満」30 UNDER 30 JAPANに選出される。
Twitter @muda_zukuri
YouTube 無駄づくり / MUDAzukuri
みんなが読んでいる記事
-
 2019/05/24アイドルは自分らしく生きられない、なんてない。高橋 愛
2019/05/24アイドルは自分らしく生きられない、なんてない。高橋 愛「モーニング娘。」のメンバーとして、10代、20代を全力で駆け抜けてきた高橋愛さん。立ち止まったら抜かされ、スパートをかけても追いつけない厳しい世界で、彼女はどう自分軸を保ちながら戦ってきたのか。女優やモデルのみならず、ファッションアイコンとしての地位も築き上げたこれまでの軌跡を綴る。
-
 2021/09/06運動は毎日継続しないと意味がない、なんてない。のがちゃん
2021/09/06運動は毎日継続しないと意味がない、なんてない。のがちゃん人気YouTuber、のがちゃん。2018年にフィットネス系チャンネル「のがちゃんねる」を開設し、現在は登録者数86万人を超えている。もともとはデザイナーとして活動しており、フィットネスやスポーツに縁があったわけではない。そんな彼女の原点は、中学や高校時代のダイエット。食べないダイエットなどに挑戦しては、リバウンドの繰り返し。当時の経験と現在のYouTube活動から見えてきたのは、「継続の大切さ」だ。多くの人が直面する体作りや健康について、のがちゃんの考えを伺った。
-
 2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】
2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】ジェンダーレスという言葉を耳にしたことがあるかもしれません。この記事では、ジェンダーレスの意味やジェンダーフリーとの違い、ジェンダーレス社会の実現に向けた取り組み、ジェンダーにとらわれず自分らしく生きることの大切さについて紹介します。
-
 2022/09/27日常の光をつかむ写真家・石田真澄 【止まった時代を動かす、若き才能 A面】
2022/09/27日常の光をつかむ写真家・石田真澄 【止まった時代を動かす、若き才能 A面】あしたメディア×LIFULL STORIES共同企画第2弾は、写真家・石田真澄さん。大塚製薬・カロリーメイトの『部活メイト』、ソフトバンクの『しばられるな』などの広告写真、そして俳優・夏帆さんの写真集『おとととい』などを手がけてきた写真家だ。
-
 2023/01/12“もうおばあさんだから”、なんてない。BACK STREET SAMBERS(三婆ズ)
2023/01/12“もうおばあさんだから”、なんてない。BACK STREET SAMBERS(三婆ズ)BACK STREET SAMBERS、通称「三婆ズ」は、65歳、68歳、72歳の女性3名で構成されるダンスユニットだ。Instagramのフォロワーは10万人超。ダンス動画には、コメントで「キレキレですね」「カッコいい」といった声が集まっている。年齢にとらわれず新たなことを始める原動力について、話を伺った。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。