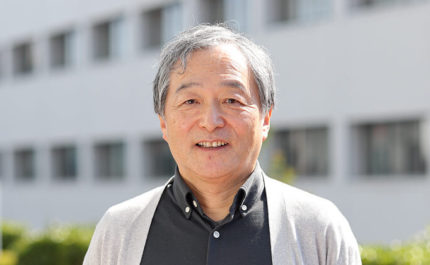なぜ、私たちは親を否定できないのか。|公認心理師・信田さよ子が語る、世代間連鎖を防ぐ方法
新型コロナウイルスの感染拡大により、実家に帰省できなくなった時。親の介護施設への訪問が制限され、面会できなくなった時。心のどこかで「ほっとした」。そういう人は少なくないのではないでしょうか。
“機能不全家族という言葉は現在は使用しない(中略)。どこかに機能十全な(完全に機能する)家族があるというのは誤解であり、そんな幻想を抱かせる言葉は、犯罪的であるとすら今は考えているからです”
この言葉は、公認心理師・信田さよ子の著書『アダルト・チルドレン:自己責任の罠を抜けだし、私の人生を取り戻す』の初版から25年経った新版の「あとがき」に追記されました。
どこかに機能十全な家族があるというのは誤解である――。つまり、家族ってそんなにいいものじゃない。日常的に目にする虐待のニュースや家族に会えなくなってほっとした安心感に焦点を当ててみると、ドラマやCMで見る“あたたかい家族の物語”とはまったく違う、家族の姿が見えてきます。
HCC原宿カウンセリングセンターの所長である信田さよ子さんは、DVや虐待の加害者・被害者に向けたグループカウンセリングに長年取り組んできました。なぜ、私たちは家族や親を否定することが難しいのか。また、世代間連鎖が起きる背景や防ぐ方法についても教えていただきました。

災害時に強調される“家族の絆”の裏にあるもの
――30年以上臨床に携わる中で、私たちが抱く家族のイメージはどのように変化してきましたか?
家族のイメージというのは、大きな災害が起きるほど強まります。東日本大震災のあと、「ACジャパン」のCMで強調されたのは“親子の絆”でした。新型コロナウイルスの緊急事態宣言時も、他人にはあれだけ気を配っていたにも関わらず、家族の前ではマスクが免除されました。まるで、最後のよりどころかのように“家族”が強調されるのです。
しかし、その副作用は必ずやってきます。家族のイメージは実は二重構造になっていて、“家族の絆”が強調されるほど、家族の問題も起きやすくなるんです。
阪神淡路大震災のあとには「AC(アダルトチルドレン)ブーム」、東日本大震災のあとには「毒親ブーム」が起きたことが、この二重構造をよく物語っています。実際、パンデミックのあと、日本でもヨーロッパでもDVの相談件数は激増しました。
「家族は時に怖いものである」そういう視点に立たない限り、聞こえてこない当事者たちの声があります。家族の愛、母の愛という、社会では美しいとされる「光」に殺されてしまう人たちがいるんです。
――なぜ、私たちは“理想の家族”をよりどころにしてしまうのでしょうか?
そもそも“理想の家族”というのは、社会規範の1つです。社会規範というのは、「赤信号を渡ってはいけない」とか「人のものを盗んではいけない」とか、社会をうまく回していくための「こうあるべき」というもののことを指します。
日本は、介護や子育てなどの福祉の機能を家族に頼ってきました。「病める時も支え合うのが家族」という前提が失われると、この国は成り立たなくなります。
社会規範がないと赤信号を渡っちゃう人もいるし、ものを盗んじゃう人もいる。だからこそ、社会規範が生まれるわけで、それは家族も同様です。
「こうあるべき」という家族像を目標に、みんな努力をする。でも、その通りにいかない人が多いからこそ、社会規範は残りつづけます。「こうあるべき」の裏には、そうでも言わないと、この基盤は簡単に揺らいでしまうことに気付いているからではないでしょうか。
「親を否定できない空気」が世代間連鎖を招く

――「子どもを持つことに不安がある」「自分の母親のような毒親になったらどうしよう」といった話をすると、「考えすぎ」と言われたり、「親も親なりの苦労があったんだよ」と言われてしまったり、どこかまともに聞いてもらえていない感覚があります。
私からするとね、家族を持つことに不安を感じるのは、いたってノーマルな反応ですよ。
HCC原宿カウンセリングセンターに来る女性たちの8割以上が「我が子に暴力的になってしまったらどうしよう」とか「母親にされたようなことを自分の子にしてしまったらどうしよう」とか、そういった世代間連鎖を恐れてやって来ます。
でも、虐待的な環境で生きてきた人でも、穏やかな家庭を築いている女性はたくさんいるんです。
女性には生理があり、妊娠があり、出産がある。その過程を踏んでいく中で、自分の生育歴を振り返ることになります。「親はどう自分を育ててくれたのか」、唯一の教科書を求め、過去の記憶を思い出すんです。
その中には被害的な体験の記憶も含まれますから、1人で向き合うのではなく、カウンセラーのような第三者の援助が必要になります。そうやって生育歴を振り返ることができれば、世代間連鎖は避けられると思います。そんなに恐れることはありません。
むしろ、カウンセリングに訪れることの少ない男性のほうが心配ですよ。女性に比べて男性のほうに世代間連鎖が起こりやすいことは、DV加害者のプログラムで感じてきたことです。
私が代表理事を務めるNPO法人RRP研究会では、DV加害者プログラムを17年間実施してきました。参加男性たちの80%近くが過去に親のDVを目撃しており、そのほとんどが父から母へ向けたDVです。
――なぜ、男性のほうが世代間連鎖が起こりやすいのでしょうか?
やっぱり一部の男性はね、「20歳過ぎて親を悪く言うなんて幼稚だ」「親には親の苦労があったんだから、責任転嫁するな」と、親を否定することに対して極度にネガティブなイメージを持つ人が多いんです。
だから、ほとんど生育歴を振り返らない。もしくは、振り返っているつもりでも捏造的な記憶をつくり出してしまうことさえあります。
たとえば、父親から虐待されていた男性は、ある時から父親を擁護するようになります。だいたいの父親は息子が自分よりも背が高くなった時、虐待を止めます。そして、手のひらを返すように次の家長となる息子に媚を売るようになる。
「お父さんも大変だったんだ。お母さんさえ素直ならあんなことしたくなかったんだ」と言われた息子は、「親父も苦しかっただろう」とやっと父と心が通じた喜びを噛み締める。
すると、父の加害は正当化され、母の被害は捨象される。むしろ母のいたらなさのせいで、父は暴力を振るうしかなかったのだと、ホモソーシャルで、ある種捏造的な“父息子の絆の物語”が出来上がるんです。
――男性に限らず、なぜ私たちは親を否定することが難しいのでしょうか?
親を否定することを許してくれない空気がありますよね。「親も大変だったんだ」とか「親を否定しているうちは一人前じゃない」みたいな。
最近ではメディアの規制も強くなり、家族礼賛のテレビドラマばかり目にするように思います。なんだかんだ「いろいろあったけど家族っていいよね」という物語に帰結する。親と決別して終わる物語はそうそう見ませんね。
1人ひとりと話をすれば、家族についてマイナスの言葉もちゃんと聞こえてきます。でも、集団になると社会規範に落ちついてしまう。親を否定するのが難しいのは、やはり、それだけ家族を礼賛して母性を称揚するという規範がこの国の根幹だからなんですよ。否定を許さない空気が強固としてあるわけです。
苦しさの根底には共通の構造がある

――原宿カウンセリングセンターでは、アダルトチルドレンやDV被害者などを対象に、さまざまなグループカウンセリングを実施しています。全体を通じて「生育歴の振り返り」をおこなう場だと伺いましたが、具体的にはどのようなことがなされているのでしょうか?
1人ずつ自分の話をし、他の人たちは絶対に口を挟まず、聞くことに徹する。家族や親をいくら否定しても、絶対に口を挟まれることのない場所です。
初めて来た人は、何を話したらいいかわかりませんよね。ですから、「なぜ、原宿カウンセリングセンターに来たのか」そして「あなたの親はどれだけ変か、どれだけ酷い親だったかを他のみなさんにわかるように説明してください」とお伝えしています。
自分の話をし、人の話をただ聞く。そうやって回数を重ねていくと、蓋をしていた記憶も蘇ってきます。思い出して言葉にする際に、自身の被害者性を承認してくれるカウンセラーがそばにいることも非常に重要です。
――グループで向き合うことの良さは、どんなところにありますか?
自分の経験には個別性ももちろんあるけれど、他の人が語る被害体験にも共通の構造があると気付いていくんです。自分だけの苦しさだと思っていたけれど、実はその根っこには他の人にも共通する構造や歴史的背景があるのかもしれない、と。この気付きは本人たちにとって、非常に大きなものになります。
私たちのグループカウンセリングは、オープン、つまりいつからでも入れる形式を採用しています。そのため、同じグループにも長く通う人もいれば、初めての人もいるわけです。この「経験の差」が非常に生きてくる。
初めての人にとっては、経験の長い人がロールモデルになるし、逆に長く通う人にとっては、新しく来た人の変化を見ることで、自分がたどってきた道のりを振り返ることになります。
グループは親の評論会のようなものです。過去の被害経験がひどければひどいほど、一般の社会では話しにくくなりますよね。でも、ここではむしろ大変な経験をした人ほど「お〜すごい!」って賞賛されるんですよ(笑)。すごく変だけれど、本人たちにとっては、安心して話せる“価値の逆転”が起きる場所なんです。
過去を見ないと、未来は見えない

――昨今では、「これからどうしたいか、どう生きたいか」といった未来志向の問いを投げかけられることが多いように感じます。しかし、なぜ、私たちは過去を振り返ることが必要なのか、改めて教えてください。
歴史学者のあいだでは、「過去にこそ未来がある」と考えられています。これは人間も同じで、自分がどうやって生まれて、どういうところで育ったのかを知らないと、未来は見えてこない。
だから、生育歴を振り返ることはネガティブでも後ろ向きでもありません。むしろ前を見るために過去を振り返るのです。それができれば、世代間連鎖を防ぐことも、親とちょうど良い距離感を築くことも可能になります。実際、過去に大変な被害体験がありながらも、たくましく生きる人たちを私はたくさん見てきましたから。
たとえ後ろ向きだと言われても、後ろ向き万歳ですよ。すべからく後ろ向きでいきましょう。
取材・執筆:佐藤伶
撮影:山中散歩

1946年岐阜県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部哲学科卒業、同大学院修士課程家政学研究科児童学専攻修了。駒木野病院勤務、CIAP原宿相談室勤務を経て1995年原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。2024年2月に新著『暴力とアディクション』(青土社)が刊行される。
X @sayokonobuta
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜
2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント
2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜
2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。
-
 2026/01/22「将来への不安」にどう向き合えばいいのか。生きづらさを抱えた人たちを支援する抱樸・奥田知志さんに問う
2026/01/22「将来への不安」にどう向き合えばいいのか。生きづらさを抱えた人たちを支援する抱樸・奥田知志さんに問う「将来ホームレス状態になる可能性がある」という調査結果に、支援歴38年の奥田知志(おくだ・ともし)さんはどう答えるか。貧困の背景にある社会構造の変化と、孤立を防ぐために必要な「他者性」の視点。「なんとかなる」と言える社会を作る、新しい「希望のまち」構想について。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」