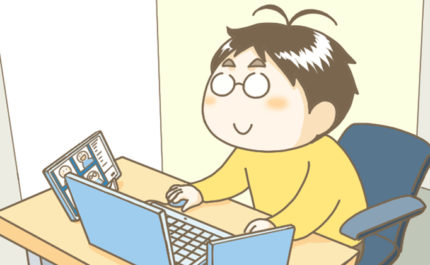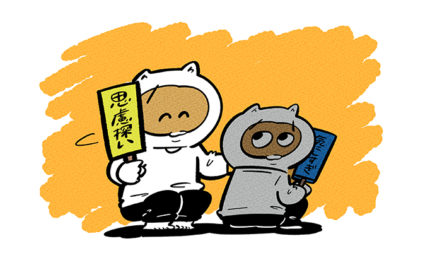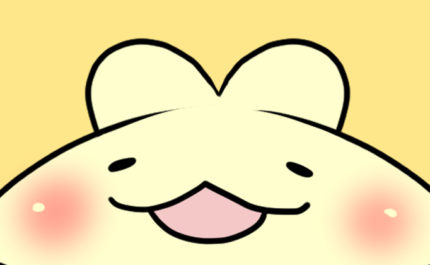【寄稿】ライフイベントを起こさなきゃ、なんてない。―「幸せのため」に逆算思考しなくていいし、他人と比べなくていい―

幸せの形も、心地よい暮らしも、一人ひとり違うはず
平日の昼間、会社の近くの中華料理店で山椒の利いた麻婆豆腐をかきこんでいたら右隣からよもやま話が聞こえてきた。
「あの人、結婚指輪してなかったよね?」
「何歳なんだろう」
「もう40くらいじゃない?仕事バリバリやるタイプなのかな」
同じ色のストラップを首から下げている男女3人。会社の同僚同士で、取引先の女性のことを話しているようだった。失礼な噂話は、その卓に運ばれてきた麻婆豆腐の匂いにかき消され、次の瞬間には別の話題に移っていった。

私たちは、何かと年齢を引き合いにして語りたがる。住まいも生活圏も価値観も、好きなアイスの味も家庭の事情もそれぞれ違うのに、年齢だけは確かな基準。分かりやすい数字というものは、悪しき拠りどころになりがちだ。
隣席で耳をダンボにしながら眉をひそめていた私にだって、思い当たる節はある。
とある女性役員を取り上げたインタビュー記事を読んでいた時、記事の最後に記された彼女の生年から年齢を計算した。そして、「この人は結婚しているのだろうか、子どもはいるのだろうか」と不躾な関心がむくむくと胸に湧いたので、つい検索をかけてしまった。彼女が真摯に語った言葉よりも、彼女のキャリア以外のステータスに固執したのだ。
そうした一連の流れを通して、軽率な私は自分の心の中に根深く巣食った偏見に、いつも向き合わされる。
他者への先入観やジャッジの目線は、同時に自分自身を苦しめる重石となり、私を苦しめる。幸せの形も、心地よい暮らしも、一人ひとり違うはずだと頭では理解しながらも、「他の人たちがこなしたライフイベントに未着手の私」という思いに苛まれるのだ。
結婚や出産、転職や家購入などのライフイベントのスタンプをぽんぽん押す友人たちと、自分の手の中の白紙のスタンプカードを見つめながら、私は時々静かな焦りに駆られる。激しい変化のない生活を送る自分を、心の端っこで見下しているような気さえしてくる。
「年齢」や「ライフイベント」なんて、ふた昔前の指標だ

ライフイベントというものは、「年齢」と同じで極めて分かりやすい指標になる。それらは全員に課された宿題のように「片すべきこと」として私の背中にのしかかり、着々とライフイベントを進める周りの人たちのことを「人生順調でいいなあ」と、何も知り得ない外野の立場から失礼なことを思ってしまう夜もあって、そんな時は自己嫌悪の沼に身を浸す羽目になる。
とりわけ27~28歳のアラサー真っ盛りの頃は30歳の大きな節目を強く意識するようで、同級生と会うたびに「誰々が結婚した、同期の何割が既婚者になった」という結婚ラッシュの話題で持ちきりだった。
すでに結婚した大学同期の名前を順々に挙げながら、「“残っている”のは私だけ」と、昭和かと聞き間違えるような自虐をかましながら酔い潰れた未婚女子もいた。“女は25を過ぎたら売れ残り”というかつてのクリスマスケーキ理論は、今や「蛇の抜け殻を財布に入れるとお金が貯まる」程度の迷信でしかない。蛇の抜け殻なんぞ見たこともない。
そして私たちの生きる現代は、「普通」や「当たり前」が崩れつつある潮目の時代だ。今や無限にある人生の分岐において、多いほうと少ないほうの「多いほう」の波に乗っても幸せになれるわけではない、と証明されてしまった。
年齢やライフイベントなどの目に見える指標だけを拠りどころに生きられるような、シンプルな時代は終わったのだ。
私たちの目の前に広がる景色を表すならば、就職、結婚、出産、育児、定年、老後……と段々に上がっていく「ライフステージ」という垂直に伸びた階段ではなく、「ライフコース」という果てなく横に広がる地平の道、と表した方がしっくりくるだろう。
遠くに霞んで見える、さまざまな色の目印に向かって私たちはめいめいに歩いている。心惹かれるどれかの旗に向かって歩いてみるものの、実は道が蛇行していたり、行き止まりや山道に遭遇したりして、誰しも汗水垂らしながら進んでいく。
ようやく辿り着いた場所も、思い描いていた桃源郷とは程遠く、「こんなはずじゃなかった」と何度も道を引き返す。何度も道を選び直す。そうして自分の足で歩いているうちに思わぬ景色に遭遇し、その場所に留まってみたり、行き先を変更してみたりする。
最初に定めた目的地ではなく、その時の運や縁に導かれながら楽しんだ道草こそが、今の自分を形成していることに気付くのだ。
人生の“逆算”なんて、考えなくてもいい

かつて私は、人生の分岐点の締め切りを決め、転職や結婚などの出来事を計画通りに進める人生が賢いと思っていた。
年齢を軸にすえて、経験したいライフイベントを「適齢期」という乱暴な枠に当てはめさえすれば、人生の“逆算”ができるはずだと思い込んでいた。
そこで、いざ社会に出てみると、道はそんなに単調ではなく、数キロ前の自分が立てた目標など「現在地の私」にとってはさほど重要な場所ではないことを思い知る。この途方のない道のりを、逆算して歩けるわけもない。
もちろん「何がなんでもあの場所にたどり着くのだ」と一つのゴールに向かって猛進する人も、なかにはいるだろう。
だが、そういう人生の攻略法は自分には向かないということを、私はようやく自覚し始めた。今の自分の気分を押し殺してまで当初の目的地を優先させる生き方や、自分自身に道草を許さない生き方は、多分私には無理なのだ。
ましてや一生という長い自由時間においては、経由するスポットは無限に発生する。ゴールなんて死ぬまで何度も設定し直せる。「やっぱりやーめた」と途中で諦めるゴールがあってもいいし、「なんとなく南に向かうか」と直感で目的地を選ぶ時期があってもいいはずだ。
音を立てずに静かに流れる川は、深い

アラサー真っ盛りの時期を過ぎた私だが、いざその峠を越えてみると、「みんなでギャーギャー騒いだ楽しい祭りだったな」という達観した気分で後ろを振り返れるようになった。
「残っているのは私だけ」という昭和発言をしたあの子も、今は結婚の話題に飽きたのか、新しく始めた趣味に夢中で幸せそうだ。
そして、「誰かとつがいになる」「子どもをつくる」「職や住居を変える」などの人生の経由地は動的だからこそ注目を集めがちだが、「今のままの生活を続ける」「新卒で入った会社に勤め続ける」という静的な営みの尊さはなかなか語られることがない。
動的なイベントを経由しない道の楽しみは可視化しづらいため、その道を歩く当人にしか感じ得ないのかもしれない。
「未経験」「未婚」などの頭につけられる“未”は、ある状態が実現していないという否定的なニュアンスで使われることが多いが、英語で「まだ・今でも」という意味の“still”は肯定文にも使われる。さらに「静かな・じっとした」という意味も持つ。
“still waters run deep”ということわざは、日本語の「能ある鷹は爪を隠す」という意味にあたるが、直訳すると「静かに流れる川は深い」だ。
音を立てずに静かに流れる川は、深い。
じっと留まった時間にだけ貯まる価値、静かな営みにしか持ち得ない面白みもあるはずだ。
分かりやすい音に惑わされることなく、むやみに他者の歩みと比べることもせず、自分が深く刻んだ軌跡だけに集中して、どうにか人生をやっていきたい。

しがないOLコラムニスト。X(Twitter)やnote、Webメディアや女性誌にてコラムを執筆中。今年3月に『私たちのままならない幸せ』を刊行。著書『恋愛の方程式って東大入試よりムズい』『そろそろいい歳というけれど』(共に主婦の友社)はSNSで話題になり、重版となった。Xのフォロワー数は6万人超。
X @graduate_RPG48
Instagram @jealousy_krm
note https://note.com/jelousy_krm/
多様な暮らし・人生を応援する
LIFULLのサービス
-



叶えたい!が見えてくる。
LIFULL HOME'Sは一人ひとりに寄り添い、本当に叶えたい希望に気づき、新たな暮らしの可能性を広げるお手伝いすることで、住まいの社会課題解決に取り組みます。 -



老後の不安をゼロに。
LIFULL 介護は、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、さまざまな高齢者向けの住まいを探すお手伝いをすることで、高齢化による「2025年問題」などの社会課題解決に取り組みます。 -



LIFULL HOME'SのFRIENDLY DOORでは、外国籍、生活保護利用者、LGBTQ、高齢者、シングルマザー・ファザー、被災者、障害者、家族に頼れない若者、フリーランス等の方々に親身な不動産会社を探せます。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/02/25なぜ、災害時にデマが起きるのか。│防災心理学・木村玲欧教授「善意のリポスト・転送が、助かる命を奪うかもしれない」
2025/02/25なぜ、災害時にデマが起きるのか。│防災心理学・木村玲欧教授「善意のリポスト・転送が、助かる命を奪うかもしれない」災害時のデマが引き起こすリスクについて詳しく解説しています。感情を揺さぶる巧妙なデマが増加する中、情報の真偽を確認し、防災に備えることの重要性を兵庫県立大学の木村玲欧教授が語ります。災害時に適切な情報活用法を知り、デマ拡散による危険を防ぐ対策を紹介しています。
-
 2024/03/19「若いね」「もういい年だから」……なぜエイジズムによる評価は無くならないのか|セクシズム(性差別)、レイシズム(人種差別)と並ぶ差別問題の一つ「エイジズム」。社会福祉学研究者・朴 蕙彬に聞く
2024/03/19「若いね」「もういい年だから」……なぜエイジズムによる評価は無くならないのか|セクシズム(性差別)、レイシズム(人種差別)と並ぶ差別問題の一つ「エイジズム」。社会福祉学研究者・朴 蕙彬に聞く『日本映画にみるエイジズム』(法律文化社)著者である新見公立大学の朴 蕙彬(パク ヘビン)先生に、エイジズムに対する問題意識の気付きや、エイジズムやミソジニーとの相関関係について、またメディアやSNSが与えるエイジズムの影響や、年齢による差別を乗り越えるためのヒントを伺ってきました。
-
 2021/11/08起業するなら社会人経験が絶対に必要、なんてない。水谷 仁美
2021/11/08起業するなら社会人経験が絶対に必要、なんてない。水谷 仁美大正元年(1912年)創業の歴史ある養蜂園の長女として生まれた水谷仁美さんの夢は「専業主婦になる」だった。確かにその夢を実現し、一度も就職することなく幸せな結婚を遂げ、アメリカで主婦として子育てにまい進していた。しかし、社会人経験もなく会社経営のイロハすら皆無だった彼女が、2004年にビューティーブランド『HACCI(ハッチ)』を創業し、最高経営責任者(CEO)としてハチミツの良さを世の中に伝えている。彼女が、なぜ100人以上の社員を抱える会社の代表になったのだろうか? お話を伺った。
-
 2024/04/04なぜ、私たちは親を否定できないのか。|公認心理師・信田さよ子が語る、世代間連鎖を防ぐ方法
2024/04/04なぜ、私たちは親を否定できないのか。|公認心理師・信田さよ子が語る、世代間連鎖を防ぐ方法HCC原宿カウンセリングセンターの所長である信田さよ子さんは、DVや虐待の加害者・被害者に向けたグループカウンセリングに長年取り組んできました。なぜ、私たちは家族や親を否定することが難しいのか。また、世代間連鎖が起きる背景や防ぐ方法についても教えていただきました。
-
 2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記
2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記人と会話をするのが苦手。場の空気が読めない。そんなコミュニケーションに自信がない人たちのことを、世間では“コミュ障”と称する。人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めたり、人気芸人やアーティストと交流があったり……アナウンサーの吉田尚記さんは、“コミュ障”とは一見無縁の人物に見える。しかし、長年コミュニケーションがうまく取れないことに悩んできたという。「僕は、さまざまな“武器”を使ってコミュニケーションを取りやすくしているだけなんです」――。吉田さんいわく、コミュ障のままでも心地良い人付き合いは可能なのだそうだ。“武器”とはいったい何なのか。コミュ障のままでもいいとは、どういうことなのだろうか。吉田さんにお話を伺った。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」