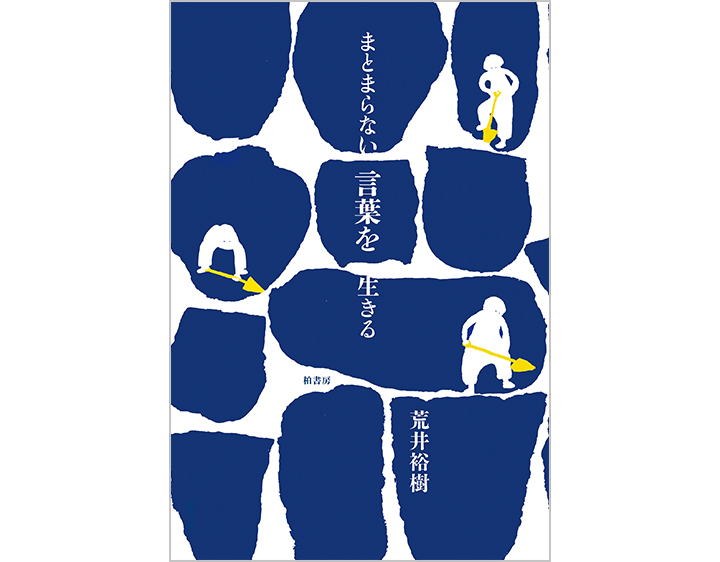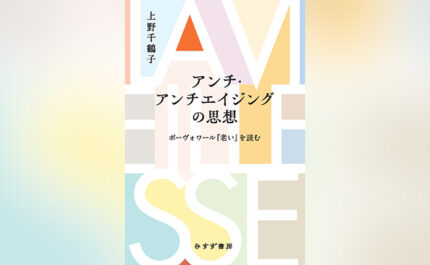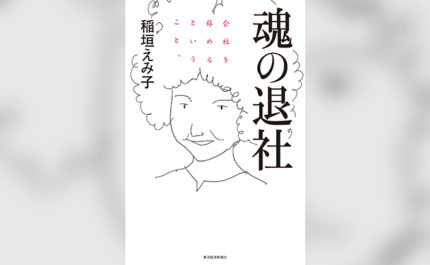「あちら側の人」が被る理不尽は対岸の火事ではない。『まとまらない言葉を生きる』から自分のありようを考える。
日常の中で何気なく思ってしまう「できない」「しなきゃ」を、映画・本・音楽などを通して見つめ直す。今回は『まとまらない言葉を生きる』(荒井裕樹・柏書房)から、今の社会の生きづらさについて考えます。
荒井裕樹 『まとまらない言葉を生きる』(柏書房・2021年)
『まとまらない言葉を生きる』はどんな本?
著者は障害者文化論・日本近現代文学が専門で、本書では主に障害者運動に携わってきた人たちの言葉をもとに、現代の生きづらさについて考察している。
まず、まえがきでは近年になって「言葉が壊されてきた」と指摘している。「言葉が壊されてきた」とは、生きることを楽にしない言葉、人の心をそぐような言葉がためらいなく発せられ、その言葉が生活の中に紛れ込んでいることに慣れてしまっている状態だ。
本編は、第一話から第一七話と終話で構成されている。たとえば、第四話では自身の保活(子どもを保育園に入れるために保護者がする活動)経験を経て、ジェンダー差で生じる女性の自尊心の損失を取り上げている。
育休が終わるのに子どもが入る保育園のめどが立たない女性が発した「私が子どもを産んだのは迷惑だったのか」という言葉を受けて、今の社会は彼女が自尊心を損なってしまう状況を社会問題にせず、個人の問題に変換させていると考察する。そして、個人の問題に変換させられるのはたいてい弱い人たちだと。
このような社会に対して、著者はウーマンリブ運動家の言葉を引用し、今この社会で女性が惨めさを感じるならば、社会そのものが惨めなのだと結論する。
どの話にも共通しているのは、著者が社会的な弱者の側に立って考察していることだ。真に励ます日本語がないという考察にはハンセン病回復者の言葉を、「自己責任」という言葉の不気味さに対して「らい予防法闘争」に尽力した人の言葉を……といったように、社会的な弱者らが発した力強い言葉を引用し、「言葉が壊されてきた」状況にあらがっている。
紹介されている言葉は心に残るものばかりで、おそらく多くの人が勇気をもらい、時に自戒を促す言葉になるだろう。
自分は「こちら側」だから大丈夫、なんてない
『まとまらない言葉を生きる』を読んで、思い出したことがある。
ある日、電車に乗った時のこと。知的障害者と思われる女性が一人で電車に乗ってきて、扉近くの床に座って食事をはじめた。女性の周りにいた人たちはサッと移動し、席が埋まるくらい混雑した車内で彼女の周りだけ空間ができていた。私は少し離れた場所に座って様子を見ていたが、そもそもなぜ彼女を避けるのかなどモヤモヤと考えていた。
本書に、このモヤモヤの正体を言語化している一文がある。
「『障害者』=『あちら側の人たち』というイメージを勝手に作り上げることで、ぼくという人間は間違いなく『こちら側』の存在なのだという幻想にしがみつこうとしていた」(244ページ)
あの日の私の中にも、「私は『こちら側の人』だから彼女に関わらなくていい」という感情があったと思う。
本書は「こちら側の人」にカウンターパンチを食らわせる。「性暴力も貧困も病気も育児も被災も、どれも『自分に起こりえること』だ。いまは他の誰かの身に起きていることかもしれないけれど、いつ自分や、自分の大切な人に起きてもおかしくはない」(191ページ)
考えてみれば当たり前だが、「あちら側」と「こちら側」は簡単に逆転する可能性がある。もしも明日、事故にあって自分が障害者になったら、電車に乗った私の周りには空間ができるのだろう。そうなってから、今の社会の生きづらさと理不尽に怒っても遅い。
著者は本書の中で、さまざまな切り口から社会の生きづらさや理不尽にあらがい、「言葉が壊されてきた」状況と対峙する方法を示唆してくれている。ここでは、明日から誰もが具体的に行動できる箇所を紹介しておく。
ぼくたちは「理不尽に抗う方法」を学ばなければならない。今回紹介した森田竹次にならうなら、理不尽な社会と闘う<勇気>を得たいなら、孤立しない・孤立させないことが大切なようだ。そのためには何をしたらよいのだろう。差し当たり、ぼくは「いまこの瞬間、怒っている人・憤っている人・歯がみしている人」を孤立させないことからはじめたいと思う。
※引用:荒井裕樹(2021年)『まとまらない言葉を生きる』柏書房、198ページ
※森田竹次(1920〜1977年)。長島愛生園(国立ハンセン病療養所)入所者で、らい予防法闘争に尽力した。書籍に『偏見への挑戦』長島評論部会、1972年など。
出る杭は打たれるから、何も起きませんようにと丸まって暮らすのも一つの生き方だ。でも著者は、「あちら側」の理不尽と闘うために立ち上がった人を孤立させて、つぶされるのを見て見ぬふりしてはいけないと言う。たしかに、今の社会は少しの意見の相違で簡単に孤立してしまう。自分が孤立したら声をあげる勇気を持ちたいし、その声を聞いてくれる人の存在は、とてもうれしいものだろう。
すでに多くの人は、社会の理不尽と一人で闘えるほど人は強くないと分かっているはずだ。私は、いま社会の在り方に怒っている人の意見に耳を傾けることから、生きづらい社会を少しずつでも改善していきたいと思う。
※『まとまらない言葉を生きる』内の記載に合わせて「障害」と記載しています。
文:石川 歩
みんなが読んでいる記事
-
 2021/09/06運動は毎日継続しないと意味がない、なんてない。のがちゃん
2021/09/06運動は毎日継続しないと意味がない、なんてない。のがちゃん人気YouTuber、のがちゃん。2018年にフィットネス系チャンネル「のがちゃんねる」を開設し、現在は登録者数86万人を超えている。もともとはデザイナーとして活動しており、フィットネスやスポーツに縁があったわけではない。そんな彼女の原点は、中学や高校時代のダイエット。食べないダイエットなどに挑戦しては、リバウンドの繰り返し。当時の経験と現在のYouTube活動から見えてきたのは、「継続の大切さ」だ。多くの人が直面する体作りや健康について、のがちゃんの考えを伺った。
-
 2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】
2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】ジェンダーレスという言葉を耳にしたことがあるかもしれません。この記事では、ジェンダーレスの意味やジェンダーフリーとの違い、ジェンダーレス社会の実現に向けた取り組み、ジェンダーにとらわれず自分らしく生きることの大切さについて紹介します。
-
 2022/09/27日常の光をつかむ写真家・石田真澄 【止まった時代を動かす、若き才能 A面】
2022/09/27日常の光をつかむ写真家・石田真澄 【止まった時代を動かす、若き才能 A面】あしたメディア×LIFULL STORIES共同企画第2弾は、写真家・石田真澄さん。大塚製薬・カロリーメイトの『部活メイト』、ソフトバンクの『しばられるな』などの広告写真、そして俳優・夏帆さんの写真集『おとととい』などを手がけてきた写真家だ。
-
 2023/01/12“もうおばあさんだから”、なんてない。BACK STREET SAMBERS(三婆ズ)
2023/01/12“もうおばあさんだから”、なんてない。BACK STREET SAMBERS(三婆ズ)BACK STREET SAMBERS、通称「三婆ズ」は、65歳、68歳、72歳の女性3名で構成されるダンスユニットだ。Instagramのフォロワーは10万人超。ダンス動画には、コメントで「キレキレですね」「カッコいい」といった声が集まっている。年齢にとらわれず新たなことを始める原動力について、話を伺った。
-
 2023/02/21【前編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説
2023/02/21【前編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説少子高齢化により、日本の人口減少は加速しています。その結果、さまざまな問題が引き起こされていますが、その一つが空き家問題です。「家の片付けができていない」「売りたくても売れない」といった理由で空き家を放置している所有者も少なからずいて、相続した家が「負の不動産」となり得る問題もはらんでいます。総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、2018年時点での空き家は全国で約848万9000戸と過去最大となっており、空き家の管理や活用は喫緊の課題と言えるでしょう。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」