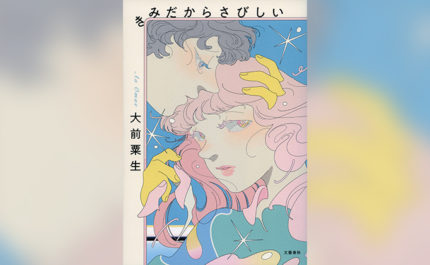LGBTは受け入れられない、なんてない。
「最近、LGBTの人が増えたよね」という声に対し「増えたわけではなく、表に出てこられない、言えないという現実があっただけ」と語るのは、心と体の性が一致しない「トランスジェンダー」である杉山文野さん。LGBTへの理解や認知を広める活動が功を奏し、埋もれていた多様性の形が少しずつ世間から認められるようになってきている。

LGBTとは、Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、性別越境者)の頭文字をとった単語で、セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)の総称のひとつ。株式会社 LGBT 総合研究所(博報堂DYグループ)の2016年度調査によると、日本の総人口におけるLGBTの割合は8.0%。13人に1人という計算だ。この割合は年々増加しており、その陰にはLGBTへの理解が徐々に深まりを見せているという背景がある。トランスジェンダーのひとりとしてさまざまな偏見や葛藤と向き合ってきた杉山さんにこれまでの生き方や価値観の移り変わりと、肌で感じる世間の変化について話を聞かせてもらった。

居場所がなくなるのが怖くて
本当の自分を見せられなかった
物心つく頃には「なんか違うな」という違和感があった。
幼稚園の入園式で親にはかされたスカートが嫌で泣いた。式典のたびに女の子側に分けられることが不思議だった。女の子を見ると「かわいいな、好きだな」という感情が芽生えた。毎日短パンをはいて男の子とサッカーをするほうが楽しかったし、そのほうが自分らしいと思っていた――。
「なんか違う。でも、どうやらそうじゃなきゃいけないらしい。けど、これは何なんだろう? という感じ。でも小学校からは女子校だったので、『僕はこっちだったんだ……』と自覚せざるを得ない状況で。でも幼いながらも『人には言っちゃいけないことなんだろうな』と察していたので、誰にも言えないままでした」
それでも「大きくなったら男になるのでは?」という淡い期待はあった。「誰も教えてくれないだけじゃないか?」「もうすぐ体が変わるんじゃないか?」。だが、生理がきたことで「やっぱり違った」「自分は決定的に女子なんだ」と絶望したという。
中学~高校にかけてはさらに苦しみが増した。二次性徴以降、体は女性として順調に成長していく一方で、気持ちの上では男性としての自我が強くなっていく。つらさが表に出ないよう、外では明るく元気に振るまっていたものの、家に帰るとひとり部屋で泣く。苦しくても誰にも打ち明けられない。根拠のない罪悪感で自分を責め続け、「早く死にたい」と思うこともあった。
「それでも生きてこられたのは、すごくいい家族と仲間がいてくれたおかげですね。でも関係性がよくなるほど、『嫌われたら』『いじめられたら』『気持ち悪いと言われたら』『居場所がなくなっちゃったら…』というバレたときの恐怖が膨らんで、余計に本当のことを隠さなきゃと思っていました」

カミングアウトを始めたら自分の中の偏見にも気がついた
ずっとカミングアウトを恐れていた杉山さんだが、その瞬間は不意に訪れた。きっかけは人生初の失恋だった。
「中学のとき、『女の子が好きなわけじゃないんだけど、文野のこと好きになっちゃったんだよね』と言ってくれた子とつき合うことになったんですが、高校の途中でフラれちゃって……。辛いのに誰にも言えないし相談もできない。『唯一の理解者がいなくなっちゃう』とか、『こんな気持ち悪い僕を好きになってくれる人は二度と現れないんじゃないか……』って不安も相まって、極限状態まで自分を追い詰めていました」
学校には行っていたものの、ごはんものどを通らないし、夜も眠れない。様子がおかしいことに気づいた友達に問い詰められ、涙ながらに胸の内を語ることとなる。
「18年間近く誰にも言えなかった思いを吐き出すように打ち明けました。その子はずっと黙って聞いてくれて、最後にひとこと『話してくれてありがとね。性別がどうであれ、文野は文野に変わりがないじゃん』って言ってくれたんです」
そのことが大きな転機となり、少しずつほかの友達にもカミングアウトできるようになっていった。意外だったのは、皆が当たり前のように自分を受け止めてくれたこと。
「『世の中が~』と言ってる自分の中にもいろんな偏見があったんですよね。『誰もわかってくれない』とか『理解されるはずがない』とか。カミングアウトや社会とのつき合いを通じて自分と向き合うことで、己の中にある偏見も見直していくべきだと気づいたんです」
家族へのカミングアウトは紆余曲折あったという。「なんでわかってくれないんだ!」というやりとりと葛藤を繰り返すうちに新たに気づいたのが、両親にLGBTの知識や情報がないということと、自分自身も家族や社会のことをわかっていなかったということだ。
「まずは『わからないという親父や社会のことをわかってみよう』という努力を。次に『どうしたらわかってもらえるか?』という方向に意識を向けるようにしたんです。面と向かって話すこともあれば、この本読んでみてと情報を渡したり、新宿二丁目に一緒に飲みに行ってみたり。お互いを理解し合う努力を重ねるうちに、親父にも理解してもらえるようになりました」

人との違いこそが人生の彩りであり面白みである
さまざまな人に会い、性同一性障害や性別適合手術についての見聞を広めるうちに、活動の幅も広がりを見せていく。そのひとつが大学生のとき、新宿で偶然出会った乙武洋匡さんのアドバイスを受けて上梓した著書『ダブルハッピネス』(講談社)だ。「性別は関係ない。性同一性障害の人はみんなのすぐ近くにいるということを伝えたい」という思いで書かれた同書は性に悩む人々に勇気を与え、大きな反響を呼んだ。
だが、著書と名前が有名になる一方でレッテルにも悩まされた。何をやっても、「性同一性障害の杉山さん」と紹介されるようになってしまったのだ。
「性別から解放されたいと思って本を書いたのに、逆に性別のことばかり言われるようになっちゃって……。窮屈だなと思って逃げるように海外へ行ったんです。もう少し暮らしやすい場所があるんじゃないか……って」
しかし世界でもあらゆる場面で「she」や「he」、ムッシュなのかマドモアゼルなのかと性別を問われ続けることになる。南極船に乗ったときも、男性と女性のどちらと部屋をシェアするかでひと悶着(もんちゃく)あったという。
「世界の果てに行っても、性別と自分自身からは逃げられないんだなって思い知りました。だったら今いる場所を生きやすく変えていくことが大事だと思ったのが、現在の活動をするようになった原点でもあります」
現在の杉山さんの活動は、LGBTやいろいろな個性を持つ人と「違いを知り、違いを楽しむ場をつくる」のが目的という株式会社ニューキャンバスの運営をはじめ各地での講演会、メディア出演など多岐にわたる。世間の目を恐れず、精力的に活動するその原動力は何なのだろうか?
「結局、自分のためにやってるんですよ。社会の前に自分がハッピーじゃないと、隣の人の幸せまで考えられないじゃないですか。そのうえで自分と社会のハッピーが比例するようなことができれば一番いいかなと。活動が進むことでLGBTに限らず、みんなが本当に暮らしやすい社会に近づいていけるんじゃないかという、希望を持ってやっています」
地道な活動の成果は着実に世間を変え始めている。
「最近病院で僕がトランスジェンダーであることを話したら、『そうなんですね。でもそんなことでどうこう言うスタッフはうちにはいないので安心してくださいね』って、大げさでもなんでもなくサラッと言ってもらえたんです。初めてのことなのですごく感動したし、長きにわたってこういった活動をしてこられた方々への感謝と共に、自分も活動に関わってきて本当によかったと実感しました。まだ課題は多くありますが、それでも時代は明らかに変わってきているんです!」

1981年8月10日 、東京都新宿区生まれ。
早稲田大学大学院教育学研究科卒。フェンシング元女子日本代表。大学院にてジェンダー論を学んだ後、その研究内容と性同一性障害と診断を受けた自身の体験を織り交ぜた『ダブルハッピネス』を講談社より出版。韓国語翻訳やコミック化されるなど話題を呼んだ。卒業後、2年間のバックパッカー生活で世界約50カ国+南極を巡り、現地でさまざまな社会問題と向き合う。帰国後、一般企業に3年ほど勤め独立。現在は日本最大のLGBTプライドパレードを主催するNPO法人東京レインボープライド共同代表理事、セクシュアル・マイノリティの子供たちをサポートするNPO法人ハートをつなごう学校代表、各地での講演会やメディア出演など活動は多岐にわたる。日本初となる渋谷区パートナーシップ証明書発行に携わり、渋谷区男女平等・多様性社会推進会議委員も務める。
杉山文野公式ホームページ http://fuminos.com/
Twitter @fumino810
Facebook https://www.facebook.com/fumino.sugiyama
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜
2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント
2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜
2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。
-
 2024/03/19「若いね」「もういい年だから」……なぜエイジズムによる評価は無くならないのか|セクシズム(性差別)、レイシズム(人種差別)と並ぶ差別問題の一つ「エイジズム」。社会福祉学研究者・朴 蕙彬に聞く
2024/03/19「若いね」「もういい年だから」……なぜエイジズムによる評価は無くならないのか|セクシズム(性差別)、レイシズム(人種差別)と並ぶ差別問題の一つ「エイジズム」。社会福祉学研究者・朴 蕙彬に聞く『日本映画にみるエイジズム』(法律文化社)著者である新見公立大学の朴 蕙彬(パク ヘビン)先生に、エイジズムに対する問題意識の気付きや、エイジズムやミソジニーとの相関関係について、またメディアやSNSが与えるエイジズムの影響や、年齢による差別を乗り越えるためのヒントを伺ってきました。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。