災害の備えは自分が助かるためのもの、なんてない。
LIFULLのCoReStock事業責任者を務める北原潤。LIFULL入社後から数多くの新規事業や戦略立案を行い、社会課題に向き合ってきた彼が現在取り組んでいるのが防災備蓄である。自身が直面した災害時の不安や、少子高齢化が及ぼす防災への影響により生まれたのがCoReStockのサービスだという。私たち一人一人が持つべき「災害に対する備え」への意識とは。

度重なる台風や地震により日本では毎年のように各地に被害がもたらされている。ニュースですさまじい被害が報道されているもののどこか人ごととしての認識が強く、「災害に対する備え」の認識が広まらず、災害が発生すると不安な気持ちからスーパーやコンビニで買い占めが行われ新たな問題となっている。重要なのは災害が発生したときを想像し、自分の大切な人が無事に過ごすために今できる備えがある、と気づくことだと語る北原。CoReStock事業を通じて北原は人々の「災害に対する備え」への意識をどのように変えていくのだろうか。
※CoReStock事業は終了しています。
スーパーから物がなくなり子供の食料のことを考えたとき、災害の怖さをリアルに感じた
-CoReStockのテーマである「防災」「備蓄」に関心を持った経緯についてお聞きします。
「防災や備蓄に関心を持ったきっかけとしては2つ。1つは、2019年に関東に上陸した台風19号です。仕事帰りに翌日の食料を買おうと近所のスーパーに寄ったところ、インスタントの食品やパン、生鮮食品などがほとんどなくなっている状態を目の当たりにしました。あまりに大きな台風だったこともあり、不安が不安を呼び、皆が必要以上のものを買い占めてしまったんですね。私は子供もまだ小さかったため、自分自身のことより明日、明後日、子供にしっかりとした食事を提供できなくなる怖さを初めて感じ、備蓄の重要性を強く意識するようになりました。
もう1つは、自分が住んでいる地域の自治会の集まりでの出来事です。防災・備蓄に関する呼びかけや確認などが行われたのですが、参加していた多くの高齢の方が必要な備蓄を行っておらず、さらに無関心だったんですね。私たちくらいの年齢であれば、車を使って遠くに移動できるため、近くで食料が買えなくても、遠出をして買い物に行き数日分の食料は確保することができるのですが、高齢の方の場合、同じようにはいかないため、実際に災害が起こった場合、大きな問題になる、と考えるようになりました」

-CoReStockはどのようにしてスタートしましたか?
「私はLIFULLに2011年に入社しました。新規事業や新しいことへの挑戦、社会課題の解決をしていくことを常に発信している部分にとても引かれたのがきっかけです。入社後は既存のビジネスに加えて、不動産関連のメディアやシステムの構築など、不動産会社の業務支援に関するサービス開発を行い、新規事業の提案や企画などにも取り組んできました。常に新しいことに挑戦をすることが自身のミッションであると考えており、事業の立ち上げを行っていく中で、不動産以外の新しいジャンルにも挑戦して、自身の知識や経験の幅を広げていきたいと考えていました。事業として継続性があり社会課題を解決するビジネスを、会社も私自身も考えていたため、災害の経験を経て持つようになった防災や備蓄に関する危機感・問題意識を事業を通して解決していくために、社内の新規事業公募制度『SWITCH』を利用してCoReStockをスタートさせました」
-どのようなサービスになっていますか?
「サービスの内容としては月々数百円の定額で、国が推奨している最低3日間分の食料・飲料等をお届けしています。災害発生時には消化してしまった分の備蓄も追加で支給する仕組みになっているため、常に十分な備蓄を維持することができるようになっています。
そもそも備蓄が広まりづらいのは、3日間分の備蓄をそろえるのに1人分でもけっこうな金額がかかりますし、家族がいれば人数分必要になるため金額面での課題が理由としてありました。また、いつ使うかわからず、5年たてば保存期限が切れてしまい、再度買い直しが必要になることも普及しない理由の一つですね。CoReStockは金額面と、災害時に不足分を補充できる安心面で導入してもらいやすいサービス設計をしています。
サービスのベースには私たち一人一人が、『自分たちの身は自分で守れるように』という考えがあります。実は、『防災』には日本の社会課題でもある『少子高齢化』も大きく影響しているんです。災害時の備えとして、『自助・共助・公助』を最近よく耳にしますが、少子高齢化により若い世代の割合が少なくなると、『助ける人』よりも『助けを求める人』が多くなり、共助や公助が困難になってしまいます。また、少子高齢化によって労働人口が減ると、自治体の税収も少なくなり避難所や支援物資を賄う予算が確保できなくなってしまう可能性があるため、国や自治体を頼りすぎずに自分や家族の身は自分たちで守れるようにしていきたいですね」

本当に困っている人が支援を受けるために気づきを広めたい
– CoReStockがもたらす暮らしの変化、可能性について教えてください。
「『大きな災害が起きた際に、慌てず、冷静に災害を乗り越えられる環境づくり』ができると考えています。スーパーやコンビニの買い占めからもわかるように、大きな災害が起きると人々は不安になり、思いやりや譲り合いの精神が薄れてしまい、物の取り合いなどの行動をするようになってしまい、より大きな混乱や問題が発生してしまいます。CoReStockが普及していくことで、大きな災害が起きても自宅で安心して3日間は難をしのげるようになり、皆が混乱する状況を少しでも改善できるのではないかと思います。一人一人が安心できる状況になれば、思いやりのある行動をするようになり、本当に助けが必要な状況の人たちが支援を受けられる状態になるので、CoReStockを通じてその変化をもたらしていきたいです。
自身が災害への備えをしっかりすることで、『本当に困っている人たちへの支援になる。』そのように考えてくれる人たちが増えていけば、きっと大きな災害が発生したときでも、私たちは本当の意味で助け合い、困難からも脱することができると思っています」
-利用者からはどのような声がありますか?
「お申し込みをいただいた方から経緯を聞くと、自分が災害に遭ったときのことを想像して、今の備えに不安を感じたり、自分の子供に何も食べさせてあげられなくなることに危機感を持って防災用品を置いておくことを決めるケースが多いですね」
-今後の課題について教えてください。
「サービスの導入数を増やしていくことです。保険の場合は病気や亡くなったりしたときのことを考えた備えとして広く普及していますが、備蓄に関しても未然のうちに備える点は同じはずなのに普及していかないのが現状です。どこか人ごとで「自分は大丈夫」「今はまだ大丈夫」という認識の人が多いと感じます。結局は災害時の状況を想像した気づきの問題です。都心に住んでいると想像がしにくいですが、例えば田舎に住んでいる親のことを想像すると、買い物に行けずに困るだろうな、とか気づきが出てきますよね。なので、災害時を想像して、自分の大切な人が無事に過ごせるのか、ということを考えて、気づいてもらうことが重要だと感じています。親孝行の一つとしてCoReStockをプレゼントしてもらい、いざというときに備えてもらう使い方も増えていくと良いですね。月々数百円で、親孝行できるっていいと思いませんか?」

-CoReStockを通じて今後実現していきたい社会について教えてください。
「個々へサービスを広めるアプローチはもちろん必要ですが、CoReStockのサービスを自治体や企業と連携して、広めていくことを考えています。防災に関して実施されたアンケートを見ると、防災備蓄をしていると回答した人は半数くらいいますが、国が推奨する備蓄の最低基準である3日分の蓄えは回答者全体の25%程度しかできていないのが現状です。備蓄の本来の価値は、自分が備えておくことで本当に困っている人が必要な支援を受けられるようになることだと思うので、日本に住んでいる人たち全員が備蓄をしている状態をつくり、お互いに助け合う世の中が実現できればと思っています。
自治体では、CoReStockを利用することにより、避難所だけではなく各世帯へ備蓄の支援を行っていくことで、避難所における混乱が避けられ、本当に支援が必要な人たちを優先することができます。既に会社に一定量の備蓄をしている企業も増えてきていますが、そこで働く従業員やその家族がいる世帯では、まだまだ備蓄が進んでいない状況ですので、新たな福利厚生として従業員やその家族の備蓄を支援していくこともできると思います。また昨今のテレワーク下ではほとんど出社をしていない企業もあるため、会社の備蓄を充実させること以外に、自宅で仕事をしている従業員が災害時に困らないように支援していくことも必要になってくると思います。企業におけるBCPの観点からも、従業員やその家族を守っていくことは今後重要な戦略になってくると思います。
自治体や企業と連携し、防災備蓄の支援をしていくことが実現できれば、世の中が変わり、防災に関する安心・安全性が確立した日本社会になっていくだろうと思っています。
また、いずれは日本だけではなく世界に広げていきたいです。世界には日本とは比にならないくらい大きな災害が起こる国もありますし、防災備蓄への関心が薄い国もあります。そもそも食料に困っている国であれば災害が起きると、死がよりリアルなものとなるため、備蓄への意識を広めていく必要があります。日本から世界に広げていくことで、被災して困っている人や亡くなってしまう人を少しでもこの世界から減らしていきたいです」
撮影/加藤木 淳
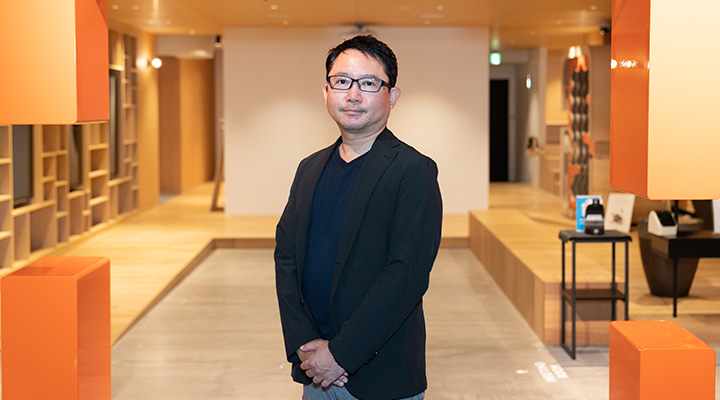
株式会社LIFULL CoReStock事業責任者。
1976年生まれ。多摩美術大学卒業後、住宅メーカーのデザイナー職を経て2011年LIFULLに入社。
入社後は、注文住宅・リフォーム領域事業におけるプロダクト責任者に従事。その後、不動産業界向けの業務支援事業を新規で立ち上げ、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)のAnnex(アネックス)や、不動産登記簿を活用した不動産登記簿Managerなど数々のサービスを開発し、不動産業界におけるDX化を推進。また旧株式会社レンターズ(現LIFULL)の執行役員を務め、不動産業界のDX化をより加速させるために、経営戦略等、経営に関わるミッションに従事。
2020年10月より、社会課題の解決を目指し、防災備蓄事業「CoReStock(コレストック)」を立ち上げ、自然災害発生時における、「自助・共助・公助」のうち「自助」を推進するための、サブスクリプション型防災備蓄サービスをリリースする。現在は防災事業を通じて、個人・企業・自治体が連携を図り、自然災害時の脅威に対して常に「安心」ができる世の中の実現を目指し、各分野で広く活動を行う。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/02/02【実話】ペットの闘病で心が折れそうなとき――余命20日の愛猫を看取った猫マスターが語る“心のセルフケア”
2026/02/02【実話】ペットの闘病で心が折れそうなとき――余命20日の愛猫を看取った猫マスターが語る“心のセルフケア”愛猫が余命20日のリンパ腫と宣告された時、飼い主はどう心を保てばいいのか。猫マスター・響介さんが実践した「未来への手紙」や、後悔しない看取りのための思考法、ペットロスとの向き合い方を語ります。【実話インタビュー】
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。












