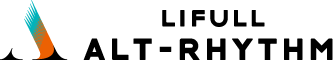性別によって服を選ばなきゃ、なんてない。―ドラァグクイーンAndromedaが語る、着物のフルイディティ―
性別の固定観念に縛られない表現活動を行うマルチアーティストであり、雑誌『IWAKAN』編集者のEdo Oliverによるドラァグクイーン・Andromeda(アンドロメダ)。2021年からは、着物を表現の一つとして取り入れるようになった。今ではパフォーマンスに限らず日常的にビンテージ着物を着こなすAndromedaだが、きっかけは意外にもその「実用性」と「自由度」だったという。着付けや季節ものなど決まりごとが多いイメージの着物が、性別にとらわれないAndromedaにとって最適な表現方法の理由とは?着物との出会いまで遡り話を伺った。

女の子はスカート、男の子はズボン。
時代や国によってその内容は変われど、「服」と「性別」は長らく結び付けられてきた。今でこそ「ジェンダーレス」という言葉が広まり性別にとらわれないファッションが増えてきたが、日常的に男性がスカートを履いているシーンを見ることはまだまだ少ない。2019年に起こった、職場で女性がハイヒールやパンプスの着用を義務づけられていることに抗議する社会運動「#KuToo(クートゥー)」も記憶に新しいのではないだろうか。そんな中、一見洋服以上にルールが多そうな和服を日常的に取り入れているのが、ドラァグクイーンのAndromedaだ。性別にとらわれない表現活動を行っているAndromedaが着物を好む理由とは?
どうしてお母さんはズボンを履けるのに、
私はスカートを履けないの?
レディースの古着を着たくても、自分に合うサイズがなかった
「どうしてお母さんはズボンを履けるのに、私はスカートを履けないの?」
メキシコで生まれ、カナダで育ったAndromedaは、幼い頃から性別にまつわる服装の制限に違和感を持っていた。ティーンの頃に自分のセクシュアリティを自覚してからはゲイ男性を自認していたが、数年前に軽い気持ちで着用したワンピースがとてもしっくりきたことが自身のジェンダーについて考えるきっかけの一つになったという。
「数年前に、軽いノリで友達とワンピースを着てみたいねって話してたんです。その数日後、彼氏とランチした後に散歩していたらセールをしているお店で900円のワンピースを見つけて。まぁ900円だし、と思って買って着てみたら『ちょー楽しい!』ってなったし、『あ、いける』って思ったんです。それまでは自分がワンピースを着るって現実的じゃないなって思ってたのに、急に身近になりました。そこから性別のラベルを超えて自分らしい表現に挑戦するようになったんですけど、今も模索中です」

Andromedaは、性別による服装の制限から解放されたことで自由になったが、同時に服選びが難しくなったとも話す。それまではメンズファッションの中でフェミニンさを表現するなど、自分らしいスタイルが確立されていた。しかし「なんでもOK」となると、選択肢が多すぎて自分が本当に好きなものは何かと迷い始めたそうだ。
「女性のファッションを含めると系統も細かくたくさんあるし、どれが自分の本当の趣味なのか分からなくなってきちゃって。それに、自分がその服を“女性らしいから”身に付けたいのか、本当に好きで選んでいるのかも分からなくなったり。
なのでいろいろ迷って、今クローゼットはカオスだし、人生でこんなに自分がおしゃれじゃないって感じたことはないかもしれないです(笑)。ある意味で感覚は子どもの頃に戻っているのかもしれない。ファッション的にこれとこれを合わせようって感覚がなくなってきて、子どもがプリンセスドレスが好き、っていうふうに、ただただ好きなものを手に取っている感じ」

そんなAndromedaと着物の出合いは、友達のフォトグラファーに頼まれた撮影だった。数年前に友達の作品作りのためにモデルを頼まれ着物を着たが、その当時は着付けも分からず自己流。それからしばらく着物を着ることはなかったが、服について悩んでいた時にその存在を思い出したという。
「レディースの服を着るようになってから、もともと私が好きな60年代の古着を探し始めたんですけど、その時代の背の低い女性のためのものがほとんどだからサイズが見つからなくて。環境のためにも好み的にもビンテージがいいけど、あんまり自分が着られる服がないなと思い始めていました。
そんな時に着物だと、着方次第でサイズを調整できるってことに気がついて。パンデミック中は時間もあったし、撮影の時に使った着物をYouTubeで着付けの方法を見ながら着てみました。そしたら案外できたんです。もちろん綺麗に着ることとただ着ることは別物だけど、とりあえず着ることができた。それで興味を持ち始めました」


その人のサイズに合わせて着こなせるという着物の実用性や自由度の他にも、サステナブルなところが気に入ったとAndromdaは話す。大量に生産されてはトレンドとともに“古く”なり、質も悪くなっていくファストファッションと違い、着物は長い間着ることで魅力が増していく。
「着物は質が良いのに中古だと安いものが多いし、全部がそうではないけれど、カスタムメイドなことが多いのに感動しました。最近の洋服は着るほど状態が悪くなっていくけど、着物は着るほど体に馴染んでいく。例えば、大島紬(鹿児島県南方にある奄美群島、主に奄美大島で伝統工芸品としてつくられる織物)は最初の頃と時間をかけて着てきたものだと触り心地が全く違う。着てみれば、その着物が長年着られてきたことが分かるんです。それは短い時間で再現できるものではないから、愛着が湧く。何度も着るのが楽しみになります」
性別関係なく歓迎してくれる着物コミュニティの存在
今では、ドラァグクイーンのパフォーマンスや撮影の時のみならず、日常的に着物を取り入れているAndromeda。日本人ではないことや男物・女物にとらわれずミックスしながら着ていることに対して、周りの反応はどうかと聞くと、ポジティブなものばかりだと話す。
「着物好きのおばあさんに気に入られることが多いです(笑)。性別のこともみんな受け入れてくれるから、それには正直すごくびっくりしました。こないだも箱根で旅行していた時に、レストランでおばあさんがずっと私のことを見ていたんですけど、帰り際に『私のクローゼットに眠っている着物をあげたいな』って言ってるのが聞こえてきて嬉しかったです」


日本舞踊を習い始めた時も、「女形を勉強したい」と先生に言うと、顔色一つ変えずに受け止められたのが印象に残っていると話す。また、一番の行きつけの着物屋の店主との出会いは、偶然だが縁を感じるものだった。
「高円寺のよく行く中古の着物屋さんに初めて行った時、私はドラァグクイーンとしての撮影のために着物を探していました。そしたらお店のおばあさんがなんのための着物なのかとか興味津々でいろいろ聞いてきたから、『実は……ドラァグクイーンって知ってますか?』って聞いたら、『もちろん分かるよ!』と言ってくれて。実はその方は、もともと新宿二丁目(日本で最大のゲイタウン)の近くの中古の着物屋さんで働いていて、二丁目のママさんたちの着付けをしてたらしくて。すごくオープンな方で、結局撮影当日に着付けもしてくれました。今でもお店に私のサイズが入ると、連絡してくれるんです」

ここ数年でジェンダーやセクシュアリティをはじめとする性の多様性に関する議論は日本でも増えてきた。とは言っても、性別に関して二元論的な考え方が主流だった時代を生きてきた年代の人々がオープンなのは少し意外だった。Andromedaは、「着物について詳しい方と話すと、着物が長く変わり続けてきた歴史を知っているから、そんなにルールにこだわらなくてもいいっていう意見があるのかも」と、話す。
誰かにとって必要かもしれないから声を上げる

ジェンダーやセクシュアリティの観点から日常の違和感に切り込む雑誌『IWAKAN Magazine』創刊メンバーの編集者として活動しながら、ポットキャストやイベントへの登壇、アーティストとしての作品作りを通して日々発信を行っているAndromeda。2023年1月には、TED x Sophia Universityで「ラベルの限界とラベルに当てはまらない喜び」についてスピーチした。今回の取材も含め、発信の原動力はなんなのだろうか。
「20代前半ぐらいの頃は自分のために発信したい気持ちが強かったんです。おかしいと思うことをちゃんと言いたい、この社会の中でちゃんと自分の声を聞いてほしいって。でも段々と、自分が発信することが誰かのためになると感じ始めて。自分が悩んでることをただ個人的に日記に書けば自分は救われるけど、さらにそれをみんなが読めるようにすると、自分だけじゃなくて同じように悩んでいる人も救えるかもしれない。そう感じるようになってからは、それを原動力に自分のことをなるべくオープンにシェアしています。日本ではまだまだジェンダーの話が少ないからなるべく声を増やすために自分が声を上げているという面もあります」
Andromedaにとって着物とはどんな存在か、最後に聞いてみた。
取材・執筆:南のえみ
撮影:岩田エレナ

Andromedaは東京を拠点に活動するノンバイナリー/トランスジェンダーのドラァグ・パフォーマーであり、IWAKAN Magazineの創刊メンバーと編集者、ポットキャスト番組『なんかIWAKAN !』のホストの一人、そして写真家でもあります。人生経験から、ジェンダー、身体醜形障害、文化的帰属、伝統、人間と環境との関係といったテーマを探求する方法としてアートを用いています。
Instagram @andromeda.offixial
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。