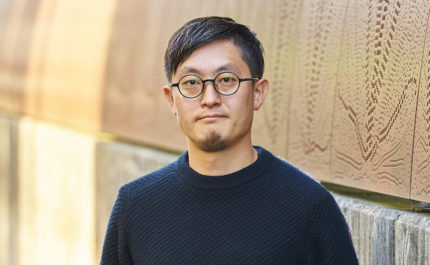中古から新品の服は生み出せない、なんてない。
日本環境設計株式会社のサステナブルブランド「BRING(TM)」は、「服から服をつくる」をコンセプトに、着なくなった服を回収し、自社工場で原料にまでリサイクルし、再び糸・生地・服を作り販売している。この取り組みは、服をリサイクルしたい人とリサイクルしたい企業をつなぐプラットフォームとしても機能する。「楽しみ」をつくることで、消費者が服を回収に持ち込みたくなり、アパレルメーカーやブランドが参画したくなり、結果的にファッション業界で大きな問題となっている大量のごみを減らすことやCO₂排出量削減につながるよう、全体が設計されている。こうしてものが循環しながら経済効果を生み出す状態は、サーキュラーエコノミー(循環型経済)と呼ばれ、BRING(TM)は2020年にグッドデザイン金賞を受賞した。
その統合的な活動のブランドディレクターを務めてきた中村崇之さんは、学生時代には映像制作やメディアアートの世界にいた。分業制が敷かれ、サプライチェーンの長いファッション業界で、サーキュラーエコノミーをかたちにした中村さんはどんな経験を糧に、何を考えて行動してきたのか。中村さんに話を伺った。

ファッション産業が地球環境に与える影響は甚大だ。年間9200万トンの膨大なごみが、ファッションの世界では排出されている(※)。中には、ほとんど着られていない服や、そもそも買われることがなく在庫のまま廃棄となる服も多く含まれている。日本環境設計によるサステナブルブランド「BRING(TM)」は、そんな大量生産・大量廃棄の現状にくさびを打ち込む。回収した服に含まれるポリエステルを再生し、再生した素材を用いて新たな服にして売ることで、“経済”も“タンスの中身”も、そして“地球環境”も持続可能なかたちで循環させる。
「BRING(TM)」ブランドディレクターの中村さんは、学生時代にはメディアアートの世界で権威のある「アルス・エレクトロニカ」で受賞するなどの活躍を経て、ファッション業界に入った。「服から服をつくる」をコンセプトに、サーキュラーエコノミーを実現させる中村さんは、自身を「今でもメディアアーティストだ」と語る。
(※)Global Fashion Agenda and The Boston Consulting Group, Inc. (2017), Pulse of the Fashion Industry
「服から服をつくる」という文化を創る
高校生だった中村さんは映画鑑賞にのめり込み、大学・大学院ではアートの世界に進んでいった。それはのちの「BRING(TM)」の活動に大きな影響を与えている。
「もともと映画監督になりたかったんです。高校時代は映画をたくさん見ていたせいで留年して、4年間通いました。東京造形大学に進学してから実写の映像、そして手描きのアニメーションをやっていました。そのあと、メディアアートを学ぶために大学院に行きましたね。芸術・先端技術・文化の祭典といわれるメディアアートに関する世界的なイベント『アルス・エレクトロニカ』の賞をもらうことができ、授賞式でオーストリアのリンツに行ったのですが、僕は英語をしゃべれなかったんです。でも、英語をしゃべれる日本人を探してくっついて行って、その人の現地の知り合いの家に1週間くらい泊まらせてもらったりして、“なんとかする”という力はこの時期に身についたと感じています。
ちなみに、今は趣味で年に一度、山で行われるアドベンチャーレースに出場すると決めて参加しています。1泊2日、マイナス2℃ほどに下がる環境で、10kgぐらいの装備を背負って走ります。持っているものでやり繰りして、こういった目標のために行動が収斂(しゅうれん)する物事の進め方が好きなんですよね。
大学院生の頃、アニメーションや映像など何でも自分で作ることの延長線上で、自分でプログラムを書いて、インスタレーションに仕上げるのが、当時僕にとってのメディアアートだったんですよね。“やっていた”というか、BRING(TM)の活動もメディアアートだと思っているんですけど」
映画製作の世界で分業制が敷かれているように、ファッション産業でも長いサプライチェーンが分業制で構成されているが、中村さんはインスタレーションを作るようにして「BRING(TM)」をつくっていった。
「僕がファッション業界に入ったのは、現社長の髙尾正樹に『Tシャツを作ってくれへん?』と誘われたことだったのですが、もともと僕のアート活動もよく知ってくれていたので、僕が事業をつくるときには『全体を見られるだろう』と期待してくれていたんだと思います」
ファッション業界でもの作りに向き合ったとき、ごみ問題に取り組むことは中村さんにとって当たり前だったという。
「小学校の道徳や社会の授業で、当然のように『日本にはごみ問題があって、もう土地がないからこれ以上埋め立てできません』から始まります。だからZ世代だけではなくて、僕たち1980年代生まれも環境教育は受けているんです。子どもの頃にそういう教育を受けたので、ファッション産業で仕事をするときにごみ問題を考えるのは当たり前で、それがあった上でのもの作りでしょう、と考えていました」
ファッション産業を持続可能にしていく方法とは?

「ファッションの世界では、年間9200万トンのごみが排出されています。そして、繊維生産量のうち、ポリエステルは繊維生産量の約6割を占めるほどの重要な素材になっていて、これからもどんどん増えるといわれていますが、コットンに比べるとCO₂排出量が多い繊維でもあります。しかし、僕たちは、ポリエステルを使うことを減らしたりやめたりするのではなく、ポリエステルをサステナブルな原料に変えることを選びました。それはBRING(TM)で服を回収し、原料にまでリサイクルし、再び糸・生地・服を作ることです。
これまではペットボトルを繊維にリサイクルする方法が主流でしたが、リサイクルできる回数は一度だけでした。僕たちは、いつまでも何度でも循環し続けられるケミカルリサイクルの“BRING Technology(TM)”を開発しました。ショッピングモールで服の回収イベントを実施すると、イベント1回で3トンもの服が集まることがあります。着られる服は海外へ寄付し、着られない服は素材ごとに分けて、それぞれをリサイクルします。コットン素材は細かくちぎって自動車の内装材に、ポリエステルは自社工場で化学分解して、もう一度ポリエステルに生まれ変わらせます」
急拡大してきた資本主義の経済活動が地球環境を害し、気候変動の危機を迎えていることは、今や世界の共通認識となっている。SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)やESG投資(Environment:環境、Social:社会、Governance:ガバナンス<企業統治>)は、課題解決のための世界的な潮流だ。中村さんはそうした潮流を踏まえつつ、サステナブルな環境をつくるには、参加する人々が楽しめることが大事だと考える。
「結局、人間は楽しいことや面白いことだったら続けられるし、好きだと思える服であれば買います。だから、ちゃんと人間の欲望を満たしたかたちで、サステナブルな仕組みを作っていくことが大事だと考えています。
僕は以前、服の回収で、BRING(TM)のハチのロゴを模した着ぐるみを着て店頭に立っていました。着ぐるみは手作りです。『明日イベントだ』というときに、レモンのかぶりものを買ってきて、それの先っちょを切って丸くしたらハチの頭になる。針金をピンポン玉に刺して、触覚に。黒い短パンに黄色いガムテープを貼って、そうしたらしま模様ができるじゃないですか。顔は出たほうが面白いよね、ということで僕の顔を出して。子どもたちは喜んでいたと僕は理解しています(笑)。
そんなふうにお客さんとのインターフェースを楽しく作って、『いらない服を持ってきてください』と言うと、みんな持ってくるんですよね。回収した服には、子ども服が多かったです。あとクリーニングに出して袋に入ったまま、タグが付いたままの服。それから、サイズ表記のシールが貼ったままの、つまり着ていない服です。そして、家には資源が大量に眠っていることがわかってきました。
他にも、服を持ってきてくれたら、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に出てくる車のデロリアンに乗れる、といったイベントも行いました。当時、綿からエタノールを作っていて、ガソリン代替燃料として使えました。その燃料を使って車を走らせれば、それは服のごみでデロリアンを走らせたことになる。イベント期間中は、これまで大手衣料品店さんで回収してきた約1年分の服が、わずか3カ月で集まりました。やはり、楽しんで参加できることがサーキュラーエコノミーの実現にとって欠かせないと感じます」
「楽しめること」に加えて重要なのは、「経済が循環すること」だ。
「あらゆる部分が経済的に循環するように設計しています。ボランティアだけだと長続きしないので、例えば現在約100ブランドとコラボしている店頭での回収では、お客さんが1着服を持ってきたら、次回の買い物で使える割引クーポン券を1枚お渡しする運用を採用しているブランドさんもあります。『いらない服がクーポン券に替わるんだ』と思うと、お客さんは家の中のタンスを開けて、持ってきてくれる。それで物理的にタンスが空くんです。すると、新しい服を買いたくなるんですね。
僕はその行為は、無駄なものを買っているわけではなくて、本当は新しい服を買いたいんだけど、タンスがいっぱいで買えなかったということだと思うんです。ちゃんと経済的にメリットのあるかたちで、リサイクルしながら、購買につなげることができる。そうするとお店もうれしいし、お客さんもうれしい。BRING(TM)の回収では、『みんながうれしい』をベースに決済を作る仕組みを積極的に導入しています。これもサーキュラーエコノミーの考え方ですね」
最終的なゴールは「新しい文化を創ること」

今後の「BRING(TM)」、そしてサーキュラーエコノミーをどのようにしていきたいのだろうか。
「糸・生地・服を作っていますが、服は現状、ECサイトを中心に販売をしています。もっと日常で使われるものにしていくために店舗を作って、世界中に広げ、販路を広げていきたいです。
最終的には、文化を創りたいです。服をリサイクルに出すとそれが資源になって、しかもお得に買い物ができるということがまだまだ皆さんに伝わっていないと思います。それが伝わっていって、人々の習慣になって、その習慣が世代を超えても続けられるようになれば、それは文化だと思うんです。『服から服をつくる』という文化を創っていきたいですね」
中村さんはアートを好み、鑑賞していたうちの一人はマルセル・デュシャンだったそうだ。彼の有名な作品『泉』は、陶器で作られた既製品の便器を倒し、署名をしたもの。そうした既存の価値とは違う新しい価値を生むことが大事だと中村さんは感じている。「僕はあくまで会社員というパフォーマンスアートをしているだけ」と笑う中村さんは、メディアアーティストとしてファッション産業をとらえ直し、分業制に取り込まれていては決して生み出せないようなサーキュラーエコノミーをつくっている。
未来の持続可能な社会は、中村さんのように枠にとらわれず発想し、ものを作る「アーティスト」を必要としているのではないだろうか。

「BRING(TM)」ブランドディレクター。日本環境設計プロダクトマーケティング課課長。高校時代に映画監督を志し、東京造形大学メディア造形専攻でアニメーション制作などに取り組む。のちにメディアアートに軸足を移し、早稲田大学大学院国際情報通信研究科に進む。制作した作品の「Wonderful World」が、「アルス・エレクトロニカ」の「Next Idea」を受賞する。その後、日本環境設計株式会社の現社長が立ち上げたWEBデザイン会社を経て、2010年から同社に合流。服のリサイクル事業の設計に従事している。
BRING(TM)https://bring.org/
みんなが読んでいる記事
-
 2018/11/28表舞台じゃないと輝けない、なんてない。Dream Aya
2018/11/28表舞台じゃないと輝けない、なんてない。Dream Aya“華やか”で“幸福”、そして“夢”が生まれ、かなう場所。そこに、自らの信念で辿り着いた女性がいる。ガールズダンス&ヴォーカルグループの「Dream」「E-girls」の元ヴォーカル、Ayaさんだ。ステージでスポットライトを、カメラの前でフラッシュを浴びてきた彼女は、自ら表舞台を去り、後輩たちをサポートする道を選んだ。Ayaさんの唯一無二な人生を辿れば、誰もがぶつかる「人生の岐路」を乗り越えるヒントが見えてくる。
-
 特集 2025/06/30【特集:家族システムを見直す】 家族だから当たり前、なんてない。
特集 2025/06/30【特集:家族システムを見直す】 家族だから当たり前、なんてない。「家族だから当たり前」という言葉に息苦しさを感じていませんか?多様化する時代に、"普通"に縛られない、自分にとって心地よい家族との関係を築くヒントを探ります。
-
 2019/12/10言葉や文化の壁を越えて自由に生きることはできない、なんてない。佐久間 裕美子
2019/12/10言葉や文化の壁を越えて自由に生きることはできない、なんてない。佐久間 裕美子言語や国境、ジャンルの壁にとらわれない執筆活動で、ニューヨークを拠点にシームレスな活躍をしている佐久間裕美子さん。多くの人が制約に感じる言葉や文化の壁を乗り越え成功をつかんだ背景には、やりたいことや好きなものを追いかける熱い思いと、「見たことがないものを追い求めたい」というあくなき探求心があった。
-
 2021/07/20子育て支援は貧しい人だけのもの、なんてない。【前編】湯浅 誠(ゆあさ まこと)
2021/07/20子育て支援は貧しい人だけのもの、なんてない。【前編】湯浅 誠(ゆあさ まこと)今の親たちは毎日相当なエネルギーを使っています。心休まる時間もありません」。そう話すのは、ホームレス状態の人々や失業者への支援など、長年日本の貧困問題に取り組んできた社会活動家・湯浅誠さん。現在は、東京大学先端科学技術研究センター特任教授、そして認定NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」の理事長を務め、子どもの“貧困問題”に取り組む。貧困は「自己責任」――そんな言葉と向き合ってきた湯浅さんに、今の日本の子育ての在り方について、お話を伺った。
-
 2023/02/24対話の質とは?【前編】多様性を深めるコミュニケーション
2023/02/24対話の質とは?【前編】多様性を深めるコミュニケーションSNS等で失われた「対話」の重要性が増しています。価値観多様化の今、相互理解には対話が不可欠。本記事では、会社、家庭、学校などあらゆる場面で役立つ対話の仕方を解説します。対話力向上は、より良いコミュニケーションと人間関係を築く第一歩です。ぜひ、極意を学び、豊かな人間関係を育みましょう。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。