なぜ、私たちは「お金を貯めなきゃ」に縛られるのか。社会的金融教育家・田内学が語る、“お金の不安”との付き合い方
老後の2000万円問題が象徴するように、私たちに付きまとう「お金を貯めなきゃ」という不安。
過度な“お金の不安”は、今やりたいことにお金を使えなかったり、合わない環境でも我慢して働きつづけてしまったりと、時に私たちに不自由さをもたらします。
社会的金融教育家・田内学さんは、著書『きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』(東洋経済新報社)の中で、お金は人と人が助け合うためのツールであると述べています。
なぜ私たちは闇雲に「お金を貯めなきゃ」に縛られてしまうのか。また、お金の不安から解放されるには、どのような価値観のシフトが必要なのか。田内さんに伺いました。

お金を貯めることが本当に将来への不安の解消につながるのか。今一度、考えてみてほしい
――著書『きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』には、「みんなでお金を貯めても意味がない」という章があります。田内さんがそのことに気づいた経緯をお聞かせいただけますか。
田内学さん(以下、田内):ずっと金融機関に勤めていたので、世の中のお金の流れについて考える機会がすごく多かったんですよね。そんな中、「老後の2000万円問題」が注目されるようになり、この問題はどう解決されるべきなんだろうと、考えを巡らせていました。
例えば、年金基金が投資している対象の一つに日本国債があります。日本は今金利が低いですが、もし金利が高ければ、日本国債を保有することでたくさんの金利収入が得られますよね。そうやってお金を増やすことで、この問題は解消されるのではないかと。そう聞くと、なんだかそのやり方が正しそうに聞こえませんか。
しかし、その金利を誰が払うかを考えると、それは政府であり、政府のお金はどこから来ているのかというと、みんなの税金なんですよ。よくよく考えると、金利収入によって年金を増やすということは、私たちの将来の税金が増えることとイコールなんです。
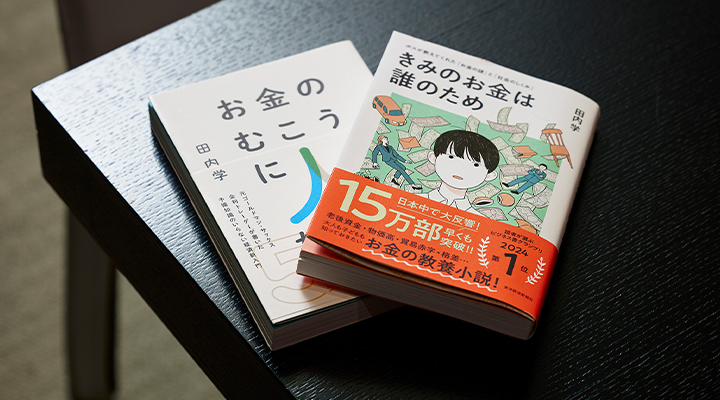
――本書でも書かれていたように「お金は全体として増えることはなく、移動しているだけ」ということですね。
田内:そうなんです。局地的に見ればお金を増やすことはできるけれど、その分、必ず誰かのお財布からお金が減っています。
そもそもお金は、自分の代わりに人に働いてもらうための一つの手段です。今の日本は少子化に伴う労働人口の減少が問題になっています。働く人が少なければ物の供給が減り、すると物の値段は高くなる。そのような社会は、イス取りゲームと同じです。いくらお金を持っていても限られたイスを奪い合うようなもの。
みんなでお金を貯めても、将来イスに座れる人数は変わりません。個人としては、イスに座るためにお金を貯めておく必要はありますが、それと同時に、イスを増やすために何をすべきなのかをみんなで考えた方が良いと思います。しかし、世の中にあるのは「個人がどうやってお金を増やすか」の情報ばかり。そのことに危機意識を持ちました。
日本の政策を考えるような人たちにも、そして将来世代の若者たちにも、多くの人にこのことを知ってほしいと思い、本を出版することにしたんです。
お金以外の選択を持つことが「貯めなきゃ」「稼がなきゃ」から解放される糸口

――「お金を稼がなきゃ」「お金を貯めなきゃ」という意識は、どこから生まれると考えますか?
田内:最近では、大学生などの若い世代でさえ、「年金が足りなくなるから貯金している」なんて話を聞きますよね。この傾向は昔に比べてかなり強くなっていると思います。
やはり1つは、老後2000万円問題という、具体的な数字を出されてしまったのが大きいのかなと。
あとは、昔はご近所付き合いなど、お金を介さずに助け合うコミュニティが身近にあったんだと思います。いまでも、地方は高齢化が進んでいますが、それでも彼らだけで生活ができているということは、いまだに地域での支え合いが成立している証だと思うんです。
――特に都心に住んでいると、いわゆる“ご近所付き合い”というものは、ますます希薄になっていますよね。
田内:誰かに何かを頼りたいと思っても、頼れる人間関係が築けない。自分のことを気にかけてくれるのは親くらいしかいない。でも、親だっていつかは先にいなくなってしまう。じゃあどうしたらいいんだろう――。
そう考えたとき、安心して頼れるものがお金しかないように感じてしまうのではないでしょうか。本来は、人は一人で生きられないはずなのに、お金を貯めておけばすべての問題が解決できる気がしてきてしまうんですよね。
――たしかに、家族以外の誰かの助けを求めるよりも、お金で解決するほうが人間関係に縛られずに「楽」だと思う傾向は増しているのかもしれません。
田内:令和3年の社会生活基本調査では、6歳未満の子どもを持つ親が育児に割く1日の平均時間が男女ともに5年前より増えていることがわかっています(※)。
女性の労働参加率は上昇し、共働き夫婦が増えているにも関わらず、育児にかける時間が夫婦合わせて約1時間も増えている。不思議に思いませんか?
※令和3年社会生活基本調査 図2-2 6歳未満の子供を持つ夫・妻の育児時間(2016 年、2021 年)
――専業主婦の数は減っているにも関わらず、女性の育児時間も増えているというのは驚きです。
田内:ここからは僕の予想でしかないですが、子どもがある程度大きくなれば、昔だったら近所の公園で遊ばせている間に、親は自分の時間を過ごすことができた。地域社会の支え合いみたいなものが緩やかに存在していたんだと思います。
お金を払って託児サービスなどを利用することを否定するつもりはまったくありません。しかし、解決方法が「お金を払ってサービスを受ける」だけになってしまうと、「稼がなきゃ」という思考になるのは当然ですよね。
自分の親に頼ったり、近所の施設を利用したり、友人のお家で預かってもらったり、いろんな選択があるなかの一つにお金での解決があるべきだと思うんです。しかし、すべてをお金で賄おうとすると「稼がなきゃ」となり、ますます社会全体のことを考える余裕が失われてしまいます。
「私」から「私たちへ」。目的を共有し仲間を見つける
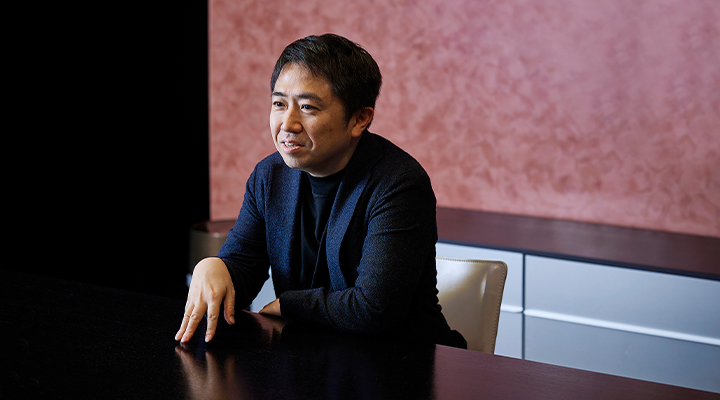
――お話を聞いていて、お金の不安を和らげるには「お金以外の選択肢を持つこと」が非常に重要なように感じました。具体的に、何か私たちにできることはあるのでしょうか?
田内:仲間を増やしていくことが鍵なのではないかと。仲間を増やすために一番大切なのは、「目的を共有すること」だと僕は思っています。
例えば、僕が初めての本を出版できた裏には、まったくの未経験から文章の書き方を教え、ここまで育ててくださった編集者がいます。「この本を通じて、僕はもっとこういう社会にしていきたいんです」と伝えたところ、それならば協力したいと言ってくれました。
もし仮に「金儲けをしたいから」とか、僕が自分のことしか考えていなかったら、編集者も協力したいとは思いませんよね。
家族だったら共通の目的がなくても協力してくれるかもしれない。でも、家族以外の人と手を取り合いたかったら、「なぜ協力してほしいのか」「その先でどんな未来を見据えているのか」、目的に公共性を持たせる、つまり主語を「私」ではなく「私たち」にする必要があります。
――「私」ではなく「私たち」で語ることで、協力者が現れる。企業も同じなのかもしれません。
田内:そうですね。一つの目的のために集まって、協力し合うのが企業ですよね。ただ、もしその目的が「営業利益を上げる」だけだったら、例えば同僚が育休を取れずに困っていたとしても、「それは自分には関係ない、だってその目的のためにこの会社にいるわけじゃないから」という思考になってしまいます。
しかし、もし「自分たちの働き方も含めて、より良い社会にしていこう」という目的を共有している会社だとしたら、“困った時はお互いさま”の精神でいられると思うんです。
協力し合える社会を身の回りから

――書籍の最後には「愛する人を見つけてほしい」というメッセージが記されていました。物語に出てくる「七海」という女性が、愛する存在を見つけることで「お金」から「人」へ視点を変えていく姿が描かれています。
田内:僕の場合は、子どもができたことが価値観をシフトさせるきっかけになりました。
子どもの将来を考えて親ができることを考えた時、2つのアプローチがあると思っています。1つは、その子自身が1人でも生きていけるように望むことです。例えば勉強が得意だったら、質の良い学びの機会を提供することもできるでしょう。
そして、2つ目はどんな人でも生きやすい社会を望むこと。自分の子がどんな特性を持っていようと関係なく、社会が生きやすい場所であれば、その子は幸せになれるはずです。
僕はこの2つ目の視点を忘れたくないと思っています。前者は、個人の特性に委ねられる部分が大きい。でも、後者のやり方は、みんなでがんばった分だけ、暮らしやすい社会の実現に近づきます。
――前者はその子の特性や努力に委ねてしまう部分が大きそうですが、後者の視点であれば、親ができることの範囲が広がりそうです。
田内:日本財団の18歳の意識調査では、「自分の行動で国や社会を変えられると思う」という問いに「はい」と回答したのは、日本はたったの26.9 %でした(※)。6カ国中最下位という結果です。
それだけ、自分と社会の距離が遠いんです。一人ひとりが社会をつくっているのにもかかわらず、お金の本質的な意味を知らないと、お金さえあれば良いと考えてしまいます。
著書『きみのお金は誰のため』で知ってもらいたいのは、そこなんです。老後資金にしても、物価高にしても、実はお金自体の問題じゃないんですよね。問題を正しく理解するには、社会全体のことを考えないといけません。
お金を過信するのではなく、政治への参加や地域での関係性づくりなど、みんなで協力し合える社会を身の回りからつくっていく。それが“お金の不安”を和らげる方法なのではないでしょうか。
※18歳意識調査「第46回 –国や社会に対する意識(6カ国調査)–」報告書
取材・執筆:佐藤伶
撮影:佐藤侑治

1978年生まれ。東京大学工学部卒業。同大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了。2003年ゴールドマン・サックス証券株式会社入社。以後16年間、日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーディングに従事。日本銀行による金利指標改革にも携わる。2019年に退職してからは、佐渡島庸平氏のもとで修行し、執筆活動を始める。著書『きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』(東洋経済新報社)は20万部突破。他にも、『お金のむこうに人がいる』(ダイヤモンド社)などを執筆。お金の向こう研究所代表。社会的金融教育家として、学生・社会人向けにお金についての講演なども行う。
X @mnbtauchi
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」





