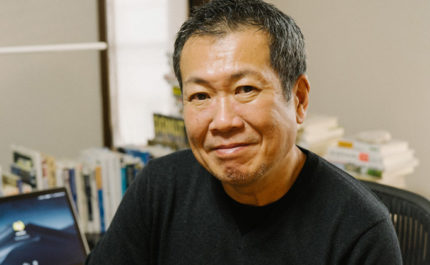地方都市に“閉塞感”、なんてない。
全国で増え続ける空き家。総務省の住宅・土地統計調査によると、2018年の空き家総数は約849万戸(※)で、およそ7戸に1戸は居住者がいない計算になる。防犯などの面からどう撤去を進めるかが課題となってきたが、近年はむしろ有効利用して地域活性化につなげようという機運が盛んだ。その中で注目を集めるのが、株式会社巻組(まきぐみ)の活動。条件の悪い築古の空き家を独自の手法で改修し、個性的なシェアハウスなどとして運用する。ただ、代表取締役の渡邊享子さんは地方創生を目的として創業したわけではないという。その目指すところを伺った。
※出典:総務省「平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要」https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/kihon_gaiyou.pdf

巻組は、宮城県石巻市で渡邊さんが2015年に立ち上げた会社だ。現在、宮城県内および東京都内で計15軒の賃貸物件(民泊付きシェアハウスなど含む)を運用している。数自体は多くないが、その取り組みが全国メディアで紹介される理由は、ただ「空き家を収益物件に生まれ変わらせるノウハウ」だけでなく、「なぜやるのか」、その理念が共感を集めるからだろう。それは創業時以来のスローガン、「出る杭、作ります。」に集約されている。
「出る杭」になって世の中の既製概念を覆す
家は人生のためにある。逆じゃない
「うちのシェアハウスは1日から入居できるのが特徴です。敷金・礼金なし。途中解約でも違約金なし。一般的な賃貸住宅の『入りにくさ・出にくさ』をぜんぶ排除したのは、使う人に自由で多様なライフスタイルを追求してほしいから」
渡邊さんはそう説明する。実際、巻組の物件利用者は多様だ。起業家やアーティストの他、狩猟免許を持って狩りをする人や、裏庭を畑にして烏骨鶏(うこっけい)を飼う人もいるという。そんなクリエイティブな人たちの楽しそうな暮らしぶりに引かれ、さらに人が集まり、結果として地域の魅力が高まる。そういう好循環をつくってきた。
「デザイナーや映像作家だけがクリエイターではありません。どんな課題にも想像力を駆使して能動的かつポジティブに向きあう、その姿勢をクリエイティブと呼ぶのだと思います。課題をお金で解決する方法もあるでしょうが、そんな世界では生きづらさを感じる人たちに『こういう暮らしもある』という選択肢を提供したい」
とはいえ、1日から出入り自由なシェアハウスなど、通常の賃貸経営の感覚では考えにくいビジネスモデルではある。だからこそ渡邊さんは、初期投資を短期で回収できる築古住宅、中でも接道しないなど「絶望的条件」の空き家を中心に投資対象としてきた。加えてそこには、大量生産・大量消費を是としてきた日本社会に対する、渡邊さんの強い違和感がある。

「新築住宅が大量に供給され、みんな安定した大企業に勤めて35年ローンを組んでそれを買う。それが『最善』だとして社会が回っていたのが高度経済成長期でした。その結果が今、大量に発生している空き家です。家は生活の基盤であって、どんなにライフスタイルが変化しても家が不要になることはありません。ただ、その形は変わっていくべき。35年ローンを返すためだけに働き続けるって不幸じゃないでしょうか。『人生のための家』のはずが『家のための人生』になってしまう。そういう世の中をなんとかしたい、というのが私の考えです」
「自分の人生、自分で変えよう」と気づいた
埼玉県のサラリーマン家庭に生まれた渡邊さん。大学時代に世界を旅して日本と違う街並みの造り方に興味を覚え、大学院では都市計画を研究した。
「大学院時代、広島県尾道市など、当時すでに空き家をかっこよくリノベーションして移住者を呼び込み、まちづくりに生かしている各地域で活動しました。でも学生の私ができることは限られていたし、当時は自分が地方移住するという選択肢にもリアリティーがなかった。あくまでも研究対象としてのまちづくり・空き家活用だったんです。漠然と研究職に就くことを考え、とにかく論文をたくさん書きました」
そこへ東日本大震災が起きた。直後、壊滅的な被害を受けた石巻へボランティアに行ったことが、そんな渡邊さんの価値観をじわじわと揺さぶることになる。
「被災した商店街に手伝いに行くと、商店主たちが毎朝自主的に集まって情報交換していました。そこで若手経営者たちが口々に、『震災前の石巻はなんにもなかったんだから、この機会におもしろい町に変えちゃおうぜ』と語っていた。人に助けてもらうのを待っていたら死んじゃうから、『生きるために動こう、自分の人生を自分で変えよう』という雰囲気だったんです。それを見ていたら、敷かれたレールの上で生きるより、こういう人たちと一緒に何かやったほうが絶対に楽しい、と感じました」
それを機に就職活動を一切やめた渡邊さん。最初の1年余りは週1回、夜行バスで東京と石巻を往復していたが、そのうち「東京にいる時間がもったいなくなってきて」、ついに移住を決断する。2012年夏のことだった。
「最初のシェアハウスを始めたのはその年の暮れでした。当時、現地ではボランティア仲間たちが起業し始めていましたが、住むところがなくて続けられないという声が上がっていました。震災直後は本当に住宅が足りなかったので、そういう人たちに場所を提供したら町が盛り上がるんじゃないか、と思ったのです。
でも、肝心の空き物件がなかなか見つかりませんでした。住宅地図を片手に歩き回り、しらみつぶしにしていったら、接道しておらず通りから見えない一画が白く浮かび上がった。そこの1軒だけ空いていたんです。8畳2間の平屋でトイレはくみ取り式。解体しようか迷っていた大家さんを説得し、借りた30万円で床だけ直して貸し出しました。
その後もいくつかシェアハウスをつくりましたが、この頃はまだビジネスとは考えておらず、会社を興す気もありませんでした。でも、最初に借りた30万円が1年半ほどで返済できてしまい、後は利益が出始めたんです。短期で投資回収する今のビジネスモデルの原型ですね。これを100軒やったら月100万円か、なんて漠然と考え始めました。3年後の2015年、それまで受給していた研究費が終了するタイミングで、これを自分の仕事にしようと決心して会社をつくりました」
ユーザーと一緒に価値をつくっていく
空き家探しに苦労した最初のシェアハウスから10年。この間、石巻市では新築住宅が大量に供給され、今では再び大量の空き家が発生しているという。市場の変化とともに巻組のビジネスも進化を遂げた。2021年11月には株式会社ガイアックスと資本業務提携し、事業エリアを石巻市外へと拡大。今年6月には日本初といわれるDAO型シェアハウスプロジェクト(※)をリリースした。
※DAO=自律分散型組織。住人自身が主体的にシェアハウス運営に参加し、その貢献度が報酬に反映される仕組みを取り入れたプロジェクト。「日本初」はガイアックス社および巻組調べ。

「起業7年、苦労しなかった年も、楽しくなかった年もありません。むしろ大変さは年々増していますが、それは『自分一人が食いつなぐ』フェーズから、『世の中にインパクトを生む』フェーズに変わったことの証拠だと思っています。
資産価値が低い空き家を入手し、短期で投資回収して価値化するのが私たちのビジネスモデルの根幹ですが、そのためには物件ユーザーが単なる『消費者』にとどまらず、自ら価値創造に加わってくれることが不可欠です。例えば、民泊を兼ねた巻組のシェアハウスでは、1軒の中に居住者と宿泊者が混在するため、おのずと住んでいる人に運営協力してもらう必要があります。そこにインセンティブの構造を組み込んでいるのが私たちの特色。DAO型シェアハウスはさらにそれを一歩進めたものです。
空き家に限らず農産物でも何でも、これまで価値が上がりにくいと思われてきたものについて、お客さまと一緒に価値を創造していくファンマーケティングは、これからの時代に必須のアプローチだと考えています」
まずはユーザーありきで家のあり方を考える渡邊さんだが、一方で相続した実家の処分に困っているというニーズに応えたい、とも考えている。国土交通省の空き家所有者実態調査によると、空き家を取得した理由の過半を占めるのが「相続」なのだ(※)。
「家とはそこに住んでいた人の人生そのものですから、ただ高く売れればいいという相続人ばかりではありません。いろんな事情で不動産業者には任せられないという人はたくさんいます。そういう物件が生かされて次世代の受け皿になり得るなら、私たちはそこをつなぐ役割を果たしたい」
※出典:令和元年空き家所有者実態調査 報告書 – 国土交通省https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001377049.pdf
どこへでも行けるし、なんでもできる
コロナ禍を経て地方移住や多拠点居住がトレンドになり、地方側ではそれを地域活性化につなげることを期待する。だが渡邊さんは、「自由に生きたい人たちに『まちづくり』への貢献を強制すべきではない」と明言する。
「空き家を再生して価値を向上させれば、結果として地域の魅力も上がるのは確かです。でも、私たちの指標は移住者の数や定着率ではありません。大切なのは移住者一人ひとりが自分らしく幸せに暮らすこと。地域がおもしろくなるのは、あくまでもその結果です。
よく聞く“若い世代の閉塞感”なんて、既成の価値観でしか生きられない人たちが保身のために言っているだけ、と私には思えますね。若者自身は“閉塞感”なんて持っていないと思いますよ。もっと言えば、彼らの多くは決して“地域の衰退”や、“日本経済の衰退”によって不幸になるわけではない。パソコンひとつでどこでも仕事ができる時代、どこへでも行けるし、やろうと思えば何でもできる。そういう新しい価値基準でクリエイティブに生きる未来の世代を、私は応援したいのです」
そこに前の世代が残した「空き家」を活用する、というのはまさに象徴的だ。既成の価値観に“右へ倣え”しない。『出る杭、作ります』のスローガンのとおり、渡邊さんの挑戦はまだまだ続く。
取材・執筆:中川雅美(良文工房)
撮影:山田真優美

2011年、大学院在学中に東日本大震災が発生、石巻へ支援に入る。その後に移住し、中心市街地の再生に関わりつつ、被災した空き家を改修して若手の移住者に活動拠点を提供するプロジェクトをスタート。2015年3月に巻組を設立。地方の不動産の流動化を促す仕組みづくりに取り組む。2016年、シェアハウス「COMICHI石巻」の事業コーディネートで日本都市計画学会計画設計賞を受賞。2019年、「第7回DBJ女性新ビジネスプランコンペティション女性起業大賞」を受賞。
株式会社巻組 Web
シェアハウスRoopt Web
Creative Hub シェア型アーティストインレジデンス Web
みんなが読んでいる記事
-
 2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子
2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。
-
 2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと
2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。
-
 2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会
2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。
-
 2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト
2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。
-
 2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題
2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。