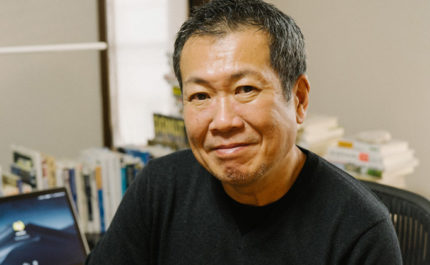映画で地方は創生できない、なんてない。
子供の頃から「表現の仕事をしたい」と映画に関わる仕事を目指し、俳優の経験を経て現在は株式会社and picturesのCEO/プロデューサーとして、地域と連携した映画製作、俳優向けワークショップ、プラットフォーム開発で映画産業の発展を目指している伊藤主税さん。愛知県蒲郡市の全面協力を受けて製作した映画『ゾッキ』、その撮影の裏側をドキュメンタリーにした映画『裏ゾッキ』の製作を通じて、感じた「映画」による「地域創生」の可能性について伺った。

地域の人々の力を集結させ、一つのことを成し遂げるためには、きっかけと仕組み作りが必要だと語る伊藤さん。映画製作というきっかけと、官民一体で取り組むための仕組み作りが今回、蒲郡市の町を一つにし、近隣地域へ影響を与えて地域連携の可能性を生んだという。そんな伊藤さんの現在の仕事、そして映画『ゾッキ』および『裏ゾッキ』の製作に至るまでの経緯や、今後の映画産業発展のために実現していきたいことについてお話を伺う。
映画は人と接していなくても作品として残り、
見てくれた多くの人に自分の考えを伝えることができる
映画に関わる仕事を目指した経緯について伺った。
「今の活動のほぼ原点だと考えているのですが、表現の仕事をしていきたいという感覚的なものが小学校3年生ごろからずっとありました。もともとは、経済的に大きな格差がある二つの親戚の家庭環境を見ていく中で、『お金があることが当たり前で人の気持ちを考えられなくなる子供』と『貧しいが故に、自分の親を否定してしまう子供』の両方と関わってきた経験があり、家庭の経済状況により、教育に支障が出ることへの問題意識を持っていました。それが理由で子供たちと関わる立場で、人の気持ちを考えることや自分の置かれた状況を否定しないことなどを伝えていきたいという考えに至り、教員になろうと思っていました。でも、教員になるために調べていく過程で、叔父が高校の校長先生だったこともあり身近で教員の働く姿を見ることができたのですが、自分には向いていないと感じてしまい、教員を目指すのはやめてしまいました。
その後、高校3年生のときに友達と『バスケットボール・ダイアリーズ』という映画をレンタルして見ることがありました。その友達は当時いわゆる不良だったのですが、その映画を見てとても感化されたようで、『映画に出てきていたような不良みたいにはなりたくないよね』というような会話になりました。そのときに、映画は人と接していなくても作品として人に届き、自分の考えや感じたことを伝えていけるんじゃないかと思い、その影響力のすごさを実感したことがきっかけで映画を仕事にしたい、関わりたいと考えるようになりました。
当時は、監督やプロデューサーには絶対になれるわけない、でもお芝居ならできそうだなという感覚から芝居をするために19歳で東京に出てきました。東京に出てきてからは芝居の勉強の傍ら、とにかく何事も経験だと思い、アルバイトを50種類くらい経験しました(笑)。事務所に所属してオーディションを受けていく中で、芸能や映画の業界について疑問に思うことが増えてきたこともあり、23歳のときに自分で会社を立ち上げて映画を作っていこうと決意しました」
起業に至るまでにはどのような苦労がありましたか。
「起業を考えたときにまず問題だったのが、当時の自分には2万円くらいしかお金がなかったということ(笑)。なので、お金をためつつ企業の社長に営業ができる方法を考えて、銀座のクラブで黒服として働くようになりました。1年目で仕事を覚えて、2年目にはクラブのママたちから関係者を紹介してもらい3年目には人脈も広がり、お金もたまったので26歳のときに会社を設立しました。映画学校にも通っておらず、我流でやってきた中で会社を設立できたのは3年間のアルバイトを通じて映画の会社をつくりたいという思いをいろんな人たちに伝えて、応援してもらえたことが大きかったです。
経験もない26歳の青年がただお金を持っているだけなので、1本目の映画を作ったときにだまされることがあり、撮り終わったときには数千万円借金を背負ってしまい、家なき子になりました。そのときお世話になったのが、ホームレス界のカリスマのヒデさんという方でした。この方ももともと社長をされていた方で、『伊藤君はまだ若いから、頼れる人に正直に失敗したことを話せば助けてもらえるよ』と、アドバイスを頂けたおかげで、他の人に素直に相談することができ、再起を図ることができました。
そこからは同じ失敗をしないように、まずは映画のことをしっかり勉強しようと思いました。当時あまり主流ではなかったショートフィルムを年に20本以上撮って映画製作のノウハウを2年かけてためていきました。その他にも、才能のあるクリエイターを探すためにいろんな映画祭に行ったり、知り合いを通じてクリエイターの集まりに参加して、ものづくりにおける軸をつくろうと奔走していました。そのころに出会い、自分がいいなと思って一緒に映画を撮っていたのが日本アカデミー賞をとった藤井道人監督や『おっさんずラブ』で話題になったYuki Saitoさんとか、『カメラを止めるな!』の上田慎一郎監督といった方々です」

-地域密着での映画を撮り始めたきっかけやそこで感じたことはありますか?
「僕は愛知県豊橋市出身なのですが、3年ぶりくらいに地元に帰ったときに、小さいころによく行っていた八百屋さんとか駄菓子屋さんなどがなくなっていて、すごい寂しい気持ちになったんですよ。それで、今の子供たちはどこで遊んでいるんだろうと気になり、町を取材して回ったんです。今まで遊んでいた場所や人を取材しているうちに、この状況は町が廃れているんじゃなくて、人に活気がなくなっているんだなって思ったので、人に活気を持たせて、町を興そうと考えるようになりました。
人に活気を持たせるのに必要なことを考えたときに思いついたのが、みんなで一つのものを作り上げることと影響力のある人を誘致して、人々が盛り上がるきっかけをつくることでした。例えば、学生時代の文化祭を思い出してもらうと分かりやすいと思うのですが、教室や学校など、一つの場所で必死にものづくりをしたり、有名な人がゲストで来たりするのってものすごく夢がありましたよね。この感覚や施策が映画製作と似ている気がしたので、映画と地域創生のために生かし、人をつなげ町を一つにできると考え、地域密着で映画を撮ろうと決めました。
地域密着での映画製作では、京都で川端康成原作の『古都』という映画を撮影したときが一番苦労しました。地域創生に興味を持ちだしたタイミングで日本の文化とその象徴である、京都について改めて考えるようになり、そのときたまたま『古都』の映画をまた現代を舞台にして撮りたいっていう相談があったんですよ。
いざ製作を始めようと京都の町であいさつや取材のお願いに回ってみたところ、自分が京都について何も知らないこともあり、最初は全て門前払いで。それで半年間くらい京都に住んでみて、京都の町の人たち総勢5,000人くらいにひたすら取材をしました。取材をしていく中で、京都の文化や人について少しずつ分かってくるようになり、最終的には人脈が少しずつつながってきて京都市長にお会いしたり、日本の文化を支える方々に少しずつ知り合うことができ、いろんな人が協力してくれるようになり製作をすることができました。できないと思っていたことが、気合で思いを届け続けることで何とか形にできました」
「映画」が持つ「地域創生」の可能性を広げていきたい
-今回の映画『ゾッキ 』製作での取り組みについてお伺いします。
「京都の他にも大分、鳥取、長野などの地域で撮っていく中で、官民一体でないとうまくいかないかもしれないと思っていたんです。というのも、行政だけでやっても民間はそこまで深く関わろうとしないですし、民間だけでやっても行政は関わりづらい傾向があるなと思っていて。なので、『ゾッキ』製作時には官民一体で必ず実行委員会をつくると決めていました。その地域で撮影だけをして終わりにするのではなく、官民一体で実行委員会をつくり、映画を作ってくれる仲間をその地域に残すことをとにかく大事にしました。行政でシティープロモーションをしてくれる方々がいることで、仕事が生まれるので、その人たちが軸となり民間の方々や商工会、青年会議所の方々の力を集結させるという取り組みが実現できましたね。
また、映画の宣伝やニュースリリースの出し方なども2年間かけて一緒に勉強し合い、地元の記者クラブからすぐに展開できるようになっていきました。今では一声でニュースリリースなどを発信できるようになっています。食料部会というものを組成し、協力し合いもしました。撮影時のお弁当一個一個に市民の方々からメッセージカードを付けるアイデアを頂いて、監督やキャスト、スタッフが毎回お弁当のたびに市民の方々からのメッセージを受け取って、『頑張ろう』って思えるような。食料部会の方々に撮影期間ずっと続けてもらうことができました。1カ月ぐらいたつと自ずと映画製作サイドと蒲郡市民の方々がつながっていきましたね。
今回『ゾッキ』では著名な方々が何人も監督をしたり、出演したりしていて、その方々がどのように映画を作り、コロナ禍でも負けずに取り組んできたのかというドキュメンタリー映画を裏側で撮っていて、『裏ゾッキ』として、その映画ができる結果と経過を同時に見ていただけるようになっています」

-映画『ゾッキ』の撮影で感じたことや手応えはありますか?
「地域の中で一つのことを成し遂げようとするには、気持ちがあればいいわけではなく、何かきっかけとなるものが必要だなと考えていて、町の人がつながるきっかけにはなれたかなと思っています。地域の方としっかり話し合いながら映画の製作や宣伝、商品開発を行ったので、そのノウハウに関しても共に勉強できて、地域創生のモデルケースの役割を担い、近隣地域に派生していってる感覚があります。『ゾッキ』の場合だと、愛知県蒲郡市で撮影をしたときに愛知県庁や近隣の、豊橋・岡崎・豊川・常滑・東海市などの方々に見学に来ていただけました。一つの地域からモデルケースさえ作れれば近隣地域に派生していって地域連携ができるという可能性が、すごく面白いなと思っています。他の県からも同じ取り組みのご相談をいただいていたり、展開していっていることが、すごくうれしいです。とはいっても、僕たちが同じように2年間かけて、いろんな地域で行っていくのは大変なので、映画業界が地域密着で映画製作を行うプロデューサーを育成したり、企業がいろんな地域にシェアハウスや集まれる場所などの環境を用意するなど、映画サイドと企業の連携が必要だなと考えています」
-今後挑戦していきたいことについて教えてください。
「『ゾッキ』『裏ゾッキ』の製作を通じて映画による地域創生の形は作れた気がするので、地域連携をして広げていきたい、というのがまずは一つ。もう一つは演劇の教育に力を入れていきたいですね。演技というのは役やセリフを通して人の感性や想像力をかき立てるものだと考えており、現在でもリモートで演劇教育を軸にワークショップを開催していますが、もっと人の心を動かし、豊かにするような演技の教育をしていきたいなと考えています。あとは、今回蒲郡市の信用金庫を映画館に変えて1カ月映画を上映したことで、人が集まる場所やアイデアさえあれば、眠っている資材を活用することができるということが分かったこともあり、各地域に隠れている、映画を上映できるような場所を増やしていきたいと考えています」
もう一つは、自分で自分の評価を決め過ぎないでほしいです。人は社会の中で、他の人との関わりのもと、成立していくと思うんですよね。なので、時には他の人の意見を聞き入れたり、評価を委ねたりしてみて駄目ならまた頑張ってみる、というように自分の中だけで完結しないでもらいたいなと思います。最後は、今のコロナ禍で日々の生活がマンネリ化してしまい、「自分は何なんだろう」とか「今やってることは将来的に何のためになるんだろう」のように疑問に思っている人もいると思うのですが、そういった疑問や自分の持つ価値観を共有できる人を一人でも多く見つけてほしいですね。価値観が合う人が集まれば、現状を変えるアイデアや面白い企画なんかも生まれてくると思うんですよね。そしてそのアイデアや企画にチャレンジしてみる。僕も、失敗から再起した経験がありますからね、何でもやってみることです。
撮影/加藤木 淳

1978年生まれ、愛知県豊橋市出身。俳優活動を経て、映画プロデューサーとして活動。映画で文化を生みたいと、映画製作会社「and pictures」を設立。短編オムニバス企画「Short Trial Project」シリーズや長編映画を製作し、国内外映画祭で受賞歴多数。プロデュース作品に『ホテルコパン』『古都』『栞』『青の帰り道』『デイアンドナイト』『Daughters』『ゾッキ』『裏ゾッキ』など。山田孝之、阿部進之介とともに発足した、俳優に学びとチャンスを提供するサービス「mirroRliar」にて一般クリエイターや監督を巻き込み、映画製作の魅力を伝えるプロジェクト「MIRRORLIAR FILMS」を始動。映画製作をきっかけとした地域活性化プロジェクトの推進などを目指す。教育にも力を入れており、2020年10月よりオンライン・アクターズ・スクール「ACT芸能進学校」(通称A芸)を開校。
https://andpictures.jp/
みんなが読んでいる記事
-
 2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子
2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。
-
 2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと
2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。
-
 2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会
2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。
-
 2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト
2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。
-
 2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題
2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。