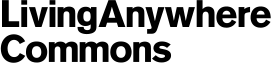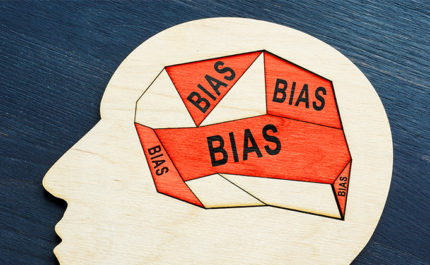ピンクやフリルは女の子だけのもの、なんてない。
ピンクのヘアやお洋服がよく似合って、王子様にもお姫様にも見える。アイドルとして活躍するゆっきゅんさんは、そんな不思議な魅力を持つ人だ。多様な女性のロールモデルを発掘するオーディション『ミスiD2017』で、男性として初めてのファイナリストにも選出された。「男ならこうあるべき」「女はこうすべき」といった決めつけが、世の中から少しずつ減りはじめている今。ゆっきゅんさんに「男らしさ」「女らしさ」「自分らしさ」について、考えを伺った。

私たちは、社会から長い間「男らしさ」「女らしさ」といった価値観を刷り込まれてきた。だけど本当は、男も女も関係なく、誰もが自分らしく自由に生きていけばいいのではないだろうか? そんな思想を体現しながら、アイドルとして活躍しているのがゆっきゅんさんだ。「自分の好きなものを正直に好きだと言える生き方を、多くの人にしてほしい」と願う彼から、自分や相手の個性を尊重するためのヒントを探る。
人の「らしさ」を決めつけない。その上で、ただ、目の前にいる人に優しくできればいいんだと思う。
間違ったことはしていないんだから、私は私のままでいい
ピンクのショートヘアに、つやめくアイシャドウが美しい。アイドルとして活躍するゆっきゅんさんは、岡山に住んでいた子ども時代からずっと、「自分らしさ」を疑わずに貫いてきた。
「昔から少女漫画や女性歌手が好きで、話していて面白いと感じるのは女の子ばかり。男の子にはよくバカにされていました。でも、私はかわいいものやきれいなものが好きなだけで、何も間違ったことをしていない。男子と仲良くしないといけないと思ったこともありませんでした。だから私は、このまま私らしく生きていけばいいと考えていました」
まわりに媚びない意志の強さは、昔からだった。かわいいものが好きだという気持ちも、小学校3年生の時に観た映画『下妻物語』で、さらに高まってゆく。中島哲也監督・嶽本野ばら原作の、ロリータ少女とヤンキー少女が織りなす友情ストーリーだ。
「朝の情報番組で、ロリータファッションの深キョン(深田恭子)が作品の宣伝をしていたんです。初めて自主的に『これは観なくちゃ!』と感じて、お母さんに『これを観に行かんといけんのんじゃけど……』と頼み、連れて行ってもらいました。こんなに面白いものがあるんだ! って衝撃でしたね。ロリータにも映画そのものにも興味が湧いて、嶽本野ばらさんの著作も読み漁りました。そのときはっきり自覚していたわけではないけれど、今思えば、こんなに面白くてかわいい作品の監督と原作者が男性であることに、少なからず救われた部分があったんだと思います。世界が、広がったように感じられたんです」
一方で、学校生活の窮屈さは変わらない。
「ホモソーシャル※的な空気が無理だから、体育の時間は特にイヤでした。着替えの時に男子だけになった教室は居心地が悪かったし、競技の勝敗にも興味が持てず、まわりとは温度差がありました。でも、そういう環境になじめなくて悲しいとか、自分をまわりに適応させようなどとは考えたことがありません。ただただ、早く時間が過ぎろと思っていただけ。実際に小学校でも中学校でも、時間が経てばみんなのほうが私に慣れていきました。高校は個人が尊重される校風だったから、受け入れられるのが特に早かったですね」
※ホモソーシャル
恋愛や性的な意味を持たない、同性同士の絆やつながり。男性間に流れる「男ならこうあるべき」といった空気を指すことも多い。
なりたい自分を求めて動いていたら、自然と「ミスiD」にエントリーしていた

ゆっきゅんさんが上京したのは、たくさんの面白いものに出合いたかったからだ。音楽も映画もアイドルも好きなのに、岡山では見たくても見られないものが多い。東京に来てからは様々なカルチャーにふれながら、アイドル活動もスタートした。大学3年の時には、多様な女の子のロールモデルを発掘するオーディション「ミスiD2017」で、男性初のファイナリストに選出されている。
「『ミスiD』は、好きなクリエイターたちが選考委員をしていたんです。それで『オーディションに出るならこれしかない』と思っただけで、『ジェンダーの壁を打ち破ってやるぜ!』とか考えていたわけではないんですよ。エントリーしたのもファイナリストに残ったのも、自分のなかではとても自然な流れのことでした。もちろん、ミスコンに自分がいるという状況には自覚的に取り組みました。
オーディションは、自分の見せ方や見え方を、まわりからのさまざまな言葉で改めて認識する良い機会になりました。他のファイナリストたちと比べられる機会を通じて、逆に「ゆっきゅん」という個性を認めていただいたとも感じています。同じ年には、アイドルユニット『電影と少年CQ』も結成しました。
今のところは、大人になるにつれてどんどん自由になっていく感覚があるんですが……自分がどういう人間で何をやりたいのか、最初からわかっていたわけではありません。だからこそ、なりたい自分や居心地のいい自分を実現できる場所を求めて、いろいろ動いてきたし、その結果として今があるんだと思っています」
思春期の男の子たちに「自分のままで個人として生きること」を届けたい
2021年5月、26歳の誕生日にはソロ活動『DIVA Project』を開始した。「DIVA ME」「片想いフラペチーノ」の2曲を配信リリース。デビューに寄せて「自分のままで個人として生きることを楽しく美しく面白く肯定してきました」とコメントしている。
「これまでの活動を通じて、私みたいな存在を待っている人が必ずいるって確信できたんです。私自身も10代のころに、「ゆっきゅん」がいたらもっと楽に生きられたと思うから。だからこのプロジェクトは、誰に届くのも心からうれしいんですが、最終的には思春期の男の子たちへちゃんと届けなくちゃって思っています。自分の好きなものを正直に『好き』と言いながら生きていくか、まわりとなじむために好きなものを隠して生きていくかの二択があるとしたら、前者の自分らしく生きていける人を増やしたい。そのためには一刻も早く、まだ出会っていない人たちに出会って、生き方を見てもらいたい。
実は、今までの私はそういう覚悟ができていなかったんですよね。誰かにマイナスなことを言われたり叩かれたりしたくないし、いろんな視線をうまくかわして、自分の世界を自己完結させてきました。そうすれば、誰も何も言いたいと思わないだろうから。でも、ソロとして表現をはじめるなら、社会に影響を与えるような意味を持たなければ、わざわざ発表する必要がない。これは『イン・ベッド・ウィズ・マドンナ』というマドンナのドキュメンタリー映画を見て感じたことでした。社会に向けてちゃんとポップなミュージックを届け、聴いてくれた人に影響を与えていくために、自分を守ってくれるお城から踏み出した気持ちなんです」
そんなDIVA Projectの楽曲は、男女を問わず、幅広い層に届いた。

「繰り返し出てくる『DIVA』とは何なのか、はっきりとは説明していません。でも楽曲を聴いてくれたら、きっとその精神性は伝わるはず。私の曲を聴いたあとには、他人本位ではなく、自分を思いやった選択ができるんだと感じてほしいんです。
それに、私自身は女の子のために作られた作品を好きになっても疎外感を感じない気持ちがあったから、ここまで来れたけど……自分のための映画や音楽がどこにもないって感じている人も絶対にいるから『Girls don’t cry』と言われても『Boys don’t cry』と言われてもピンとこなかった人たちに『DIVAs DIVAs don’t cry』を届けたい。これは私のことだと感じてくれる人が、一人でもいたらいいなって思います。
うれしいことに『DIVA ME』の歌詞にはすごく反響がありました。」
 DIVA Projectのデビューシングル「DIVA ME」は幅広い年齢層から反響があった
DIVA Projectのデビューシングル「DIVA ME」は幅広い年齢層から反響があった
好きなものを自分で選び、優しくしあえる世界でありたい
ジェンダーやセクシュアリティなどと関係なく、ゆっきゅんさんはたった一人の自分を生きている。そこで、あえて「男らしさ」「女らしさ」についてどう思うかを聞いてみた。
「男らしさは、特権についての無自覚さですよね。学校とか社会とか男子とかに対して、私はずっとジェンダー的な違和感をおぼえていました。それで、高校2年生の時に上野千鶴子さんの『女ぎらい――ニッポンのミソジニー』とか加藤秀一さんの『ジェンダー入門―知らないと恥ずかしい』を読んだら『あれもこれも差別じゃん! 男らしさとか女らしさって社会が勝手に作ったものじゃん!』って気付いた。今まで自分が感じていた違和感はちゃんと言葉や学問にされていて、たくさんの人が問題として感じていることなんだって知ったんです。それまでの自分の生き方は、やっぱり間違っていなかったんだとも思えました。
男らしさとか女らしさって、自分で選ぶならいいんですよ。自ら何かを選んだ結果、それがたまたま男らしいとか女らしいとか言われるような嗜好であることと、まわりからどちらかを強制的に選ばされてしまうこととは、全然違います」
誰もが自らの物差しで、好きなものを選べる世界がいい。世の中にはそんな風も少しずつ吹きつつあるけれど、「こうあるべき」を人につい押しつけてしまう場面も、まだきっとある。その人らしさを尊重するために、今日からできることは何だろうか。
「自分の気持ちも目の前にいる人も、そもそもどんどん変わっていくものですよね。だから何も決めつけず、ただ目の前にいる人に優しくしていればいいんだと思っています。もちろん人がどう生きようと自分とは違う人間なのだから、自分と他人の区別をちゃんとつけた上で、相手を尊重する。私の家族はたまたま、私のような自由な考えの息子をもったけれど、私の生き方について何か否定するようなことを言ってきたことはありませんでした。それは別にジェンダー意識が高いとかじゃなくて、ただいつも私に優しくしてくれていただけなんですよね。特別な知識がなくても、まずはそれで充分なんだと思います」
取材・執筆:菅原さくら
撮影:内海裕之

1995年、岡山県生まれ。新時代の自由を体現するポップアイコン。青山学院大学文学研究科比較芸術学専攻修了。「電影と少年CQ」のメンバーとしてライブ活動を続けながら、セルフプロデュースでのソロ活動「DIVA Project」を始動。水野しずと共に編集長を務める雑誌『imaginary』(夢眠舎)を2021年12月8日に創刊。
Twitter
@guilty_kyun
Instagram
@guilty_kyun
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
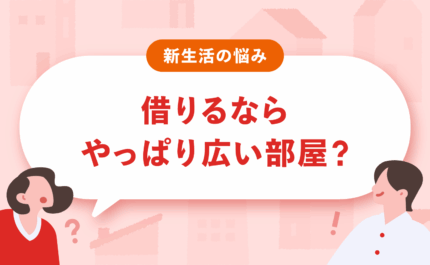 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
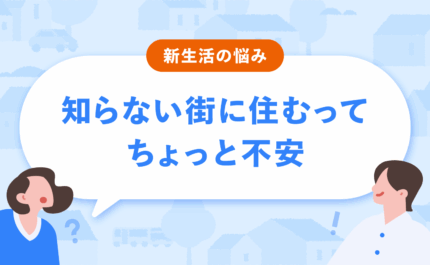 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
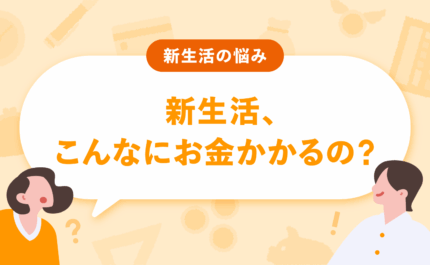 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
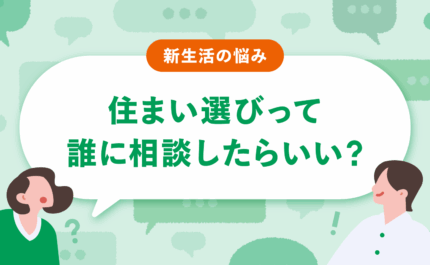 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。