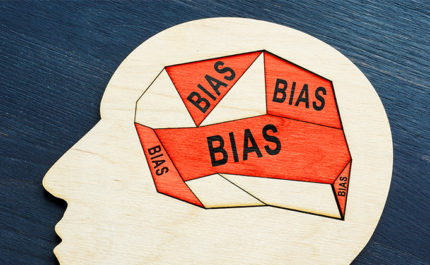仕事場での女性の服装は女らしくなきゃ、なんてない。
職場でのパンプス着用義務付けに反対する「#KuToo運動」の発起人・石川優実さん。彼女のTwitter投稿に端を発したこの運動では、国に対し「企業が女性にパンプスを履くよう強制するのを禁じる」ことを求めた署名1万8856筆が提出された。多数のメディアに取り上げられた運動の影響は大きく、2020年には、JAL、ANAでヒールの義務付けが相次いで撤廃。就職活動のマナーサイトにも「パンプスが足に合わない場合は無理に履かなくてもよい」と記されるようになった。石川さんが目指す“みんなが生きやすい”社会とは?

ルッキズムとは、外見でその人の価値を測り差別する考え方のこと。容姿を侮辱するだけでなく、他人を画一的な美の基準に当てはめ、一方的にジャッジすることも含まれる。ルッキズムがはびこる日本では、特に女性に対して「美しくあれ」と強いる空気が強い。石川さんが問題提起したパンプス着用の強制も、こうしたルッキズムに基づいて引き継がれてきた制約と言えるだろう。ルッキズムの問題が絶えない原因は、いったいどこにあるのだろうか。また、社会を変えるために私たちはどう行動すべきだろうか。#KuToo運動の発起人であり、アクティビスト、俳優、ライターというマルチな肩書で社会に問題提起し続ける石川さんが、自身の体験談を交えながら語ってくれた。
足が痛み、血が出るのを我慢してまで
パンプスで働かなきゃいけない理由って何?
高校卒業後、芸能活動と並行して観光の専門学校に通っていた石川さん。そのときに行われたホテルでの泊まり込みの研修で、生まれて初めてパンプスを履きながらの仕事を経験した。
「想像以上に足に負担がかかって、爪先が血まみれになりました。あまりにもつらかったので、ホテルの仕事内容を覚えることよりも、『どうしたら少しでも足が痛くならないように働けるか』で頭がいっぱいになってしまうほどでした」
違うパンプスを試してみたり、爪先にティッシュを詰めてみたりしたが、足の痛みは一向に改善しない。毎日8時間、この状態で立ち仕事をするのは無理だと感じた。
「なんとなくふに落ちない、モヤモヤした気持ちはありましたが、当時はパンプスを強制される社会規範がおかしいんだと気付くことはできなくて。私にはホテルの仕事は向いていないと感じ、専門学校をやめたんです」
その後も、アルバイト先で店長に「化粧をしていないなら働かせられない」と帰された同僚を目撃するなど、“モヤモヤした気持ち” を経験する場面は何度もあった。しかし、決まっていることなら仕方がないと、無理やり自分を納得させながら生きてきたという。
時は流れ、2017年。芸能界で受けた性暴力を「#MeToo」のハッシュタグとともに告発したことをきっかけに、フェミニズムと出合う。ジェンダーや差別について一から学ぶ中で、過去の自分が受けたパンプス強制を思い出し、ようやく「あれはおかしいことだったんだ」とハッとした。
「仕事の場にまで『女性は美しくいなければならない』という価値観が持ち込まれ、それが正しいことかのように指示される。業務と美しさは関係がないはずなのに、女性なら奇麗でいるのが常識と、男性には求められないことが強いられる――。明らかなジェンダー差別であり、ルッキズムの典型ですよね。なのに、こうした構図が当たり前になり過ぎていて、それが変だとなかなか気付けませんでした」
「常識」は変えられる。理不尽に黙って従う必要はない
2019年、女性だけがパンプス着用を強要される現状にTwitterで異議を唱えたところ、多くの人から共感を得る。ツイートが大反響を呼び、各種メディアに取り上げられたのを機に、賛同者と協力して「#KuToo運動」をスタート。社会にさまざまな変化をもたらした一方、ネット上では苛烈なバッシングを受けた。

2019年11月に初の著書『#KuToo(クートゥー) 靴から考える本気のフェミニズム』を発売。
引用:石川優実公式Instagramアカウントより
「#KuTooに対しては、『上の指示には従うのが当然でしょ』といった批判がものすごく多かったですね。職場でのパンプスや化粧の強制などを『社会の常識だから必要なこと』と信じて、固く決まっていて揺るがせないと思い込んでいる人がたくさんいると知りました」
しかし、女性が足を痛めてまでパンプスを履くことは、本当に業務に必要なルールなのだろうか。これが「女性は職場でも美しくいなければ」といったルッキズムによって生み出されたものであり、なんら合理性のない制約ならば、取り払おうと声を上げるのは当然だろう。
「何かが変わっていくときはいつも、誰かが声を上げてきた歴史があります。バッシングをする人たちはそのことを知らず、声を上げること自体がわがままに見えているのかもしれませんね。でも、私は『これは黙っている問題じゃないですよ』『怒っていいことですよ』とみんなに知ってもらいたいので、何を言われても発信を続けますし、反論もします」
そもそも、日本ではなぜ、非合理的で理不尽な制約に黙って従う人が多いのだろうか。
「さまざまな要因が複雑に絡み合っているとは思いますが、学校教育の段階から『みんな一緒が正しい』といった感覚がたたき込まれるのが一因ではないでしょうか。
今の社会をつくっている大人たちの多くはそうした教育を受けてきて、『ルールに従ってみんな同じが当然』『“普通”から外れた人はおかしい』という前提の意識を共有している。だからこそ、人権侵害のような規則であっても疑問を持たず従ってしまうし、下の世代にも強制してしまう人も多いのかなと。たとえ『この規則はおかしい』と気付けても、学校や職場での立場を気にして逆らえない人も多いですし。
ただ、近頃は一般的に考えたら明らかに理不尽な校則が強く批判されるなど、社会の問題を自分のこととして捉え、声を上げる人も増えつつあります。そうした方々と連帯して、少しずつ社会を変えていきたいですね」
ルッキズムの呪いを解くために、私たちができること

上からの権力や規則による押し付けだけでなく、私たちの周囲でも、他人の容姿を「太った」「老けた」などとぶしつけにジャッジする、能力ではなく美しさで評価する、若い女性を勝手に “職場の華” 扱いするといったケースは絶えない。
「一方的に容姿をジャッジすること、人を中身ではなく外見で評価することはとても失礼だともっと知られてほしい。けなすのはもちろん、褒めるのであっても、赤の他人に容姿を観賞物のように扱われること自体を不快に思う人はいます。
本人が言い返せないときは、できればまわりの人が『それ、セクハラですよ』と指摘してあげてほしいですね。自分はどう思うかという個人的な感情をぶつけるよりも、淡々と『セクハラだからアウトですよ』と事実を述べるのが効果的だと思います」
また、日本には、幼い頃からルッキズムにさらされ続けて育ち、自身でも「美しくならないと愛されない」とルッキズムを内面化してしまっている女性が少なくない。近年はボディポジティブの概念が認知されつつあるが、それでもなお、ありのままの自分を受け入れられないという人が大半だろう。
ルッキズムの呪いを解いて自分らしく生きるために、私たちはどうすればいいのだろうか。
「私はルッキズムに異を唱えるような活動をしていますが、それでもやはり体重の増減は気になるし、自分の容姿を許せないこともたくさんあります。子どもの頃からずっと、周囲の人やいろんなメディアから『かわいくなきゃ』『瘦せなきゃ』『愛される女性にならなきゃ』というメッセージを受け取り続けているので、いきなり『いや、そんなことはない』って転換できるわけがないんですよね。
なので、普段から自分の体のいいところを見つけて、心の中で『ここがいいよね』って自分自身に言い聞かせるようにしているんです。あとは、パートナーの目に付く場所に『今日もかわいいです、と言いましょう』という紙を貼って声掛けしてもらったり(笑)。信頼関係ができている人に肯定してもらえるだけで、だいぶ気が楽になるので。少しずつ自分の容姿をポジティブに捉える癖をつけています。
それに、美しさって実は不変のものではなく、時代や場所によって変わり得るものなんです。必ずしも、私たちがとらわれている美しさだけがすべてとは限らない。『美は画一的なものではない』という考えがもっと浸透するよう、今後もいろんな体形、いろんな顔立ち、いろんな肌の色の人がメディアに起用されるようになってほしいし、『どんな人でもおかしくないよ』という価値観をみんなで共有し合っていきたいですね」

1987年、岐阜県生まれ。アクティビスト、俳優、ライター。グラビアアイドルや俳優として活動していた2017年末、芸能界で経験した性被害を「#MeToo」のハッシュタグとともに告発し話題に。2019年、職場でパンプス着用を義務付けることに反対した「#KuToo運動」を展開し、世界中のメディアに取り上げられる。2019年、英BBC「100人の女性」選出。
Twitter @ishikawa_yumi
公式サイト https://ishikawayumi.jp/
Instagram @ishikawa_yumi.official
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
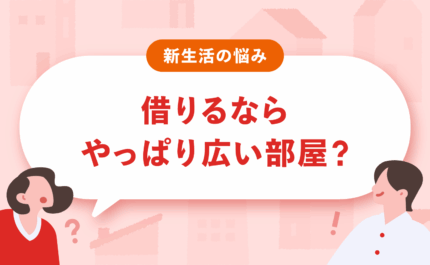 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
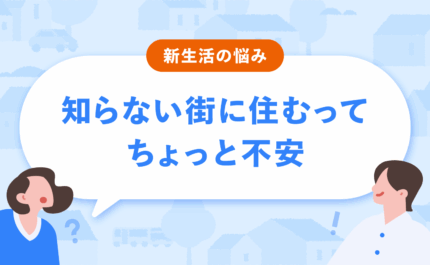 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
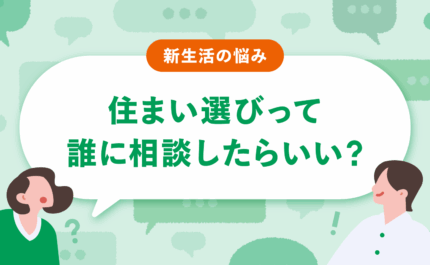 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
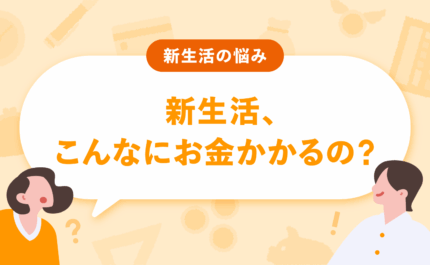 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。