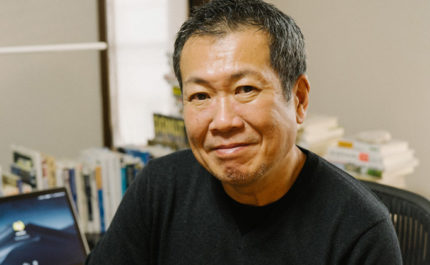家庭を持つサラリーマンに移住は難しい、なんてない。
静岡県内で移動販売の「朝霧高原 あおぞらピッツァ」を営む大塚祐介さん。かつては都内で19年にも及ぶ会社員生活を送り、正直息苦しく感じることもあったという。しかし現在は、昔からの「憧れ」だった、大自然に囲まれた生活を手に入れることができている。夢を追って東京から地方へ移住した大塚さんから、生きるヒントをもらった。

出身は神奈川県鎌倉市。湘南の海と山に囲まれて育った。工作が得意で、よく自然のものを使って遊び道具を作り、山へ入って探検ごっこをするなど自然とともに暮らす日々を送っていた。好奇心が旺盛で元気いっぱいの小学生だった。このまま大人になってものびのびと暮らしていきたかった。むしろ暮らしていけると思っていた——。
都内にある理系の大学に4年間通ったのち、教育関連会社に就職した。その後、スキルアップを求めて3回転職を経験した。うっすら「このままでいいのか」と思うこともあったが、「ようやく描いていた“理想”に近づいた」と思えたのは41歳の時。一念発起して朝霧高原へ移住したのだった。
確かに起業・独立したいという気持ちは以前からあった。そのためにスキルアップを求め続けて、自分の居場所を数回移した。そして今、ようやく誇れる人生を手に入れることができている。そんな彼はサラリーマン時代、そして地方へ移住した今、何を思うのか。
移住願望は昔からあったが
“今”ではなかった
大学時代、大塚さんはパラグライダーサークルに入り、毎週末のように長野へ通った。子どもの時と同様、自然と触れ合う生活を送っていたのだった。
「パラグライダーはライセンスまで取得するほどのめり込み、 “いつかこんな暮らしがしたいな”と思うこともありましたが、サラリーマンとして働こうという気持ちの方が強かったです。当時、1990年代半ばはインターネットが出始めの時代。IT企業もほとんどない時代で、家電や半導体メーカーなど、昔ながらの企業を就職先に選ぶ人が多かった印象です。私はインターネットの世界でやっていくと決め、大学の先輩に教えてもらいながら自分でもホームページを開設したり、ネットを使った情報発信なども早いタイミングでやっていました。リフレッシュのため、週末にパラグライダーやキャンプをしに朝霧高原へ足を運ぶこともありましたが」
そんななか、2社目であるインターネット広告代理店に勤務していた2004年、大塚さんが28歳の頃。激務に追われる日々を過ごしている最中に、渋谷の書店である一冊の本と出会い、心動かされることになった。
「ふと手に取ったその本は塩見直紀さんの著書『半農半Xという生き方』でした。半農半Xとは、1990年代に提唱されたもので、食料の自給をしながら自分の好きなことを天職として現金収入を得る生き方を指すんですが、兼業農家ではない新しい働き方だと思ったんです。この半農半Xに感銘を受け、こんな生活をしたいなと思い始めるようになりました。ちょうどその頃、仕事が深夜にも及び、 “これは長くは続かないだろう”と考え、少し落ち着いた生活もしてみたいなとも思うようになっていました。しかし、会社にいればある程度責任はのしかかり、簡単に辞めることはできない。 “環境を変えたい”と思っても生活があるため、固定給を放棄する決断はなかなかできません。一向に踏み出せず、それから10年以上サラリーマンを続けることになりました……」

一方で、大塚さんはサラリーマンを続けながらあることも続けていた。これが理想に近づく、第一歩だったのかもしれない。
「とにかくピッツァの食べ歩きを続けていたんですが、100店以上もの店を食べ歩きました。私がサラリーマンとして働いていたビジネス街にはピッツァ店がとても多く、いろいろな味の食べ比べをすることができました。そうしているうちに、自分でも作ってみようと考えるようになりましたね」
その後、2013年からは野菜作りも始め、着々と理想へと近づいていく。
「三鷹の有機貸し農園で野菜作りをしていたのですが、農園内にピザ窯を作って、ナポリピッツァを焼いて食べたりしていたことがあったんです。時には人を集めてピザ焼き体験会を実施したり。それがすごく好評で、商売になるのではないかなと考えていました。現在移住して暮らしている朝霧高原は年間180万人が訪れる観光地。キャンプ場やアウトドア施設に来る方に向けて販売すれば、収入源として成り立たせることができるのではないかと事業計画を立てたんです。移住もそうですが、場所を選ばずにできる移動販売についても、これからの時代に沿ったやり方だと考えていて。加えてピッツァは、発酵管理、薪窯の管理となかなか簡単にできる料理でなく、それが特別感、差別化を図れる商品だとも思いました」

決断前は不安
踏み出してしまえばワクワクに
そしていよいよ移住のきっかけとなる転機が訪れる。2016年に男の子が生まれたのだった。
「子どもが誕生したことにより、毎日満員電車に揺られ、都会の喧噪の中高層ビルで朝から晩まで働く会社員生活をするより、自分で起業して自然の中でやりたいことをしながら家族みんなで仲良く暮らしていくのもいいのでは、と考えるようになったんです。目の前の仕事とその仕事を定年までずっと続けていくことと、移住をしてその土地で起業して暮らしていくことを天秤にかけて考えると、自分の中で葛藤が起きてしまい、心身ともに疲弊してしまいました。会社に着くと仕事はしますが、それ以外の通勤電車内や昼休みは“人生についてどうすべきか”をいつも考えていて……。気分が落ち込んで、モチベーションを維持、高めることが非常に難しくなってしまいました。社会人19年間、気分を入れ替えてやってきたのですが、それがいよいよできなくなってしまったんです」
こうして2017年8月に脱サラし、9月から3カ月間山形県にある農家レストランのピッツェリアで住み込みで修行。ピッツァ店開業の準備をした上で2018年2月に朝霧高原に移住をした。
「サラリーマンを辞めることは、やはり大きな決断でした。これまでは学校や企業などの肩書きがあって生きてきましたが、それがない『大塚祐介』そのままで生きていくことでどうなるのか、想像がつかなかったんです。でも、決断した後は逆に不安がなくなり、楽しさやワクワクとした気持ちになったんです。『なんだ、全然そんなことを気にして生きていかなくても大丈夫だ』って。そんなことを周囲は誰も気にしていない。要するに自分自身が他人や世間ばかりを気にしていたということなんだと気づいたんです。そして、今やっているピッツァの移動販売はあくまで収入源の一つです。ピッツァ店をやりたいから移住したわけでなく、移住して暮らしていくために選んだ“自分のやりたいことの一つ”ですね」
実践している人を参考にして
理想のライフスタイルを手に入れる
現在、大塚さんは「朝霧高原 あおぞらピッツァ」のオーナーとしての人生を歩み、理想のライフスタイルを目指して日々を過ごしている。
「今は消費に追われない生活になっています。ここでの暮らしもお金は使いますが、都会にいる時と比べたら出ていくスピードがゆっくりになっている気がします。オンラインで買い物ができますし、不便さはあまり感じないです。強いて言えば、光回線が敷設されていないのが一番の不満でしょうか。『朝霧高原 あおぞらピッツァ』は単にピッツァを売っているピザ屋ではなく、これからのライフスタイルとして共感をいただけるように心がけています。生き方、暮らし方の中に“あおぞらピッツァ”があり、その思いや理念のようなものをお客様に直接話をしたり、Facebook、Instagram、Web、チラシなどで発信しています。地方移住や起業、家族との暮らしなど、私が今経験している全体的なことを発信できるように、運営しています」

富士山麓の薪を使い、400度の窯で一気に焼き上げるピッツァは、誰もが食欲をそそられる逸品だ。そして彼がキッチントレーラーを運転し、手作りのピッツァを販売する日々も、2019年4月で1年が経つ。
かつての都内でのサラリーマン生活は、やりたかった仕事とはいえ正直息苦しいと感じていたこともあった。しかし、標高700mに位置する朝霧高原、目の前に富士山が大きくそびえる大自然での暮らしは、趣味であるパラグライダーを堪能することができ、のびのびとした生活ができている。何より、元気よく育つ子どもの成長が見られることが嬉しい。
幸せは、この手で、この体で実感している。こうして今日も、香ばしい本格的ナポリピッツァを、彼は朝霧高原で焼き上げている。

「朝霧高原 あおぞらピッツァ」オーナー。1976年生まれ、神奈川県出身。大学卒業後は、教育関連会社、インターネット広告代理店、ゲーム制作会社、インターネットプロバイダ・携帯会社の4社でのマーケティング、事業立ち上げを経験。2017年8月に脱サラし2018年2月に静岡県富士宮市の朝霧高原に移住し、同年4月末に「朝霧高原 あおぞらピッツァ」をオープン。アースオーブン(土窯)作り、ピザやパン作り、ベーコン作り、味噌作り好き。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント
2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜
2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜
2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。
-
 2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子
2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子「老いると自由を失う」は本当?上野千鶴子さんとスイス在住の介護職・リッチャー美津子さんが対談。リスクより本人の意思を尊重するスイスのケアや、安楽死の現場での葛藤を通じ、最後まで「機嫌よく」生きるためのヒントを探ります。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。