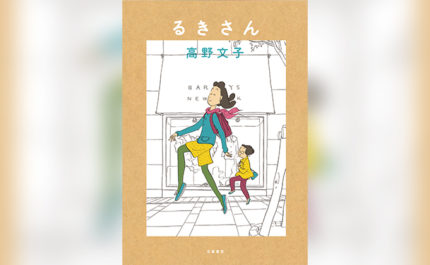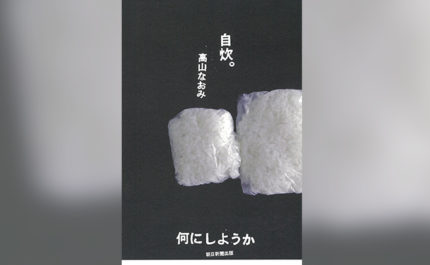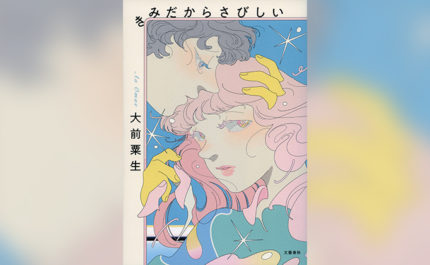男も“らしさ”に縛られていた。──フェミニズムが気づかせた、男性の生きづらさの正体―『私は男でフェミニストです』を読んで―
日常の中で何気なく思ってしまう「できない」「しなきゃ」を、映画・本・音楽などを通して見つめ直す。今回は『私は男でフェミニストです』(チェ・スンボム/著 金みんじょん/訳 世界思想社)から、『男性視点のフェミニズム』について考えます。
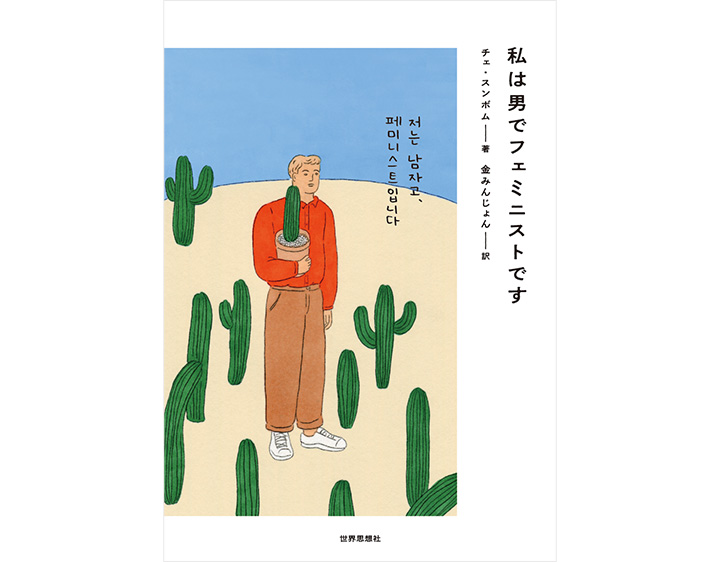
『私は男でフェミニストです』(チェ・スンボム/著 金みんじょん/訳 世界思想社)
毎年6月、世界経済フォーラム(WEF)は各国の男女格差を各国の統計をもとに評価した「Global Gender Gap Report」(グローバル・ジェンダーギャップ・レポート、世界男女格差報告書)を公表する。今年は6月11日に公開され、日本は148カ国中118位と、2024年の118位(146カ国中)からは変化はなかったものの、不名誉な順位だった。
だが、この順位はとてもリアルだ。日本の女性はいまだに「家事は女がするもの」という無意識下に植え付けられたような概念に苦しめられやすい。結婚や出産、育児による女性のキャリア・ブランクは、大きな社会問題でもある。
また、男性は経済力や心身のたくましさなど、「男らしくあること」を求められ、本音を溜め込む。人前で涙を流すことを恥と思う人も少なくないのではないだろうか。
こうした現状を変えるには、自身や相手の性との向き合い方をどう変えていけばいいのだろう。韓国発のエッセイ本『私は男でフェミニストです』(チェ・スンボム/著:金みんじょん:訳/世界思想社)は、そんな難しい問いへのアンサーを導き出す。
分からないから「フェミニズム」を学んだ30代の男子教師
「フェミニズム」は女性の権利獲得から始まったという歴史があるため、“女性の権利を守るための思想”だと思われやすい。だが、本質的には、男女問わず、すべての人が性差別や搾取、抑圧を受けない社会の実現を目的とした活動だ。
男子校の教師であるスンボムさん(30代男性)がフェミニズムを学び始めたのは、20歳の頃だった。周囲からは「男なのに何のためにフェミニズムの勉強をしているの?」との言葉を浴びせられることもあったが、「分からないから学ばないと」と思ったそうだ。
フェミニズムに興味を持ったのには、幼少期の歯がゆい経験が関係している。好きな遊びをしていただけなのに、周囲の大人からは「女の子みたい」と叱られたそう。また、「男は生涯で3度しか泣いてはいけない」という理不尽な価値観に、納得できなかった。
周囲の声に屈し、「男になる努力」に励んだこともある。だが、心が晴れることはなく、むしろ、互いの上下関係を確認した後に胸襟を開いて相手と向き合うなど、目の前に広がる男性社会の“当たり前”にも違和感を募らせていった。
加えて、自身の母が歩んできた人生に「女性軽視」が溢れていたこともフェミニズムを学ぶきっかけとなったという。
母は賢かったが、女性であることを理由に中学校への入学を兄弟に譲らされ、人生選択の幅が狭まった。結婚後は夫から雑な扱いをされ、良き母・良き妻であることを常に求められていたという。
女性性を理由にした理不尽な制限は、かつて日本にもあり、対等ではない関係性の夫婦は今の日本にも意外と多い。だからこそ、スンボムさんの母が経験した痛みを「他人事」と片付けるのは、あまりにも安易だ。
本来なら対等であるはずの男女間で、なぜ性差別が起きるのか。フェミニズムを学び始めたスンボムさんはその背景にはそれぞれの性が抱える生きづらさが関係していることを知り、自分が感じていた“男性性ならではの生きづらさの正体”にも気づく。
それと同時に、社会に根付く「女性軽視」が自分の無意識下にもあったと知り、女性性に対する考え方も変化していった。
男が泣いたっていい… “囚われていた男性性”から解放してくれた「フェミニズム」
スンボムさんいわく、フェミニズムは以前とは異なる視点から現実を客観視させてくれるものだという。不条理を認識するように誘導して不条理を正す勇気をくれ、自分を犠牲にせずに生きていける人生を考えられる思想であるからこそ、男性にも有効であると語る。
力と勇気、意思と節制に代表される固くて狭い枠にとらわれた男性性から救い出してくれる。泣く男、しゃべる男、力のない男でも大丈夫だと勇気づけてくれる。
『私は男でフェミニストです』(チェ・スンボム/著 金みんじょん/訳 世界思想社)P47より引用
まだまだ男性が優遇されやすいこの国で生きていると、女性としては「男性」という性が羨ましく思えることもある。だが、男性には「家父長制度」という歴史が深く関係している“男性特有の生きづらさ”があるとスンボムさんは打ち明ける。
苦しい時でも泣けない、酒に酔わないと本音が吐き出せないなど、“男らしさの呪縛”は根深くて重い。そうした見えない苦しみを抱えている男性はきっと自分の身近にもいる。そう気づくと、女性側も男性性の捉え方が少し変わる。
自分を押し殺し、耐え続ける人生は誰だって苦しい。そうした辛さは虚勢で一時的にごまかすことはできるが、根本的な部分と向き合わない限り、苦しみはつきまとう。自分を救い、違う性の相手が抱える痛みを想像するきっかけを得るためにも、本書が男女問わず、多くの方に届いてほしい。
なお、本書は、スンボムさんがフェミニズムを自身の中に落とし込んでいく過程もリアルだ。夜道を歩く時、男性が歩いていると怖いと話す後輩の言葉を受け、「すべての男性が潜在的な加害者ではない」と憤った日のことや、自分自身も問題意識や罪悪感を持たずに周囲の女性の価値を外見で決めていたと気づいた日のことなども包み隠さず綴られている。
そのため、これまでジェンダー問題をあまり気にかけてこなかった男性も、時には共感しながら、自分が当たり前だと思っていたジェンダー観の歪みに気づくことができるはずだ。
育休を取る男性が増え、ジェンダー平等に向けた法整備を求める声も多くなるなど、社会は今、少しずつ変わろうとしている。だが、法の制定だけでは意味がない。本当に大切なのは、人々の意識が変わることだ。
例えば、スンボムさんいわく、男性から女性に対する性差別的な発言への忠告は男性が行うと、スムーズに受け取られやすいそう。また、女性軽視の発言がなされた時に同調して笑わないことや、夜道で自分より前に女性がいた時はしばらく待ってから後ろを歩くなどの配慮も性の尊重に繋がる。
自分とは異なる性別の相手をどう尊重し、自分の性も守っていくか。スンボムさんのように日常生活の些細な場面からジェンダー平等を意識し、行動を変えることができたら、人は男性と女性ではなく、“ひとりの人間”として分かり合うことができるのではないだろうか。
持って生まれた性に関係なく、フェミニズムを学ぶことは丸い社会を実現するひとつの手段となる。
文=古川諭香
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」