人生は一本ロード、なんてない。
1990年代、「トゥギャザーしようぜ!!」など英語と日本語交じりの言葉遣いと、海パン姿の個性あふれるキャラクターで一世を風靡したルー大柴さん。その後、いったんテレビの出演は減るものの、2000年代に入りNHKみんなのうた「MOTTAINAI」をきっかけに再ブレイク。現在は、タレント・役者だけでなく、茶道師範・大柴宗徹としてお茶の魅力を広めるなど、幅広い分野で活躍している。60代になっても新しいチャレンジを続けるルーさんに、その半生を振り返りながら、心豊かな人生を送るヒントを伺った。

「人生100年時代」といわれる。日本政府は2017年に「人生100年時代構想会議」を設置。生涯にわたる学習の重要性を説き、高齢になっても活躍できる社会の実現を提唱している(※1)。また、「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、企業は70歳まで就業機会を確保することなどが求められている(※2)。60代・70代になっても働くことが当たり前の時代がすでにやってきているのだ。そんな社会で、年齢を重ねても現役として活動するにはどうすればいいのか? 芸能界という浮き沈みが激しい業界で活躍し続けることは、並大抵のことではない。世に出るまで長い期間を要する方も少なくない中、ルーさんも30代中頃でブレイクしたが、自分の夢と、名前を売るためのキャラづくりとの板挟みに苦労した。そのひたむきな姿に、「挑戦するのに遅すぎるなんてことはない」と気づかされる。
※出典1:厚生労働省 「人生100年時代」に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207430.html
※出典2:厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
“ライフ・イズ・ワンス”
花は開かないかもしれないけど、チャレンジしてみよう
「ルー大柴」を演じたらファイアがついた
ルーさんの活躍を全国の人が目にするようになったのは、ルーさんが30代中頃の時期だから、“遅咲き”といえる。ブレイク前の20代~30代前半はどのように過ごしていたのだろうか?
「すべてのきっかけは幼稚園の学芸会でした。演技することにとても楽しさを感じたんです。それ以来、ずっと役者を目指してきました。私の実家は印刷屋だったので、『印刷屋の若旦那になれ』と言われていたんですが、役者になるのが夢でしたから家を出たんです。勝新太郎さんが主宰していた勝アカデミーに入って、講師の岸田森さん(※)にかわいがってもらったりしたんですが、芽が出なくてね。自分は『ダメな人間』と思い込んでいました」
※俳優。演劇学校の勝アカデミーで審査員を担当しており、オーディションでルーさんを見て、演技を高く評価してくれたという。
売れることを目指し奮闘していた30代の頃、ルーさんは結婚し子どもも生まれたが、アングラの劇団で細々と役者をしている状態だった。
「ある日、母から『もういいじゃないか』『夢なんかあきらめろ』『女房子どもを泣かすな』と一喝されました。真面目に子育てをしないといけないと思いながらもなかなか腰を上げられなかったのですが、母のこの一言で火がつきました。当時はバブルの最後の時期だったんで、いいアルバイトがけっこうあったんですよ。結婚式の司会、ポスター貼り、ティッシュ配りとか。それでなんとか生活はできていました。役者の夢に未練を持ちつつも、『じゃあ、何するんだ?』と、どんなビジョンで生きるか迷っていましたね。『チャンスにつながるかも』と思ってモデルをやっていたら、パンフレットに名前を載せてもらえるようになったりしました」
このパンフレットがルーさんの人生を大きく変えるきっかけとなる。
「関根勤が友達のところでパンフレットを見て『なんだこれは!?』って思ったらしく、小堺(一機)と一緒にやっていたラジオ番組『スーパーギャング・コサキン無理矢理100%』にゲストで出てくれって頼まれたんですよ。小堺とは勝アカデミーの同期で、関根とも面識があった。ラジオの話は最初お断りしたんだけど、『一回出てみようか』と思って出演したんです。そうしたらファイアがついちゃって」
ルーさんの独特の持ち味がリスナーに受け、一気に番組の人気者になった。アルバイト生活を脱し、関根さんや小堺さんと同じ芸能事務所・浅井企画に所属。関根さんの主宰する劇団「カンコンキンシアター」の旗揚げにも参加し、劇団の看板役者として圧倒的な存在感を見せた。テレビ番組やCMなどに出演するようになると、ルーさんの“クドい”キャラクターは大ヒットした。
とはいえ、海パン姿でパフォーマンスをする姿は、ルーさんが目指していた役者像とは異なっているようにも思えるのだが。
「当時は30歳を過ぎていて崖っぷちでした。まあ、いつも崖っぷちなんだけど(笑)。まずは名前を覚えてもらうのが先決だったんです。そうしないと仕事につながらないですから。『ルー大柴』を演じることで世間に知ってもらい、それから役者業に専念しようかとね」
ルーさんの思惑どおり、「トゥギャザーしようぜ!!」などのルー語とともに、「ルー大柴」の名は全国に広まっていった。1992年には第29回ゴールデン・アロー賞芸能新人賞を受賞する。

「街を歩いていても『ルーさんだ!』と言われたりして、世間に自分のことを知ってもらえたという満足感がすごくありました。心の中で『俺、やったな!』と思いましたよ。『これでいつ死んでもいい』と(笑)。20代に売れなかったことが想像できないほどスケジュールが埋まって、寝るヒマがないくらい。何カ月か浅井企画で売上がナンバーワンだったこともあります(笑)。『夢なんかあきらめろ』なんて言っていた母は『お前はいつかやる人間だと思っていたよ』って。『いい加減にしてくれよ』って思いましたけど(笑)。あの当時やっていたことがブラッド・アンド・ミート、今の私の血肉になっていますね」
「ルー大柴」にタイアードしたから捨てた
順風満帆に思えた芸能生活だったが、ルーさんは少しずつ違和感を覚えるようになる。
「自分のキャラクターが10だとすると、当時の『ルー大柴』は1の部分なんですよ。ほかの9は全く違う。その1を演じたらウケたんですね。でも、どこへ行っても『ルーさん、テンションアップでお願いします』とか『なんかあったら邪魔してください』って言われて、求められる『ルー大柴のキャラクター』を演じるのに疲れてきて。ああいう『ルー大柴』もあっていいんだけど、オールウェイズそれだと、とてもタイアードになってしまう。本番で力も入らない。それで、だんだん“商品価値”がなくなっていってしまったんです」
やがて活動の軸足を舞台に移すようになる。次第にテレビでルーさんの姿を見かける機会は少なくなっていった。
「当時は、年に何回か舞台に立っていました。だいたい4番手ぐらいの役で。収入は減りましたが、なんとか食いつないでいました。最初はおもしろかったですよ。『ライフ・イズ・ワンス(人生は一度きり)、やってやろうじゃないか!』『今日、俺は舞台で死ぬ』なんて意気込んでいました。ただ、どんな役でも、あくまで『ルー大柴』がやっている芝居という感じで、みんなが持っている『ルー大柴』像をまだ演じている気がしていたんです。40代半ばでしたが、『これからどうしようか?』とジレンマにも陥った時期でした」
ルーさんにとって、ラジオ「コサキン」以来の転機が訪れる。NHKみんなのうた「MOTTAINAI」が子どもたちの間で話題になったのだ。これをきっかけに、テレビ出演はもちろん、環境活動にも注力するようになり、再び世間から注目され始めた。ただし、かつてのアクの強い「ルー大柴」の姿はそこにはない。
「昔の『ルー大柴』は捨てました。昔があるから今があるのはわかるんだけど、50歳を過ぎたら新しいものに挑戦して、別の武器を持たないといけないと思ったんです。かつての『ルー大柴』像は強すぎました。だから消すのも大変(笑)。完全に消えたのはここ5年ぐらいじゃないでしょうか」
新たな「ルー大柴」像を創りあげたのは、じつはルーさん自身ではない。陰の功労者がいる。マネージャーの増田順彦さんだ。
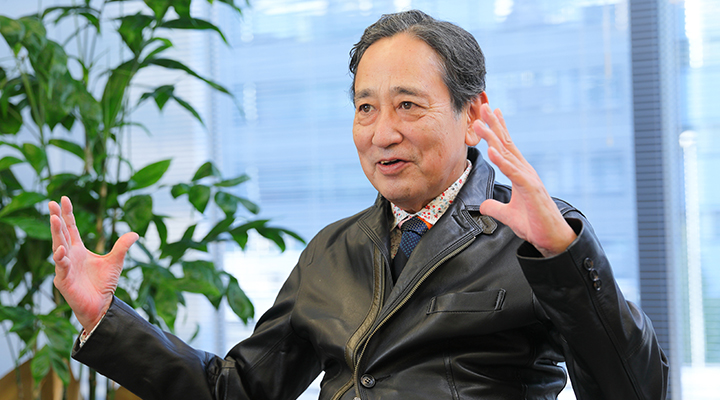
「『MOTTAINAI』をやったり、ブログを始めたりしたのは、裏で増田が考えてくれたことなんです。増田は私にないものを持っていて『こうしたほうがいいんじゃないですか?』と、いろいろ提案をしてくれる。私はそれを素直に聞いて、うまくできるよう努力していたら、この年になってリトルビット、少し花開いたわけです。ダメだったこともいっぱいあるんだけどね。これはデスティニーだと思っています。いろんなことの積み重ねで今があるし、ムダの中にも宝がある」
ルーさんと増田さんの関係は、ほかのタレントとマネージャーのそれとは異なっている、という。そこに再ブレイクの秘密がありそうだ。
「タレントが売れたり、年をとったりするとマネージャーの言うことを聞かなくなるものです。反対にタレントが若いうちはマネージャーのほうがきつかったり。それでダメになってしまうことも多いんです。でも、私は年下の人の意見を聞くのもインポータントだと考えていて、増田と私は“二人スリー脚”でタレントとマネージャーの垣根がなく、トゥギャザーで戦略を立てています。まさに運命共同体。これは珍しい関係だと思います」
ルー大柴にニーズがあるうちはライフ懸命やる
ルーさんはタレント・役者として活躍する一方で、茶道師範・大柴宗徹としての顔も持つ。ルー大柴とティー道(茶道)。奇妙な取り合わせにも思えるが、なぜティー道を始めたのだろうか?
「これも増田くんの戦略ですね。芸能人がやっていないことをモノにしたらいい感じだし、異質な組み合わせが受けるんじゃないか、と。最初はやる気はなかったんです。お稽古はしてみるけど、無理かもしれない。でも、『嫌だ』って増田に言って『だからルーさんはダメなんですよ』って返されたらしゃくだなあと思い、お稽古に通うことにしました。そうしたら、少しずつティー道の作法が身についていって、師範をいただくところまでいきました。人生はロング、人間いつ死ぬかわからないけど、チャレンジする気持ちをなくしたら、そこで終わっちゃう。『人生こんなもんでいいや』ってあきらめていたら、ティー道もゲットできなかったでしょうね」
最近も、世間がルーさんに驚かされる出来事があった。特撮Webドラマ『仮面ライダー BLACK SUN』で、主人公たちに敵対する総理大臣として登場。その怪演ぶりに視聴者たちは舌を巻いた。
「『岸田森さんが降りてきたんじゃないですか』なんて増田と話していました。ただ、最初はうまくいかなくてね。長編ドラマはずっと出ていなかったし、セリフも長いし、主人公より出番が多いし(笑)。でも、『ここで失敗したら申し訳ない』と思って、役者を目指してがんばっていた若いころを思い出しながら、集中して役に入り込むようにしました」
ルーさんが幼稚園の学芸会で役者を志して以来、60年あまりの紆余曲折を経て、目標が本来のカタチで結実したことになる。
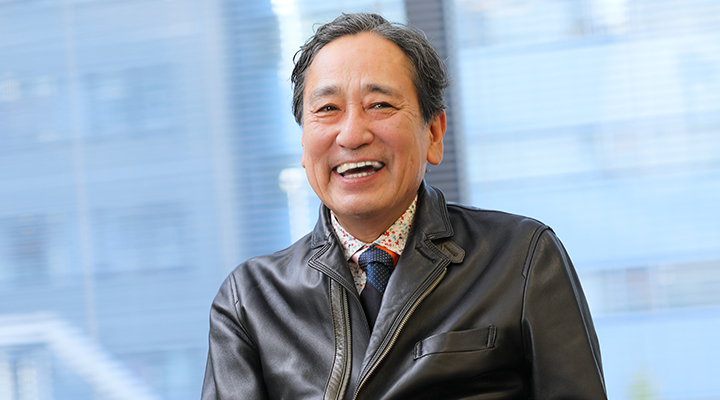
「この年になって大きな役をいただけたのはサプライズでした。今後も『ルーさん、これやっていただけますか?』『こういう役なんだけど、お願いします』と依頼されて、自分ができそうならお引き受けしたい。68歳の私にもニーズがあるなら、“ライフ懸命”(一生懸命)やっていきたいと思っています」
夢は必ずかなうとは限らない。しかし、実現の可能性を少しでも高めることはできる。その方法の1つが、「人生こんなもんでいいや」とあきらめず、ルーさんのように何歳になっても新しいチャレンジを続けることなのかもしれない。
取材・執筆:米田政行(Gyahun 工房)
撮影:内海裕之
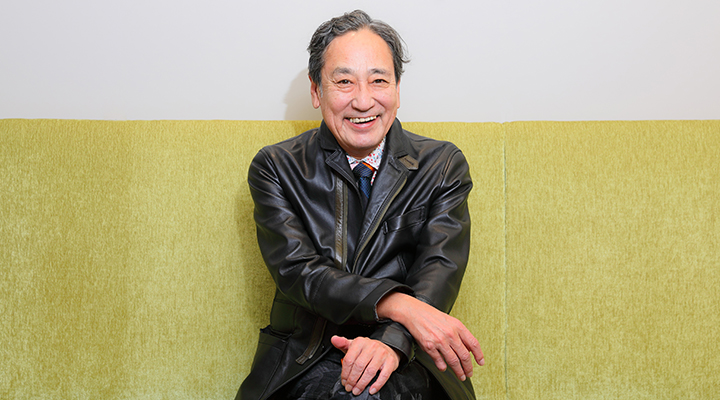
1954年、東京生まれ。俳優・タレントとして日本語と英語をトゥギャザーした話術を使う独自のキャラクターで脚光を浴びる。2007年、NHKみんなのうた「MOTTAINAI」をきっかけに、富士山麗の清掃や地域のゴミ拾いをするなど環境活動にも積極的に取り組む。趣味はドジョウやメダカの採集、水墨画。芸能活動のほかに、茶道・遠州流師範、山野美容芸術短期大学客員教授も務める。
ルー大柴オフィシャルブログ TOGETHER Web
みんなが読んでいる記事
-
 2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子
2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。
-
 2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと
2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。
-
 2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会
2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。
-
 2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)
2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。
-
 2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題
2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。








