結婚できない女性はかわいそう、なんてない。
東大卒、財務省入省、ニューヨーク州弁護士資格取得と、誰もが認めるエリート街道を歩んできた山口真由さん。だが、30代後半に待ち受けていたのは「結婚できない女はかわいそう」の大合唱だった。彼女が考える日本の家族や法律の問題点、アメリカとの比較、親に自分の考えを理解してもらうために必要な姿勢について伺った。

専業主婦として会社員の夫を支え、2人の子どもに恵まれる――。こんな典型的な「女の幸せ」の形は今、揺らいでいる。いわゆる生涯未婚率やひとり親世帯の増加、LGBTQ+カップルの社会的認知の高まりなどを受け、家族や夫婦のあり方も多様化。にもかかわらず、いまだに結婚や出産のプレッシャーにさらされ続ける女性は多い。39歳独身、アメリカで「家族の多様性」を学んだ山口さんは、日本の家族の画一化に疑問を投げかける。
“古くさい考え”の排除と“ふつう”の強制は同じ。相手が攻撃していると決めつけないで
35歳を過ぎて結婚しないのはイタい女?
財務省を退官後、ハーバード・ロー・スクールに留学した山口さん。そこで夫婦・親子・相続など家族関係を規律する「家族法」と出合い、現在も研究を続けている。2021年に発売された著書『「ふつうの家族」にさようなら』は、家族の本質とは何かを問い直した一冊だ。
そもそも山口さんが“ふつうの家族”に疑問を持ったきっかけは何だったのだろうか。幼少期にさかのぼって聞いた。
「私の家は両親と妹の4人家族です。私は少し不器用で間の悪いところがある子どもでしたが、両親は愛情深く育ててくれたと思います。
いわゆる一般的な家庭で育ちましたが、“ふつう”から外れることには大きな恐怖心を抱いていました。その一因は、当時通っていた中学校で非常に強い同調圧力があったこと。いじめなどの標的にされないためには皆と同じことを同じようにやらなくては、という強迫観念に悩んだこともありました。
でも、いかに周囲からはみ出さないかを考えていた私が35歳を過ぎてアメリカ留学から帰ってきた時、初めて“ふつう”の概念に違和感を覚えたのです。同級生は皆、結婚して子どもがいる。『結婚したほうがいいよ』『その年で結婚をしていないのはおかしいよ』って何の疑問もなく言われて。
私がいくら『幸せだよ』と説明しても全く分かってもらえないし、説明すればするほど“イタい女”になる。その時、日本には結婚や家族に対して画一的なイメージがあり、それが未婚の女性にとって居心地の悪さにつながるんだと気づきました。そこで、日米の家族を研究対象にしようと決めたのです」

アメリカで「家族とは多様なものである」と学んできた山口さんにとって、帰国後のギャップは非常に大きかった。しかしそこで、自身の研究の目標が見えてきたと話す。
“家族”は法的定義の曖昧な社会通念
実は、日本人の多くが抱く「結婚」のイメージは世界共通の認識ではない。山口さんによると、アメリカでは歴史的に3つの大きな潮流があったという。
まずは、「結婚制度」そのものを破壊し、個人と個人が自由に契約を結べる形にしたのが1970年代のこと。その後、同性パートナーシップを法的に承認する「シビルユニオン」が2000年にバーモント州で初めて成立。このまま「法律婚に準ずる事実婚」が広がりを見せるかと思いきや、2015年、連邦最高裁判所により同性婚が憲法上の権利として認められた。それにより社会にもう一度、法律婚を尊重する流れが生まれているという。
「日本で結婚(法律婚)は、役所に男女が婚姻届を提出する『届け出婚』を意味します。一方アメリカでは、儀式を行うことで婚姻が認められる『儀式婚』のほか同棲が正式の結婚と認められる『事実婚』など、いくつか種類があります。
日本の制度はあまりに画一的で、『結婚』か『未婚』の2択しかありません。さらに、法律婚は税制、福祉、相続などあらゆる面で優遇されます。これでは公に『結婚は最良の選択』と言われているようなもので、制度に当てはまらない人たちを疎外することにつながります。もう少し選択肢が増えればいいなと思いますね」
欧米と比較すると、日本で事実婚を選択するカップルや婚外子の割合は少ない。日本人は全体的に保守的なので、なかなか既存の概念を打ち破れないと山口さんは言う。
「家族というと、一般的には婚姻でつながった夫婦や、血縁でつながった親子関係を指します。しかし、日本もアメリカも、法律上は“家族”に明確な定義はありません。
実際、日本の法律で家族の単位は微妙にズレるんです。例えば、事実婚で相続は認められないけど財産分与は認められますし、医学的に家族の同意が必要な場合、医事法の観点で言うと『同居者』が家族と見なされます。だから、法律上は家族の捉え方が定まらなくても特に問題ないのかもしれません。
“家族”は法的な定義を超えていて、より強固な社会通念の中に出来上がっていると言えるでしょう」
法律上、実は曖昧だという家族の形。時代とともに社会構造も変わり、「家族は素晴らしいもの」「結婚こそが幸せだ」という概念はもはや幻想と言えるのかもしれない。
「結婚しないの?」と聞かれても、攻撃されていると決めつけないで
一方で、結婚や出産に関してデリカシーのない質問をされたり、親からのプレッシャーを感じたりした経験のある人は多いだろう。山口さんも、親との関係に悩んだことがあると語る。

「正直に言うと、両親と結婚に関する話はあまりしたことがありません。子どもを持たないとなると、両親から無限に注がれた愛情を自分の世代で止めてしまうかもしれないと感じることもあります。二人とも見守ってくれてはいますが、自分の中で葛藤はいまだにありますね。
ただ、そのあたりの複雑な感情も含めて、頑張って説明してみるのは大事なんじゃないかと思います。『なんで結婚しないの?』『早く孫の顔を見せて』と言われると今の自分を否定されているような気がするからほかの問題よりも話しにくいし、感情的になる。
でも、踏み込んだ話をすることを避け、受け流し続けた結果が今の社会をつくったことを、そろそろ実感しなくてはいけない時期がきたのかもしれません。
私もステレオタイプに乗っかって自分の生きづらさを増幅してしまうことがないよう、メディアで発信する時などは注意しています」
家族の多様化は、急速な高度経済成長が終息した1970年代後半から顕在化した現象といわれる。それ以前の世代にとって、今の世代の幸せはなかなか実感しづらい点もあるかもしれない。だが、山口さんは家族法の歴史や体系を学んだことで、保守的な人たちに反発する気持ちが和らいだと話す。
「近年、日本でもアメリカでも、『家族』に対して保守派とリベラル派との間で分断が始まっています。社会の革新的変化に寛容なアメリカのリベラル派にはいいところもありますが、メインストリームになじまない意見が排除されてきた歴史も忘れてはならないと思います。
未婚の女性にとって大事なのは、自分が攻撃されていると思い込まないこと。“古くさい考え”を排除しようとするのは、“ふつう”であることを強制するのと何ら変わらない同調圧力の一種です。それぞれの人が置かれたヒエラルキーや社会的背景を知ることで、なぜその考え方に至ったのかが理解できるようになります」
自分の考えを尊重してほしいと思うのであれば、相手の育ってきた環境や価値観も受け入れることが大切なのかもしれない。
マイノリティ精神を忘れない
著書『「ふつうの家族」にさようなら』を発売した時、意外にも既婚の女性から「考えさせられた」とのメールが多数届いたという。既婚者も同じように葛藤を抱えていることが分かり、温かい気持ちになったと話す山口さん。これから目指す生き方を尋ねると、「マイノリティの感覚を忘れずにいたい」との答えが返ってきた。

「マジョリティ、マイノリティの考え方はとても相対的で、マジョリティと思われている人の中にもマイノリティな部分があるものです。例えばジェンダーの観点で男性は“強者”と見なされますが、一方で『一家の大黒柱にならないと』など、強固なステレオタイプを背負わされているとも言えますよね。そういう意味では、男性にも弱者と呼べる部分はあるのかもしれません。
私の経験で言うと、アメリカ留学中、英語が話せないことで『自分はここではマイノリティなんだ』と強く実感しました。クラスメイトの無視するような態度に傷つきましたが、『私はかつて他人に同じことをしたことがなかっただろうか?』と反省するきっかけにもなりました。
自分がマジョリティ側にいる時って、マイノリティのことは全く無関心なんです。私は子どもの頃、先生から『お父さんとお母さんに感謝の手紙を書きましょう』と言われても、何の疑問も持っていませんでした。でも今振り返ると、父子家庭や母子家庭の子もいたし、複雑な家庭環境で悩んでいる子もいたと思うんです。
マイノリティの存在を私たちがつねに自覚していないと、社会で多様性が受け入れられるようにはならないのではないでしょうか」
家族の数だけ形があり、誰もがマジョリティの要素とマイノリティの要素を持ち合わせている。互いの中に潜むマイノリティな部分を自覚し、受け入れ、対話を繰り返す。認識の溝を埋めていくには、粘り強い努力が必要なようだ。
取材・執筆:酒井 理恵
撮影:内海 裕之

1983年生まれ。北海道出身。東京大学法学部卒業。卒業後は財務省に入省し主税局に配属。2008年に財務省を退官し、その後、15年まで弁護士として主に企業法務を担当する。同年、ハーバード・ロー・スクール(LL.M.)に留学し、16年に修了。17年6月、ニューヨーク州弁護士登録。帰国後は東京大学大学院法学政治学研究科博士課程に進み、日米の「家族法」を研究。20年、博士課程修了。同年、信州大学特任准教授に就任。21年より現職。著書に『「ふつうの家族」にさようなら』(KADOKAWA)などがある。
Twitter @mayuyamaguchi76
山口真由オンラインサロン 真由'sミーティング
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
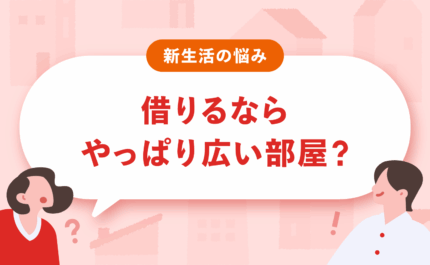 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
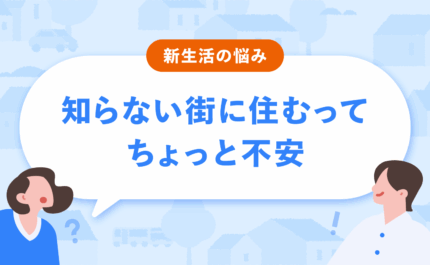 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
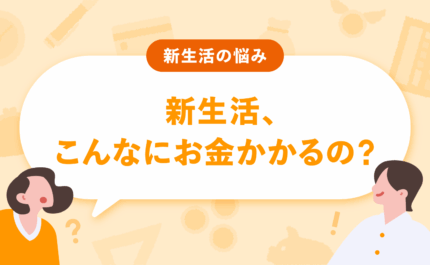 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
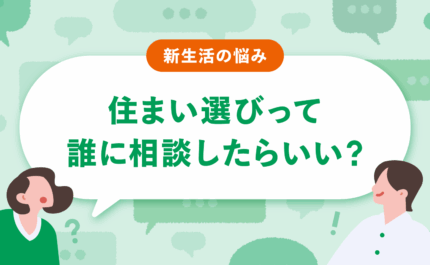 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。













