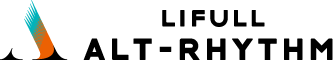LGBTQ+は “ LGBTQ+らしく” いなきゃ、なんてない。【後編】
建築デザイナー、コンサルタントとして働くサリー楓さん。慶應義塾大学院在学中に社会的な性別を変えたトランスジェンダーの当事者として、LGBTQ+にまつわる発信を行うモデルの顔も持つ。
「日常を生きるトランスジェンダー」のロールモデルになりたいと、世界的なビューティーコンテストへの出場を決意した楓さん。主演を務めたドキュメンタリー映画撮影の過程で「ダイバーシティ(多様性)の本質を見た」と語る真意とは。LGBTQ+を取り巻く日本社会の現状と課題、インクルーシブ(包括的)な社会に必要なことについても伺った。
連載 LGBTQ+は"LGBTQ+らしく"いなきゃ、なんてない。

前編では、大学在学中に周りにトランスジェンダーであることをカミングアウトしたこと、念願の建築設計事務所に入所し、夢への第一歩を歩み始めたことについて伺った。「私はたまたま、性のあり方に関して寛容な環境に身を置いていた。恵まれていたんだなって気付いたんです」と話し、ありのままの自分の姿を発信して『日常を生きるトランスジェンダー』のロールモデルになりたいと、胸中の思いを語っていただいた。
後編では、意を決して出場することになったトランスジェンダーのビューティーコンテストに端を発したドキュメンタリー映画への出演やメディアを通した発信活動についてお話を伺う。“ジェンダーのボーダーを越える”とはどういうことなのか。
トランスジェンダーであることは
私の大切な要素の一部であっても、
私のアイデンティティの全てではない
「息子のままで」“受け入れられない”父の愛情
コンテスト出場に向け、厳しいトレーニングの日々が始まった。コンテストでは、ファッションショーのように高いヒールを履いてランウェイを歩く。日常生活でヒールを履くことも、ウォーキングやダンスのレッスンを受けたこともなかった楓さんは、最初は苦戦したそうだ。
「ウォーキングのレッスン中、トレーナーに私がこのコンテストにかける思いを話したことがありました。『日常を生きるトランスジェンダー当事者として、この大会に出場することに意味があるんだ』と。
すると、彼からコンテスト以外でも発信する場を設けた方がいいと提案されて。コンテスト出場の過程や私の日常に密着したドキュメンタリーを撮ることになったんです」
思いがけず決まったドキュメンタリー映画撮影。楓さんの日常を追った映画のひとこまには、父親と対話するシーンも含まれている。
「私がメイクした姿をSNSに載せていたのも見ていたみたいで。でも、私の口から話したのは初めてでした。父に話すと『学校はどうするのか』『就職できるのか』とも言われました。そう思うのも無理はないと思っています。だって、社会で“普通”に日常を送るLGBTQ+の姿って、あまり知られていないから。父は理解しようと精一杯努めてくれていたようですが、それでもすぐに受け止められるものではない、と言われました。
ダイバーシティ(多様性)が叫ばれて、『LGBTQ+には理解を示さないと』という同調圧力も少なからずある中、表面上で理解した気になるのではなく、葛藤や複雑な胸の内をありのまま伝えてくれたのはうれしかったです。決して美談でもなく、ドラマティックな展開でもないけれど、ダイバーシティの本質を突きつけられた気がしました」
完成した映画は世界で上映された。国内向けにつけられた邦題は『息子のままで、女子になる』だった。そこには、撮影を重ねる中で起こった楓さんの心境の変化が表れている。

「LGBTQ+当事者を取り巻く社会はなんて不寛容で、理解がないんだろう。私はこれまで、そう思っていたんです。でも、必ずしもそうではないのかもしれないなって。当事者のまわりに生きる人たちと話す中で、『受け入れられない』という人たちにも、彼らなりの正義があるんじゃないかと気付いたんです。
それは、カミングアウトをした私に『それでも息子だと思っている』と話す父の姿を見て、強く実感しました。18年間、父は『息子』として、私にたくさんの愛情を注いでくれていたからです。私のアイデンティティを受け入れられないのは、父なりの愛情や正義がある。それが私自身にとって、大きな気付きでした」
男らしさ、女らしさ。そして“LGBTQ+らしさ”
現在も建築設計事務所でデザイナー、コンサルタントとして働く楓さん。トランスジェンダーの「新しいアイコン」としてLGBTQ+に向けた講演会を行うなど、発信活動にも精を出す。
「カメラに映ること自体に重きを置いているというより、メディアを通して私の存在を知って、ジェンダーに関する正しい知識にアクセスするきっかけになればと思っています」
そんな楓さんは、LGBTQ+を取り巻く日本社会の現状についてどう思うのか。
「男性として生きていると『男性らしさ』を求められますよね。それが嫌で女性として生きようとすれば、『女性らしさ』を押し付けられる。そしてトランスジェンダーだとカミングアウトをすれば、今度は“LGBTQ+らしく”あれ――。つまり、世間一般の『平均的なLGBTQ+のイメージ』をあてがわれるんです。
例えば『美容とかファッションに詳しいんでしょ』とか『面白いことやってよ』と言われたり。あとは差別や偏見を苦労して克服するまでの“大変だったエピソード”を聞かれることもあります。結局どう生きようとしても、既存のジェンダーの枠組みにカテゴライズして捉えられてしまう。
もちろん、ジェンダーについて葛藤や悩みがなかったわけではありません。ただ一つ強調したいのは、トランスジェンダーであることは私の大切な要素の一部であっても、私のアイデンティティの全てではないということです。大学に通い、夢が叶って建築家として働いている。それが私です。だから『トランスジェンダーらしく』振る舞おうと思っているわけではありません」
ダイバーシティ(多様性)がうたわれ、LGBTQ+についても少しずつ理解が広まってきた。社会は一歩前進しているように見えるが、楓さんはまだLGBTQ+について誤った認識が広まっている点があると指摘する。
「企業もD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)が求められるようになり、多様なアイデンティティを受け入れることは企業努力の一つとして重視されるようになりました。
一方で、昨今の議論を見ていると『LGBTQ+に関する問題は福祉活動』と捉えられている面があるように感じていて。つまり、LGBTQ+当事者と共に生きていくためには、手を差し伸べたり助けてあげたりする必要がある、と認識されている側面があるのではないかなと。
『SDGsの一つ』とも誤解されがちですね。SDGsの目標の中に『ジェンダー平等』は含まれていますが、LGBTQ+に関する課題は入っていないんです。『何か社会に良いこと』くらいに思われているのだとしたら、もう一歩社会が進む必要があるかな」
建築家、モデルとしてボーダーを越えていく
建築家とモデル――。一見すると結びつかない肩書きだが、どちらも楓さんにとって自身を表現できる大切な仕事だ。そして、それぞれの活動を通して伝えたい軸も、実は一つだという。

「大学を卒業する時、ゼミの先生からもらった言葉がずっと心に残っていて。『あなたがボーダーを乗り越えた経験を、建築の仕事に生かしてください』と言われたんです。トランスジェンダーというのは、その名の通り『ジェンダーというボーダーを“越境”した人』。実は建築にとっても“越境”ってとても重要で。
例えば都市や空間の設計には、使う『言語』や規範が異なるさまざまな関係者を巻き込み、対話していく必要があります。つまり『ボーダーを超える』ことで一つのものをつくり上げるのが私の仕事なんです。建築家としても、“越境”を目に見える形で見せていきたいですね」
LGBTQ+当事者としての発信活動については、「ジェンダーレスを次の段階に進めたい」と話す。
「私はトランスジェンダー当事者として発信活動をしていますが、どちらかというとジェンダーレスに近い存在だと思っています。これまでジェンダーレスといえば『中性的』とか『ジェンダーを感じさせない人』と定義されてきましたが、私にとっては『“男らしさ”も“女らしさ”も両方楽しむ』ことじゃないかなと思っていて。
ジェンダーのボーダーを超えて、男性・女性両方の性を自由に行き来して楽しむ。そんな新しいジェンダーレスのあり方を提示していきたいです」
『You decide.(あなたが決める)』――。“越境”を続ける楓さんの姿は、あなたの目にどう映るだろうか。ジェンダーに限らず、私たちをカテゴライズするボーダーを軽やかに“越境”していく。
「こうあらねば」の呪いを解くことは、誰しもが自分らしく生きられる社会への第一歩なのかもしれない。
取材・執筆:安心院彩
撮影:阿部健太郎

1993年、京都府生まれ、福岡県育ち。建築デザイナー、モデル。ブランディング事業を行う傍ら、トランスジェンダーの当事者としてGSM(Gender and Sexual Minority)に関する発信を行う。建築学科卒業後国内外の建築事務所を経験し、現在は日建設計にて建築と都市のコンサルティングを行う。
Twitter @sari_kaede
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。