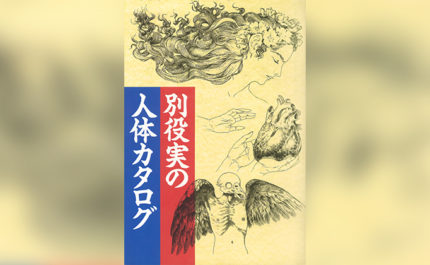“男らしさ“に乗っかりさえすれば幸せになれる、なんてない。
ジェンダーに関する報道が日々取り沙汰される中、エンターテインメント業界にも例外なく時代の変化が訪れている。立場ある男性による女性へのセクシュアルハラスメント被害などの背景には、業界に根付いた「男社会」やその根幹にある「男らしさへの呪縛」といった影響もあるのではないだろうか。
そのような中、男性たちは「男らしさ」とどのように向き合っていけばよいのか。芸人・ミュージシャン・俳優・文筆家とさまざまな分野で活躍し、独自の視点で世の中を観測し続けるマキタスポーツさんに話を伺った。

女性のことは大事に思っているけれど、かわいいからついからかってしまう……そんな経験がある男性は少なくないはずだ。そしてその「からかい」がエスカレートして誰かを傷つけたことや、同性の友人の手前思ってもいない振る舞いをしたことのある男性もまた、同様に少なくないかもしれない。しかし時代は変わりつつある。「かっこいい男」に憧れお笑いの世界に飛び込み、自身も多くの男性の心をつかんできたマキタスポーツさんが考える「男らしさ」との向き合い方とは。
今までが楽だったから自分を変えない、っていうのはいつか損するよ?と男性たちに言いたい
“敬い”を保険に、女性をこき下ろして男性同士で満足していた
約1年半前、とあるインタビューでマキタスポーツさんが高校生の娘さんに「これからは“男らしさ”“女らしさ”があれば大丈夫という時代ではなくなる。『あなたらしさとは?』が問われる時代になる」と語っていたことが話題となった。ホモソーシャル(※)が形成されやすい業界でどういった経験からそうした考えに至ったのか。始まりは幼少期にさかのぼる。
※ホモソーシャル
恋愛や性的な意味を持たない、同性同士の絆やつながり。男性間に流れる「男ならこうあるべき」といった空気を指すことも多い。
「僕は1970年生まれで、物心ついた時から“男の子でしょ”としつけのレベルで言われてきた世代なんですよね。きょうだい喧嘩で負けて泣いていれば『男の子なんだから泣いちゃダメ』と言われるような。
僕自身は口数も少ないタイプで、体も小さかった。そうすると、自分より大きな女の子に体力で負けることも言い負かされることもしょっちゅうあった。すると『女に泣かされてどうするんだ!』って叱られるのが当たり前。田舎で、両親は昭和一桁代の生まれで戦争経験者ですし、そういった原体験はやっぱりどうしてもありますね」
「男とは強いもの」という“常識”を擦り込まれながら、青年期を迎える。

「思春期ぐらいになると、今度はそれなりにませてきて、口も達者になってきてね。女の子の外見を何かに見立ててからかって。それで男性たちが笑っているのを見ていい気になったりしていましたね。みんなが見ているテレビタレントやお笑い芸人たちが率先してやっていたことを見習っていた。
女の子のことを敬う気持ちは心の中にあるんです。でも、“敬い”をむしろ自分の中の保険にして、わざと強い言葉をぶつけて男同士で笑う。ゆがんだ感覚ですよね。それを『愛情表現だ』としていたんですから……。って、学生時代のことのように言っていますが、つい最近までやってました 」
高校卒業後、上京。いくつかの職を経て、お笑いの道に進む。門をたたいたのはビートたけし率いるオフィス北野。ビートたけし本人に弟子入りこそしてはいないものの、男社会にどっぷりと漬かった世界で「男らしさ」への美学はさらに強固なものになっていった。
「なんせトップのたけしさんが“殿”と呼ばれているようなところですから(笑)。“THE ホモソーシャル”な世界ではありました。いまだに週刊誌沙汰の記者会見でのたけしさんの鋭い眼光を『かっこいい!』と思う自分も当然いますし。
ただ、ここ5年~10年ほどでエンターテインメントも含めた社会の空気は劇的に変わった。自分の道徳観念がどうとかよりも先に、メディアに出ている側の人間として、あり方を変えなくてはいけないと思うようにはなってきました。とはいえそれは、世の中の空気を受けて慌てて心の方を後からこしらえている……というのが正直なところです」
マキタスポーツさんの俯瞰(ふかん)した視点や時代を切り取る芸風には、男性ファンも多い。すでに芸人や音楽、俳優の分野で活躍し地位を築いていながら、自身のあり方を変えることに怖さはなかったのだろうか。
険しい表情で歩く老人を指し「パパもああいう顔してるよ」と妻から一言
「家族との日々の出来事の積み重ねが大きく影響しています。ウチ、娘が2人いまして。2人いる息子はまだ小さいので、娘たちと妻といると“男の権威”なんてどんどん奪われていくんですよ。父という存在は一国一城の主だったはずなのに、まずいぞ?って思いも初めはあったんです。でも、日々彼女たちと会話をする中でやっぱり学ぶことも多くて。
ある日、街を歩いていたら妻が『あそこ歩いてるおじいさんすごい怖い顔してるでしょ? パパもそうだからね』って言うんです。言われてみると、おじいさんって女性に比べて全然表情がない。しかも、自分もそうなんだと。びっくりしましたね」
なぜ、男性はそんな風に年をとっていくのかを徹底的に分析する。そうすると、男性たちが社会の中で無自覚に優位に生きてきた事実が見えてきた。
「いわゆる女性文化の中で生きてきた方たちは、人と接する中で表情にバリエーションをつける訓練がだいぶできているのに対し、男性は『俺がなぜビジネスでメリットがあるわけでもない場で笑わなきゃいけないんだ』みたいなことを思っていたりするんです。
女性だけでなく、セクシュアルマイノリティーの方々も同様かもしれません。社会通念上、構造的に長らく虐げられてきた方々は、その分、“人をむやみに傷つけない”とか“自分が機嫌よくいることで相手から得られるものもある”という心の交流をきちんとする訓練ができている。それはもちろん、虐げられてきた結果とも言えるので『だから良い』という簡単な話ではなく、皮肉なことだとも思うのですが。
ただ、男性たちはずっと自分たちのことをトランプゲームの大富豪でいう“2”のカード、つまり、一番強いカードを持っている存在だと思い込んでいるから。とっくに“革命”が起こって最弱のカードになっていて、今までやってきたコミュニケーションの取り方じゃ通用しなくなっていることに気づいた方がいいと思うんですよね」
女性特有の文化だから男にはムリ、なんてことはない
しかし、男性が「男らしさ」から解放されるにはまだまだ課題が残っている。学校や会社、友人同士といったホモソーシャルな関係ができやすい環境で“NO”と言うことは難しいかもしれない。

「今までが楽だったからやってきたことを変えないというのは、いつか自分が損するよ?と男性たちには言いたいですね。年を重ねると、どんどん面白くなくなって、どんどん意固地になっていく。若い頃、デイサービスに余興の仕事に行ったりもしていたんですけど、圧倒的に男性たちが楽しくなさそうなんです。後ろの席で険しい顔して『笑ってやるもんか』っていう目でこっちを見ている。一方の女性たちは、握手してきたかと思ったらいつの間にかあめを握らせてきたり(笑)。これを“女性文化”と言葉にして区切るのは簡単かもしれないけど、そういう柔らかさを他人に持ち続けられることが、きちんと社会に対して“個人”でいられるってことなんだと思います」
一方で、一時的な言葉の流行をなぞることにも注意深くいるべきだと指摘する。
「“多様化”とか、そういう能書きがわっと流布して、自分らしい生き方とかっていうことがすごく尊ばれていると思うんですけど、そんなに簡単な話じゃないはずでしょう。女性やセクシュアルマイノリティーの方々はずっと、そのジェンダーだというだけで時につらい思いをしてきた歴史があるから、結果として“個”として世の中と向き合うしかなかった。彼女ら彼らが背負わされてきたものはすごく大きいものだったんですよ。多様性の世の中!って口にするだけで解決するはずなんてない」
「時代に合わせて慌てて心をこしらえた」と自嘲気味に語ったマキタスポーツさんだが、自伝的小説ではかつての“男性的”な自分を赤裸々に描いている。過去の自分をそのままさらけ出したのには理由があった。
「自分で読み返していて思ったのは『本当に腹が立つな、この男は』と。同じ円環の中から全然抜け出せていないんですよ。面白いと思われたい、さらにはモテたいという肥大化した自意識がむき出しで。8年前から連載で執筆してきたものなので、出版にあたりもう少し女性に寄り添った視点を増やそうかとも迷いました。でも、無理でした。その頃の自分はやっぱり、そんなふうに思えてはいなかったから。だから泥まみれのまま、あえてきれいにしないまま出しました。『こんな時代もあったんだ』と、男性の悩ましさをそのまま描くことも、自分の役割だと思ったので」
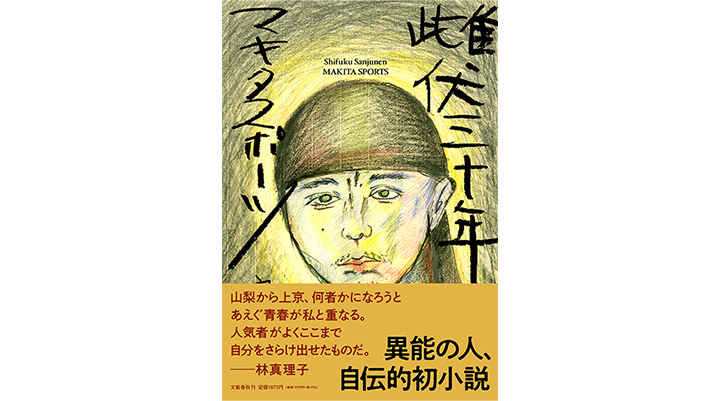 3月に自伝的小説『雌伏三十年』(文藝春秋)を上辞。
3月に自伝的小説『雌伏三十年』(文藝春秋)を上辞。
主人公のキャラクターに手を加えながらも、エピソードはほぼマキタスポーツさんの実話がベースだとか。
「男らしさ」への呪縛を小説で成仏させた、とまではいかないと言う。社会的に優位であることに自覚的になりつつ、これからのためにできることをやっていく。そのためにマキタスポーツさんが意識して持っている“感覚”はあるのだろうか。
「根がお笑い芸人なので、真っすぐに物事を見ないようにする癖は割とついていて、自分が常識だと思っているものを疑ったりとか、その疑いの目を自分自身にも向ける作業は、ずっとやっているんだと思います。そうすると、男性たちが信じ切っている“正しいとされていること”が実は滑稽だったりすることに気付きやすくなるんです。
凝り固まっている価値観をモミモミとほぐす、お笑いっていうのはそういう側面を持っているんですよね」
多くの人を感動させたり笑わせたり、心を動かすエンターテインメントも、実は「男性らしさ」「女性らしさ」の上に成り立ってきた歴史がある。そんな過去をなかったことにせず、ちゃんと次の時代を見据える、しかも時に面白おかしく。マキタスポーツさんの時代を見据える目線は、自分の思考を見つめ直すヒントになるかもしれない。
マキタスポーツさんの視点を変えた一冊は?
取材・執筆:田中春香
撮影:内海裕之
スタイリスト:小林洋治郎(Yolken)
ヘアメイク:永瀬多壱(VANITÈS)
シャツ¥30,800(税込み)/FACTOTUM/Sian PR
パンツ¥29,700(税込み)/meagratia/Sian PR
ベレー帽¥11,000(税込み)/MAISON Birth/Sian PR
他、スタイリスト私物

芸人・ミュージシャン・俳優・文筆家
1970年、山梨県生まれ。“音楽”と“笑い”を融合させた「オトネタ」を提唱し、各地でライブ活動を行う。俳優としては映画『苦役列車』で第 55 回ブルーリボン賞新人賞などを受賞。近年では映画『前科者』『劇場版 きのう何食べた?』『面白南極料理人』などがある。
また独自の視点を生かした執筆も多く、著作には『雌伏三十年』一億総ツッコミ時代』すべての J-POP はパクリである』などがある。
Twitter @makitasports
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント
2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜
2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。
-
 2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜
2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。
-
 2018/11/30若者じゃないと夢は追えない、なんてない。HABU(羽部 恒雄)
2018/11/30若者じゃないと夢は追えない、なんてない。HABU(羽部 恒雄)毎分毎秒と移り変わる空。一瞬たりとも、同じ表情のときはない。そんな空に魅せられ、空の写真を撮る“空の写真家”がいる。それがHABUさんだ。これまで、数々の空の写真集や空に言葉を乗せた写真詩集を発表。HABUさんの撮る空は、見る者全てを魅了する不思議なパワーがある。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。