子どもは褒め過ぎちゃダメ、なんてない。
今や日本を代表する書道家として活動するのみならず、ベスト・ファーザー イエローリボン賞を受賞し子育て本も出版している武田双雲さん。書道家・武田双雲が誕生したきっかけは? 何より「自己肯定感」をはるかに超えたポジティブさはどこから? コロナ禍で、さまざまな行動を制限される今こそ必要な、武田さんのポジティブさや育った環境、子育てについてじっくりと伺った。

「自己肯定感」という言葉は、近年人格形成の重要なファクターとしてさまざまな場面で使われる。「自己肯定感が高い子に育てよう」「自己肯定感が高ければ、難しいチャレンジができる」「自己肯定感が自分には足りていない」……etc。つまりは「高い自己肯定感さえあれば、たいていのことは乗り越えられる」という、まるで打ち出の小づちのような使い方だ。お話を伺った武田さんは「自己肯定感」なんていう既存の言葉が薄っぺらく感じるほどのポジティブさ。明るさ。そして揺るぎない自分への信頼。
意識してつくり上げたポジティブさではないからご本人にその自覚さえないのに、多くの人が彼に巻き込まれてしまうのだ。それも、関わる人みんなが大きなhappyをもらいながら。さまざまな枠にとらわれず、出会った人を一瞬で武田ワールドに取り込んでしまうような陽のオーラは、一体どのように誕生したのだろうか。
両親から惜しみなく承認を受けた結果、既成概念の枠から外れたオリジナリティあふれる自分に
両親共にエネルギッシュ! 幼少期から多くの習い事を
「会う人全てをファンにする」と断言できる武田さんの明るい人格の形成には、書家であるお母さまの影響が強い。
「僕は熊本で生まれ育ちましたが、うちは父が競輪予想の新聞社を経営していて、いつもたくさんの大人がにぎやかに家の中にいる環境で育ちました。当時は日本がバブルに向かっていく時代でもあり、日本全体も明るく元気で、そんな時代背景に加えて両親がめちゃくちゃパワフルで! うちは両親共にADHD(注意欠陥多動性障害)だと思うんですよね。ものすごいエネルギッシュで前向きだけど、夫婦げんかも激しい。そんな夫婦に加えて日々いろいろな人が家に顔を出しているから、それはにぎやかな環境で。小さな頃からそんな環境で育っているから、人見知りなんてなるはずもないですよね。
子どもってその環境しか知らないで育つから、友達の家に行った時お母さんが黙って家にいる姿に、めちゃくちゃ驚きましたよ。『えっ、他の家のお母さんってあんなに静かなの!?』って」
アクティブでいて家事も完璧というお母さんにより、武田さんは小さな頃から空手・少林寺拳法・公文・音楽と、体を動かす系・勉強系・音楽系、さまざまな習い事を始める。その一つが書道だった。
「3歳から習いに行っていましたが、小学校の頃に母親が書道教室を始めたから自然とそこでやるようになって」
いくつもある習い事の一つだった書道だが、のちに自身のライフワークになり、従来の枠におさまらないアートへと昇華する唯一無二のエンターテイナーの道につながる。
「あんたは神様ばい」と無条件に存在を褒めたたえられた幼少期

「うちの両親のすごかったところは、とにかく僕の存在や、やることなすこと全てを褒めたたえるんですよ。もう生まれただけで『あんたは生まれた時から光っとった』『あんたは神様ばい』って。もう良いこと悪いこと何をやっても、そして何もしなくてもですよ。
僕が生まれた瞬間からこんな調子で、今の妻との両家の顔合わせで初めて相手の両親に会った時も、父も母も僕の自慢が止まらない!『この子はこんなにすごい』『こんなエピソードがある』って夫婦で競い合うように延々と2時間も!
でもそうやって育ったんですよ、僕は。だから大人になって『承認欲求』とか『自己肯定感』とか聞いても意味がわからなかったですね。承認欲求なんて満たされ過ぎてて満たしてほしい部分とか認めてほしい部分なんて、もう残ってないレベル。それって親が自分の存在自体を無条件に認めて、褒め続けてくれたからなんですよね」
思春期に向かい人生の暗黒期に入った時に出会った量子力学の世界
生まれた瞬間から何をやっても褒められて育った武田少年は、思春期になるにつれ社会とのズレに気づくようになる。
「両親ADHD(※)で僕もADHD。しかも両親の考えを引き継いで異常にポジティブだから、思春期特有の悩みを周囲が抱えていても、よくわからないんですよ。『なんか難しいこと考えてるんだな、みんな』って感じで。自分はとにかく、自分も周囲も楽しいのが一番だと思ってるけど、だんだんみんなが難しいことを言いだしたら、すっかり浮いちゃったんですよね。
その結果、どこに行っても無視されるようになったり、ADHD特有の不注意さから『決められたことを決まったようにやる』といったことが苦手というのもあり、怒られることばかり増えて、何だかわからないけど何もうまくいかない。10代はそんな感じが続きましたね」
学校が楽しくなさそうと感じ取った母親が中学2年の時に量子力学の本をプレゼントしてくれた。量子力学は原子や分子、光などの現象を理解するために生まれた学問だが、その世界にどっぷりとハマってしまうのだ。
「量子力学の理論を読んでいたら、そこに自分の置かれている状況の答えが見えたんですよ、中学生の僕には。量子力学では世の中全ての原子は、固有の波動で振動しているんですがそこに不協和音があると均衡がおかしくなっちゃう。自分が今学校って楽しくないと感じるのはまさにその状況で、不協和音がストレスやネガティブな感情につながっているんだ、宇宙とつながっているんだ!って感じたんですよね。その時の発見は書道家になった今の作風にも生かされているし、専門家たちと一緒に学べるチャンスにも恵まれました。
あの時に量子力学の面白さに気づいたから、学校でどんなに無視されても平気でした。そう考えるとやっぱり母親すげーな!って。まあでも、僕自身ポジティブ過ぎて『嫌だから学校に行くのやめよう』なんて発想が浮かんだこともなかったんですけどね」
※ADHD(注意欠如・多動症)は、「注意欠陥」と「多動・衝動性」を主な特徴とする発達障害の概念のひとつ。特別な才能が爆発することがある一方で「注意欠陥」という特性上、ミスが多かったりなかなか相手の期待に応えられなかったりというケースもあると言われる。
同僚の感動の涙が導いた今の自分
基本的に何でも楽しみたい武田さんが日本の伝統ある企業に入社。果たしてサラリーマンに向いていたのだろうか。
「僕ね、『誰かに勝ちたい』とか『俺が一番』っていう自己主張の強さは全くないんですよ。誰とも争いたくない平和主義者だし、人を怒らせたり嫌な気持ちにさせるのも嫌で。郷に入りては郷に従います。
自分に与えられた仕事をしながらも自分なりの楽しみを確保したくて、電話の内容とかをメモする時に自分は墨で書き始めたんです。ちゃんと硯(すずり)を置いてね。自分の中では全くなんてことないことだったんだけど、それがうわさになって他の部署の人が見に来たりするようになったんですよ。メモをあちこちに貼っているから。
そのうち、他部署からちょっとした書き物の依頼なんかが来るようになったんですよ。うれしい気持ちと同時にびっくりしましたね。24歳で初めて家族以外の人に褒められたから。それが書道だったんですよ」
あちこちに頼まれて筆で宛名などを書いていた時、同僚に「自分の名前を書いてほしい」と頼まれた。このささいなことが武田さんの運命も、また書道が大河ドラマのタイトルで使われるようになど、日本の伝統的な書道のあり方をも大きく変えていくことになる。
「なんとね、名前を書いたらそれを見て同僚が涙を流したんですよ! もう『えええええええ!!! 泣いてる!!!』ってびっくりしちゃって。もちろんそんなに喜んでくれてうれしいんですが、それより驚きですよ。だって名前を書いただけで泣いちゃったんですよ?
でもその瞬間、脳がすごい勢いで動きだしたんですよ。『これだけ喜んでもらえるなら、これって仕事として成り立つんじゃないか。確かに、世の中の名刺ってつまらないパソコンのフォントしか無いよな。街中の看板だってチラシだって、みんなパソコンフォントだ! 世の中にある全ての印刷物が自分のターゲットになるな』って。そう思いついたら、すぐに辞表を出していました(笑)」
そこから書道家として独立し、最初は名刺を筆で書くところから始めさまざまな「既成概念」を超えて活動を広げていく。その挑戦は、何も書道だけではない。自分自身も「今思うと普通の家とずいぶん違った」と語る武田家流の育てられ方をしてきた経験から、武田さん自身の子育てもとてもユニークで独創的だ。
ベスト・ファーザー イエローリボン賞を受賞した武田家の子育てとは
スーパーポジティブな両親に育てられて今がある武田さんも今では3児の父であり、2019年にはベスト・ファーザー イエローリボン賞を受賞している。きっと日本の育児書にあるような一般的な考えとは無縁な、フリーダムな子育て論をお持ちなのではないだろうか。

「子育てって本当に楽しいし、子どもたちってすごい。子育てって言うと一般的にはしつけたり何かを教えたりということだと思いますが、僕は怒ったり何かを無理やりやらせたりっていうことは一切しません。彼らは僕にとって、一緒に過ごしていてとても楽しい“親友”。子どもそれぞれに個性もやりたいことも違うから、 それぞれの意見や発想を『すげーなー』と思いながらニコニコ見て一緒に楽しんでいます。僕の父も全く怒らず、なんでも面白がって褒めてくれましたから、自然とそれを受け継いでいるのかもしれませんね。
規則やルールで縛らない一方で大切にしているのは会話で、とにかくいろんな話題を家族でいつもしゃべりまくっています。うちの子どもたち、3人とも天才で特にコミュニケーション能力がすごい。これは会話を大切にしてきたからかな。子どもの成長は早いからアート鑑賞のように『一瞬一瞬を見逃さないように』って常に思っています。日々感動をもらっているので、子どもには感謝しかないですね。
中学校の時に生徒会長をやっていた長男は、新型コロナウイルスの感染拡大という出来事から何か感じるところがあったんでしょうね。突然『もう学校は行きません!』って登校拒否宣言をして。普通なら『義務教育なんだから、ちゃんと学校に行って』って親が説得するのかもしれないけど、『すげーなお前、そんなこと思いついたなんて! 本当にすげーよ』って素直に思えたんですよ。僕がこんな感じなので、人として大切なルールやしつけは妻がビシッと押さえてくれています。そこがすごいし、妻は最強ですね。
長男は学校生活のことだけじゃなくて世界に目が向いていて、中学1年生の時にアフリカの児童労働問題を支援する学生団体『チョコプロジェクト』を立ち上げました。視座が高いって言うのかな。目先のことや自分の置かれている環境より、広い視野で物事を見ているんです。長男は今、アメリカの高校で学んでいます。今まで子ども3人でいつも大騒ぎだった我が家ですが、長男はアメリカに留学し、長女は中学生になり、ちょっと子育てが一段落した感覚ですね」
武田さんのご長男が自分の心の声に従った行動ができるのは、武田さん同様自分への揺るぎない信頼があるのだろう。そしてその多くは、親との関係性から育まれたものかもしれない。
最後に「自分を信じられる人に育てるにはどうしたらいいでしょう?」という質問をぶつけたところ、武田さんのご両親の話が返ってきた。
「無条件で子どもを信じる、認めるってことですかね。うちの親が僕を褒めてくれた時には『100点取ったから偉いね』『勉強頑張ったから良い子だね』という条件が一切ない。何をしても褒められる。『あなたはダメな子だから、勉強しなさい、努力しなさい』なんて、将来を不安にさせるような言葉も言わなかった。そんな環境で育てば、『自分はダメかも』なんて発想は浮かばないですよね。
だって僕は、生まれた瞬間から両親から見たら『神』だから。なんか生まれた時から光って見えたんでしょうね(笑)。でもどんな親だって本当は子どもにそう感じるでしょう? 『うちの子は天才!』 『この子は特別』って。それを子どもに伝えればいいんじゃないですかね」
取材・執筆:阿部知子
撮影:内海裕之

書道家、現代アーティスト。1975年、熊本県生まれ。3歳より書道を始め、小学生より書家である母・武田双葉に師事する。東京理科大学を卒業後NTTに入社し、入社から数年後に書の道を目指して独立。以後、NHK大河ドラマの「天地人」のタイトル作成で全国的にも有名になり、独創的な作品が多くのファンの心をつかむ。また近年は子育て本の出版やベスト・ファーザー イエローリボン賞の受賞など、枠にはまらない子育てにも注目が集まる。3児の父。神奈川県藤沢市在住。
公式サイト https://souun.net/
Twitter @souuntakeda
みんなが読んでいる記事
-
 2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜
2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。
-
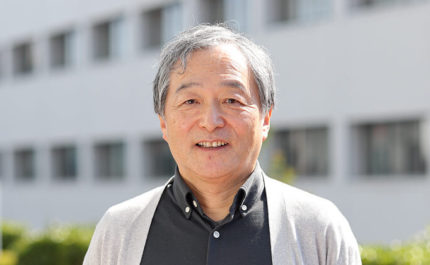 2023/11/14なぜ「結婚しなきゃ」に縛られてしまうのか|社会学者・山田昌弘
2023/11/14なぜ「結婚しなきゃ」に縛られてしまうのか|社会学者・山田昌弘「おひとりさま」「ソロ活」という言葉や、事実婚や選択的シングルマザーなどが話題になり、「結婚」に対する一人ひとりの価値観が変化し始めている。「婚活」「パラサイト・シングル」などの言葉を提唱した家族社会学者の山田昌弘さんに、結婚に関する既成概念についてお話を伺った。
-
 2024/05/24
2024/05/24 “できない”、なんてない。―LIFULLのリーダーたち―LIFULL HOME'S事業本部FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群(キョウ イグン)
“できない”、なんてない。―LIFULLのリーダーたち―LIFULL HOME'S事業本部FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群(キョウ イグン)2024年4月1日、ソーシャルエンタープライズとして事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLは、チーム経営の強化を目的に、新たなCxOおよび事業CEO・責任者就任を発表しました。性別や国籍を問わない多様な顔ぶれで、代表取締役社長の伊東祐司が掲げた「チーム経営」を力強く推進していきます。 シリーズ「LIFULLのリーダーたち」、今回はFRIENDLY DOOR責任者の龔軼群(キョウ イグン)に話を聞きます。
-
 2022/01/12ピンクやフリルは女の子だけのもの、なんてない。ゆっきゅん
2022/01/12ピンクやフリルは女の子だけのもの、なんてない。ゆっきゅんピンクのヘアやお洋服がよく似合って、王子様にもお姫様にも見える。アイドルとして活躍するゆっきゅんさんは、そんな不思議な魅力を持つ人だ。多様な女性のロールモデルを発掘するオーディション『ミスiD2017』で、男性として初めてのファイナリストにも選出された。「男ならこうあるべき」「女はこうすべき」といった決めつけが、世の中から少しずつ減りはじめている今。ゆっきゅんさんに「男らしさ」「女らしさ」「自分らしさ」について、考えを伺った。
-
 2023/04/14【前編】SNS上で起こる「エコーチェンバー現象」とは? デマやフェイクニュースへの対策を解説
2023/04/14【前編】SNS上で起こる「エコーチェンバー現象」とは? デマやフェイクニュースへの対策を解説「エコーチェンバー現象」についてこの記事では下記の5点を解説します。①「エコーチェンバー現象」とは? ②過激な考えに傾倒してしまう危険性がある ③エコーチェンバーの要因となる確証バイアス ④SNSを健全に利用するためには? ⑤思い込みや偏見に支配されず、多様な意見を理解するには
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。








