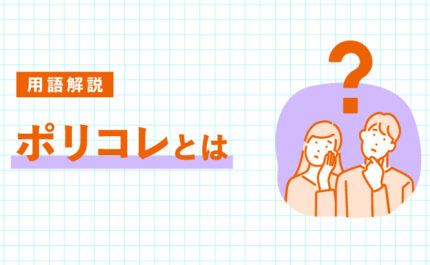住宅弱者とは? 社会問題となっている背景・住まい探しの不安・取り組みを紹介
日本社会が抱える問題は多岐にわたります。その中には少子高齢化、シングルマザーの増加、障害者、外国籍の人との共生などが含まれます。それらの問題が絡み合った先に浮かび上がってくるのが「住宅弱者」と呼ばれる存在です。まだあまり知られていない住宅弱者について、この記事で解説します。
社会問題となっている「住宅弱者」とは
住宅弱者とは、年齢、国籍、セクシュアリティー、経済力、社会的立場などを理由に賃貸の入居を断られてしまう人たちです。具体的には、高齢者、外国籍の人、LBGTQ+の人、生活保護利用者、シングルマザー・ファーザー、被災者、障害者などが含まれます。
個人間の賃貸借契約において、不動産オーナーは誰に自分の物件を貸すか自由に決められます。そして、不動産オーナーが住宅弱者と呼ばれる人たちの入居に不安を感じるのには、いくつかの理由があります。
例えば、相手の経済状況への不安が挙げられます。入居者が非正規雇用のシングルマザーの場合、子どもが病気になると働ける日数が減り、給料にも影響します。その結果、支払いが滞ってしまうのではという不安です。
また、事故やトラブルへの不安もあります。具体的には高齢者の孤独死や、外国人入居者と他の入居者とのトラブルなどです。事故や事件が発生した場合、次の入居者に告知する義務があり、新しい入居者を探しにくくなります。そうなると、家賃を下げざるを得なくなり、不動産オーナーの収入にも影響が出るリスクがあります。
さらに入居者への偏った思い込みも、不安の一つとして考えられます。例えば、日本語が話せ、保証人がいるにもかかわらず、「外国人だからコミュニケーションがうまく取れない」「友人を呼んで騒ぐかもしれない」などと決めつけることで、入居を断るケースもあるのです。
拡大する日本の住宅弱者問題と国・自治体の取り組み

日本の住宅弱者問題は、どの程度深刻なのでしょうか?
ここでは、住宅弱者のうち、高齢者に目を向けてみましょう。2021年の国民生活基礎調査によると、65歳以上の単独世帯は約742万7,000世帯で、全世帯の28.8%を占めます。そして、この中には配偶者の死亡等による収入の減少や、生活の利便性の低下を理由に賃貸住宅に転居する人たちが多く含まれています。
※出典:2021(令和3)年 国民生活基礎調査の概況 – 厚生労働省
一方で賃貸物件を提供する不動産オーナーの65%が家賃滞納や孤独死などを恐れて、単身の高齢者の入居に拒否感を示しているようです。また、これまで住宅弱者のセーフティーネットとして公営住宅が機能してきましたが、財政難や人口減少によりこれ以上戸数の増加が見込めなくなっています。
他方で注目すべきなのは、民間住宅の空き家増加です。総務省統計局の調査によると、2018年における空き家の戸数は849万戸であり、全住宅の13.6%にもなります。このことから、住宅弱者と空き家の借り手に悩む不動産オーナーの橋渡しの役割を果たす制度が求められていることが分かるでしょう。
こうした住宅課題に対処するために2017年に新たな住宅セーフティネット制度がスタート。同制度では、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、その他住宅の確保に特に配慮を要する人たちを「住宅確保要配慮者」と定めています。そして、ハード面の支援として「物件の登録制度の実施」を定め、ソフト面では入居や生活の向上に関する情報の提供や相談、援助を行うことで「要配慮者の入居円滑化」に取り組んでいるのです。また、登録住宅に対して、国と地方公共団体による改修費や家賃・家賃債務保証料の低廉化への補助も行っています。
東京都では住宅セーフティネット制度に「東京ささエール住宅」という愛称をつけ、住宅弱者と、賃貸住宅の空き家、空き室を持つ不動産オーナーをつなぐ制度を2017年にスタート。2025年までに登録数3万戸を目指しています。
東京都の場合、不動産オーナーが空き家などを、住宅確保要配慮者のみが入居可能な「専用住宅」として登録した場合、1戸あたり5万円の報奨金が交付されます。他に、エアコン設備など7種類の住宅設備の購入費や設置費に対して補助金を交付するシステムがあります。
住宅弱者の住まい探しの実態とは

ここからは、実際に住まい探しをしている人たちがどんなところに苦労し、不安を感じているのか、実態調査をもとに紹介します。
株式会社LIFULLが2022年7月に行った「住宅弱者の『住まい探し』に関する実態調査」によると、住宅弱者層の約6割が自身のバックグラウンドを理由に不便を感じたり、困ったりした経験があることが分かりました。新型コロナウイルス感染症などの社会的変化により2019年の調査よりも約16ポイントも増加したのです。また、約7割の住宅弱者層が「自分の社会的立場に理解のある不動産会社との出会いが重要だと思う」と回答しました。
また、65歳からの部屋探しを専門で支援する株式会社R65の調査によると、65歳以上に「不動産会社に入居を断られた経験がありますか?」という質問に対し、全国では23.6%、関東圏では27.9%が「はい」と答えました。
高齢者の入居を妨げる原因として、連帯保証人や緊急連絡先の確保の他、「入居中に高齢者が認知症などにより判断力が低下した場合、どう対処したらいいのか分からない」といった不動産オーナー側の不安が挙げられます。さらに、最大の不安としては、高齢者が亡くなった時、特に孤独死の場合、事故物件と思われたり、残置物の処理などに手間や時間がかかったりすることで、次の入居に支障があることを心配する声が聞かれました。
こうした中、R65の代表取締役、山本遼さんは高齢者向けの賃貸住宅を取り扱うことに力を入れています。同時に不動産オーナー側の「孤独死の不安」にも寄り添い、見守り機器を付け、保険で孤独死の損害をカバーできるようにしています。
※出典:LIFULL HOME'S 住宅弱者の「住まい探し」に関する実態調査結果を発表 – 株式会社LIFULL(ライフル)
※出典:65歳以上の「4人に1人」が賃貸住宅への入居を断られた経験あり。6割の20〜30代は、この問題を“知らない”|株式会社R65のプレスリリース
住宅弱者フレンドリーな不動産会社を探すコツ
「住宅弱者」という社会課題に取り組むプロジェクトは他にもあります。その一つが「FRIENDLY DOOR」です。事業責任者の龔 軼群(キョウ・イグン)さんは、中国籍の両親のもと上海市で生まれ、5歳で来日。日本で進学・就職をしたものの、社会人になってから自身も中国籍であることを理由に住まいを借りられない経験をしました。
このプロジェクトを通じて、生活の基盤となる住まい選びの不平等さを解決すべく、高齢者やシングルマザー・ファーザー、外国籍者、障害者と空き家を抱える不動産オーナーの架け橋になろうとしています。
住宅弱者だからと住まい探しを諦めることはない

住宅弱者と呼ばれるシングルマザー・ファーザー、外国籍の人、LBGTQ+の方々などはどのように住まい探しの難しさに対処しているのでしょうか? 以下では、日本国内での取り組みや、実際に住まい探しで苦労された方の声を紹介していきます。
秋山怜史さんは、一級建築士として2008年に事務所を設立して以来、家を建てるだけでなく、「住まい」そのものを通して社会問題に向けたアプローチを開始。その一つが2012年からスタートしたシングルマザー向けのシェアハウスでした。空き家を母子家庭向けシェアハウスにすることで、空き家問題とシングルマザーの住居問題を解決しようとしています。
三遊亭好青年(ヨハン・ニルソン・ビョルク)さんは、初のスウェーデン人落語家です。日本でさまざまな壁にぶつかりましたが、その一つが住まい探しだったそうです。「外国人はゴミ出しなどのルールが理解できないかもしれない」との思い込みゆえに、多くの不動産オーナーから入居を次々と断られ、アパートが決まるまで長い時間がかかりました。三遊亭さんは「外国人だからという理由だけで拒絶せず、ぜひ歩み寄ってほしいと思います」と述べます。
須藤あきひろさんが代表を務める「IRIS(アイリス)」は、LBGTQ+の方々にもフレンドリーな不動産会社です。須藤さんは、同性カップルも男女のカップル、家族同様に認めてもらえるように不動産オーナーと交渉し、物件を確保、住宅弱者の問題を解消できるよう力を尽くしています。
まとめ

日本社会の課題の縮図とも言える「住宅弱者」。しかし、絡み合う糸をほどいていけば、解決策は意外にシンプルなのかもしれません。行政による取り組みも進んでいますが、解決策を制度だけにゆだねるのではなく、誰もが住宅弱者になり得ることと意識して、この問題を「自分ゴト」にすることが何よりも大切だと言えるでしょう。
■「障害者」の表記について
「自身が持つ障害により社会参加の制限等を受けているので、『障がい者』とにごすのでなく、『障害者』と表記してほしい」という当事者からの要望と本記事の監修者の思いから「障害者」「障害」という表記を使用いたします。
株式会社LIFULL ACTION FOR ALL / FRIENDLY DOOR事業責任者。中国・上海市生まれ。5歳で来日。中央大学総合政策学部卒業後、2010年株式会社ネクスト(現・LIFULL)に入社。2019年に、外国籍者やLGBTQ+、高齢者などの住宅弱者問題を解消するため、LIFULL HOME’S FRIENDLY DOOR(フレンドリードア)を立ち上げ、事業責任者に。その他、認定NPO法人Living in Peaceの代表理事、一般社団法人Welcome Japan 理事、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 あんしん居住研究会委員、書家の顔も持つ。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」