性被害や性差別はなぜなくならないのか?『これからの男の子たちへ』著者 太田啓子さんとジェンダーの問題を考える
令和の時代になってもなくならない性差別や性被害。日本の男女共同参画が進まない理由の一つに、ジェンダー不平等が根底にあることは否定できません。それが如実に表れるデータとして、国会における女性議員の比率があります。内閣府男女共同参画局の調べによると、衆議院女性議員比率を海外と比較した際、日本は190カ国中168位(2022年3月時点の数値)という結果。政府レベルでさまざまな策を講じても一向に男性優位の社会構造が変わる気配がないのが現状です。
男らしさを求められることに疲れる男性、「女性が社会で頑張ってもどうせ出世できない」と後ろ向きになる女性など、それぞれが「ジェンダー不平等」に悩まされ、半ば諦めているように思います。
「性差別をなくしましょう」「みんな自分らしい生き方をしましょう」という掛け声だけではおそらくこの先も一向に解決しない根深いジェンダー問題について、著書『これからの男の子たちへ』が大反響を呼んでいるジェンダー専門の弁護士ママ・太田啓子さんに話を伺いました。
※出典:男女共同参画の最近の動き 令和4年3月10日

性別で「こうあるべきでしょ」と押し付けられることに違和感を抱いていた
――現在ジェンダーの専門家として活躍されている太田さんが弁護士を目指したきっかけを教えてください。
太田啓子さん(以下、太田):最初に弁護士という職業を意識し始めたのは、私が小学生の頃に父に言われた「将来弁護士になったらいい」という一言でした。父もそれほど真剣だったわけではないと思いますが、当時会社員として働いていた父は、女性が社会で活躍していくことの難しさを身をもって知っていたからだと思います。それで「女性でも資格があれば対等に活躍できる」と思ったようです。父がイメージしていたのは企業法務を専門とする弁護士だったので全く違う弁護士をやっていますけれど、小学生の時に言われて以来頭の片隅にずっと「弁護士」という職業のことはありました。
でも大学を選ぶ時点では弁護士に絞りきれずに、「いつか弁護士になるかもしれないし、ならないかもしれないな」という気持ちで、ICU(国際基督教大学)でリベラルアーツを学ぶことにしました。
――大学の時点ではまだ弁護士とは決めていなかったのですね。その後に弁護士を目指したきっかけは何だったのでしょうか?
太田:ICUでリベラルアーツを学んで、大学院で何か専門的な研究をするというようなことも考えていたんです。そんな時に大学でセクハラに遭って、そのままそこで学び続けることがすっかり嫌になっちゃったんですよね。
そんな時、子どもの頃から頭の片隅にあった「弁護士」という仕事にまた興味がわいてきたんです。
当時は日本のロースクール制度の開始前夜だったので、大学3年生から予備校に通い始めましたが、学んでいるうちに弁護士としてジェンダーを専門にするのも面白いなと思うようになったんです。私自身幼い頃からジェンダー……、当時はそういった言葉では認識していなかったですが、性別で「こうあるべきでしょ」と押し付けられることに違和感を抱いていたので。その後、1年半の司法浪人を経て弁護士になりました。

着替えは男女一緒、健康診断では裸が当たり前の小学校は“性的な尊厳”を最もないがしろにする空間
――「子どもの頃から抱いていたジェンダーの押し付けへの違和感」というのは、例えばどのようなことでしょうか?
太田:小学生の頃から「男の子らしさ」「女の子らしさ」を当たり前に求められる環境に違和感がありました。自分で本を読んでいたりテレビを見ていたりすると、“性的な尊厳”をないがしろにされるシーンに度々ぶつかり、それがとても嫌だったんですよね。私にとって、当時の小学校はとりわけ、「生徒の性的尊厳の尊重に欠ける場所」でした。学校って今思ってもとても野蛮で、高学年にもなれば女の子は胸が大きくなり生理が始まっている子が多いのに、同じ教室内で水着に着替えたり、健康診断で上半身裸にならなくてはならず、しかもそこに男性担任が立ち会っていたことまでありました。
体育の時に女子が着用していたブルマーだって、もう下着ですよね、色がついただけの(笑)。高学年頃には生理が始まり出す子がいて、そうすると女の子同士でもからかったり、いじられるネタになる。男女間でも同性同士でも、性的な尊厳に関わる事柄なのに下ネタとして扱われることにもとても違和感がありました。
「女の子だから」「昔からこういうものだから」と粗雑に扱われていることがとても嫌で、“人間”としての尊厳を大事にされていない、と小学生の頃から感じていたんです。
中高生になると、痴漢や公然猥褻(わいせつ)といった、多くの女性が経験するであろう被害にも遭うようになりました。公共交通機関を利用する女性の多くは、とても怖くて嫌な経験が何度もあると思います。場合によっては電車に乗れなくなるくらいの被害を受けるのに、ほとんどの場合は誰も捕まらないし、みんな野放し。これってあまりにおかしいですよね。
私自身が幼い頃から感じていた違和感や、実社会でさまざまな性に関わる不条理が起きているという事実が、弁護士になった際にジェンダー問題に関わろうというきっかけになりました。
――仕事ではどのようなジェンダー案件に関わり、どのようなことを感じられていますか? また日本のジェンダー不平等にはどのような原因があると思われますか?
太田:ジェンダー問題に関わりたい、というと「離婚案件?」と言われることが多いですが、実際に私も多くの離婚案件やハラスメント・性暴力事案などを扱い、多くのことを学んできました。離婚事案には日本という性差別社会の問題が凝縮されているんです。DVであったり離婚後の養育費の問題であったり、女性の経済的自立の困難さであったり。
日本の社会では長らく「女性が子どもを産んだら家庭に入って、家事育児を一手に担うことが当たり前」とされてきました。その結果、多くの女性は仕事を辞めざるを得ず、離婚しようと思っても自立できるほどの経済力がありません。しかし、これは夫婦で話し合った選択でもあり、「日本社会で出産後も労働を続けることの難しさ故」でもあります。「男性は月40万円稼いでも女性はせいぜいパートで5万~6万円」というのが多くの日本の夫婦の平均像です。この状態で離婚を考える時に大きな壁となるのが女性側の経済力で、離婚問題ってお金の問題が非常に重要なわけです。
子育てや配偶者の転勤のために自分は仕事を辞めて家庭を支えてきたという女性が、離婚したら、キャリアの中断の弊害を自分だけでかぶる形になってしまう。財産分与では、婚姻期間に形成した財産を半分ずつ分けることはできますが、定年までいられる正社員の夫と、家庭のためにキャリアを中断しパートの不安定雇用の妻みたいな場合、2分の1ずつの財産分与は本当に「公平」なのかといつもモヤモヤしてしまいます。「夫婦で決めたことだから」とはいえ、これで本当に公平と言えるのでしょうか。
OECD(経済協力開発機構)が15~64歳の男女を対象にした調査によれば、日本の女性は男性の5.5倍の無償労働をしているとされています。これは世界的に見てもずば抜けて高く、お隣・韓国では4.4倍、フランスは1.7倍、アメリカは1.6倍、スウェーデンでは1.3倍というのが現実です。これだけ当たり前に女性が「無償労働」を強いられていて、それが評価されていないのが日本の現状です。
この原因は、介護や子育てといったケア労働の本当の大変さを実感値として持っていない人々、具体的には無償労働を自分ごとに捉えていない年配の男性が意思決定をしているからでしょう。「意思決定にさまざまな多様な人が関わる」ことが実現されない限り、なかなか日本の現状は変わらないように思います。
※出典:人生100年時代における結婚と家族~家族の姿の変化と課題にどう向き合うか~ 男女共同参画白書 令和4年版 全体版(PDF版) | 内閣府男女共同参画局

ジェンダー平等の実現には男性の意識変革やバイアスへの気付きが不可欠
――政治が変わらないと日本は変わらない、男性の意識も変わらないということでしょうか。
太田:「政治が変わらないと」というのは間違いないと思います。でもこれに関しては希望があるんです。「ジェンダー不平等」は決して日本だけの問題ではありません。2020年現在日本の国会議員の女性比率は2割以下ですが、1980年代に同じような女性の国会議員比率だったにもかかわらず、現在は比率が数倍になっている国はいくつもあります。これは、「他の国は変わったが日本は変わらなかった」ということで、その事実は残念ではありますが、数十年かけて変わることはできる、という証明でもありますよね。
日本も30年前よりはマシにはなっているのですが、歩みが遅すぎます。しかしこれからは世代交代が進み加速していくのではないかと期待したいです。
また、社会が変わるには「男性の意識」も変わっていかなければなりません。例えば性交渉においては「同意の有無」が重要なのに、恋愛のつもり、同意があったはず、という男性の思い込みや認知の歪みがさまざまな性暴力の根源にあるのです。こういった加害者の歪んだ認知を正すのは難しく、弁護士の仕事の範疇ではないもののそういう思い込みをなくしたいと考えています。
――さまざまなジェンダー問題や離婚事案などを扱ってこられた中で、「女性だけでなく男性にも有害な男らしさへの呪縛」を感じている、と著書で拝見しました。そこに、単純に「男性が被害者」「女性が被害者」という構図だけでは測れない、ジェンダー不平等やジェンダーバイアスがあるように思います。
太田:おっしゃる通りです。女性が被害者であり差別を受けているというのはなんとなくイメージがしやすいと思いますが、育てられる過程で男性も多くのジェンダーバイアスに基づく抑圧を受けているのです。例えば女の子が転ぶと親がすぐに飛んでいくのに、男の子は転んで泣いていても「男は泣くな!」と言われたり、「メソメソするのは男らしくない」と当たり前のように言われたりします。
男性トイレは今でもオープンで、それがいたずらやいじめを生むこともあるでしょう。上半身裸が当たり前の男性用の水着に違和感や抵抗感があっても、声に出すのは難しいのです。男性の性被害にも深刻なものがあるのに、なかなか問題として捉えられなかったりもしますね。そういった「男の子ならではの尊厳の大事にされなさ」も、将来的に歪んだジェンダーバイアスが生まれる下地になっているのではないでしょうか。
ジェンダー平等を実現するには、日本社会のマジョリティー側である男性の積極的な参画が不可欠です。そもそも「自分たちは優位な立場にいる」という認識も含め、男性側の意識の変革やバイアスに気付くことが重要だと思っています。
――今のお話を伺っていると、大人になってからの教育ではなく、子育て中の親の働きかけ方もとても重要だと感じました。現在子育て中の親は、性差別を植えつけないようどのような意識を持てばいいでしょうか。また太田さんは2人の男の子がいらっしゃいますが、子育てで意識していることを教えてください。
太田:まずは、親世代の誰もがジェンダーバイアスを無意識に持っている、ということを自覚することが大切だと思います。もちろん私自身にもあります。「私たちがそう育ってきて刷り込まれたのだからしょうがない」ではなく、その負の連鎖をいかに断ち切っていくか、女性だけではなく男性だって「男らしさ」にとらわれることなく、自分の思うように生きていける社会が理想ですよね。
私自身が意識しているのは、以前の自分の発言が間違えていたなと思った時には素直に謝ることです。「こういう理由や思い込みでこう発言してしまったけれど間違えていた。ごめんなさい」「疲れていたのであんなことを言ってしまった」など、具体的に伝えるようにしています。
日本社会には「謝ったら負け」「非を認めるのは弱さ」のような風潮がありますが、それこそが社会のさまざまな問題点の原因だと思います。謝れる勇気こそ強さだし、強い人も間違えることはあるし、そんな時にはきちんと謝る、という背中を見せたいと思います。
子育て世代は、パートナーに対してジェンダーバイアスの押し付けをしないこと

――難しく見えるジェンダー問題ですが、実は一人ひとりがジェンダーバイアスを押し付けないことで少しずつ社会を変えていけるのですね。
太田:理想とする未来は「ジェンダー差別がない社会」「貧困と差別、そして暴力がない世界」ですね。ジェンダーによる差別は女性の抑圧だけではなく、男性にもあります。例えば、男性は働かなくてはならない、家族を養い続けなければならない、などですね。特に子育て世代の私たちは、そういったバイアスを押し付けないことを意識し続けていかなければなりません。女性で「あなたは出産したら仕事を辞めるから、学歴もそこそこでいいのよ」という育てられ方をしている人がたくさんいます。
また結婚生活を見ると、個人が個人に経済的に依存せざるを得ない状況は、DVの温床になりやすいと感じます。「子どもを大学に行かせるために夫からのDVを我慢しなきゃ」などの不幸が起きないよう、女性が子育てのために稼げないなら支援する仕組みを充実させるなど、社会も変わっていかなければならないでしょう。
私たちが声を上げたり、子育ての中で意識をしていくその積み重ねで、歩みは遅くとも社会は変えられると信じています。
「性差別」というと、とかく女性ばかりが被害者のように思われがちですが「性別により役割が固定される」という意味では、男性も同じなのです。性別や属性にかかわらず、個人が希望する人生を選択できる社会について、今一度考えてみてはいかがでしょうか。
Profile
太田啓子
弁護士。2002年弁護士登録、神奈川県弁護士会所属。離婚・相続等の家事事件、セクシュアルハラスメント・性被害などを多く手がける。2019年には「DAYS JAPAN」広河隆一元編集長のセクハラ・パワハラ事件に関する検証委員会の委員も務めた。「憲法カフェ」(出張憲法勉強会)などの講師としての講演活動も行う。2020年に発売した著書『これからの男の子たちへ』はAmazonジェンダー部門で1位を獲得した。
Twitter @katepanda2
取材・執筆:阿部知子
撮影:徳山喜行
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
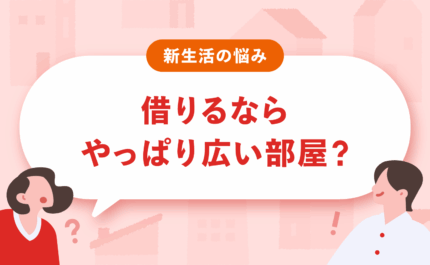 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
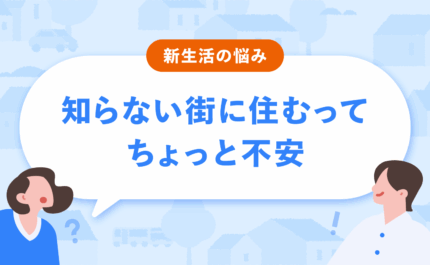 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
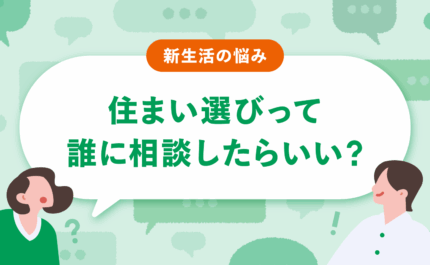 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
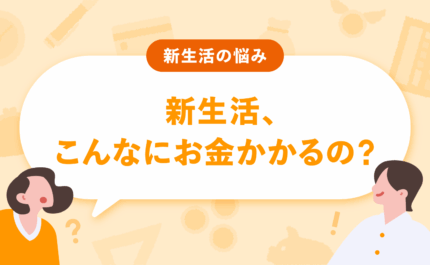 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」














