恋愛で傷つくのが怖いから相手に忖度しなきゃ、なんてない。
2000年代にアカペラブームを巻き起こしたテレビ番組「ハモネプ」出場経歴を持つボイストレーナー白石涼さん。2年前にYouTubeと出会い、2020年には登録者100万人を達成するなど順風満帆な人生かと思いきや、アルコール依存症とうつ病の併発に苦しむなど20代は壮絶な苦労を経験してきた。しかし、動画の向こうにいる本人はそのつらい経験を笑いながらぶっちゃけトークしている。悲壮感がなく、なぜか元気をもらえる。自身のチャンネルで配信した動画にてゲイであることをカミングアウトし、“おしらさん”の愛称で親しまれる新世代YouTuberに、セクシュアルマイノリティーの立場から恋愛で大切にすることは何かを伺った。

新型コロナウイルスの影響で職を失った人は、全国で7万人を超えるというデータが厚生労働省の調査でわかった。年が明けた2021年もコロナの脅威は衰えず、1月8日に1都3県に緊急事態宣言が発出され、不景気ムードがさらに加速。飲食店は20時に閉店を余儀なくされ、1年前まではきらびやかだった都内の繁華街は一層暗く見えた。しかし、影あるところに光あり。外出自粛によって需要が増えた市場では、好景気が訪れた。インターネットの動画視聴の利用率が大幅に増え、YouTuberの活躍が目覚ましかったのだ。
YouTuber白石涼さん(通称おしら)も、その恩恵を受けた1人。本業であるボイストレーナーのスキルを生かした歌い方解説もさることながら、視聴者を引きつける魅力は「オネエ」という個性にある。メインチャンネルでは大好きな歌を饒舌に解説し、サブチャンネルではカミングアウト、HSP※、生きづらさといった自身のパーソナリティーに触れ、本音を赤裸々に語る。世間ではさまざまな多様性の議論が進む中、LGBTの恋愛や結婚観はどのような変化があり、当事者たちは何を思って愛のカタチを模索しているのか。一般常識にとらわれず自分の尺度で正直に生きる「おしら流の恋愛観」を率直に語っていただいた。
※HSPとは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略で、感受性が豊かな気質を持つ人のことです。周囲の刺激に対して非常に敏感で、繊細な感覚を持っています。
参照元:HSP(Highly Sensitive Person)の特徴と向き合い方 | 医療法人社団 平成医会
「一般的に」「世間的に」という話は自分が主語になっていない
コロナ禍で外出機会が減り、男女の出会いも生まれにくくなった。将来への不安から独身男女の恋愛観や結婚願望に変化が起き、オンラインで婚活が盛んに行われている。こうした世間一般で語られる結婚への憧れ、結婚観に対しておしらさんはどう感じているのだろうか。
「結婚式を挙げる=愛の象徴・証しっていう図式にそもそも疑問を感じるんです。あれってブライダル業界が作ったイメージだと思うから。チョコレート売るために、バレンタインデーというキャンペーンを始めたみたいなものですよね」
しかし、結婚式を挙げること自体を否定しているわけではない。おしらさんが気になるのは、結婚の「コスト」と「リスク」だ。
「披露宴に何百万円もお金をかけて、『私たち最高に幸せ!』って笑顔でケーキ入刀していた2人が、何年かしたら不倫して離婚とか普通にあるじゃないですか。子どもがいたら養育費の問題も出てくる。それなのにお金かけて式をやる意味あるのかなって。何にお金をかけるかは人それぞれですけどね。もちろん、家族や親友が結婚することはうれしいし、式に参加したら楽しいんですけど、結婚式を通過儀礼として一様にみんなが受け入れていることには共感できないなって思います。
『結婚して得られる喜びや感動がある』とか『見える景色が変わる』という意見も聞きます。それも一理ありますが、異性や同性に関係なく結婚が最善の方法とは言えないんじゃないかなと個人的には思います」
自身のYouTubeチャンネル上で、改めてゲイのカミングアウトをしたのは2020年の10月11日。カミングアウトをしたセクシュアルマイノリティーの人々をお祝いする「国際カミングアウト・デー」の日だ。
YouTubeでは恋愛相談に答えたり、世の中のジェンダーギャップを斬ったりとオネエのポジションを生かしたコンテンツを配信しているおしらさん。足立区議会議員の発言を受け、同性婚について思うところを動画で語った。
「同性婚については、私は賛成でも反対でもありません。『したい人がすればいい』という、中立的な立場です。現在パートナーと暮らしていますが、今のところ結婚への憧れはありません。自分は結婚自体にメリット・デメリットで判断しがちなので、ちょっとこじらせた価値観なのかもしれないですが(笑)。結婚が愛する2人にとって重要なライフステージのイベントだとしたら、そこに異性も同性も関係ないですよね」
同性カップルを「結婚に相当する関係」と認めるパートナーシップ制度は全国60以上の自治体で導入されているが、税制面の優遇措置を受けたり、築いた財産を相続させたりすることが認められておらず、法的効力は一切ない。パートナーシップ制度は同性婚を認める社会への第一歩だが、同性カップルが望む幸せのかたちまでは実現できそうもないようだ。
「同性婚が認められる世界が早く来てほしいと願うゲイやレズビアンカップルは、『かけがえのないパートナーと結婚式で愛を誓い合い、みんなに祝福されて幸せな人生を歩みたい』という夢を持っている人が多いと思うし、そこは否定しません。
個人的に同性婚制度はあってもなくてもいいけれど、同性婚制度がないことで若い子達の潜在意識に“セクシュアルマイノリティーは世間的に認められない存在だ”と影を落とすことになるのではと少し心配しています」
自分の言葉に責任を持ちつつも、言いたいことは言ったほうがいい
大学卒業後、一時期サラリーマンとして働いていた経歴を持つおしらさん。大手企業の営業マンとして多忙な日々を過ごしていたが、生まれ持ったHSPの特性による神経過敏な性格が、次第にストレスを増幅させ、アルコール依存症とうつ病を同時に患ってしまった。
「職場では、オフィスにいるまわりの人たちの話し声が全部耳に入ってきてしまって仕事にならないんです。プライベートでも賑やかなお店に入ったら、周囲の話し声に敏感になり過ぎて目の前の人の会話が頭に入ってこないという状態でとてもつらかったですね。注意力や集中力も散漫になって、仕事でミスが続いたり忘れ物ばかりするようになったりしてボロボロでした。平日の夜なのに、ワインを2本空けて泥酔しないと眠れないほどお酒に溺れるようになり、会社も休みがちになりました。みかねた上司から医者に行くことを勧められて、診察を受けに言ったら『あなたはアルコール依存症で、うつ病ですよ』って。『え? アルコール依存症だけじゃなくて、うつ病もなの⁉』ってショックでしたよ(笑)。治療に専念するため、会社を辞めて自宅に戻り療養することに。20代前半は、精神的にも肉体的にもまったく余裕がなかったので、恋愛も邪魔だなとしか感じていませんでしたね」
生まれつき敏感で繊細な神経を持つおしらさんは、恋愛でも細かいところに気を遣い過ぎてしまい、20代の恋愛はケンカ別れも絶えなかったそう。
「20代の頃は、相手に『~すべき』をぶつけていました。『デートの待ち合わせ時間を過ぎるなら連絡すべきでしょ』とか、『22時に帰る予定が、23時に遅れるなら連絡すべきでしょ』っていう『普通そうだよね』みたいな持論で相手を責めていました。相手からしたら大事なことと思っていないわけで、“すべきか、そうじゃないか”で言い合いをしていましたね。
でもいろんな方とお付き合いして、『~すべき』っていう一方的な主張を押し付けてもしかたないなと立ち止まれるようになりました。でも、ぶつけなかったら相手は気付いてくれないし、歩み寄りもない。そうなると自分がガマンするだけなので、冷めて興味がなくなる。感情の持っていきどころが難しいと思いました」

価値観の押し付けにならず、建設的な意見の交換ができるコミュニケーションの方法は、「自分を主語にする」ことにあるようだ。
「世間はこうだから、それが常識だからというロジックだと、絶対ケンカになります。そうじゃなくて、『そういうことされるのは、自分がイヤだ』と自分自身を主語にすることで、目の前の人間同士の話し合いになります。自分の感情を言葉に乗せて伝えているのに、相手が理解しようとしないなら諦めるしかない。だって同じ土俵に立って向き合ってくれないんですから」
ワガママだと相手に思われたくないと、感情を出せない人もいるはず。
「そもそも、同じ考えの人なんていないと思います。違う人生を歩んできた他人ですから。単なるワガママや自分勝手な考えかそうじゃないかの違いは、『言葉に責任を持っているかどうか』だと思います。自分の言葉をどう受け止めるのかは相手次第です。2人の関係性をより良くするために注意したり指摘したり話し合おうとしたりするのに、それで傷つくのはその人の問題。何を言っても傷つく人はいますから。
『あなたのここが私を傷つけるから直してほしい』と伝えたとして、『わかった、直すよ』と受け入れてくれるかもしれないし、『お前がガマンしろ!』と反発されるかもしれない。でも、『ガマンしろ』という主張も相手の主語。ようやくそこでお互い本音のぶつけあいができるんです」
自分を主語にした言葉でコミュニケーションしないと、相手が本当に不満に思っていることや気付いてほしい気持ちをスルーした平行線の話し合いにしかならないという。どういうことなのか。
「相手が『でもそういうけど、世間一般ではさ』みたいな論理で話そうとする時って、本当は別のことで怒っていたり、察してほしいという気持ちでいたりすることが多いと思うんです。例えば、自分の帰りが遅かったことに相手が怒っていたとしても、帰りが遅いことが問題じゃなくて、本当の不満は自分がないがしろにされて大事にされていないことだったりします。本音は、ちょっとズレたところに潜んでいるんですよね。そういう場合、怒っている相手に対して『ごめんね。次は22時に帰って来るね』だと、ケンカ勃発です(笑)。お互いの本音のさらけ出しを面倒だなーと思わずに、自分を主語にして伝えることでお互いが大事にしたいことが見えてくるはずです。思ったことを素直に言って、相手を傷つけたらひたすら謝る。シンプルに考えていいんじゃないですかね」
目の前にいる相手と本音で語り合おう
ガマンして自分が犠牲になるのが愛じゃないし、相手のためにもならない。ぶつかり合いや歩み寄りがないと、お付き合いしている意味がないし、人間としてお互い成長しない。あくまでも自分が感じたことをシンプルに伝えること。
数年前まで、生まれつきのHSPの特性に悩まされ、アルコール依存症で苦しんでいたおしらさん。繊細でいながら、大胆な思考と行動力で人生を切り開いてきたおしらさんの言葉は、マイノリティーだけに響くものでは決してない、珠玉の名言にあふれていた。

1990年、神奈川県生まれ。ボイストレーナー、YouTuber。慶應義塾大学在学中に結成したアカペラグループで精力的にライブ活動をスタートし、フジテレビ「ハモネプ」出演。卒業後、都内ボーカルスクールに所属し、4年間で200人以上のレッスンを担当。2019年3月からフリーのボーカルトレーナーとして独立。2019年からYouTubeチャンネル「しらスタ【歌唱力向上委員会】」を開設し、Official髭男dism、King Gnu、米津玄師などのヒットナンバーを取り上げた歌い方動画がネットで話題に。メインチャンネル登録者数125万人、サブチャンネル登録者数8.46万人と、チャンネル開設からおよそ2年弱で登録者数100万人を突破するほどの人気YouTuberとなる。
※登録者数は、2021年2月2日現在の数字です。
Official YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCbVQGCsMcqC3q7OtX8iXy9Q
Twitter @ryo_shiraishi
Instagram @shiraishi_stadium
多様な暮らし・人生を応援する
LIFULLのサービス
みんなが読んでいる記事
-
 2023/07/06心地よいはみんな違う。私たちのパートナーシップ【モーリー・ロバートソンの場合】
2023/07/06心地よいはみんな違う。私たちのパートナーシップ【モーリー・ロバートソンの場合】心地よいパートナーシップは、一人ひとり違う。しかしながら、パートナーシップのあり方にはまだまだ選択肢が乏しいのが現状だ。「LIFULL STORIES」と「あしたメディア by BIGLOBE」では、モーリー・ロバートソンさんに「心地よいパートナーシップ」について聞いてみることにした。
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2021/09/30サスティナブルな取り組みとは? 世界共通の問題の解決を目指すSDGsとサスティナブルな社会
2021/09/30サスティナブルな取り組みとは? 世界共通の問題の解決を目指すSDGsとサスティナブルな社会最近、よく耳にする「サスティナブル」とは一体何なのでしょうか。サスティナブルな世界を達成するための目標「SDGs」とは何か、サスティナブル経営に取り組む企業の事例、サスティナブルな活動を実践している人たちを紹介します。
-
 2023/08/22ジェロントロジーとは? 人生100年時代をいきいきと過ごすための考え方と超高齢社会の課題
2023/08/22ジェロントロジーとは? 人生100年時代をいきいきと過ごすための考え方と超高齢社会の課題2021年における日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳と日本はまさに人生100年時代に突入したと言えるでしょう。超高齢社会の課題に取り組んでいるのが「ジェロントロジー」という学問分野です。この記事ではジェロントロジーを解説します。
-
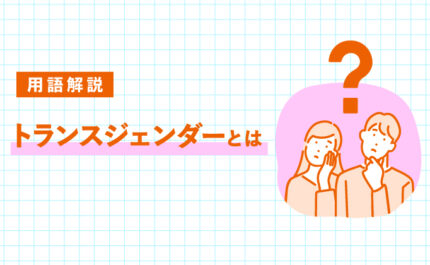 2025/09/02トランスジェンダーとは?トランスジェンダーの生活と社会課題を解説
2025/09/02トランスジェンダーとは?トランスジェンダーの生活と社会課題を解説トランスジェンダーの定義や種類、直面する社会的課題と私たちにできる配慮・支援について詳しく解説します
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。










