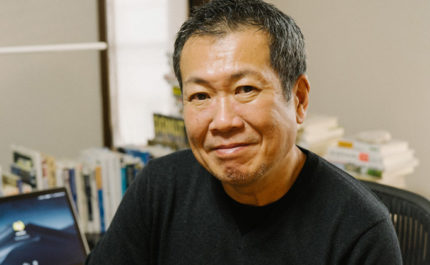かっこよく生きるには東京じゃなきゃ、なんてない。【後編】
未来をつくるSDGsマガジン『ソトコト』の編集長として、「ソーシャル」「関係人口」など、今を語る上で欠かせないキーワードが世間に広まるきっかけをつくってきた指出 一正さん。現在は日本全国を飛び回りながら、「ローカルヒーロー、ローカルヒロイン」と呼ばれる、地方で夢をかなえる人々を取材する一方で、地域の若者の夢と自治体の街おこしプロジェクトに寄り添いながら、各地を盛り上げている。
連載 かっこよく生きるには東京じゃなきゃ、なんてない。
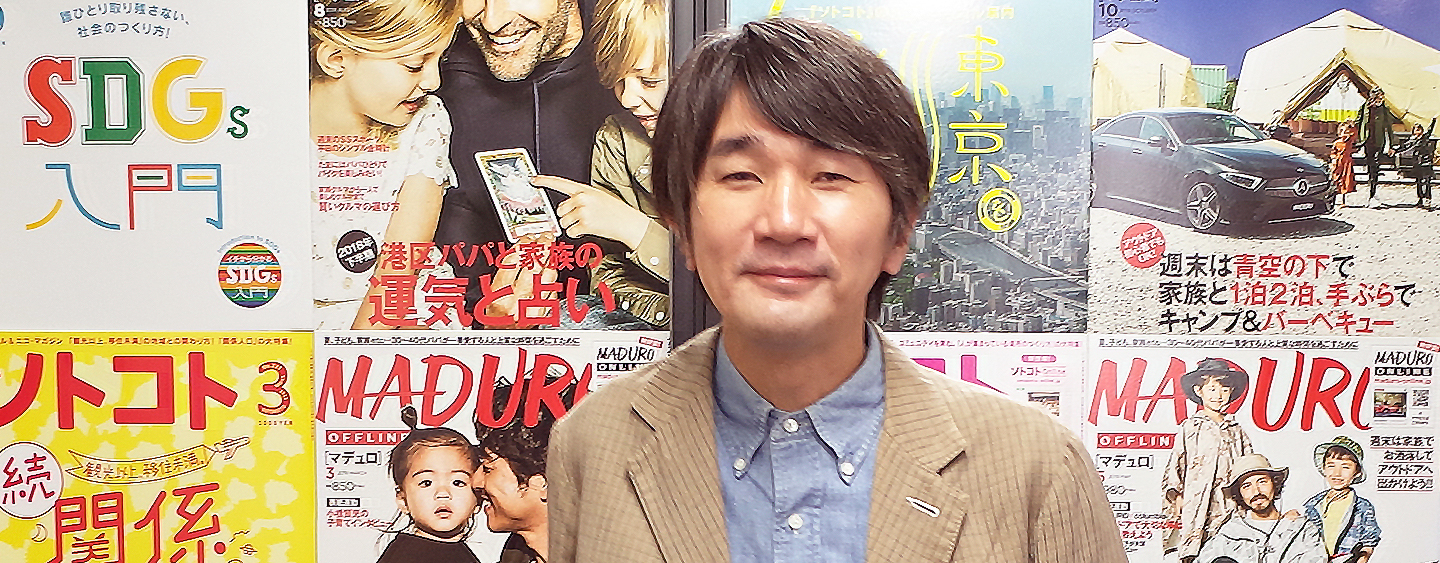
前編では、指出さんが幼少期の頃の体験を通して、コミュニティデザインの原点に触れたエピソードと、東京への憧れとコンプレックスが生み出した熱量が、「編集者になる」という夢をかなえる原動力になった過程を伺った。そして後編では、その後雑誌ソトコトというメディアを通してのローカルとの関わりや、コロナ禍以降の働き方の変化について話を聞いた。
そこに暮らす人たちの動きや移ろいをつぶさに観察する
「2004年、35歳の頃に雑誌『ソトコト』に副編集長として移りました。
その背景としては、そこまで『アウトドアが好き』という人たちに向けて、僕はメディアをつくってきたんですが、ある時そこに限界のようなものを感じ、今より少し広い視点から、自分の中で環境や未来、生態系などを伝えられるメディアに移りたいと思ったんです。
当時は『エコ』や『ロハス』のテーマがメインだったんですが、2008年のリーマンショック、そして2011年の東日本大震災を経て、社会がコミュニティ中心みたいな方向になってきたのを感じたので、編集長に就任した同年、ソトコトの方針を『ソーシャル、人』の方向に転換しました」
「エコ」「ロハス」という路線から、「ソーシャル」「人」を中心とした目線に舵を切った雑誌ソトコト。その転換の前後、指出さん自身も大きな影響を受けたものがあった。
「2008年以降の出来事を経て、なぜ僕がそこで変わったかと言うと、有難いことに日本のローカルに触れる機会は大学時代からあったんです。ただそういう場所に足を運んでいたのに、場所としてのローカルには興味があっても、人にはまったく興味がなかった。
これは『無関係人口』だったわけですよ。もちろん取材として地域の人には会うんですが、そこに暮らす人たちの動きや移ろいをつぶさに観察することを意識できたのは、2008年以降でした。
その2008年に、NPO 法人 ETIC.代表の宮城治男さんから連絡があり『地域の若者のチャレンジを応援する賞をつくるので、その審査員になりませんか?』っていうお声がけをいただき、そこにエントリーしてくる若者や、審査員として一緒に席を並べさせていただいたローカルで活躍する人達に圧倒的な影響を受けましたね」
関係人口はオンラインでもつくれる
リーマンショックや東日本大震災などの出来事は、雑誌ソトコトにも大きく影響を与え、その後のローカルで活躍する人々との出会いは、指出編集長の意識を変えた。そして今年のコロナ禍は、指出さんの働き方にどんな影響を与えたのだろう。

「まずコロナ禍以前の話をすると、週6日は地域に行っていて、そこで行政からご依頼いただいた事業の手伝いをしたりとか、人材育成ワークショップを開いたりしていました。
コロナ禍以降は地方に出かけられず、東京の自宅で仕事をしている状況が3ヶ月ぐらい続いたんです。もちろんその間も地域でのオンライン講演やワークショップをしていました。以前は1日で1つの地域を周っていたのに、今はオンライン上で1日に3地域と話をする。そういう意味では言葉の交換の頻度は増えました。
またこれまでの取材は実際に行くのが当たり前だったんですが、これからは取材が『オンかオフか』ということが前提として語られるようになったのが、一番の変化かもしれません。
一方で事業に関しては、ソトコトにはメディアとしての仕事の他に、関係人口をつくる講座や地域を編集する講座、SDGsやサスティナビリティを学ぶ講座、そういうものを行政の方から受託することも多く、それらも対面ではなくオンラインに変わってきている。
そもそも『関係人口』は『観光以上移住未満』の人口で、移住はできないけど地域に関わる人が増えていったら、ということで生まれた概念。ただオンライン講座だと『関係人口って一体何なの?』ってなりやすい。
でも関係人口はオンラインでもつくれるんです。
例えば奈良県の下北山村のお母さんが美味しいぬか床を作れるとした時に、その作り方をオンライン上で見ている女の子が学ぶことができる。一方、地方のお母さんは婦人会の計算とか、エクセルでやりたいことがあれば オンラインでそのやり方を女の子から教えてもらう。
オンラインで知識と技術の共有ができれば、それは関係人口が求めている1つの形なので『オンライン関係人口』というのも当然成り立つわけです。だから行政との事業も『今回は関係人口のオンライン講座で行きましょうか』みたいなことが言いやすくなりました。
だから今は訪れることが難しい地域でも、その場所をオンラインで知った若い人たちは、いつか当然行きたくなる。要は関係人口が生まれる入り口が二重になったんです。
もう一つ、これも関係人口の話ですけど、これまでは例えば東京の人たちが四国のある山間の地域に関わる、みたいなことがわかりやすい関係人口だった。でもコロナ禍以降は、例えば宇都宮の近郊の街、栃木市とか真岡市みたいな所から宇都宮のまちづくりに関わるみたいな、近い地域間での関係人口が見られるようになった。これはこのコロナが生み出した新しい、ひとつの関係人口の変容だと思うんですね。
実は地域の周辺にも同じような感覚を持つ人たちがいるのに、近すぎるせいでお互いの関係性が見出せなかった。それが県内の移動はいいけれど、県をまたぐのは許されない、という状況から、近くにこんなかっこいいまちづくりをしてる人がいた、みたいな発見につながる。
要は『意外と仲間は近い所にいる』という話で、移動の制限が生み出した地域内の新しい関係性をすごく感じています。これまでは距離の遠さが関係人口をわかりやすくしていたんですけど、どんどんその距離が縮まっている。つまり『地域内関係人口』ですね」
自分のやりたいことはどんな小さなことでも口に出していく
コロナ禍がきっかけで都市のデメリットが浮き彫りになり、オンラインのコミュニケーションの普及は、場所の制限を少しずつなくしていく。そんな時代に、自分のやりたいことを場所にとらわれずに実現していくには、何が必要なのだろうか。
「これまでは、割と遠い地域と知り合いになることが大事な価値と捉えられていました。もちろんそれも豊かなことですが、意外と自分に近い周りの人達が何をしているのかを知らない生活が続いている。
特に東京は人が多すぎて、どこまでを隣人と捉えていいかわからない。そう考えると自分たちが『ここに住んでいるよ』ということを、もっとその近隣の地域に伝えられる機会が増えるといいのかもしれない。
大きなプロジェクトをやるのは、ある程度それに慣れた人たちがやっていけばいい。そこまでじゃなく、自分の地域で暮らす充実度と満足度を上げる為にはどうするか?
例えば、僕の小5の息子が、コロナ禍の自粛期間中に暇だと言うので『要らないものを自由に持っていってください、みたいな無人マーケットを庭でやってみたら?』って提案したら、本当にやりだしたんです。息子がそのお客さんから『前からこのおうちのこの花が気になっていたのよ』みたいなことを聞き、それを僕の妻に伝えたりする。要するに僕たちが地域からどう見られていたのかを、息子が伝えてくれたんです。
つまり、身の回りでの小さな『マイクロプロジェクト』でいい。遠くまで行かなくても、意外と僕たちは日常を彩るような面白いことを作り出せるのでは、と思っています。
それから若い皆さんが、この先を不安に思っているのを感じ取る機会もあるんです。『このままじゃ終われない』と言う方もいる。
今、若い世代がそういう焦燥感を感じているわけですが、まずは『大丈夫ですよ』と言います。自分が好きなものが真ん中にある生活を続けていくことがまず大事。時代によって肉付けはその時のものでいい。
僕はそういう生き方をしてきたので、常にブレない。好きなものが魚釣りで、それが中心にあっても、ソーシャルとかコミュニティとか、次に大事にしているものがしっかりと僕のその周りを包んでくれている。自分の好きなことを真ん中に置いて、それを信じて逃さないことが大事です。
もう一つ、自分のやりたいことはどんな小さなことでも口に出していくといい。
実は自分の思いって、思った以上に人に届いていないんです 。僕はSNS で毎日同じ情報を流していますが、それでも届かない。自分らしく生きたいという言葉は、次の日すぐに全員には伝わらないわけです。その意味で真ん中に好きなものがあって、自分がやりたいことを毎日のように口に出していくと、知る人が増えてプロジェクトになったりする。『こういうことをやってみたい』と口に出すと現実化するっていうのは、これまで取材した皆さんからよく聞きますね。夢を語るのは照れくさいんですが、『それを聞きたかった』っていう人も、きっとどこかにいるんです」
~かっこよく生きるには東京じゃなきゃ、なんてない。【前編】へ~
「ソーシャルディスタンス」だと「とにかく近づかない」となりがちですが、もしそれが「ソーシャル“グッド”ディスタンス」だったら、これ位の距離感だったらお互い丁度いいよね、となる。それが自分と地域との関係性とか、他の地域の仲間との関係性みたいなものに引き換えられていくといい。
お互いの距離感みたいなものは、育てていけばむやみに怖がったり人を退けたりしなくてもいい。「これ位だったら大丈夫だよ」というような、生き物同士の安全な距離感があるわけですよ。それが「ソーシャルグッドディスタンス」ってもので、その言葉がいいなと思ってそう呼んでいます。
編集協力/IDEAS FOR GOOD

『ソトコト』編集長。1969年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。雑誌『Outdoor』編集部、『Rod and Reel』編集長を経て、現職。著書に『ぼくらは地方で幸せを見つける』(ポプラ新書)。趣味はフライフィッシング。官公庁や自治体の委員、メディアの監修等を多数務める傍ら、関係人口を育成する地域のプロジェクトにも多く携わる。
みんなが読んでいる記事
-
 2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜
2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。
-
 2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準
2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。
-
 2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方
2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。
-
 2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」
2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!
-
 2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢
2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。